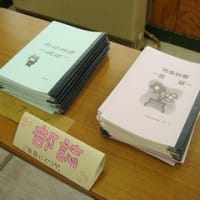3、中世の小平(2) ~九道の辻~
西武多摩湖線八坂駅から南西約100メートルの所にある、八坂交差点。木々に囲まれ、交番やダイエーがあり、多くの道が交差していて、独特の雰囲気を醸し出している。ここはかつて、「九道(くどう)の辻」と呼ばれ、鎌倉街道・江戸街道・大山街道・奥州街道・引股(ひきまた)道・宮寺道・秩父道・清戸道・御窪(みくぼ)道という9本の道が交差していた。
この九道の道に関して、1つの口碑伝説(言い伝え)が残っている。
今から672年前の元弘(げんこう)3年(1333年)5月8日、後醍醐天皇から鎌倉幕府討伐の命を受けた新田義貞は、上野国新田荘の生品(いくしな)明神(みょうじん)(群馬県太田市〈旧新田町〉)で挙兵。鎌倉街道上ノ道を南下し、12日の久米川の戦い(東京都東村山市)で幕府軍を打ち破り、幕府軍は敗走。義貞軍ははこれを追撃したが、いくつもの道に枝分かれした九道の辻に至り、どの道が鎌倉に通じるのか分からず、大変迷ったらしい。
どのようにして正しい道を発見したのかは謎だが、ともかく義貞軍は正しい道を進み、22日、鎌倉幕府は滅亡した。
その時義貞は、後にまた自分のように道を迷う人が出ないようにという優しい気遣いから、鎌倉街道の一角に桜を植えたと言う。
その後、桜は何度も植え継がれたが、大正時代には完全に枯れ、その大きな根株(ねかぶ)も第二次世界大戦後に消えてしまった。しかし、この「迷いの桜」伝説を後世に伝えるため、昭和55年(1980年)10月、小平市は八坂交差点にある八坂交番の裏に桜の苗木を植えた。
それから25年経った今、現代版「迷いの桜」はすっかり成長し、毎春見事に桜が咲いているという(私は桜が咲いている様子を、残念ながらいまだ見たことがない)。
尚、現在八坂交差点を交差する道は、府中街道と江戸街道以外は名称のない道となった。(つづく) (執筆:会長全権代行)
西武多摩湖線八坂駅から南西約100メートルの所にある、八坂交差点。木々に囲まれ、交番やダイエーがあり、多くの道が交差していて、独特の雰囲気を醸し出している。ここはかつて、「九道(くどう)の辻」と呼ばれ、鎌倉街道・江戸街道・大山街道・奥州街道・引股(ひきまた)道・宮寺道・秩父道・清戸道・御窪(みくぼ)道という9本の道が交差していた。
この九道の道に関して、1つの口碑伝説(言い伝え)が残っている。
今から672年前の元弘(げんこう)3年(1333年)5月8日、後醍醐天皇から鎌倉幕府討伐の命を受けた新田義貞は、上野国新田荘の生品(いくしな)明神(みょうじん)(群馬県太田市〈旧新田町〉)で挙兵。鎌倉街道上ノ道を南下し、12日の久米川の戦い(東京都東村山市)で幕府軍を打ち破り、幕府軍は敗走。義貞軍ははこれを追撃したが、いくつもの道に枝分かれした九道の辻に至り、どの道が鎌倉に通じるのか分からず、大変迷ったらしい。
どのようにして正しい道を発見したのかは謎だが、ともかく義貞軍は正しい道を進み、22日、鎌倉幕府は滅亡した。
その時義貞は、後にまた自分のように道を迷う人が出ないようにという優しい気遣いから、鎌倉街道の一角に桜を植えたと言う。
その後、桜は何度も植え継がれたが、大正時代には完全に枯れ、その大きな根株(ねかぶ)も第二次世界大戦後に消えてしまった。しかし、この「迷いの桜」伝説を後世に伝えるため、昭和55年(1980年)10月、小平市は八坂交差点にある八坂交番の裏に桜の苗木を植えた。
それから25年経った今、現代版「迷いの桜」はすっかり成長し、毎春見事に桜が咲いているという(私は桜が咲いている様子を、残念ながらいまだ見たことがない)。
尚、現在八坂交差点を交差する道は、府中街道と江戸街道以外は名称のない道となった。(つづく) (執筆:会長全権代行)