友人と共同で計画していたある出版企画が、その友人の紹介による某出版社の企画会議で承認された。
自分が筆者(共著者)となるのは、久しぶりだ。
これまで執筆(分担執筆、共同執筆)した、 Mookや単行本は、コンピュータやソフトウェアに関するものだが、今回は、全く違う分野である。
ある種の「社会人の継続学習のすすめ」にかかわるテーマだ。
私自身は、生来のナマケモノで、小学校から高校まで、いわゆる学校の勉強はあまり一生懸命には取り組んで来なかった。特に、予習復習はほとんどしない生徒だった。
通常、高校での進学指導は、成績の良い科目に関連した学部学科を主たる進学先としてすすめられることが多いようだ。
私の場合には、当時の高校の成績からすると社会科学に関連する学科に当然進学すると思われていた。しかし、機械工学に非常に強い興味があったので、英語や数学の成績が不調だったにもかかわらず、無謀にも機械工学科だけを受験した。
滑り止めに受けた某大学の2部の機械工学科に進学し、2年生にあがるときに1部に転部した。その後、修士課程まで進学した。
いまになって考えると、機械工学は、ある意味ですべてのエンジニアリング=工学、工業技術の基本となる学問であると思う。結果的には、機械系メーカーには就職しなかったので、高校時代に考えた方向とは少しちがっていたが、最初に機械工学を学んだこと、多くの一流の教授の教えを受ける機会を得られたことは、非常に恵まれていたと思う。
学部の4年生のとき、自分用の8bitCPUのパソコンを購入したことをきっかけに、コンピュータとソフトウェアに本格的な興味をもったため、修士論文の研究は、流体現象の数値シミュレーションに決め、ほぼ独学で取り組んだ。
そのころからずっと、私のコンピュータやソフトウェアの知識は、ほぼ独学によるものである。
修士課程修了後、最初の就職から現在まで、ソフトウェア関係の仕事をしている。いつも「自分は情報工学、計算機科学の出身ではない」ということが頭から離れたことはない。そのことは、ある種の「ひけめ」であり、それが、20数年来、私をコンピュータ/ソフトウェア分野の独習に駆り立て続けてきた原動力であったといえる。
一方、「自分は機械工学の出身である」というこをと忘れたこともない。高校時代から持ってきた、機械工学への興味とその分野の学習も継続してきた。そのことが、母校の大学院博士後期課程機械工学専攻での博士号取得につながったのだと思う。この二つの分野の、継続的な学習は、足し算ではなくかけ算的効果を相互にもたらしている。
また、ビジネス/経営の分野についても、日常の仕事の場だけでなく、色々な形で学習してきた。
そのような私の経験と、友人(共著者)の異なる分野での異なる経験と知見を、ふまえた上で「社会人の継続学習のすすめ」のある種の型について、まとめてみようと思う。
自分が筆者(共著者)となるのは、久しぶりだ。
これまで執筆(分担執筆、共同執筆)した、 Mookや単行本は、コンピュータやソフトウェアに関するものだが、今回は、全く違う分野である。
ある種の「社会人の継続学習のすすめ」にかかわるテーマだ。
私自身は、生来のナマケモノで、小学校から高校まで、いわゆる学校の勉強はあまり一生懸命には取り組んで来なかった。特に、予習復習はほとんどしない生徒だった。
通常、高校での進学指導は、成績の良い科目に関連した学部学科を主たる進学先としてすすめられることが多いようだ。
私の場合には、当時の高校の成績からすると社会科学に関連する学科に当然進学すると思われていた。しかし、機械工学に非常に強い興味があったので、英語や数学の成績が不調だったにもかかわらず、無謀にも機械工学科だけを受験した。
滑り止めに受けた某大学の2部の機械工学科に進学し、2年生にあがるときに1部に転部した。その後、修士課程まで進学した。
いまになって考えると、機械工学は、ある意味ですべてのエンジニアリング=工学、工業技術の基本となる学問であると思う。結果的には、機械系メーカーには就職しなかったので、高校時代に考えた方向とは少しちがっていたが、最初に機械工学を学んだこと、多くの一流の教授の教えを受ける機会を得られたことは、非常に恵まれていたと思う。
学部の4年生のとき、自分用の8bitCPUのパソコンを購入したことをきっかけに、コンピュータとソフトウェアに本格的な興味をもったため、修士論文の研究は、流体現象の数値シミュレーションに決め、ほぼ独学で取り組んだ。
そのころからずっと、私のコンピュータやソフトウェアの知識は、ほぼ独学によるものである。
修士課程修了後、最初の就職から現在まで、ソフトウェア関係の仕事をしている。いつも「自分は情報工学、計算機科学の出身ではない」ということが頭から離れたことはない。そのことは、ある種の「ひけめ」であり、それが、20数年来、私をコンピュータ/ソフトウェア分野の独習に駆り立て続けてきた原動力であったといえる。
一方、「自分は機械工学の出身である」というこをと忘れたこともない。高校時代から持ってきた、機械工学への興味とその分野の学習も継続してきた。そのことが、母校の大学院博士後期課程機械工学専攻での博士号取得につながったのだと思う。この二つの分野の、継続的な学習は、足し算ではなくかけ算的効果を相互にもたらしている。
また、ビジネス/経営の分野についても、日常の仕事の場だけでなく、色々な形で学習してきた。
そのような私の経験と、友人(共著者)の異なる分野での異なる経験と知見を、ふまえた上で「社会人の継続学習のすすめ」のある種の型について、まとめてみようと思う。














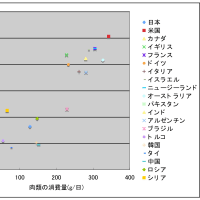
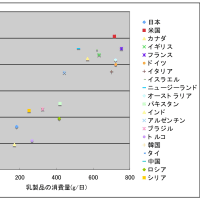
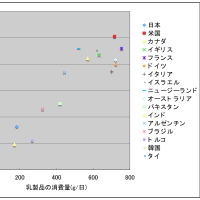







確かに、ヒトが、ここまで進歩してこれた原動力の一つは、好奇心だと思います。
未知のものごとへの好奇心が、挑戦やイノベーションを生んできました。
好奇心の維持とそれに駆り立てられた探求や学びは、我々にとって非常に本質的なものだとおもいます。