鎌倉時代の裁判制度
〔初期〕各機関の管轄は、訴訟当事者の身分と所在を基準
御家人…問注所(受理)→鎌倉殿(執権、連署が臨席する評定で確定)
非御家人…鎌倉市中は政所、諸国は問注所
御家人を一方当事者とする訴訟は後、引付が受理
〔やがて〕訴訟分類による区分
①所務沙汰
御家人などの所領相論に係る訴
②雑務沙汰
不動産を除く民事訴訟
③検断沙汰
刑事事件
※被害者・加害者の一方が地頭・御家人であること
→法は家庭に入らず、主従に入らず
手続き
①原告による訴状の提出
※訴人・論人の名を示す
※財産関係は、訴訟対象を示す
※証拠を示す
→当事者主義を徹底し、幕府は原則、捜査せず
(検断沙汰)
②「問状之召文」が論人に送られる
③訴状・陳状の往復3回「三問三答」
※論人が出頭しない、出頭しても陳状を示さないときは、日限召文を送り、それでも出頭しなければ、身柄確保となる
※途中での和与や、三問三答の打ち切りがある
④対決(口頭弁論)
※証拠が重視、物証、使者による検証、書証
⑥判決
侍所頭人・奉行が連署した下知状が、勝訴者に発給される
(所務沙汰)
①訴人が問注所の財務賦に訴状・具書(書証)を提出
②訴状の裏に賦奉行が銘を加え、引付に送付
③引付は、くじにより、担当奉行を選び、論人に問状を給付
④論人は、陳情を提出し、三問三答する
〇非理が明らかになれば、ここで判決が下る
⑤召文が発給され、当事者双方が引付によばれ対決する
※召文は3回まで、とくに期限を切るものを日限召文という
※召文違背は、訴人に道理があれば論所(訴訟の対象物)は訴人に給付し、道理なければ没収して第三者に給付
〇証拠文書を重視
〇当事者主義
・証拠の提出、文書の送達、召文違背の咎は当事者真正、謀書の立証責任
⑥審理修了後、引付で評議
⑦両当事者の主張・理非を記した引付勘禄事書(判決草案)を作成
⑧評定衆により引付勘禄事書が承認されると、裁許文が作成され、引付頭人から勝訴者に送達
尚、和与(和解)も当事者主義であり、和与状を裁判所に提出し、下知状により承認される必要があり、私和与は、後の訴訟で証拠としての効力を有しない。また、承久の乱いご本所・御家人訴訟が急増したため、和与は推奨された。
①和与状を作成し相手方に渡す
イ)和与の条件、ロ)当事者の連署
②訴訟機関に提出
③和与裁許状の発給
以上
〔初期〕各機関の管轄は、訴訟当事者の身分と所在を基準
御家人…問注所(受理)→鎌倉殿(執権、連署が臨席する評定で確定)
非御家人…鎌倉市中は政所、諸国は問注所
御家人を一方当事者とする訴訟は後、引付が受理
〔やがて〕訴訟分類による区分
①所務沙汰
御家人などの所領相論に係る訴
②雑務沙汰
不動産を除く民事訴訟
③検断沙汰
刑事事件
※被害者・加害者の一方が地頭・御家人であること
→法は家庭に入らず、主従に入らず
手続き
①原告による訴状の提出
※訴人・論人の名を示す
※財産関係は、訴訟対象を示す
※証拠を示す
→当事者主義を徹底し、幕府は原則、捜査せず
(検断沙汰)
②「問状之召文」が論人に送られる
③訴状・陳状の往復3回「三問三答」
※論人が出頭しない、出頭しても陳状を示さないときは、日限召文を送り、それでも出頭しなければ、身柄確保となる
※途中での和与や、三問三答の打ち切りがある
④対決(口頭弁論)
※証拠が重視、物証、使者による検証、書証
⑥判決
侍所頭人・奉行が連署した下知状が、勝訴者に発給される
(所務沙汰)
①訴人が問注所の財務賦に訴状・具書(書証)を提出
②訴状の裏に賦奉行が銘を加え、引付に送付
③引付は、くじにより、担当奉行を選び、論人に問状を給付
④論人は、陳情を提出し、三問三答する
〇非理が明らかになれば、ここで判決が下る
⑤召文が発給され、当事者双方が引付によばれ対決する
※召文は3回まで、とくに期限を切るものを日限召文という
※召文違背は、訴人に道理があれば論所(訴訟の対象物)は訴人に給付し、道理なければ没収して第三者に給付
〇証拠文書を重視
〇当事者主義
・証拠の提出、文書の送達、召文違背の咎は当事者真正、謀書の立証責任
⑥審理修了後、引付で評議
⑦両当事者の主張・理非を記した引付勘禄事書(判決草案)を作成
⑧評定衆により引付勘禄事書が承認されると、裁許文が作成され、引付頭人から勝訴者に送達
尚、和与(和解)も当事者主義であり、和与状を裁判所に提出し、下知状により承認される必要があり、私和与は、後の訴訟で証拠としての効力を有しない。また、承久の乱いご本所・御家人訴訟が急増したため、和与は推奨された。
①和与状を作成し相手方に渡す
イ)和与の条件、ロ)当事者の連署
②訴訟機関に提出
③和与裁許状の発給
以上










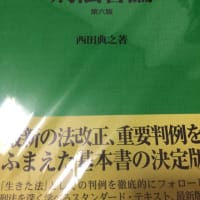
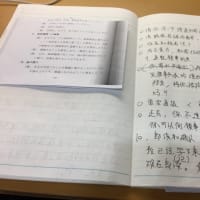
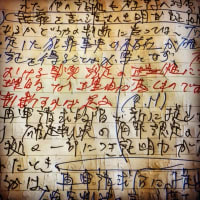

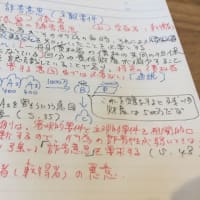
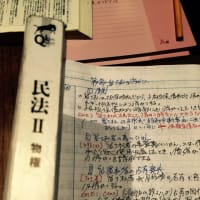
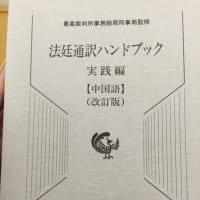
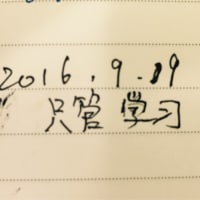

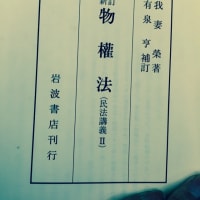
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます