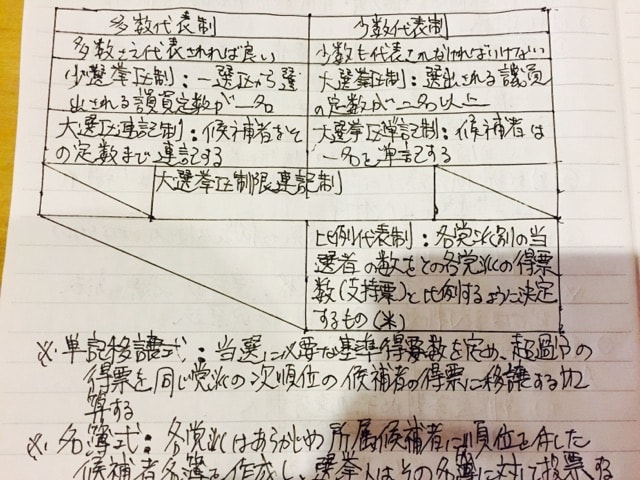議員の不逮捕権について。
偶々、ニュースを見ていたら、派遣労働法の改正にあたって、自公と維新が修正協議に応じ、同法の改正が議会を通過する見込みとなったことに呼応して、野党民主党の議員数十名による議場前でのバリケードのことが、報道されていた。どうやら、この民主党議員のバリケードは議長の議場への入室を阻むことを直接の手段として、議会での審議の開始を妨害する行為であるが、この議員による実力の行使について、一部の報道においては、「それでも、不逮捕権か」と言う見出しが、見受けられた。記事の詳細については、目を通していないので分らない。さて、議員の不逮捕権について、興味深い点があったので、記しておきたい。今回の騒動において、議長は民主党議員の妨害行為によって、もみくちゃにされたのであるが、その際に、議長は負傷を負って、自らの携帯電話を紛失したと主張しているようである。抑々、議員の不逮捕権とは国会の会期中に、院外における議員の逮捕については、議員は現行犯による逮捕のほか、院による許諾がない場合には、逮捕されないというものである。このことにより、立法権に対する行政権のみだりな行使を防がせる目的を持っている。これに対して、院内には行政権が及ばず、議員による不法行為が発生した場合には、議員内の警察権は、議長によって行使されることになっている。実際には、議長の命令のもと、衛視または警察官が犯人を逮捕する。このことの理由は、三権分立における、立法府自身の自律性と自主性を尊重することに原因する。すなわち、院内における議員の不法行為については、立法府たる両議院の院議により、これを判断することは、議会の独立を対面と独立を保つために、有される権利である。しからば、今回の件は、事件の当事者が民主党議員と衆議院の議長との間に発生しており、当事者の一方である議長は、被害者たる当事者であると同時に、院内における警察権の行使を発動する地位である。この場合に、議長が民主党議員の実力の行使について、違法行為があるとして、警察権することができるのであろうか。あるいは、懲戒にあたる行為があるとした場合には、院内ではいかなる手続きで処分されるのであろうか、見ものである。
以上。
偶々、ニュースを見ていたら、派遣労働法の改正にあたって、自公と維新が修正協議に応じ、同法の改正が議会を通過する見込みとなったことに呼応して、野党民主党の議員数十名による議場前でのバリケードのことが、報道されていた。どうやら、この民主党議員のバリケードは議長の議場への入室を阻むことを直接の手段として、議会での審議の開始を妨害する行為であるが、この議員による実力の行使について、一部の報道においては、「それでも、不逮捕権か」と言う見出しが、見受けられた。記事の詳細については、目を通していないので分らない。さて、議員の不逮捕権について、興味深い点があったので、記しておきたい。今回の騒動において、議長は民主党議員の妨害行為によって、もみくちゃにされたのであるが、その際に、議長は負傷を負って、自らの携帯電話を紛失したと主張しているようである。抑々、議員の不逮捕権とは国会の会期中に、院外における議員の逮捕については、議員は現行犯による逮捕のほか、院による許諾がない場合には、逮捕されないというものである。このことにより、立法権に対する行政権のみだりな行使を防がせる目的を持っている。これに対して、院内には行政権が及ばず、議員による不法行為が発生した場合には、議員内の警察権は、議長によって行使されることになっている。実際には、議長の命令のもと、衛視または警察官が犯人を逮捕する。このことの理由は、三権分立における、立法府自身の自律性と自主性を尊重することに原因する。すなわち、院内における議員の不法行為については、立法府たる両議院の院議により、これを判断することは、議会の独立を対面と独立を保つために、有される権利である。しからば、今回の件は、事件の当事者が民主党議員と衆議院の議長との間に発生しており、当事者の一方である議長は、被害者たる当事者であると同時に、院内における警察権の行使を発動する地位である。この場合に、議長が民主党議員の実力の行使について、違法行為があるとして、警察権することができるのであろうか。あるいは、懲戒にあたる行為があるとした場合には、院内ではいかなる手続きで処分されるのであろうか、見ものである。
以上。