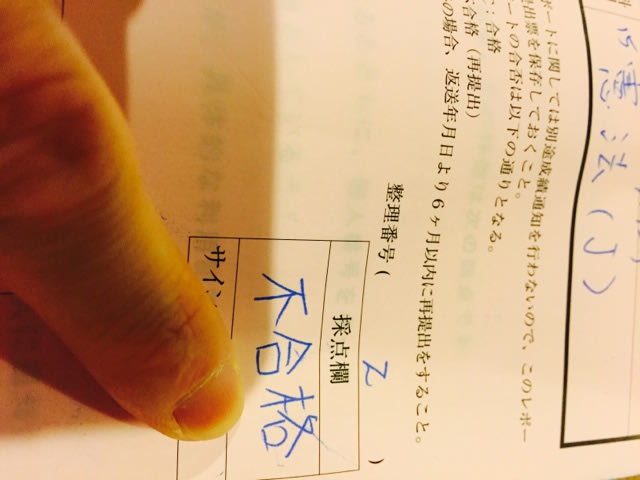10/21
昨日、図書館の貸出履歴が市町村によって収集され、個人の思想状況について、把握され得る危険性について、本書では指摘されていることに言及した。今日、ハフィントンポストの記事「村上春樹さんが図書館で借りた本はなぜ秘密にされるべきなのか?・・・」という記事で、このことが取り上げられていたので、紹介したい。
本書でも紹介されている、日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言 1979年改訂」の第一条は次のような文言である。
事件の概要は、作家、村上春樹氏が50年前、高校生の時に学校図書館で借りた本のタイトルが、本人の事前の承諾なく報道機関が報道したというものである。日本図書館協会は、このことに憂慮し、報道機関に対して、直接申し合わせたようだ。
本記事で、私の目を引いたのは、犯罪捜査と「利用者の秘密」が衝突という、項目である。2011年の調査によれば、捜査機関からの貸出記録等の照会を受けたことのある館が、調査対象図書館の20.3%であり、その内、実際に提供した館が58.9%に上っていたという、内容である。
この問題は、本記事でも指摘される通り、上掲の「図書館の自由に関する宣言 1979年改訂」の第一条の、「憲法第三五条にもとづく令状を確認した場合」に該当する場面ではなく、捜査機関による照会状のみにより図書館が開示をしている点、また、調査対象図書館の五分の一に相当する館に対し、捜査機関による照会が行われている実態について、憂慮すべき問題があると、思われる。
最近では佐賀県武雄市を皮切りに、TUTATYAを管理するCCCという企業体による、公共図書館の参画が話題になっとなっており、公的部門のみならず、民間企業体による情報の管理についても、注意を喚起せざるを得ない。(図書館の貸出履歴から個人の趣味・傾向に基づいた、ターゲティング・マーケティングが行われないという安心は、得られるのだろうか)
また、マイナンバー法においても、個人番号カードの利用範囲として、地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務に利用することができる(第18条第1号)、という規定があり図書館の貸出機能が地方公共団体の条例に基づいて付加される可能性が、大いにあると、考えられる。
以上
昨日、図書館の貸出履歴が市町村によって収集され、個人の思想状況について、把握され得る危険性について、本書では指摘されていることに言及した。今日、ハフィントンポストの記事「村上春樹さんが図書館で借りた本はなぜ秘密にされるべきなのか?・・・」という記事で、このことが取り上げられていたので、紹介したい。
本書でも紹介されている、日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言 1979年改訂」の第一条は次のような文言である。
1 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第三五条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
事件の概要は、作家、村上春樹氏が50年前、高校生の時に学校図書館で借りた本のタイトルが、本人の事前の承諾なく報道機関が報道したというものである。日本図書館協会は、このことに憂慮し、報道機関に対して、直接申し合わせたようだ。
本記事で、私の目を引いたのは、犯罪捜査と「利用者の秘密」が衝突という、項目である。2011年の調査によれば、捜査機関からの貸出記録等の照会を受けたことのある館が、調査対象図書館の20.3%であり、その内、実際に提供した館が58.9%に上っていたという、内容である。
この問題は、本記事でも指摘される通り、上掲の「図書館の自由に関する宣言 1979年改訂」の第一条の、「憲法第三五条にもとづく令状を確認した場合」に該当する場面ではなく、捜査機関による照会状のみにより図書館が開示をしている点、また、調査対象図書館の五分の一に相当する館に対し、捜査機関による照会が行われている実態について、憂慮すべき問題があると、思われる。
最近では佐賀県武雄市を皮切りに、TUTATYAを管理するCCCという企業体による、公共図書館の参画が話題になっとなっており、公的部門のみならず、民間企業体による情報の管理についても、注意を喚起せざるを得ない。(図書館の貸出履歴から個人の趣味・傾向に基づいた、ターゲティング・マーケティングが行われないという安心は、得られるのだろうか)
また、マイナンバー法においても、個人番号カードの利用範囲として、地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務に利用することができる(第18条第1号)、という規定があり図書館の貸出機能が地方公共団体の条例に基づいて付加される可能性が、大いにあると、考えられる。
以上