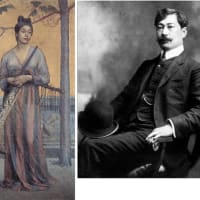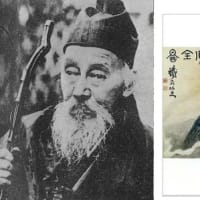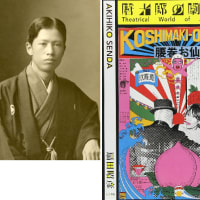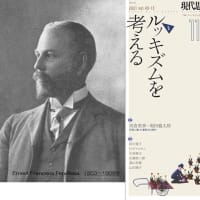A.百年前に何があったか?
今から百年前は、1917年。日本の元号では大正6年。この年に何があったか?
1月:欧州は第一次世界大戦の最中。:駐日英国大使が日本艦隊の欧州派遣を本野外相に要請。
2月:日本海軍が欧州派遣に向け第1・第2特務艦隊を編成。寺内内閣が欧州派遣を閣議決定。
3月:ロシア2月革命勃発。臨時政府を樹立し、ニコライ2世は退位、ロマノフ朝滅亡。
4月:アメリカがドイツに宣戦布告。レーニンが4月テーゼ。日本は衆議院総選挙。
5月:バレエ「パラード」パリで初演、台本コクトー、音楽サティ、美術ピカソが担当。
6月:第39議会召集。
7月:ロシア臨時政府首班にケレンスキーが就任。
8月:中華民国がドイツに宣戦布告。第11次イゾンツォの戦い。
9月:中華民国で孫文が広東軍政府を樹立。日本は金本位制が停止。関東大水害。
10月:第一次大戦 カポレットの戦い。
11月:ロシア(ロシア暦)10月革命(ボリシェビキ蜂起。ソヴィエト政権が樹立される。
12月:明治乳業(当時の社名極東練乳)創立。
細かいことは今は忘れられて、要するにヨーロッパは第1次世界大戦が続き、ロシアで大革命、日本はとくに戦争といっても南洋のドイツ領を奪っただけで、国内と国民は割合平和だった。ヨーロッパ諸国は戦争で疲弊し、皇帝を倒すロシア革命で出現した社会主義政権の衝撃が、世界を駆け巡った。そういう時代に生まれた思想史家・武田清子さんが、百歳を迎えて『世界』のインタビューで語っていた。
インタビュー武田清子氏に聞く「天皇観の相剋」と現代(聞き手・阿部菜穂子)
「近代日本思想史学者の武田清子さんが、この六月、百歳の誕生日を迎えた。武田さんは敗戦の廃墟の中で、太平洋戦争を深く反省し、日本の歩む道を探ることを目的に創刊された雑誌『思想の科学』の七人のメンバーのひとり、同人は丸山真男(政治学者)、鶴見俊輔(哲学者)、都留重人(経済学者)、鶴見和子(社会学者)各氏らで、戦後の日本を代表するリベラル教養人たちであった。サンフランシスコ講和条約締結のころには「全面講和」を主張する「平和問題懇話会」にも参加した。天皇制を生涯の研究課題とし、敗戦前後に日本の天皇制をめぐって連合国の間で起きた大きな議論を、一九七八年『天皇観の相剋』(岩波書店)として出版。著書は高く評価されて毎日出版文化賞を受けた。太平洋戦争をはさんで一世紀にわたる人生を歩み、日本の思想状況に大きな足跡を残した武田さん。戦前からのキリスト者として天皇制を厳しく見つめてきた武田さんに、現代を生きる日本人へのメッセージを聞いた。
(『天皇観の相剋』は、敗戦後の日本で天皇制を廃止させるのか、存続させるのか、天皇を裁判にかけるのか、かけないのか、など日本の天皇制をめぐって太平洋戦争中の一九四三年ごろから連合国の間で起きていた激しい議論を追い、まとめた本である。最終的に連合国は、天皇の戦争責任は問わず、日本の民主化遂行のために天皇を利用するという高度な政治判断を下したわけだが、武田さんは戦後、関係各国に出向いて当時の極秘資料を集め、まだ健在だった関係者にインタビューし、連合国がその判断にいたるまでの過程を克明に綴った。)
――敗戦時に連合国が天皇制を温存させるという政治判断をしたことについて、現在どのような考えをお持ちですか。
そうした判断がよかったのかどうか、についての答えはわかりません。でも、GHQ(連合国軍総司令部)が(天皇を利用して)民主化を実行したことは事実です。また、「象徴天皇」となった昭和天皇も、民主化の先頭に立って努力したと思います。ただ、私は“天皇制が温存された”という言い方は好きではありません。「天皇制」というと戦前の体制を意味することになりかねないからです。象徴天皇として、国民に仕えていくという「天皇の存在」が残った、と言った方がいいでしょう。
――そのような「象徴天皇」のあり方は、日本人自身が選択したものだったのでしょうか。
象徴という考え方はGHQの中にもあったと思いますが、それに呼応して「民主的な天皇」の意味を持つように実践していったのは、国民だったと思います。日本人は、象徴としての天皇をもつという、非常に賢明な選択をしたと思います。象徴天皇というのはひとつの民主主義の形です。
――国民が明確に「象徴天皇」を選択し、支持したということですね。
そうです。敗戦を経験して、国民と天皇自身がともに苦しんで、模索した結果だったと思います。戦前の天皇論ではない、民主的な天皇にするという努力です。それはどこの国のまねでもなく、日本独特の民主主義のあり方を探る道のりだったと思います。
( 中 略 )
(武田さんの指摘は、「大正デモクラシー」として現れたヒューマニズムやリベラリズム、社会主義の思想運動が知識階級にのみ限定されていたのではなく、文学運動や新教育運動、労働運動・農民運動・婦人運動などを伴って幅広い民衆の心の中に、人間尊重思想や自由主義思想の種をまいた、というものである。このような思想が、国体明徴運動と軍国主義のイデオロギーが支配していた時代にも、人々の日常の生活と心の深みに一つの地下水のような流れを形成し、それこそが連合国による戦後の「民主化政策」に対して内側から呼応して芽を噴き出させる要素だったのではないか、とみる。)
――それは実は、武田さんが「二頭立ての馬車」と呼ぶ、明治維新以来の近代日本の二重構造に根っこがあるわけですね? 一つは天皇を神格化・絶対化する側面、もう一つは天皇も憲法によって制限されるという制限君主的な側面です。前者は超国家主義につながる可能性をもち、後者は民主主義的、合理主義的要素であった、と。
そうです。時代によってそのどちらかがより強く表に出てくることがあります。だから国民が(民主的な希求を)心の中にもっているとしても、うっかりしているとつぶされてしまう可能性があります。それを守り続け、よりインプルーブ(改善)していかなければいけないと思います。
( 中 略 )
――最近の日本では、天皇を再び神格化しようという動きが強まっており、その「うっかりしているとつぶされる」という方向に向かっているかに見えます。「象徴天皇」も岐路にあるように見えます。
私は日本国民は全体として、今でも象徴としての天皇を望んでいると思います。象徴天皇という形が一番安全で、そういう天皇をなくしてしまうのではなく、あったほうが安心できると、大部分の国民が考えていると思います。象徴以上のものを天皇に求めるのは間違いです。でも、事実として天皇の存在が長く続いてきたわけですから、無理にそれを壊すこともないわけです。
( 中 略 )
――「二頭立ての馬車」の構造は実は今も、形を変えて続いているのではないでしょうか。戦前の国家神道は、占領軍によって破壊されたと言われましたが、実際は死ななかったわけですよね。
死ななかったかもしれないけれど、それが生き生きと活動をするというわけではありません。より民主化していくために、伝統主義の古い要素が顔をもたげるのをいつも警戒して、努力を続けることが必要なのではないでしょうか。
――天皇を象徴以上のものにしようとする動きが政権内部でも強まっている昨今の状況で、天皇自身が日本の民主主義を守る「防波堤」になっているという意見が聞かれます。
天皇が防波堤というより、日本の憲法が防波堤なんです。だから、憲法は守っていかなければなりません。
――「天皇制」のあるべき姿についてのモデルは、どこかにあるでしょうか。
モデルはどこにもありません。それぞれの国に独自の伝統と歴史があるわけですから、日本の独自のものをさぐり、伝統的なもののうち国体化させようとする要素は排除して、民主主義的な要素をよりインプルーブしていくことが大切だと思います。国民がそれをやっていかなければなりません。 ( 中 略 )
――日本の民主主義は大丈夫でしょうか。
大丈夫でしょうか、ではなくて、私たちがそれを守っていかなければいけません。たとえ首相が憲法を変えようとしているとしても、国民が守っていけばいいんです。常に反動化する危険性はあるわけですから、国民がそれを警戒してより民主化していくために何が必要かを正しく発見して学び、努力していかなければいけないと思います。
――最後に、現在の天皇家について何かひとこと。
天皇家では、秋篠宮家がお子さん二人を外に開かれ、リベラル・アーツの習得を勉学の目的とするICU(国際基督教大学)に行かせたのは、非常に面白いと思います。眞子内親王は高校生の時からオーストラリアやアイルランドに短期滞在し、ICU卒業後はイギリスのレスター大学大学院に留学しました。佳子内親王も今秋からイギリスのリーズ大学に留学するそうです。天皇家自身が日本の外に目を向け、違った価値や民主的な価値を取り入れようとしているわけですから、国民も努力しなければいけないと思います。日本の外の文化や違った価値観に目を向けて、学んでいく姿勢が大事です。天皇家を自分たちにいいように利用しようとする勢力には、そうさせないようにする国民の不断の努力が必要です。
武田さんは『天皇観の相剋』の最後に、「連合国による民主化政策の『共演者』となった日本人が、民主化の変革を積み重ね、明日の人類社会の形成にかかわる道を探し求めるために、そしてそれを未来に向かってさらに展開させていくために、『天皇』であれ『大統領』であれ地上の『絶対的権力』に支配される『臣』的存在には再び戻らず、みずから創作するドラマの主演者になっていく歩みはどういう道なのだろうか?」という問いを投げかけている。百歳を迎えた武田さんが、インタビューで「普遍的な価値に向かって常に現実を反省し、インプルーブしていく」と何度も言ったのは、四〇年前に自身が発した問いに通じるものであろう。
武田さんが生涯を通して問い続けてきたのは、伝統に根ざす、特殊で排他的な要素をも含む土着的価値の中のポジティブな要素を、いかにして普遍的な「民主的価値」にまで高めていくか、ということである。武田さんは二年前の『日本経済新聞』のインタビューで、個人的に親交のあったインドのネール元首相が戦後来日した際、武田さんに「日本が焼け跡から復興したのはすばらしい。ただ、日本人は良い方にも悪い方にも規律正しく集団で進むように見える。日本人の個の主体性はどこにあるのだろう」と尋ねたエピソードを紹介し、「鋭い問いで、現在につながる問題提起だと思います」と語っている(二〇一五年七月三一日付)。ネール元首相が指摘した「規律正しく集団で進む」のが日本の「伝統的価値」だとすれば、問われた「個の主体性」は、日本の土壌にまだしっかりと根付いていない普遍的価値であろう。この問いは今後も、引き続き検証されていかなければならない重要な課題のように思える。」岩波書店『世界』2017.10 pp.172-177.
『天皇観の相剋』は凄い本である。女性だから凄いというわけではないが、戦後の日本で社会科学の分野で第一級の仕事をした女性研究者といえば、この武田さん(1917-)と鶴見和子さん(1918-2006)、それに中根千枝さん(1926-)あたりがまずあがるだろう。武田さんは神戸女学院から22歳でアメリカに留学(1939年)、鶴見さんも津田英学塾から同じ年に21歳でアメリカ留学、コロンビア大学などで学ぶ。日米戦争の間、武田さんはアメリカに残り、鶴見さんは交換船で日本に戻ったが、二人より少し若い中根さんは戦後に津田英学塾から東大初の女子学生になる。この経歴だけ見ても「普通のお嬢さん」などではなく、とびきり優秀な女性だったわけだが、その仕事もスケールが大きくその後続世代への影響も大きかった。このインタビュアーも、しきりに現在の日本が戦前に回帰するような憲法否定の動きになっていることを不安に思い、武田さんにそのへんを尋ねるのだが、武田さんは日本人はそれほど愚かではないし、憲法の価値を理解しているので、天皇制をどう考えるかを含め、きちんと議論し覚悟をもって自由と民主主義を守っていかなくてはいけない、と語る。しかし、今の日本人の多くはこの国の未来に自信を失って動揺しているのではなかろうか。
安倍政権はついに憲法を変えるという一点を目指して、無謀な解散総選挙をやる。ここで有権者の覚悟が問われるチャンスなのだから、正面から議論してこの誤った政治を変えられるか?

B.何が気に食わないのか?
日本の伝統の中心に天皇を置き、万世一系を何より大事にする右翼思想では、飛鳥・奈良時代より朝鮮と中国の文明をつねに意識し、それと比較対象してヤマトのアイデンティティをいかに確保するかに心を砕いていたと思う。この国が東アジアの文明圏のなかで、独自性を主張するには中華文明を学習しつつ固有の依代(よりしろ)として大和の王権、スメラギを掲げて古代国家を樹立する努力が求められた。ぼくたちは日本の歴史を子どもたちに教えるとき、この日本、朝鮮半島、中国という基本構図を踏まえて、先人が世界をどう捉えていたのか、漢字文化圏の周辺で日本の識字インテリジェントが、この国をどうデザインしようとしたのか、みんなで知って考えることがとっても大事だと思う。でも、ぼくたちは朝鮮半島の歴史や中国の王朝の歴史について、学校で歴史の時間にさらっと教えられてはいるが、西洋史に対するより東洋にあまり興味をもたない。
そのことが21世紀の現代のシビアな問題、たとえば金正恩の北朝鮮が危険なミサイルを撃ち込んでくるかも、という恐怖に対して、ただ怯えたり興奮して戦争をやってしまえ!と即自的反応に走ることは何も考えていないに等しい愚劣でしかない。いわゆる「嫌韓・嫌中」「反日左翼を叩き潰せ」と叫んでいるネトウヨの人たちは、どうも東アジアの長い歴史や、せめて明治維新以来の日本が近隣アジアに対して何をやってきたかの基本的な知識もなにも知らないし、知る気もない。ある問題について何かを発言するには、少なくともその問題に関わる基本的な事実認識とそれをめぐる対立的な議論の要点を知った上で発言しなければ、ただの戯言、無意味な冗談に過ぎないのですね。そのことの格好の事例がまた出た。それは、天皇皇后夫妻が、私的な旅行として先日埼玉県の高麗神社に参拝したというささやかなニュースをめぐって、早速極右らしきコメントが、平成天皇ご夫妻をも朝鮮中国に同情的な「反日左翼」に汚染された敵であると、口汚く攻撃する書き込みになってネットに登場したのには驚いた。
いったいどういう立場から現行天皇すら否定する言論が右翼から可能になるのか?要するにただ単純に朝鮮と中国が憎いという素朴な心情だけに依拠して、歴史も国際政治の現実も無視した(というよりこの人たちは歴史に無知なだけの)ファナティックな発言がなされている。まともに相手をする人たちではないけれど、なぜそんなに朝鮮や中国を嫌うのか、はいちおう考える必要はあると思う。彼らが言うことの根拠は、朝鮮韓国や中国人がことあるごとに日本を悪の帝国として、頭から否定し、慰安婦問題や南京虐殺を持ち出して日本人が邪悪な悪者だという立場から一方的に、謝罪や賠償を要求するのが許せない我慢できない、ということでしょう。日韓条約や日中平和友好条約で外交的には戦後の処理は終わっていて、今さら過去のあれこれにいちゃもんつけられる筋合いはない。どうして冷静に未来志向の友好関係を実現することができないのか?というのが安倍政権のスタンスだろう。でも、もう少しお互いの「歴史的記憶」を丁寧に学ぶことも必要だと思う。
「明仁天皇は日ごろから『韓中の文化が伝わってきて今日の日本になった』と考えていらっしゃると聞いている。今回の訪問をきっかけに、韓国についてよく知らなかった一般の人々も関心を持つようになるだろう」と語った。
同日午後4時に明仁天皇一行が高麗神社を出る「20日昼12時、明仁天皇と美智子皇后が、歴代の天皇では初めて埼玉県日高市の高麗(こま)神社を訪問した。1300年前に日本に渡った高句麗の王子「高若光」(日本名:高麗若光〈こまのじゃっこう〉)を祀っている。
明仁天皇訪問のニュースを聞き、歓迎する人々が朝から約2000人集まったことから、地元の駅と同神社を結ぶ1.7キロメートルの道は大変な混雑になった。60-70代の人々が参道沿いに小さな折り畳みいすやマットを広げて座り、明仁天皇を待っていた。日本の宮内庁は明仁天皇の高麗神社訪問について「公務ではなく私的な旅行」と説明している。明仁天皇は1年のうち250-270日公務を行うため、私的な旅行を楽しむ機会は1年に1・2回だ。高麗神社への旅は明仁天 皇の意思や希望を反映して決定されたという。
明仁天皇は日ごろから日本の過去について心から申し訳ないと考えて、韓日古代交流史にも関心が高いと言われている。2001年には「桓武天皇の生母が百済の王族だったと記されている」と発言して話題になった。05年には、太平洋戦争で戦地となった東南アジア諸国や南太平洋の島を訪れた際、朝鮮人犠牲者の慰霊碑をわざわざ訪れて黙とうしている。
明仁天皇と美智子皇后は同日、高句麗の王子から60代目となる高麗文康宮司(50)の案内で境内を見て回った。高麗文康宮司は「両陛下とも朝鮮半島から文明がやって来た過程に深い関心を持っていらっしゃると聞いていたが、実際に、高句麗人と百済人はどう違うのかなどいろいろと質問を受けたので、知っていることをお答えした」と語った。
日本で高麗神社は「出世明神」としても有名だ。斉藤実(1858-1936年)ら歴代首相6人がここに来て参拝後、首相になったという話もある。だが、ある住民は「それでも今日のように、一度に多くの人々が集まったことはない」と教えてくれた。
皇室を20年間取材している毎日新聞の大久保和夫記者は、明仁天皇について「日本国民が『心温かい』と感じ、敬愛している方だ。神社の外でずっと待っていた人々もそれぞれ帰り始めた。その中にいたキモトマユミさんは「高句麗人をまつった神社を訪れた意味をいろいろと考えてみたが、『近い国・韓国とはやはり共に行くべきだ』という意味ではないかと思った」と言った。日高市(埼玉)=イ・ドンフィ特派員 (朝鮮日報/朝鮮日報日本語版)」
これを報じているのが韓国のメディアだというだけで、反日左翼の陰謀に乗せられた天皇、というありもしない話を作り上げて勝手に頭にきているのだろう。
朝鮮の歴史で三国時代というのは、4世紀から7世紀ごろに朝鮮半島と満州南部に高句麗、百済、新羅の三国が鼎立した時代をいう。220年の後漢の滅亡が、三国の発展を許した。三国のうち最大であった高句麗は、鴨緑江沿いの国内城とその山城である丸都城の二つの並存された都をもっていた。新羅は唐と結んで、660年に百済を668年に高句麗を滅ぼした。これによって三国時代は終わり、滅ぼされた百済の王族は日本に逃れ、百済王の姓を賜り、高句麗の王族も海を越えて日本に亡命し定住した人々がいた。日本人はこの人々から先進文明を学び、大和の律令制国家をデザインした。それは歴史の大事な出来事であり、日本人もリスペクトして記憶してきた過去の歴史である。
それを朝鮮人は敵、中国人は悪という民族的偏見を感情的根拠にして、口汚く罵って右翼のシンボルである天皇夫妻すら「反日」のレッテルを貼って貶める。もはや1300年前に滅んだ高句麗と、21世紀の朝鮮半島とを混同するデタラメは救いがたい。でも、これを見ていたら、もう日本の右翼は精神の支柱すら空洞化して滅びに向かうのではないかと逆に心配になった。彼らの言い方を聴いていると、皇居ではなく靖国神社、戦災の死者ではなく特攻隊、伝統の尊重より排外憎悪だけに凝り固まった言葉しか聞こえず、偏狭というより無知だけが際立つ。日本のナショナリズムの伝統を知っていれば、楠木正成、吉田松陰、西郷隆盛から東郷平八郎、乃木希典という人々に流れていた尊王の精神を、受け継ぐ気概と理想をこそ語るべきなのに、君たちは異民族をけなして喜んでいるだけではないか。
今から百年前は、1917年。日本の元号では大正6年。この年に何があったか?
1月:欧州は第一次世界大戦の最中。:駐日英国大使が日本艦隊の欧州派遣を本野外相に要請。
2月:日本海軍が欧州派遣に向け第1・第2特務艦隊を編成。寺内内閣が欧州派遣を閣議決定。
3月:ロシア2月革命勃発。臨時政府を樹立し、ニコライ2世は退位、ロマノフ朝滅亡。
4月:アメリカがドイツに宣戦布告。レーニンが4月テーゼ。日本は衆議院総選挙。
5月:バレエ「パラード」パリで初演、台本コクトー、音楽サティ、美術ピカソが担当。
6月:第39議会召集。
7月:ロシア臨時政府首班にケレンスキーが就任。
8月:中華民国がドイツに宣戦布告。第11次イゾンツォの戦い。
9月:中華民国で孫文が広東軍政府を樹立。日本は金本位制が停止。関東大水害。
10月:第一次大戦 カポレットの戦い。
11月:ロシア(ロシア暦)10月革命(ボリシェビキ蜂起。ソヴィエト政権が樹立される。
12月:明治乳業(当時の社名極東練乳)創立。
細かいことは今は忘れられて、要するにヨーロッパは第1次世界大戦が続き、ロシアで大革命、日本はとくに戦争といっても南洋のドイツ領を奪っただけで、国内と国民は割合平和だった。ヨーロッパ諸国は戦争で疲弊し、皇帝を倒すロシア革命で出現した社会主義政権の衝撃が、世界を駆け巡った。そういう時代に生まれた思想史家・武田清子さんが、百歳を迎えて『世界』のインタビューで語っていた。
インタビュー武田清子氏に聞く「天皇観の相剋」と現代(聞き手・阿部菜穂子)
「近代日本思想史学者の武田清子さんが、この六月、百歳の誕生日を迎えた。武田さんは敗戦の廃墟の中で、太平洋戦争を深く反省し、日本の歩む道を探ることを目的に創刊された雑誌『思想の科学』の七人のメンバーのひとり、同人は丸山真男(政治学者)、鶴見俊輔(哲学者)、都留重人(経済学者)、鶴見和子(社会学者)各氏らで、戦後の日本を代表するリベラル教養人たちであった。サンフランシスコ講和条約締結のころには「全面講和」を主張する「平和問題懇話会」にも参加した。天皇制を生涯の研究課題とし、敗戦前後に日本の天皇制をめぐって連合国の間で起きた大きな議論を、一九七八年『天皇観の相剋』(岩波書店)として出版。著書は高く評価されて毎日出版文化賞を受けた。太平洋戦争をはさんで一世紀にわたる人生を歩み、日本の思想状況に大きな足跡を残した武田さん。戦前からのキリスト者として天皇制を厳しく見つめてきた武田さんに、現代を生きる日本人へのメッセージを聞いた。
(『天皇観の相剋』は、敗戦後の日本で天皇制を廃止させるのか、存続させるのか、天皇を裁判にかけるのか、かけないのか、など日本の天皇制をめぐって太平洋戦争中の一九四三年ごろから連合国の間で起きていた激しい議論を追い、まとめた本である。最終的に連合国は、天皇の戦争責任は問わず、日本の民主化遂行のために天皇を利用するという高度な政治判断を下したわけだが、武田さんは戦後、関係各国に出向いて当時の極秘資料を集め、まだ健在だった関係者にインタビューし、連合国がその判断にいたるまでの過程を克明に綴った。)
――敗戦時に連合国が天皇制を温存させるという政治判断をしたことについて、現在どのような考えをお持ちですか。
そうした判断がよかったのかどうか、についての答えはわかりません。でも、GHQ(連合国軍総司令部)が(天皇を利用して)民主化を実行したことは事実です。また、「象徴天皇」となった昭和天皇も、民主化の先頭に立って努力したと思います。ただ、私は“天皇制が温存された”という言い方は好きではありません。「天皇制」というと戦前の体制を意味することになりかねないからです。象徴天皇として、国民に仕えていくという「天皇の存在」が残った、と言った方がいいでしょう。
――そのような「象徴天皇」のあり方は、日本人自身が選択したものだったのでしょうか。
象徴という考え方はGHQの中にもあったと思いますが、それに呼応して「民主的な天皇」の意味を持つように実践していったのは、国民だったと思います。日本人は、象徴としての天皇をもつという、非常に賢明な選択をしたと思います。象徴天皇というのはひとつの民主主義の形です。
――国民が明確に「象徴天皇」を選択し、支持したということですね。
そうです。敗戦を経験して、国民と天皇自身がともに苦しんで、模索した結果だったと思います。戦前の天皇論ではない、民主的な天皇にするという努力です。それはどこの国のまねでもなく、日本独特の民主主義のあり方を探る道のりだったと思います。
( 中 略 )
(武田さんの指摘は、「大正デモクラシー」として現れたヒューマニズムやリベラリズム、社会主義の思想運動が知識階級にのみ限定されていたのではなく、文学運動や新教育運動、労働運動・農民運動・婦人運動などを伴って幅広い民衆の心の中に、人間尊重思想や自由主義思想の種をまいた、というものである。このような思想が、国体明徴運動と軍国主義のイデオロギーが支配していた時代にも、人々の日常の生活と心の深みに一つの地下水のような流れを形成し、それこそが連合国による戦後の「民主化政策」に対して内側から呼応して芽を噴き出させる要素だったのではないか、とみる。)
――それは実は、武田さんが「二頭立ての馬車」と呼ぶ、明治維新以来の近代日本の二重構造に根っこがあるわけですね? 一つは天皇を神格化・絶対化する側面、もう一つは天皇も憲法によって制限されるという制限君主的な側面です。前者は超国家主義につながる可能性をもち、後者は民主主義的、合理主義的要素であった、と。
そうです。時代によってそのどちらかがより強く表に出てくることがあります。だから国民が(民主的な希求を)心の中にもっているとしても、うっかりしているとつぶされてしまう可能性があります。それを守り続け、よりインプルーブ(改善)していかなければいけないと思います。
( 中 略 )
――最近の日本では、天皇を再び神格化しようという動きが強まっており、その「うっかりしているとつぶされる」という方向に向かっているかに見えます。「象徴天皇」も岐路にあるように見えます。
私は日本国民は全体として、今でも象徴としての天皇を望んでいると思います。象徴天皇という形が一番安全で、そういう天皇をなくしてしまうのではなく、あったほうが安心できると、大部分の国民が考えていると思います。象徴以上のものを天皇に求めるのは間違いです。でも、事実として天皇の存在が長く続いてきたわけですから、無理にそれを壊すこともないわけです。
( 中 略 )
――「二頭立ての馬車」の構造は実は今も、形を変えて続いているのではないでしょうか。戦前の国家神道は、占領軍によって破壊されたと言われましたが、実際は死ななかったわけですよね。
死ななかったかもしれないけれど、それが生き生きと活動をするというわけではありません。より民主化していくために、伝統主義の古い要素が顔をもたげるのをいつも警戒して、努力を続けることが必要なのではないでしょうか。
――天皇を象徴以上のものにしようとする動きが政権内部でも強まっている昨今の状況で、天皇自身が日本の民主主義を守る「防波堤」になっているという意見が聞かれます。
天皇が防波堤というより、日本の憲法が防波堤なんです。だから、憲法は守っていかなければなりません。
――「天皇制」のあるべき姿についてのモデルは、どこかにあるでしょうか。
モデルはどこにもありません。それぞれの国に独自の伝統と歴史があるわけですから、日本の独自のものをさぐり、伝統的なもののうち国体化させようとする要素は排除して、民主主義的な要素をよりインプルーブしていくことが大切だと思います。国民がそれをやっていかなければなりません。 ( 中 略 )
――日本の民主主義は大丈夫でしょうか。
大丈夫でしょうか、ではなくて、私たちがそれを守っていかなければいけません。たとえ首相が憲法を変えようとしているとしても、国民が守っていけばいいんです。常に反動化する危険性はあるわけですから、国民がそれを警戒してより民主化していくために何が必要かを正しく発見して学び、努力していかなければいけないと思います。
――最後に、現在の天皇家について何かひとこと。
天皇家では、秋篠宮家がお子さん二人を外に開かれ、リベラル・アーツの習得を勉学の目的とするICU(国際基督教大学)に行かせたのは、非常に面白いと思います。眞子内親王は高校生の時からオーストラリアやアイルランドに短期滞在し、ICU卒業後はイギリスのレスター大学大学院に留学しました。佳子内親王も今秋からイギリスのリーズ大学に留学するそうです。天皇家自身が日本の外に目を向け、違った価値や民主的な価値を取り入れようとしているわけですから、国民も努力しなければいけないと思います。日本の外の文化や違った価値観に目を向けて、学んでいく姿勢が大事です。天皇家を自分たちにいいように利用しようとする勢力には、そうさせないようにする国民の不断の努力が必要です。
武田さんは『天皇観の相剋』の最後に、「連合国による民主化政策の『共演者』となった日本人が、民主化の変革を積み重ね、明日の人類社会の形成にかかわる道を探し求めるために、そしてそれを未来に向かってさらに展開させていくために、『天皇』であれ『大統領』であれ地上の『絶対的権力』に支配される『臣』的存在には再び戻らず、みずから創作するドラマの主演者になっていく歩みはどういう道なのだろうか?」という問いを投げかけている。百歳を迎えた武田さんが、インタビューで「普遍的な価値に向かって常に現実を反省し、インプルーブしていく」と何度も言ったのは、四〇年前に自身が発した問いに通じるものであろう。
武田さんが生涯を通して問い続けてきたのは、伝統に根ざす、特殊で排他的な要素をも含む土着的価値の中のポジティブな要素を、いかにして普遍的な「民主的価値」にまで高めていくか、ということである。武田さんは二年前の『日本経済新聞』のインタビューで、個人的に親交のあったインドのネール元首相が戦後来日した際、武田さんに「日本が焼け跡から復興したのはすばらしい。ただ、日本人は良い方にも悪い方にも規律正しく集団で進むように見える。日本人の個の主体性はどこにあるのだろう」と尋ねたエピソードを紹介し、「鋭い問いで、現在につながる問題提起だと思います」と語っている(二〇一五年七月三一日付)。ネール元首相が指摘した「規律正しく集団で進む」のが日本の「伝統的価値」だとすれば、問われた「個の主体性」は、日本の土壌にまだしっかりと根付いていない普遍的価値であろう。この問いは今後も、引き続き検証されていかなければならない重要な課題のように思える。」岩波書店『世界』2017.10 pp.172-177.
『天皇観の相剋』は凄い本である。女性だから凄いというわけではないが、戦後の日本で社会科学の分野で第一級の仕事をした女性研究者といえば、この武田さん(1917-)と鶴見和子さん(1918-2006)、それに中根千枝さん(1926-)あたりがまずあがるだろう。武田さんは神戸女学院から22歳でアメリカに留学(1939年)、鶴見さんも津田英学塾から同じ年に21歳でアメリカ留学、コロンビア大学などで学ぶ。日米戦争の間、武田さんはアメリカに残り、鶴見さんは交換船で日本に戻ったが、二人より少し若い中根さんは戦後に津田英学塾から東大初の女子学生になる。この経歴だけ見ても「普通のお嬢さん」などではなく、とびきり優秀な女性だったわけだが、その仕事もスケールが大きくその後続世代への影響も大きかった。このインタビュアーも、しきりに現在の日本が戦前に回帰するような憲法否定の動きになっていることを不安に思い、武田さんにそのへんを尋ねるのだが、武田さんは日本人はそれほど愚かではないし、憲法の価値を理解しているので、天皇制をどう考えるかを含め、きちんと議論し覚悟をもって自由と民主主義を守っていかなくてはいけない、と語る。しかし、今の日本人の多くはこの国の未来に自信を失って動揺しているのではなかろうか。
安倍政権はついに憲法を変えるという一点を目指して、無謀な解散総選挙をやる。ここで有権者の覚悟が問われるチャンスなのだから、正面から議論してこの誤った政治を変えられるか?

B.何が気に食わないのか?
日本の伝統の中心に天皇を置き、万世一系を何より大事にする右翼思想では、飛鳥・奈良時代より朝鮮と中国の文明をつねに意識し、それと比較対象してヤマトのアイデンティティをいかに確保するかに心を砕いていたと思う。この国が東アジアの文明圏のなかで、独自性を主張するには中華文明を学習しつつ固有の依代(よりしろ)として大和の王権、スメラギを掲げて古代国家を樹立する努力が求められた。ぼくたちは日本の歴史を子どもたちに教えるとき、この日本、朝鮮半島、中国という基本構図を踏まえて、先人が世界をどう捉えていたのか、漢字文化圏の周辺で日本の識字インテリジェントが、この国をどうデザインしようとしたのか、みんなで知って考えることがとっても大事だと思う。でも、ぼくたちは朝鮮半島の歴史や中国の王朝の歴史について、学校で歴史の時間にさらっと教えられてはいるが、西洋史に対するより東洋にあまり興味をもたない。
そのことが21世紀の現代のシビアな問題、たとえば金正恩の北朝鮮が危険なミサイルを撃ち込んでくるかも、という恐怖に対して、ただ怯えたり興奮して戦争をやってしまえ!と即自的反応に走ることは何も考えていないに等しい愚劣でしかない。いわゆる「嫌韓・嫌中」「反日左翼を叩き潰せ」と叫んでいるネトウヨの人たちは、どうも東アジアの長い歴史や、せめて明治維新以来の日本が近隣アジアに対して何をやってきたかの基本的な知識もなにも知らないし、知る気もない。ある問題について何かを発言するには、少なくともその問題に関わる基本的な事実認識とそれをめぐる対立的な議論の要点を知った上で発言しなければ、ただの戯言、無意味な冗談に過ぎないのですね。そのことの格好の事例がまた出た。それは、天皇皇后夫妻が、私的な旅行として先日埼玉県の高麗神社に参拝したというささやかなニュースをめぐって、早速極右らしきコメントが、平成天皇ご夫妻をも朝鮮中国に同情的な「反日左翼」に汚染された敵であると、口汚く攻撃する書き込みになってネットに登場したのには驚いた。
いったいどういう立場から現行天皇すら否定する言論が右翼から可能になるのか?要するにただ単純に朝鮮と中国が憎いという素朴な心情だけに依拠して、歴史も国際政治の現実も無視した(というよりこの人たちは歴史に無知なだけの)ファナティックな発言がなされている。まともに相手をする人たちではないけれど、なぜそんなに朝鮮や中国を嫌うのか、はいちおう考える必要はあると思う。彼らが言うことの根拠は、朝鮮韓国や中国人がことあるごとに日本を悪の帝国として、頭から否定し、慰安婦問題や南京虐殺を持ち出して日本人が邪悪な悪者だという立場から一方的に、謝罪や賠償を要求するのが許せない我慢できない、ということでしょう。日韓条約や日中平和友好条約で外交的には戦後の処理は終わっていて、今さら過去のあれこれにいちゃもんつけられる筋合いはない。どうして冷静に未来志向の友好関係を実現することができないのか?というのが安倍政権のスタンスだろう。でも、もう少しお互いの「歴史的記憶」を丁寧に学ぶことも必要だと思う。
「明仁天皇は日ごろから『韓中の文化が伝わってきて今日の日本になった』と考えていらっしゃると聞いている。今回の訪問をきっかけに、韓国についてよく知らなかった一般の人々も関心を持つようになるだろう」と語った。
同日午後4時に明仁天皇一行が高麗神社を出る「20日昼12時、明仁天皇と美智子皇后が、歴代の天皇では初めて埼玉県日高市の高麗(こま)神社を訪問した。1300年前に日本に渡った高句麗の王子「高若光」(日本名:高麗若光〈こまのじゃっこう〉)を祀っている。
明仁天皇訪問のニュースを聞き、歓迎する人々が朝から約2000人集まったことから、地元の駅と同神社を結ぶ1.7キロメートルの道は大変な混雑になった。60-70代の人々が参道沿いに小さな折り畳みいすやマットを広げて座り、明仁天皇を待っていた。日本の宮内庁は明仁天皇の高麗神社訪問について「公務ではなく私的な旅行」と説明している。明仁天皇は1年のうち250-270日公務を行うため、私的な旅行を楽しむ機会は1年に1・2回だ。高麗神社への旅は明仁天 皇の意思や希望を反映して決定されたという。
明仁天皇は日ごろから日本の過去について心から申し訳ないと考えて、韓日古代交流史にも関心が高いと言われている。2001年には「桓武天皇の生母が百済の王族だったと記されている」と発言して話題になった。05年には、太平洋戦争で戦地となった東南アジア諸国や南太平洋の島を訪れた際、朝鮮人犠牲者の慰霊碑をわざわざ訪れて黙とうしている。
明仁天皇と美智子皇后は同日、高句麗の王子から60代目となる高麗文康宮司(50)の案内で境内を見て回った。高麗文康宮司は「両陛下とも朝鮮半島から文明がやって来た過程に深い関心を持っていらっしゃると聞いていたが、実際に、高句麗人と百済人はどう違うのかなどいろいろと質問を受けたので、知っていることをお答えした」と語った。
日本で高麗神社は「出世明神」としても有名だ。斉藤実(1858-1936年)ら歴代首相6人がここに来て参拝後、首相になったという話もある。だが、ある住民は「それでも今日のように、一度に多くの人々が集まったことはない」と教えてくれた。
皇室を20年間取材している毎日新聞の大久保和夫記者は、明仁天皇について「日本国民が『心温かい』と感じ、敬愛している方だ。神社の外でずっと待っていた人々もそれぞれ帰り始めた。その中にいたキモトマユミさんは「高句麗人をまつった神社を訪れた意味をいろいろと考えてみたが、『近い国・韓国とはやはり共に行くべきだ』という意味ではないかと思った」と言った。日高市(埼玉)=イ・ドンフィ特派員 (朝鮮日報/朝鮮日報日本語版)」
これを報じているのが韓国のメディアだというだけで、反日左翼の陰謀に乗せられた天皇、というありもしない話を作り上げて勝手に頭にきているのだろう。
朝鮮の歴史で三国時代というのは、4世紀から7世紀ごろに朝鮮半島と満州南部に高句麗、百済、新羅の三国が鼎立した時代をいう。220年の後漢の滅亡が、三国の発展を許した。三国のうち最大であった高句麗は、鴨緑江沿いの国内城とその山城である丸都城の二つの並存された都をもっていた。新羅は唐と結んで、660年に百済を668年に高句麗を滅ぼした。これによって三国時代は終わり、滅ぼされた百済の王族は日本に逃れ、百済王の姓を賜り、高句麗の王族も海を越えて日本に亡命し定住した人々がいた。日本人はこの人々から先進文明を学び、大和の律令制国家をデザインした。それは歴史の大事な出来事であり、日本人もリスペクトして記憶してきた過去の歴史である。
それを朝鮮人は敵、中国人は悪という民族的偏見を感情的根拠にして、口汚く罵って右翼のシンボルである天皇夫妻すら「反日」のレッテルを貼って貶める。もはや1300年前に滅んだ高句麗と、21世紀の朝鮮半島とを混同するデタラメは救いがたい。でも、これを見ていたら、もう日本の右翼は精神の支柱すら空洞化して滅びに向かうのではないかと逆に心配になった。彼らの言い方を聴いていると、皇居ではなく靖国神社、戦災の死者ではなく特攻隊、伝統の尊重より排外憎悪だけに凝り固まった言葉しか聞こえず、偏狭というより無知だけが際立つ。日本のナショナリズムの伝統を知っていれば、楠木正成、吉田松陰、西郷隆盛から東郷平八郎、乃木希典という人々に流れていた尊王の精神を、受け継ぐ気概と理想をこそ語るべきなのに、君たちは異民族をけなして喜んでいるだけではないか。