写真と本文は関係ありません。それにしてもなぜ今頃白いタンポポなのか?
老人介護は 他人事じゃない

人間、自分の身に火の粉が降りかかってはじめて
それが大きな問題であることに気づく
在宅介護
いじめ
等々
当事者でなければわからない
当事者でなければわからないことなのか
という反論も返ってくる
当事者でなくても
当事者の痛みや苦悩、不安をどこまで感じとり
わかりあおうと意識しているか
ケアマネジャーも人間
様々なタイプのケアマネジャーがいる
勤務時間は8:30~17:30、土日・祝日は休み
大きな組織の居宅介護支援事業所ほど、勤務時間外は、対応しないところが多い
(対応するところもある?)
在宅を訪れ、宅急便ではないが利用票に印鑑をもらうだけで終わるケアマネジャーもいる
しかし、「それでいいのか~」、とバカボンの声が聴こえてくる
在宅介護者は24時間、ひとり暮らし老人、老老介護(高齢者世帯)も含め
勤務時間外に急変や突発な事故に遭遇したときまで
関わっていたらケアマネジャーの身がもたない
本当にいま緊急時のときだったら
「救急車を呼べば~」と話す人もいるが
家族介護者にしてみれば救急車を呼ぶかどうかもわからず、慌ててしまうのが実情
そのようなとき、「いつでも困ったときは夜間でもよいから電話下さい」の声かけがあれば
家族介護者は心強い
手前味噌だが拙者の場合は、たった一人の居宅介護支援事業所(株式会社として法人格を持っている)
24時間対応、深夜でも夜明けでも電話があれば駆けつける
介護相談は介護者が仕事や夕食の介助を終えた後で、訪問する(17:30以降も対応。20時の場合もある、土曜、祝日は対応)
(サービス担当者会議は、事業所の協力も頂き18:00開催もある)
(最近、無理できない身になり、緊急時以外は日曜は休みにしている)
私自身
老い先10年後の自分は
後期高齢者になる
病いもあり
高熱続きや交通事故でいつ人工透析に戻るかわからない
免疫抑制剤の副作用で骨粗鬆症が進行
骨粗鬆症が有るが故に今回チョッとした転倒により肋骨骨折
年齢相応の物忘れはある、自分も認知症老人になるのかな・・・・
老人は大腿骨骨折で入院すると、退院時には歩行困難またはふらつき歩行と認知症が出現
転ばぬ先は杖だが
転んだ先は認知症となり要介護
だから老いになると
いつ要介護になるかわからない
それだけに
老人介護は他人事ではなく
自分のことになるかもしれない
そう脅しをかけるような話であってはいけないけれど
言いたいことは
いまから在宅介護のことや介護保険サービスについて
自分が棲む市町村や町内ではどうなっているか
関心を持つことも大切
認知症サポーターでもよい
介護に関わる人々と顔見知りになる(つながりを持つ)ことが大切
顔見知りになるなかで、
老人や在宅介護者のことを本当に親身になってケアマネをしている人を見つける
介護相談が必要になったとき
自分だけでなく
近所でも
在宅介護になったとき
介護の顔見知りのケアマネジャーが頭に浮かぶ











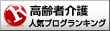


 生理的欲求と介護⑥ 「睡眠」ⅰ
生理的欲求と介護⑥ 「睡眠」ⅰ















