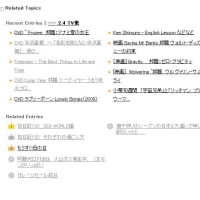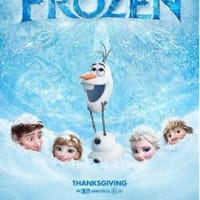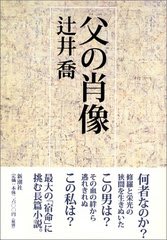
[辻井喬2冊目の挑戦]
作家辻井喬(ご存知、堤清二)といいますと最初に読んだのは「虹の岬」(1994年 谷崎潤一郎賞受賞)です。 簡単にいうと不倫の話(経済人にして歌人の川田順と、弟子である京大教授夫人の恋)で、内容に興味を持てず読み進めるのに時間がかかり殆ど根性で読み終えたという記憶がありました....川田順の生涯ということで私の父が(この本は)面白かったといっていたのを思い出します。
[オークションで購入]
おとどし(2004年)の日経新聞11月28日号に文芸評論家 清水良典氏の「父の肖像 」の書評『愛されなかった「私」の視線』が掲載され、「財政界に疎い評者のような者でさえ無類の興味深さで読み終えた.....」と書いてあったので、とてもよみたくなり、その書評を切り取って保存していました。 .......単行本を2600円で買うのは、本を大量買いする私にはちょっと高価なため......半年ほどたってから日本のオークションで1000円で落札し、送り先を実家にしてもらい、昨年夏日本に帰った際、ブリスベンにもってきました。 発刊後2年たったいまでは、もっと安くで購入することも可能でしょう。
」の書評『愛されなかった「私」の視線』が掲載され、「財政界に疎い評者のような者でさえ無類の興味深さで読み終えた.....」と書いてあったので、とてもよみたくなり、その書評を切り取って保存していました。 .......単行本を2600円で買うのは、本を大量買いする私にはちょっと高価なため......半年ほどたってから日本のオークションで1000円で落札し、送り先を実家にしてもらい、昨年夏日本に帰った際、ブリスベンにもってきました。 発刊後2年たったいまでは、もっと安くで購入することも可能でしょう。
そしていろいろな本をよんだあと昨年11月にやっとこの本を読む順番がまわってきて...それからさらに他の本も平行して読んだりして....この本は本日 3月26日やっと読み終えました。 645ページ。 ハリーポッター並です^^; この本がなければ5ヶ月間にもっとたくさんの本を読んでいたと思います...「虹の岬」と一緒で読み進めるのに時間がかかりました。
楠次郎の生涯を息子、恭次の目を通してかいてあります。 小説とはいいましても、西武の創始者堤康次郎と堤清二のこととして読んでよいものだと思います...を現在セゾン文化財団理事長で元セゾングループ総裁(?)で詩人でもある堤清二氏(辻井喬)が著しています。 野間文芸賞も受賞しています。
この本は「新潮」2000年10月号から2004年3月15日に連載されたものがまとまっています。 義理の弟の堤義明氏(本書の中では楠清明)が証券取引法違反が発覚-それについてはふれてありませんが-した2004年3月(くらい?)でおしまいになっているのは偶然でしょうか。
2005年にでた「Nikkei Business 2005年3月14日号」の特集『追放「堤支配終わりのあと-土地」』の中で堤清二氏はしっかりと、家にはいつも7-80本の名義株に使う判子があった、といっています.....「父の肖像」は厚い本ですが、書けなかったこともたくさんあったに違いないと推測されます。
[感想]
ということで、私の感想は戦前、戦後の昭和の政治と経済の流れがよくわかった(???....実は文字は追うには追いましたが頭には全くはいらなかった)ということと、堤家を財政的に成功させた堤康次郎は政治家をしながら箱根や国立付近を学園都市として開発したりとすごい。<=われながら情けない表現。 昼間はタバコの会社を運営しながら夜は船会社を立ち上げるために働いたというオナシスを思い起しました....やはり創業者というのは人一倍も二倍も働いているのか...と。しかも膀胱炎という持病を背負いながらです。 康次郎に奥さんは一人という意識がなかったのもわかるような、わからない、ような。。。これだけ肩書きと責任を抱えると、家族を見るのは不可能だったのか......最終的には少なくとも5人の女性との間に7人の子供がうまれています。 文献によっては、手当たり次第、という言葉も。。
東急の創始者で康次郎のライバル(敵?)でもあった五島慶太といい、昔の人は経済界の重鎮が政界にもポジションをもつということが当たり前のようにあったんですね。 この本を読む限りでは箱根を最初に開発しようとして鉄道などに投資してきたのは康次郎の方なので、私は箱根戦争(五島慶太は東急会長でしたが、箱根開発に関し小田急側の代表をつとめた)に関しては西武に軍配があがるのではと思ってしまいました。 まだちぐはぐらしいのですが、今ではフリーパスなど少しづつ業務提携が進んでいる(Wikipedia 「箱根戦争」)のだそうです。
康次郎氏が清二氏でなく義明氏に事業の大部分を引き継がせたのもわかるような気がします。 義明氏はひがみっぽい人間であるように描かれていますが、清二氏よりは欠点が人間らしい感じです。 といっても、義明氏の逮捕により堤家の西武支配は終わってしまったのですけど。 清二氏だったらこういう結末にはならなかったでしょうが、西武がどうなっていたかはわかりません。
この本がいいたかったことは私の感想にはひとつも含まれてないと思います。。。。ということで清水良典氏の書評を以下にどうそ!
[清水良典氏の書評より]
『(略)......本書は堤康次郎の評伝としての機能に自足していない。 「楠次郎」と名を替えられた彼の生涯を鳥瞰的に辿る記述だけでなく、「父」とは何者か、ひいてはその父につながる「私」とは何者かという問いかけに憑かれた手記が平行する複眼構造になっている。 それというのも一面では歴史的人物といっていい楠次郎は、「私」にとっては自分の出生を歪めた張本人であると同時に、反感と嫌悪を抱かずにいられない宿敵でもあったからである.....(中略)...自分は何者なのか、という自問の運動は、本書の中では実は父と息子をつなぐ架け橋であるように見える....(中略).....趣味や家庭に寛ぐ余裕を一瞬も自分に許さなかった楠次郎の人生の負の姿が、ふぞの愛を受けることのなかった「私」の視線によって炙りだされる....』以下略
[Amazonにおける内容紹介]
内容(「BOOK」データベースより)
近江商人の末裔たる誇り高き田舎者にして大隈重信の末弟子、政治家らしからぬ政治家にして専横独裁の実業家、徹底した現実主義者にして時代の理想を追求し続ける者、私の父にして私の宿敵―。果して何者なのか?地縁と血の絆、修羅と栄光の狭間をひたすら生きたこの男は?この男の血を受けた運命から逃れきれないでいるこの私は?最大の「宿命」に挑む長篇小説。
人気blogランキングへ!
作家辻井喬(ご存知、堤清二)といいますと最初に読んだのは「虹の岬」(1994年 谷崎潤一郎賞受賞)です。 簡単にいうと不倫の話(経済人にして歌人の川田順と、弟子である京大教授夫人の恋)で、内容に興味を持てず読み進めるのに時間がかかり殆ど根性で読み終えたという記憶がありました....川田順の生涯ということで私の父が(この本は)面白かったといっていたのを思い出します。
[オークションで購入]
おとどし(2004年)の日経新聞11月28日号に文芸評論家 清水良典氏の「父の肖像
そしていろいろな本をよんだあと昨年11月にやっとこの本を読む順番がまわってきて...それからさらに他の本も平行して読んだりして....この本は本日 3月26日やっと読み終えました。 645ページ。 ハリーポッター並です^^; この本がなければ5ヶ月間にもっとたくさんの本を読んでいたと思います...「虹の岬」と一緒で読み進めるのに時間がかかりました。
楠次郎の生涯を息子、恭次の目を通してかいてあります。 小説とはいいましても、西武の創始者堤康次郎と堤清二のこととして読んでよいものだと思います...を現在セゾン文化財団理事長で元セゾングループ総裁(?)で詩人でもある堤清二氏(辻井喬)が著しています。 野間文芸賞も受賞しています。
この本は「新潮」2000年10月号から2004年3月15日に連載されたものがまとまっています。 義理の弟の堤義明氏(本書の中では楠清明)が証券取引法違反が発覚-それについてはふれてありませんが-した2004年3月(くらい?)でおしまいになっているのは偶然でしょうか。
2005年にでた「Nikkei Business 2005年3月14日号」の特集『追放「堤支配終わりのあと-土地」』の中で堤清二氏はしっかりと、家にはいつも7-80本の名義株に使う判子があった、といっています.....「父の肖像」は厚い本ですが、書けなかったこともたくさんあったに違いないと推測されます。
[感想]
ということで、私の感想は戦前、戦後の昭和の政治と経済の流れがよくわかった(???....実は文字は追うには追いましたが頭には全くはいらなかった)ということと、堤家を財政的に成功させた堤康次郎は政治家をしながら箱根や国立付近を学園都市として開発したりとすごい。<=われながら情けない表現。 昼間はタバコの会社を運営しながら夜は船会社を立ち上げるために働いたというオナシスを思い起しました....やはり創業者というのは人一倍も二倍も働いているのか...と。しかも膀胱炎という持病を背負いながらです。 康次郎に奥さんは一人という意識がなかったのもわかるような、わからない、ような。。。これだけ肩書きと責任を抱えると、家族を見るのは不可能だったのか......最終的には少なくとも5人の女性との間に7人の子供がうまれています。 文献によっては、手当たり次第、という言葉も。。
東急の創始者で康次郎のライバル(敵?)でもあった五島慶太といい、昔の人は経済界の重鎮が政界にもポジションをもつということが当たり前のようにあったんですね。 この本を読む限りでは箱根を最初に開発しようとして鉄道などに投資してきたのは康次郎の方なので、私は箱根戦争(五島慶太は東急会長でしたが、箱根開発に関し小田急側の代表をつとめた)に関しては西武に軍配があがるのではと思ってしまいました。 まだちぐはぐらしいのですが、今ではフリーパスなど少しづつ業務提携が進んでいる(Wikipedia 「箱根戦争」)のだそうです。
康次郎氏が清二氏でなく義明氏に事業の大部分を引き継がせたのもわかるような気がします。 義明氏はひがみっぽい人間であるように描かれていますが、清二氏よりは欠点が人間らしい感じです。 といっても、義明氏の逮捕により堤家の西武支配は終わってしまったのですけど。 清二氏だったらこういう結末にはならなかったでしょうが、西武がどうなっていたかはわかりません。
この本がいいたかったことは私の感想にはひとつも含まれてないと思います。。。。ということで清水良典氏の書評を以下にどうそ!
[清水良典氏の書評より]
『(略)......本書は堤康次郎の評伝としての機能に自足していない。 「楠次郎」と名を替えられた彼の生涯を鳥瞰的に辿る記述だけでなく、「父」とは何者か、ひいてはその父につながる「私」とは何者かという問いかけに憑かれた手記が平行する複眼構造になっている。 それというのも一面では歴史的人物といっていい楠次郎は、「私」にとっては自分の出生を歪めた張本人であると同時に、反感と嫌悪を抱かずにいられない宿敵でもあったからである.....(中略)...自分は何者なのか、という自問の運動は、本書の中では実は父と息子をつなぐ架け橋であるように見える....(中略).....趣味や家庭に寛ぐ余裕を一瞬も自分に許さなかった楠次郎の人生の負の姿が、ふぞの愛を受けることのなかった「私」の視線によって炙りだされる....』以下略
[Amazonにおける内容紹介]
内容(「BOOK」データベースより)
近江商人の末裔たる誇り高き田舎者にして大隈重信の末弟子、政治家らしからぬ政治家にして専横独裁の実業家、徹底した現実主義者にして時代の理想を追求し続ける者、私の父にして私の宿敵―。果して何者なのか?地縁と血の絆、修羅と栄光の狭間をひたすら生きたこの男は?この男の血を受けた運命から逃れきれないでいるこの私は?最大の「宿命」に挑む長篇小説。
人気blogランキングへ!