<日立ヴァンタラIoT事業売上高は日立製作所売上高寄与率はいくらか>
<米国政府輸出管理規則に従い、米国IoT生産技術は日本や中国等の第三国への移転は不可能か(注1)>
(注1)IBM産業スパイ事件
<エレベーターやエスカレーターなどの保守サービス、銀行や自治体のシステムエンジニア、工場勤務の従業員の売上高は日立製作所売上高寄与率はいくらか>
<効率が上がったは理由は上部多段階層へ説明時間が短縮したことか>
<成長する事業の定義は日立製作所売上高寄与率50%以上か>
<中畑英信執行役専務は、次の株主総会で日立ヴァンタラ社長に転出か>
<東洋経済さんにはうそをつかない正直者のお手伝いさん5W3H8人居るんだよ
その者達の名前は1.「なに? (What) 」さん、2.「なぜ? (Why) 」さん、3.「いつ? (When) 」さん、4.「どこ? (Where) 」さん、5.「どんなふうに? (How) 」さん、それから「だれ? (Who) 」さんと言うんだよ。更に、6.誰に(Whom)7.どのくらいの数で(How many)8.いくらで(How much)
「東洋経済さん “正直者のお手伝いさん5W1H”6人探し連れてきください」
https://ja.wikipedia.org/wiki/5W1H
その者達の名前は1.「なに? (What) 」さん、2.「なぜ? (Why) 」さん、3.「いつ? (When) 」さん、4.「どこ? (Where) 」さん、5.「どんなふうに? (How) 」さん、それから「だれ? (Who) 」さんと言うんだよ。更に、6.誰に(Whom)7.どのくらいの数で(How many)8.いくらで(How much)
「東洋経済さん “正直者のお手伝いさん5W1H”6人探し連れてきください」
https://ja.wikipedia.org/wiki/5W1H
::::::
2020/07/01 5:30
冨岡 耕(とみおか こう)Ko Tomioka
東洋経済 記者
重電・電機業界担当。早稲田大学理工学部卒。全国紙の新聞記者を経て東洋経済新報社入社。『会社四季報』編集部、『週刊東洋経済』編集部などにも所属し、現在は編集局報道部。直近はトヨタを中心に自動車業界を担当していた。
:::::
コロナ禍をきっかけに、働き方が大きく変わる可能性が出ている。
日立製作所は感染の収束後も、社員の働き方は在宅勤務を標準としていく方針を発表した。在宅勤務そのものが目的ではなく、在宅勤務を変革のドライバーとして、1人ひとりの仕事・役割と期待成果を明確にする欧米流の「ジョブ型人財マネジメント」への転換を加速するためだ。
日立はリーマンショック時に7873億円という国内製造業で過去最悪となる最終赤字を計上。川村隆元会長兼社長(前東京電力ホールディングス会長)、中西宏明会長(日本経団連会長)、東原敏昭社長の歴代3トップのもとで、10年以上にわたって事業の選択と集中を大胆に進めてきた。
日立製作所は感染の収束後も、社員の働き方は在宅勤務を標準としていく方針を発表した。在宅勤務そのものが目的ではなく、在宅勤務を変革のドライバーとして、1人ひとりの仕事・役割と期待成果を明確にする欧米流の「ジョブ型人財マネジメント」への転換を加速するためだ。
日立はリーマンショック時に7873億円という国内製造業で過去最悪となる最終赤字を計上。川村隆元会長兼社長(前東京電力ホールディングス会長)、中西宏明会長(日本経団連会長)、東原敏昭社長の歴代3トップのもとで、10年以上にわたって事業の選択と集中を大胆に進めてきた。
同時に、グローバルトップ企業を目指して優秀な外部人材獲得に向けたジョブ型への働き方改革を進めてきた。
日立の働き方改革を推進してきたCHRO(最高人事責任者)の中畑英信執行役専務
日立の働き方改革を推進してきたCHRO(最高人事責任者)の中畑英信執行役専務
<
なかはた・ひでのぶ/1961年生まれ。59歳。大分県出身。1983年九州大学法学部卒業後、日立製作所入社。主に人事畑を歩み、2014年執行役常務CHRO兼人財統括本部長。2020年4月から現職(写真:日立製作所)
>
に在宅勤務導入の狙いを聞いた。
――新型コロナウイルスが収束した後も、2021年4月以降は「週に2~3日、(勤務日の)50%程度を在宅勤務にする」方針を発表しました。その狙いは何でしょうか。
事業のグローバル化を今後進めるうえで、多様な人材や働き方が必要になるからだ。
優秀な人材を広く採用するためには、日本に多い(年功序列型の人事制度である)「メンバーシップ型雇用」ではなく、職務(仕事の内容)を明確にし、そこに適切な人材を配置する、海外で主流の「ジョブ型雇用」が必須と考えている。
そのためには場所も時間も超えて仕事をする必要があり、それが在宅勤務にもつながる。今後、本格的な運用へ向けて労使で話し合いをしていく。
――なぜ5割なのですか?
外出自粛期間中は在宅勤務率が9割と高かったが、今後はおそらく出社が増える。今回、在宅勤務について3万人を対象に社内調査をしたが、いろんな意見が出た。「効率が上がった」「あまり変わらない」が半分。一方で「効率が少し下がった」という意見が4割ぐらいあった。
効率が下がった理由の1つはIT環境。パソコンの処理速度が遅い。2つ目はダイレクトコミュニケーションができないので(仕事が)やりにくいということだ。これらの課題はある程度残るため、外出自粛期間中のように高い在宅勤務率の確保は難しいと思っている。アメリカにある子会社の日立ヴァンタラ
<日立製作所の米国子会社、日立データシステムズ(HDS)が日立ヴァンタラに衣替えして1年。ストレージの販売会社をIoT(Internet of Things)ソリューション企業に変えるため、大胆な施策を断行してきた。日立の東原敏昭社長兼CEO (最高経営責任者)は「この1年で人材を劇的に入れ替えた」と明かす。
日立ヴァンタラは
2017年9月に、HDSとBI(ビジネスインテリジェンス)ツールのベンダーで2015年にHDSが買収した米ペンタホ(Pentaho)が統合して生まれた会社だ。それから1年たった2018年9月26~27日(米国時間)、日立ヴァンタラは米サンディエゴで年次カンファレンス「Hitachi NEXT 2018」を開催。親会社である日立の東原社長兼CEOが基調講演に登壇し、米国の顧客にIoTプラットフォーム「Lumada」を中心とするソリューションを売り込んだ。
>
は、平時でだいたい6割ぐらいが在宅勤務をしており、それぐらいが目安になるとみている。
もちろん出社をしないと難しい人もいる。エレベーターやエスカレーターなどの保守サービス、銀行や自治体のシステムエンジニア、工場勤務の従業員がそうだ。エンジニアでも大容量データを扱う場合、家のパソコンでは限界がある。そういう出社せざるをえない人々には手当を別途出していく。
――ジョブ型雇用へ転換加速するきっかけが在宅勤務になるのでしょうか。
そうだ。いわゆる新卒で仕事を決めずに入って、人に仕事をつけて社内で育成し、ローテーション(異動)しながらポストが上がっていき、最後は定年という形にはもうしたくない。こうしたメンバーシップ型(の雇用)ではなく、仕事に人をつける形にしたい。それがジョブ型だ。
多様な人材は日立の中だけでなく、外部にもたくさんいる。そうした人を採用するためにはジョブ型が欠かせない。今の日本は300万人ぐらいの転職市場があるとされるが、それでもまだ流動性が少ない。転職時のハードルが高くなるのは、メンバーシップ型雇用の企業がほとんどだからだ。
1つの会社でずっと育っている人が多い中に、外から入っていくのはかなりのチャレンジになる。そこでは仕事もあまり明確になっていない。これをジョブ型に変えれば、転職もしやすくなる。
――具体的にどのようにしてジョブ型へ転換させていくのですか。
今、日立ではジョブディスクリプション(職務記述書)を作っている。会社は「このポジションはこんな仕事で、こんな経験やスキルが必要です」とオープンにする。
社員にも自分のやりたい仕事や保有するスキル、キャリアプランなどを書いてもらう。自分のスキルと見比べて自分でやりたい仕事に手を上げるようにする。10人ぐらい集まると、その中から会社が最適な人をアサインする。それは年齢に関係ない。あくまでも経験やスキルで選ぶ。そうすると優秀な人材が最適なポジションにいくことになり、アウトプット(成果)が出るはずだ。生産性も上がるだろう。
日本企業の生産性が上がっていない最大の理由は、成長する事業に人を持っていけていないからだ。
企業には残念ながらこれ以上伸びない事業もあるが、そこが意外と忙しい。
利益があがらないのに、そういう事業に限って優秀な人材が張りついているケースがある。日本全体でも日立でもそうで、それを解消していきたい。











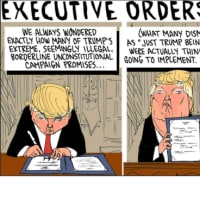



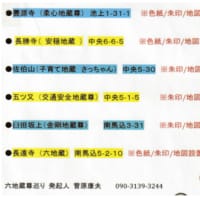

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます