〇熱中症に打ち勝つ食事#NG食習慣#おすすめの食べ物#便利なコンビニ食材を#管理栄養士が徹底解説サイト
https://www.happiness-direct.com/shop/pg/1h-vol261/
https://www.happiness-direct.com/shop/pg/1h-vol261/
【1】クエン酸を多く含む食べ物=梅干し=で熱中症対策
【1.1】中国梅加工業の対日輸出と品質管理システムの課題
【1.1】中国梅加工業の対日輸出と品質管理システムの課題
Ⅱ日本の梅輸入の拡大と問題点
・・・
こ の ように輸出量を拡大してきた中国梅産業だが 、近年発生 した基準値を上回る残留農薬の検出や、無認可添加物の使用といっ た問題も一方では発生 してい る。
具体的には、残留農薬問題では漬物メ ーカ ーや 業界団体の 自主検査の 段階で 、 基準値以上の残留農薬が検出されてお り、 無認可添加物の使用問題では、 食品衛生法で無認可のサイクラミン酸の添加が確認され、輸入販売業者が摘発される事件が発生 してい る。
・・・
[農業市場研究 第13巻第 2号 (通巻60号)2004,12]103
https://www.jstage.jst.go.jp/article/amsj/13/2/13_KJ00009596696/_pdf
[農業市場研究 第13巻第 2号 (通巻60号)2004,12]103
https://www.jstage.jst.go.jp/article/amsj/13/2/13_KJ00009596696/_pdf
【1.2】新たな課題に直面する和歌山県の梅生産
・・・
・・・
しかし、中国産の梅を使用しているにもかかわらず、和歌山県内で加工して「和歌山県産」と表示するなどの問題が発生したため、
政府は01年より梅に関し原料原産地表示を義務付けた。
また、その後、消費の減少に加え中国産食品の安全性問題が発生したこともあり、
また、その後、消費の減少に加え中国産食品の安全性問題が発生したこともあり、
梅の輸入量は減少に転じたが、
13年においても23千トンを輸入しており、供給量全体の3割近くを輸入品が占めている。
13年においても23千トンを輸入しており、供給量全体の3割近くを輸入品が占めている。
【1.3】2023年8月 9日 (水)#紀州南高梅に発がん性物質混入?
・・・
・・・
私は4年前にがんになり、なんとか一命をとりとめた。
その命=「食は生きる力!今日も元気に頂きます」=を大事にしたい。
だから口に入れる食品は、
その命=「食は生きる力!今日も元気に頂きます」=を大事にしたい。
だから口に入れる食品は、
①疑わしきは避ける。
➁君子危うきに近寄らず。
【2.1】群馬県は梅の生産量が東日本一で、全国でも和歌山県に次いで2位の梅の産地です。
株式会社コマックスの梅干のほとんどは、『昔ながら』をモットーに、調味料は一切使用していない『こだわりの梅干』です。
おにぎりはもちろん、焼酎のお湯割りも美味しく召し上がっていただけるものと思います。
https://www.komax-shop.co.jp/company.html
株式会社コマックスの梅干のほとんどは、『昔ながら』をモットーに、調味料は一切使用していない『こだわりの梅干』です。
おにぎりはもちろん、焼酎のお湯割りも美味しく召し上がっていただけるものと思います。
https://www.komax-shop.co.jp/company.html
【2.2】ぐんまのかあちゃんが作った無添加にこだわった上州そだちの逸品”梅干し”、
上州屋梅店・代表者・戸塚 裕子・TEL:027-371-5341、群馬県高崎市箕郷町富岡1039-1
https://item.rakuten.co.jp/jousiuya/ume_01a/
https://item.rakuten.co.jp/jousiuya/ume_01a/

【2.3】熱中症に打ち勝つ食べ物 の地産・地消は日本のGDP=日本がもうけた金額=
①政府支出(政府が使った金額)+民需(➁日本人の消費金額+➂国内企業の投資額の合計)+④貿易収支(輸出額-輸入額)=
向上に寄与しています。












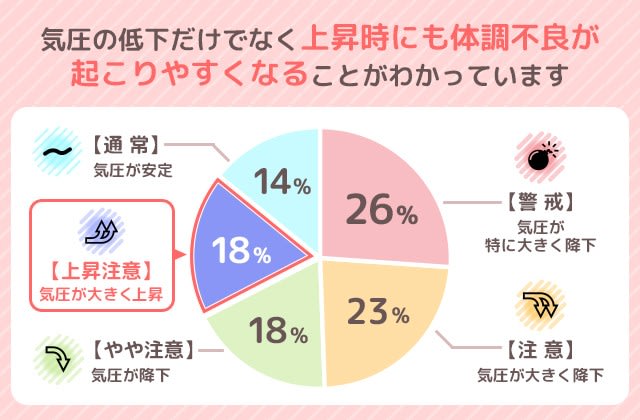



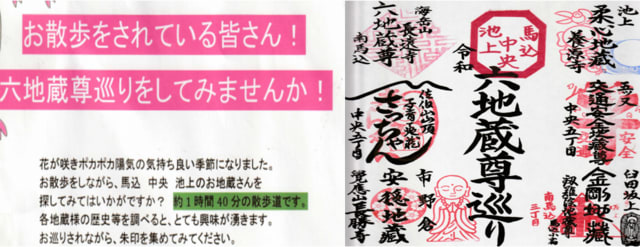
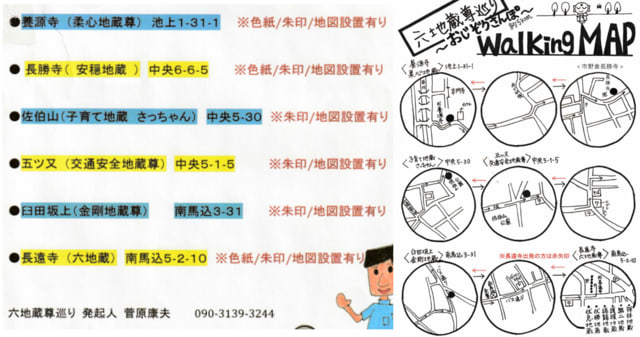 メリットとデメリットがある紫外線。
メリットとデメリットがある紫外線。

