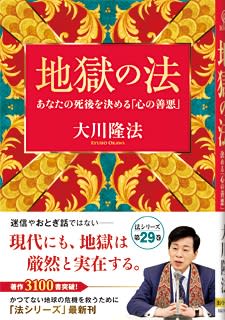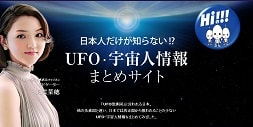2014年12月08日 ハーバー・ビジネス・オンライン記事です。
このところ「スーパーの棚からバターが消えた」とよく聞く。先月28日には、農水省がクリスマスケーキ生産などの最需要期を前に、大手乳業メーカー に供給を増やすよう要請したと報道されたが、これを受けて今月4日、各社が前月比3割の増産することを同省に報告した。今年は年間を通じてバターが不足し ているようで、農水省は今年5月に約7000トンを、その後も追加で約3000トンを緊急輸入するなどしている。

農水省はバター不足の理由として「昨年の猛暑の影響で乳牛に乳房炎等が多く発生したことや、酪農家の離農等で乳牛頭数が減少していることなどにより、生乳 (=搾ったままの牛の乳)の生産量が減少したため、バターの生産が減少し在庫量が大きく減少」したからだと言い、テレビや新聞でも、円安による飼料の高騰 や電気料金の値上げなど、酪農を取り巻く厳しい経営環境を盛んに報道している。が、ちょっと待て。確かに生乳の生産量や生産者数が減少傾向にあるのは事実 なのだが、去年と今年を比べて生産量が劇的に減少したわけではない。事実、前年比わずか2%減の98%を維持している。
その証拠にバター不足で大騒ぎしている割には、牛乳やチーズはスーパーで毎日のように特売しているではないか。つまりは安売りできるほど品物があるということだろう。原料は同じはずのバターだけが品薄になるというのは、よく考えれば不思議な話だ。
バターの”生産統制”による弊害
農業ジャーナリストの浅川芳裕氏によれば、実のところこのバター不足は、農水省の方針によって生じた、極めて人為的な問題であるのだという。
「一言で言えば、バター生産の“北海道一極集中化”という“生産統制”の弊害です。そして、一極集中化を支えているのが “加工乳補助金”という仕組みなのです」
正式には「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法」と呼ばれるもので、加工用に生乳生産量の半分以上を出荷している都道府県の酪農家に支給される補助金がある。バターや脱脂粉乳等などに利用した場合、180万トンを限度に1リットルあたり12.8円支給されるが、現状でこの条件に当てはまるのは北海道だけなので、北海道限定の補助金と言っていい。北海道が占める全国の牛乳シェアは2割にすぎない一方、加工用は8割であることからもその効果がうかがえる。
「この仕組みの名目は、生産性の高い北海道から都府県に流れる牛乳の量を規制することで都府県の酪農家を保護することになっていますが、実際には、北海道 に加工工場がある乳業メーカーに便宜を図って優遇することで、バター生産を北海道に寡占化させる結果となっている。今回のようなケースで、消費・実需サイ ドが多様な調達源を失うリスクを高めているのです」(浅川氏)
農水省のHPで生乳の“用途別取引量”を見てみると、例えば今年10月では脱脂粉乳・バター等向け生乳は全国で約96600トン、うち北海道が約 87200トンと全体の9割以上を占めている(一方、北海道産の牛乳シェアは同月、25%強にすぎない)。つまり、北海道以外の地域でバターを生産しても 補助金が出ないため、特に付加価値をつけたものでもない限り、競争力の面からバター生産はかなりハードルが高いということだろう。そのため生産する業者も 少なく、北海道でバター生産が減少するとたちまちバター不足が生じるわけだ。加工乳補助金の総額は毎年約300億円。これだけの血税を投じた結果が、「バターが消える」では納税者は救われない。
浅川氏は、このような農水省によるバターの“統制”の構造はこれだけに留まらないと指摘する。このほかにもバター不足が必然的に発生する構造的要因は複数あり、続きでそれらを紹介していきたい。
<取材・文/杉山大樹>
浅川 芳裕(あさかわ・よしひろ) 農業ジャーナリスト 1974年山口県生まれ。カイロ大中退。著書『日本は世界5位の農業大国』『TPPで日本は世界一の農業大国になる』など多数。
─ ─ ─
今年、断続的に起きてきたバター不足は、12月4日に乳業メーカー各社がバターの増産を決めたことで、徐々に沈静化しつつあるようだ。しかしながら、本当 に問題は解決されたのだろうか。「バター不足は農水省により人為的に起こされたもの」と断じる、農業ジャーナリストの浅川芳裕氏が、ほとんどメディアで伝 えられることのない騒動の背景を語る。

ここ10年の間に生乳生産量は約1割減少しているが、生乳を原料とする生産物の中で最も大きなウエイトを占める牛乳の生産量は、それ以上の約2割減少と なっている。バター・脱脂粉乳の生産量にしても、同じく2割程の度減少だ。つまり、牛乳やバター以外に振り向けられる生乳量は、逆に増えているということ になる。
ここで浅川氏が指摘するのが、“チーズ補助金”という仕組みの存在だ。農水省のHPの「生乳用途別取引数量」を確認してみると、4月以降、5月を除いて チーズ向け生乳の対前年比は生乳全体のそれを大きく上回っている。特に7月から9月にかけてはバター不足の要因が「全国的な生乳不足」という農水省の説明 とは裏腹に、それぞれ103%、103.9%、104.4%と、チーズ生産用に前年を上回る量が回されていることがわかる。
「農水省は数年前から国産チーズの増産を謳い、『チーズ向け生乳供給安定対策事業』として、チーズ製造に関わる業者(乳業メーカーや酪農家)に対して、2 分の1補助を始めています。また、チーズ向け生乳に対しても随時、補助金が支給されていましたが、この補助金が今年4月から恒常的に支給されるよう正式に 制度化されているのです」
チーズ向け生乳に対する補助金制度は、前回(http://hbol.jp/15641)触れた「加工原料乳生産者補給金」に、別枠として新たにチーズの項目を設けたもので、チーズ向け生乳に対して1リットル15.41円の補助金が支給されることになっている。
「ただし、最大52万トンという上限があるため、この補助金枠をとるためにメーカーはこぞってチーズの増産を始めた。つまり、バターに回る生乳量が政策的 に減少した可能性がある。5月段階でバターが足りなくなり、農水省による緊急輸入が始まっていることを考えると、このことが今回のバター不足の要因であろ うことは十分に推測できます」
簡単に言えば「チーズをいっぱい作ったら、バターが足りなくなっちゃいましたぁ」という実に単純な話なのだが、霞が関の官僚が自らの失敗を正直に話すはずもない。
「農水省は11月28日、“チーズ補助金”をもらっている乳業メーカー各社にバターを増産するよう要請して、それによりバター不足が解消されるとしていますが、これはすなわちチーズを減産しろというお達し。つまり、農水省は全体の生乳量は足りていることを知っている。自らの失政を隠すために、先手をうって 乳業メーカーにバター増産を要請するというパフォーマンスを演じたわけです」(浅川氏)
乳業メーカーも、本音では「好き勝手にチーズを増やす方向に業界を誘導しておきながら、今さらバターを増産しろ(=設備投資したチーズ事業が赤字化)と は何事だ」と言いたいところだろうが、農水省から様々な補助金をもらっている手前、決してNOとは言えず唯々諾々と従うしかない。要請からわずか1週間で バターを増産することを決定した。
これで当面はバターが市場に出回ることになるのだろう。スーパーの棚には再びバターが並ぶようになり、メディアで騒がれることもなくなって、人々も一過 性の事として忘れていく。こうして農水省の責任は国民に知られることなく、ウヤムヤにされるというわけだ。しかし、制度がそのまま続く以上は、いつまた同 じことが起きても不思議ではない。
「バターとチーズ合わせて約500億円の補助金、つまりは税金が使われています。それでこのザマですから、農水省の命令による計画生産、要するに社会主義政策が生む結末というのは、歴史が証明しているように、その被害を国民が蒙ることになるわけです」(浅川氏)
農水省が統制しているのは生産だけではない。国内でバターの供給が足りないのであれば、自由主義経済の日本においては、国産が足りなくなりそうと察知すればすぐさまスーパーやコンビニが直接海外から調達するか、商社なりがビジネスチャンスとして大量輸入してもよさそうなものだろう。何故わざわざ農水省が緊急輸入しなければならないのか。次回は輸入バターに関する非合理な仕組みについて解説する。<取材・文/杉山大樹>
─ ─ ─
前2回(『バター不足の怪。牛乳やチーズは山ほど売ってるのに、なぜ?』『バター不足は農水省による「チーズの作らせ過ぎ」が原因』)では、バター不足が生じる下地ともいえる農水省の補助金制度について説明したが、今回は国産バターの不足を補うことができない、特殊なバターの輸入制度について、農業ジャーナリストの浅川芳裕氏が解説する。

写真はイメージです。
「常日頃から国産、外国産を問わず、仕入れルートや商品ラインナップを多様化して消費者ニーズに応えることで、小売り・食品業界は成り立っています。それが先進国における豊かな消費生活の前提です」
そう語る浅川氏は、それを阻害しているのが農水省の天下り団体「農畜産業振興機構」によるバター輸入業務の独占だとする。
輸入バターには特殊な関税割当制度が適用されていて、一定の輸入量までは一次税率(関税35%)が課せられ、その枠を超えると二次税率(関税 29.8%+1kgあたり179円)が課せられる。ただし、一次税率の対象は600トンと極めて限られた数量で、これは機構が国際航空会社や国際物産展に あらかじめ割り当てるので、普通に輸入しようと思えば、より高率な二次税率を払わなければならない。
さらに、輸入業者はわざわざ機構にバターを買い入れてもらい、農水大臣が定めた1kgあたり最大806円の輸入差益(マークアップ)なるものを上乗せされた価格で買い戻さないといけないという、不可思議な制度になっているのだ。
例えば、国際価格500円のバターを1kg輸入したとする。まず関税29.8%プラス179円が課せられる。そこに輸入差益806円を上乗せすると 1634円と輸入価格の3倍以上となり、流通業者や小売業者の儲けを乗せれば優に2000円を超える価格になってしまう。これほど高価格では、いくら農水 省が緊急輸入しましたと言ったところで、せいぜいどうしても必要な業務用に回るくらいで、とても一般消費者にはとても手が出ない。
その上、機構は「輸入するバターの数量、時期について、国内の需給・価格動向などを勘案して決定」できる権限を握っているので、仮に民間業者が多少高く てもいいから輸入しようとしても、自由に輸入できないのだ。輸入できるのは機構が実施する入札時だけで、しかも一定の条件をクリアした指定輸入業者しか入 札に参加できないことになっている。
これらの措置は国内酪農家の保護のためといわれるが、実際には何が起きているか。
「例えば、多様なバターが自由に生産・調達できないため、諸外国と比較して日本ではマーガリンのシェアが異常に高くなっている。つまり、その原料となる米国トウモロコシ農家を安定して潤わせる政策であり、国内の酪農保護とはむしろ正反対の結果を生んでいるという側面があるのです」(浅川氏)
また、実のところ「農畜産業振興機構」の仕事といえば、書類を右から左に流すだけ。それだけで巨額の収益を得ていることになる。農水省によれば24年度 のバター輸入量は4千トンで、農畜産業振興機構に入った輸入差益は約23億円あったといい、緊急輸入が行われた昨年は1万3000トンだから、その約3倍 の“儲け” があったと考えられる。輸入差益は酪農家への助成に使われるとされるものの、農畜産業振興機構の15人の役員の大半は農水省OB及び出向者で、理事長の報 酬は1672万3千円、一般職員の平均年収も665万円と、国家公務員平均を上回る高給を得ている(平成25年度)。農水省にとっては、実においしい利権 となっているわけだ。
「この団体設立の大義名分は酪農家保護ですが、実際には消費者、バター関連業者、さらには酪農家にも厄災をもたらす厄介者です。百歩譲って本当に農水省が バターの国家貿易が必要だと信じているなら、農水省本体がやればいいこと。なぜ民間開放の流れにかこつけて独立行政法人に仕事を回すのか。いずれその天下り団体で自分たちが高給を得るためなのです」(浅川氏)
農水省は酪農業の保護を謳って行う偏った補助金制度や輸入制限によってバター不足を生じさせている割には、現実には生乳生産量や酪農家の戸数は年々減少している。にもかかわらず、それを理由にバターが足りませんというのはあまりに矛盾してはいないか。その一方で、自分たちの生活の安泰だけは頑なに守ろうとする。そのツケが消費者に回ってくるのではたまったものではない。
「解決策は実にシンプルです。輸入利権を廃止し、バター輸入を自由化するだけなんですから」(浅川氏)
<取材・文/杉山大樹>
http://hbol.jp/15641
─ ─ ─ ─
3%から5%、8%そして10%へ消費増税やその他増税が盛んに行われようとしています。また貯蓄を好む日本人に貯蓄税やそれらを一元管理するマイナンバー制など、政府はあれやこれやと国民が働いて稼いだ所得に手を出そうとしています。
財政難や高齢化社会への福利厚生などと体のいい事をいっていますが、ここでいう利権が欲しいだけです。
こうして集めた税金が国民にどれ程返ってくるのでしょうか?
多く取られた人も少なく取られた人も、みな同じ少々の金額を支給されるのみです。そのほとんどはここでも述べられているように、自分達にとって都合のよい一定の団体や企業などにだけ補助金を出す。そして偏った商品を多く作らせて足りなくなった商品を輸入させ、そこに多く税金を課し
後は、自分達の給料やボーナスとするわけです。
中国へのODAも続けています。これは・・・多分中国が怖いんでしょう・・彼らが自分の都合のいいように税金を使っているすると、考えられることはやはり単に献上でしょうね。
アメリカのトウモロコシ業者を潤しているというマーガリンシェアの異常な拡大ですが、このトウモロコシは遺伝子組み換えであることは間違いありません。
遺伝子組み換えはモンサントという会社が独占してやっていますが、ここを潤しているのでしょう。
日本の役人は中国も怖いけど、アメリカにも頭が上がりませんから。こうした形でアメリカにも日本人の血税が回っています。しかも、遺伝子組み換えはモンサントの実験では表向き健康に害はないと発表されていますが、フランスの大学が実験したところ、実験用マウスの体中にガンが発症するというデータになりました。つまり日本人の健康とも引き換えです。日本人はお「金」と「命」をアメリカに削り取られているわけです。
こうして上にいる者が能無しだと下にいる私達が大変迷惑を被るのです。
それだけでなく、国家をも危ういものにしていきます。
政治家が誰になろうと官僚にはどうすることもできないとあきらめ、まだましだと思う自民党でさえもこの顛末です。票を入れ続けていい事は何もない。
自民党では変わらないということです。変わらないだけでなくむしろこのままでは危険な方向へと向かっていると言えます。