中国企業の巨額負債が中国国内はもちろん、世界経済にも深刻な影響を及ぼす可能性がある。その理由は不良債権額の大きさ。現在負債額の多い企業のランキング上位6社の合計負債はおよそ9兆元に達し日本円にしておよそ200兆円にもなる。もし負債がきちんと処理されなければ関連する数百の中小企業が経営難に陥る可能性がある。それに伴い多くの従業員やその家族の生活にも大打撃が及ぶ。この巨額の資金は一体どこへ消えたのか?2024年後半中国共産党は経済刺激策を次々と打ち出したが景気は一向に回復しなかった。特に9月以降経済支援策が集中して実施されたが12月にはすでに効果が薄れていた。一部ではこれらの政策の狙いは景気回復ではなく政府の債務負担を軽減することだ。と指摘されている。習近平政権が全人代で決めた財政出動を拡大しても「中国経済のデフレはさらに深まっていく」との見方をしている識者もいる。
深刻な不動産不況を背景に、需要不足が大きな問題になっている。全人代で出てきた政策は供給サイドの強化に偏っており、需要不足に十分な対応ができない。中国の消費者物価指数(CPI)は2月に前年同月比で0.7%下落した。需要が足りないところに供給を増やしたら、物価が下落するデフレ圧力が一段と高まるのは避けられない。
主要都市では住宅価格が大幅に下がっている。中国経済は債務の負担がとてつもなく大きく景気後退の流れはまだ始まったばかりだ。2024年9月に景気刺激策が発表された直後は、株価や不動産価格が一時的に回復したが2025年に入ると市場を押し上げる力は続かず上昇は一時的なものだった。株価、不動産が一時的に上がっても失業率は上がり、物価指数は下がり、消費者の購買意欲は回復しなかった。消費が低迷すると物価が下がり企業の利益も減少その結果大規模な人員削減が続き、負のデフレスパイラルに突入する。中国の株式市場の上場企業の最大株主はほとんど国有企業です。株主は政府系の投資会社や中共国務員などが中心で市場そのものが国の管理下にあります。さらに市場を監督する証券監督管理委員会も国務員の管理下にあるため、公平な取引が成立しにくく不正が起こる可能性が高い。つまり、個人投資家の資金が政府の都合で吸い上げられる状況が続いている。今の中国株はカジノ以下でしょう。カジノには固定されたルールがあり誰もがそれに従うが、今の中国の株式市場では運営側の政府にとって都合の良いようにルールを変え、不正をされても訴えることすらできない。1番の被害者はプロパガンダを信じてしまった中国の一般富裕層です。結果として庶民が1年かけて稼いだお金をわずか数日で失うケースも珍しくない。国債市場では中国人民銀行が年明けに国債の買入れを一時停止すると発表し市場に衝撃を与えた。通常は中央銀行が国債を購入することで市場に潤沢な資金を供給するがそれを突然停止したのです。これは政府が掲げていた史上最大の金融緩和という方針と矛盾しており、多くの市場関係者にとって予想外の決定だ。変更の理由は2つが考えられる。1つ目は国債価格と利回りの急落。一般的に国の長期国債の利回りはGDP成長率とインフレ率との関係があるとされている。しかし中国の10年国債の利回りは現在1.66まで低下しており市場が中国経済の成長を監視していることを示している。2つ目は投資家のリスク回避です株式や不動産実態経済への投資を避け、安全資産である国債に資金が集中その結果国債の価格が上がり、利回りがさらに低下する悪循環に陥っている。中国人民銀行は今回の購入を一時停止した。本来なら特に発表する必要はなくただ買わなければいいだけだが、それでも公告を出したのは国債の利回りが低すぎ価格が高騰しているのは異常で、中国経済はそこまで悪くないので国債を買ってリスク回避する必要はないと国民に伝えるためと見られている。もう1つの理由は人民元の下落を抑えるためだ。現在中国とアメリカの預金金利の差は3%以上に広がり、歴史的な水準となっている。この金利差が大きいほど資金は国外に流出しやすくなり人民元の下落圧力が強まる。中央銀行が市場への資金供給を抑えることで人民元の価値を維持しようとしている。現在中国の10年物国債の利回りは1.6%と過去最低水準でアメリカの4.4%や日本の2.2%と比べても極端に低い状況だ。中国の低金利は資本流出を招き人民元の下落を加速させる。国債の購入を停止すれば国債の価格が下がり利回りが上がる。これにより資本流出を抑えつつ人民元のさらなる下落を防ぐ効果が期待できる。しかし国債の買入れを止めることは市場への人民元供給を絞ることを意味し、中国の中小金融機関、地方政府の債務状況が悪化すれば金融システムの不安定化につがるリスクがある。輸出は2兆元増えたとされていますがそれだけでは経済全体を支えきれない。不動産市場の低迷が深刻だからだ。かつて、ソ連も崩壊前の、2、30年の急成長を経験したが1970年代は深刻な経済問題に直面し成長率が低迷した。現在の中国はその時期のソ連と非常によく似ていると分析し今後中国経済は長期的な低成長時代に突入すると予測している。



















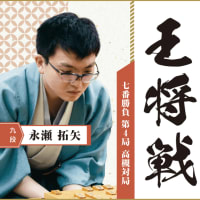






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます