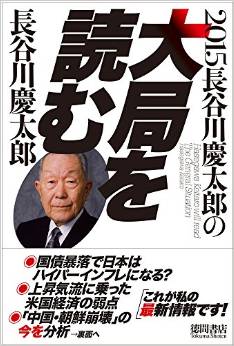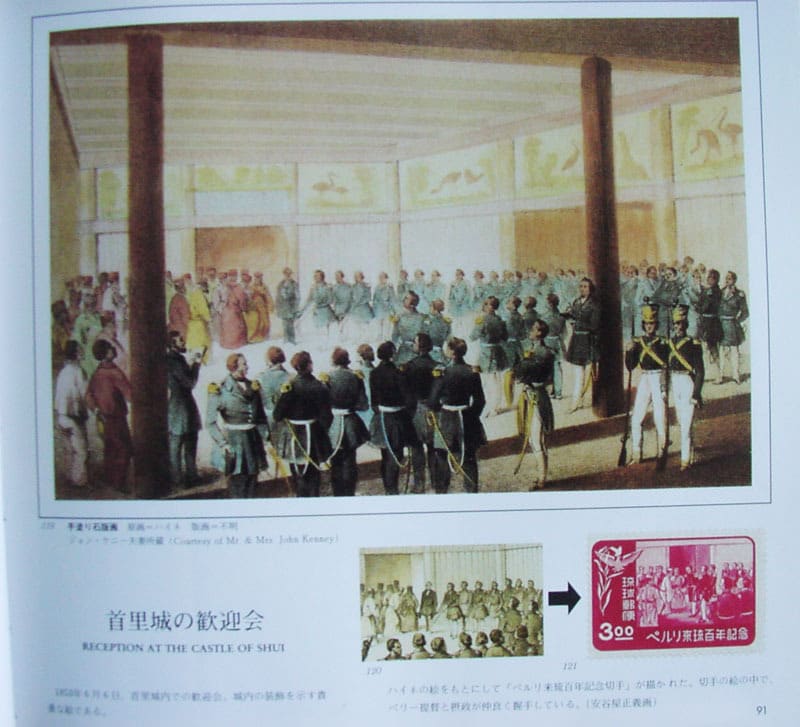ハゲ特集





昔からの言い伝えがある。口に喰われる。人を呪わば穴二つ。言霊。エネルギーの反転。因果応報などなど。いろいろな言い含み
がある言葉ですね。今日のブログのカテゴリーは、人の体編なので、私の体験を話しましょう。
tiger60は若い頃から額が広い、周囲の人はやがて頭の毛が禿げてなくなるとみていた。確かに額が
広いし少しずつ年と共に薄くなってはいる。自分自身も中年まで頭髪が残ればいいが、望むすべもな
いと観念気味だった。当時の口の悪い友人達は自慢のフサ
フサした長い髪を風になびかせて、私をいじっていたものだ。私の家に遊びに来るときの挨拶・合図
は、「オーィ、ハゲいるか
~!」だった。私もそれを甘んじて受けていた。父親はもちろん先祖代々ハゲの家系だから、あきら
めも早かった。日々カガミの前の自分の頭の毛の状態を見ていつ無くなるのだろうと気をもんでい
た。二十代から三十代。四十代と仕事や生活に忙しい日々が続き、頭のことはいつしか忘れていた。
ある日買い物の途中、昔の悪友にしばらくぶりに会った。あれほどロン毛を自慢していた友人がマ
ルッパゲに様変わりしていた。
驚愕した、もしかして人違いかと一瞬思ったくらいだ。間違いなく友人だ。これやぁ、変わったなと
思った。時の流れは人を変える、こちらは少ししか変わっていないが、相手が完全に変わった。友人
は照れくさそうだった。昔のさんざん弄られたことがウソ
のようだった。これこそ口に喰われることかなと思ったものだ。
修学旅行の高校生達を観光ガイドして歩く時、いろいろな学生たちがいる。おりこうな生徒、明るい
生徒、いろいろ質問する生徒、わんぱくな生徒など。先日ある本土の高校の修学旅行生達を案内して
説明している時、ある男子学生がカメラを向けて写真を撮ろうとしていた、静止写真ではなくビデオ
モードにして音声も入れているようだ。こちらが説明している隙に、放った言葉が「ハゲ!」だっ
た。なんとtiger60に向かってカメラを廻してハゲと言い放ったのだ、一瞬耳を疑ったが間違いなく
聞いた。ムカッとしたが怒れない。その少し後、近くの日本軍の使用した戦争時のトーチに場所を移
して説明することになった。トーチカの前も後ろも穴が空いている。中は暗い。ハゲと言ったわんぱ
く学生はペンライトを点けて穴を覗きこんでいる。周囲の学生達も彼を見ている。tiger60は一計を
案じた。中には毒ハブが潜んでいるかも知れないから中には入らないでと注意した。
そう言うと本当にハブがいるかも知れぬと先入観を持つが、わんぱく学生は英雄気取りで、屈んで中
をのぞきこんでいる。tiger60が彼の背中に手を置き少し押して脅かした。するとわんぱく学生はハ
ブだと思い飛び上がった。周囲の学生達も引率の先生も大笑いした。tiger60はしてやったりと思っ
た。それからはわんぱく学生と他の学生達とも友達のように親しくなった。別れ際、みんなが楽し
かったと感謝の言葉を言ってくれた。
我が家に孫達が遊びに来る。ワイワイガヤガヤと騒がしいが楽しい時でもある。孫とは来ると嬉しい
が変える頃になるとこちらが疲れ気味になっていて、帰るとなると嬉しいものである。子供とは笑わ
ないじぃじぃでも孫には破顔の笑顔を見せる。孫から何を言われても、されても嬉しいものだ。ある
日、ソファに座りテレビを見ていると、頭をいじる孫がいる。最近淋しくなった大事な貴重品の我が
頭髪をもてあそんでいるのだ、ブラシ状のもので髪を撫でているのだ、幾本の長い細い棒状が付いた
快感ブラシとのこと。「じぃじぃ、気持ち良いでしょう!」と言う孫。確かに気持いいのだ。こちら
も一言、言った、「じぃじぃの髪は一本一億円するから大事に梳いてね」と。孫が聞く、「どこのお
で一億円で売っているの?」本気にしているのだ、おもわず我が家族みんなが大笑いした。
tiger60
今日のブログはハゲの話しでした。男のシンボルでもある髪、こればかりは自分の努力ではどうにも
なりません。一番いいのは無駄な抵抗をせず自然に任せているのがいいですね。もうロマンスグレー
のファッションになるのは諦めました。ブロガーの皆さんはどうでしょうか?