今回は防災・救急についてお知らせします。
9月1日は防災の日です。
1923年(大正11年)9月1日は、神奈川県の相模湾付近を震源として関東大震災が起こりました。
マグニチュード7.9、死傷者は10万5000人と言われており、現在のような建設技術や、
ライフラインの安全性が確保されていなかったために、倒壊した建物と広がる火災で街は絶望的な被害状況だったようです。
以前の衛生通信でもお伝えしたように、日本は4つのプレートの上に位置しているため、世界的に地震が多い地域です。
「防災」は被害を出さないようにすることが目的ですが、いざ災害が発生すると防災力を上回る被害が起きてしまい、
被害を完全に防ぐということは不可能であると明白になりました。日本では阪神淡路大震災以後、「減災」という取り組みが行われています。
「減災」とは?
減災とは、来たる災害時にその被害をできるだけ小さくする取り組みを言います。
災害の発生前、発生時、発生後のそれぞれの段階で適切な行動をとることによって、被害を小さくすることができるのです。
すなわち、減災は被害を最小限に抑えることが目的で、防災は被害を出さないようにすることが目的です。
内閣府は減災対策として、7つのポイントを挙げています。
①自助、共助 ②地域の危険を知る ③地震に強い家 ④家具の固定
⑤日頃からの備え ⑥家族で防災会議 ⑦地域とのつながり
障害者福祉に携わる事業所としては、特に①自助、共助と、⑦地域とのつながりが重要だと考えています。
自分の身は自分で守るのが「自助」、地域や身近にいる人どうしが助け合うのが「共助」。
利用者さんが被災した時にどのような共助ができるか、エンジョイでも考えていきたいと思います。
阪神・淡路大震災で、家の下敷きになった人々の多くを助けだしたのは、家族や近所の人たちだったそうです。
一人暮らしの利用者の方は特に、普段から地域とのつながりを持つことが大切であり、
一緒にいるヘルパーさんがそのお手伝いをすることは可能です。
地域の人たちと利用者さんがきちんとコミュニケーションがとれるように、
ヘルパーとして何ができるかということを、この機会に考えてみていただけたらと思います。










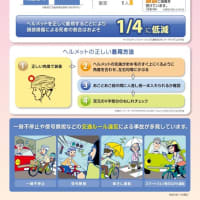
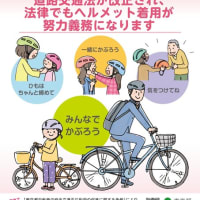
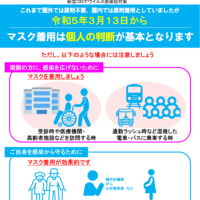
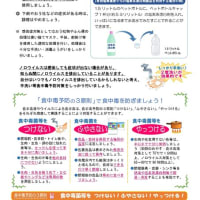
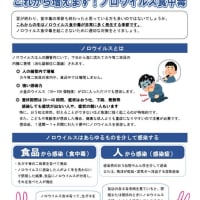
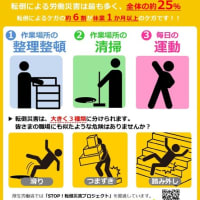
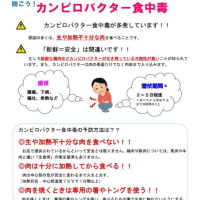
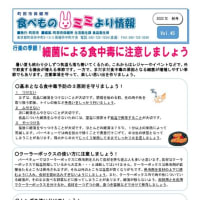
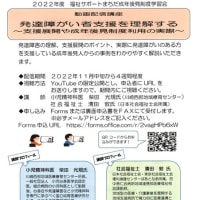
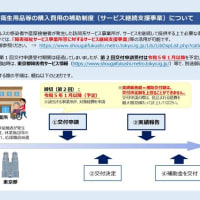
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます