櫨の灯り展には、名弓「肥後三郎」も展示してます。
…でも、実は製品としての「肥後三郎」ではありません。
あらかじめ「肥後三郎」を借りるということで了承を得ていましたが、
当日借りに行くと…
相良「肥後三郎でなくてもいいやろ。」
私「いえ、肥後三郎をお借りしたいんです。」
相良「そうだ!折れた肥後三郎ならあるよ。」
私「……折れた弓を展示するのは…。」
相良「それじゃ、切ってやろう。そうすれば弓の側面が見えるから、櫨にはいいやろ。」
私の不満顔に構わず、相良さんはさっさとノコで肥後三郎を真っ二つ。

まあ、確かに肥後三郎の断面を見ることができますね。
弓胎弓(ひごゆみ)の構造がよくわかります。
私「それじゃ、これと肥後三郎じゃなくてもいいから、もう一本弓を…。」
相良「ダメダメ。」
私「この折れた弓は、もういらないんですか?」
相良「いらないわけやない。まだ使うとこはあるから、一ヶ月後にちゃんと返して。」
私「…わかりました。それじゃ、櫨の灯り展、来てくださいね。」
相良「来ないよ。興味ないもん。」
私「…じゃあ、一ヶ月後にまた来ます。」
後から別の方に聞いたら、
「肥後三郎は20万以上する貴重な弓だし、常に肩入れしたり形を整えないといけないから
一ヶ月も放置しておくなんてムリムリ。使いモンにならなくなったら責任持てんやろ。」
確かに、相良さんは私にとって一番ふさわしい「弓」を貸してくれたみたいです。
そんなわけで、「肥後三郎(半分)」を展示してます。

↓押してくださると励みになります。

人気blogランキングへ
…でも、実は製品としての「肥後三郎」ではありません。
あらかじめ「肥後三郎」を借りるということで了承を得ていましたが、
当日借りに行くと…
相良「肥後三郎でなくてもいいやろ。」
私「いえ、肥後三郎をお借りしたいんです。」
相良「そうだ!折れた肥後三郎ならあるよ。」
私「……折れた弓を展示するのは…。」
相良「それじゃ、切ってやろう。そうすれば弓の側面が見えるから、櫨にはいいやろ。」
私の不満顔に構わず、相良さんはさっさとノコで肥後三郎を真っ二つ。

まあ、確かに肥後三郎の断面を見ることができますね。
弓胎弓(ひごゆみ)の構造がよくわかります。
私「それじゃ、これと肥後三郎じゃなくてもいいから、もう一本弓を…。」
相良「ダメダメ。」
私「この折れた弓は、もういらないんですか?」
相良「いらないわけやない。まだ使うとこはあるから、一ヶ月後にちゃんと返して。」
私「…わかりました。それじゃ、櫨の灯り展、来てくださいね。」
相良「来ないよ。興味ないもん。」
私「…じゃあ、一ヶ月後にまた来ます。」
後から別の方に聞いたら、
「肥後三郎は20万以上する貴重な弓だし、常に肩入れしたり形を整えないといけないから
一ヶ月も放置しておくなんてムリムリ。使いモンにならなくなったら責任持てんやろ。」
確かに、相良さんは私にとって一番ふさわしい「弓」を貸してくれたみたいです。
そんなわけで、「肥後三郎(半分)」を展示してます。

↓押してくださると励みになります。

人気blogランキングへ















































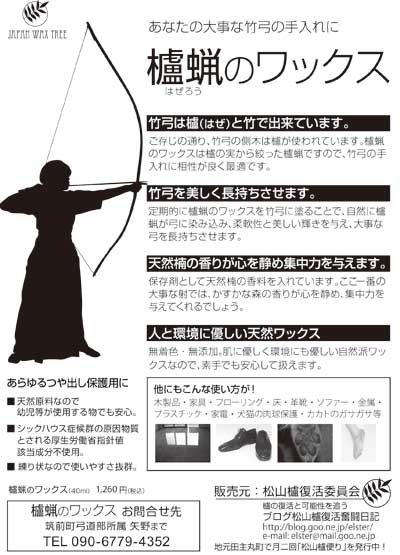

 ご主人に撮影していただいたものですが
ご主人に撮影していただいたものですが
