図書館で借りた昭和18年の本から、
こんなものが出てきました。
 (←クリックで拡大)
(←クリックで拡大)
大興奮!
しかしながら、
ふすまの下紙になっていた古紙を解読するみたいな
歴史学者の基本能力がないのに
歴史を名乗っていいのか!という議論が頻繁になされるあたりで
研究している者としましては、
「おもしろがる」からなかなか発展しにくいのもこれまた事実(恥)。
◎現時点でわかったこと・わからないこと◎
所属の知性?(ただし皆専門外)を結集した結果10月19日修正
・横書きが右から、電話番号が短い
…というあたりはすぐ目がいくとして
・落合観光ホテルは落合温泉(黒石温泉郷)に現存しない
落合観光ホテルは、ちとせ屋として現存
http://www.tocoo.jp/detail/basicInfo/1005760
・青森だから「林子」づくし?
「林子液」はりんごジュース?
「ジュース」「ヂュース」は昭和初期の広告で見るけれど、
庶民はカルピスやシロップの時代。「液」なのは戦中だから?
→適正言語統制は法律ではなく民間運動で、
このころにはすでに地域によっては行われている。
その隣の「リンゴ丼」みたいなやつは何?
→「井」ではないし「キリ」でもないし、
値段的にもリンゴを切って出した小鉢くらいのものか?
・飲食代の割に宿泊料が安いのはなぜ?
当時の物価は物価指数では現在の330分の1らしい
林子液はつじつまがあうけど、宿泊料は変。
もちろん、モノによって物価の上昇率には差があり、当時山手線初乗り10銭。
・税率がやたら高い 税金相当額=税金対象額ですね。
→ちなみに戦時の二重経済にはぎりぎり入る前か?
・奉仕料=サービス料もやたら高い
(ちなみにホテルが心付けではなく奉仕料をとる習慣は戦前からある)
→やはり値段的に芸者を呼んだ代金ではないか?
・領収書の変遷ってどうなっているのだろう?
収入印紙は印紙税が明治初期から制度化されているけれど…
「様」が書いてあって「上様」っていつかららうんだろう?
「領収候也」は証文風だなあとか…
※明治中期くらいだと筆書きと印刷が混在しているはず
・筆記具はボールペンは進駐軍が持ち込んだらしいので、万年筆?
そうは見えないけど…。(でも十八年よねえ?)
→考えてみればカーボン複写ですね…。筆記具の歴史って意外に知らない。
誰か色々教えてください!
※当該文書の処遇は、現時点で図書館に相談中です。
→問い合わせた結果、正式に譲り受けることになりました!
(10月19日追記)
◎読み下し◎
第七号 料金領収書
泊宿料金
室名又は室番号 十五雪
一人一泊の通常料金 六円
右内訳 宿泊料又は室料 三円六〇銭
夕食料 一円五〇銭
朝食料 九〇銭
宿泊年月日 昭和十八年九月二十五日
宿泊人員 御一泊御二人
御料金 一二円
宿泊料又は室料 七円二〇銭
税金相当額 一円四四銭
遊興飲食料金
遊興又は飲食年月日
夕、朝、昼食の区分
種類又は品名 数量 金額 一人一回又は一人前の料金 税金相当額
二級酒 ニ 一円四四銭
林子酒 一 二円四五銭
鯉のあらい 三 一円八〇銭
御料理 四 二円
林子丼(?)一 七〇銭
林子液 一 一円五○銭
小計 九円八九銭 六円四四銭 六円四四銭
奉仕料 四円三七銭
総金額 三十四円二十四銭
立替金内訳 黒石電 一 十銭
右金額領収候也 昭和十八年九月二十六日
上様
青森県南津軽郡山県村落合温泉
落合観光ホテル 電話(温湯)十二番


こんなものが出てきました。
 (←クリックで拡大)
(←クリックで拡大)大興奮!
しかしながら、
ふすまの下紙になっていた古紙を解読するみたいな
歴史学者の基本能力がないのに
歴史を名乗っていいのか!という議論が頻繁になされるあたりで
研究している者としましては、
「おもしろがる」からなかなか発展しにくいのもこれまた事実(恥)。
◎現時点でわかったこと・わからないこと◎
所属の知性?(ただし皆専門外)を結集した結果10月19日修正
・横書きが右から、電話番号が短い
…というあたりはすぐ目がいくとして
・
落合観光ホテルは、ちとせ屋として現存
http://www.tocoo.jp/detail/basicInfo/1005760
・青森だから「林子」づくし?
「林子液」はりんごジュース?
「ジュース」「ヂュース」は昭和初期の広告で見るけれど、
庶民はカルピスやシロップの時代。「液」なのは戦中だから?
→適正言語統制は法律ではなく民間運動で、
このころにはすでに地域によっては行われている。
その隣の「リンゴ丼」みたいなやつは何?
→「井」ではないし「キリ」でもないし、
値段的にもリンゴを切って出した小鉢くらいのものか?
・飲食代の割に宿泊料が安いのはなぜ?
当時の物価は物価指数では現在の330分の1らしい
林子液はつじつまがあうけど、宿泊料は変。
もちろん、モノによって物価の上昇率には差があり、当時山手線初乗り10銭。
・
→ちなみに戦時の二重経済にはぎりぎり入る前か?
・奉仕料=サービス料もやたら高い
(ちなみにホテルが心付けではなく奉仕料をとる習慣は戦前からある)
→やはり値段的に芸者を呼んだ代金ではないか?
・領収書の変遷ってどうなっているのだろう?
収入印紙は印紙税が明治初期から制度化されているけれど…
「様」が書いてあって「上様」っていつかららうんだろう?
「領収候也」は証文風だなあとか…
※明治中期くらいだと筆書きと印刷が混在しているはず
・筆記具はボールペンは進駐軍が持ち込んだらしいので、万年筆?
そうは見えないけど…。(でも十八年よねえ?)
→考えてみればカーボン複写ですね…。筆記具の歴史って意外に知らない。
誰か色々教えてください!
※当該文書の処遇は、現時点で図書館に相談中です。
→問い合わせた結果、正式に譲り受けることになりました!
(10月19日追記)
◎読み下し◎
第七号 料金領収書
泊宿料金
室名又は室番号 十五雪
一人一泊の通常料金 六円
右内訳 宿泊料又は室料 三円六〇銭
夕食料 一円五〇銭
朝食料 九〇銭
宿泊年月日 昭和十八年九月二十五日
宿泊人員 御一泊御二人
御料金 一二円
宿泊料又は室料 七円二〇銭
税金相当額 一円四四銭
遊興飲食料金
遊興又は飲食年月日
夕、朝、昼食の区分
種類又は品名 数量 金額 一人一回又は一人前の料金 税金相当額
二級酒 ニ 一円四四銭
林子酒 一 二円四五銭
鯉のあらい 三 一円八〇銭
御料理 四 二円
林子丼(?)一 七〇銭
林子液 一 一円五○銭
小計 九円八九銭 六円四四銭 六円四四銭
奉仕料 四円三七銭
総金額 三十四円二十四銭
立替金内訳 黒石電 一 十銭
右金額領収候也 昭和十八年九月二十六日
上様
青森県南津軽郡山県村落合温泉
落合観光ホテル 電話(温湯)十二番














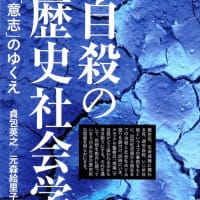






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます