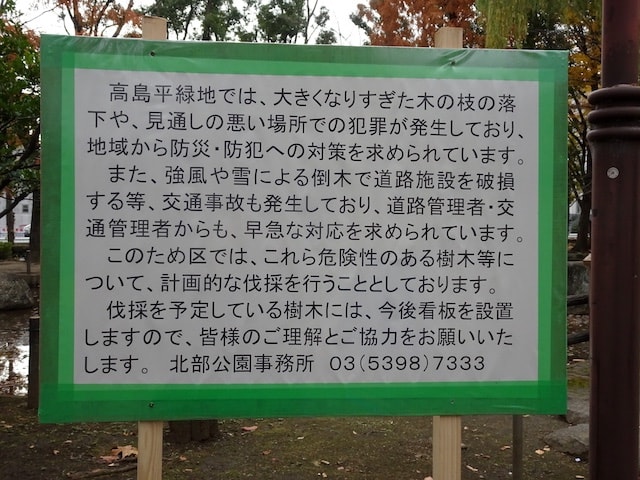大東文化大学法学部で月曜日の2限に担当する「税法」で扱う判例をあげておきます。法律の解釈の仕方を、このサラリーマン・マイカー訴訟で学んでみてください。
事案
・Xは神戸市兵庫区内の会計事務所(A事務所)に勤務する給与所得者であり、昭和46年に自家用車を68万円で購入した。Xは、この自家用車を通勤で使用するとともに、外回り業務や私用にも利用していた。昭和51年、Xは自損事故を起こした。自家用車の修理は可能であったが、修理費用がかさむために廃車にすることとし、Xはスクラップ業者に自家用車を3000円で売却した。
・翌年、Xは、昭和51年分の所得税について源泉徴収税額の還付を受けようと考え、所轄税務署長(加古川税務署長)に対し、昭和52年7月2日に次のような申告を行った。
給与所得額:130万6000円
譲渡所得金額損失:29万7000円(事故がなければ自家用車の価値は30万円であるとして)
総所得金額:100万9000円
還付金額に相当する税額:3万4800円
・昭和55年5月12日、加古川税務署長は、次のような更正処分を行った(Xには同月14日に通知した)。
給与所得金額:130万6000円
譲渡所得金額:0円
総所得金額:130万6000円
還付金の額に相当する税額:0円
納付すべき税額:3万4800円
・Xは加古川税務署長に異議申立てをしたが棄却され、国税不服審判庁に審査請求をしたが棄却されたので、出訴した。
争点
・事故によって廃車した自家用車の譲渡損失を、給与所得と損益通算することの可否。
・自家用車の、資産としての性質。
判旨
(下線は、すべて引用者による。また、表記を変えた部分がある。)
(1)神戸地判昭和61年9月24日判時1213号34頁
「資産の譲渡による所得には、事業所得、山林所得、譲渡所得又は雑所得があるが、資産を譲渡したことにより生じた損失(譲渡損失)の処理については、これら各種所得の金額の計算要素の一つとしてこれら各種所得の金額の計算構造のなかに取込み処理されている(法27条2項、32条3項、33条3項、35条2項)。ただし、その譲渡による所得が非課税とされている資産の譲渡による損失は、所得金額の計算上ないものとみなされている(法9条2項1ないし3号)ので、各種所得の金額の計算構造のなかには取り込まれないこととなる。そして、この非課税とされる資産のうちに、『自己が生活の用に供する家具、じゆう器(―什器。引用者注)、衣服その他の資産で令25条各号に記載したものを除く生活に通常必要な動産』が含まれている。
このように資産(非課税扱いの資産は除く。)の譲渡による損失を各種所得の金額の計算構造のなかに取り込んだ結果、各種所得の金額の計算上損失が生じたときは、その損失は他の各種所得の金額に損益通算されることとなる(法69条一項)が、それには例外があり、譲渡所得の計算上生じた損失のうち生活に通常必要でない資産の譲渡による損失部分は、競走馬の譲渡による損失が競走馬の保有に係る雑所得とのみ損益通算されるほかは、損益通算の対象とならない、つまりその損失の金額は生じなかつたものとみなされることとなる(法69条2項、令200条)。」
「前記認定事実(中略)によれば、Xは給与所得者であるが本件自動車の使用状況も大崎事務所への通勤の一部ないし全部区間、また勤務先での業務用に本件自動車を利用していたこと、本件自動車を通勤・業務のために使用した走行距離・使用日数はレジヤーのために使用したそれらを大幅に上回つていること、車種も大衆車であることのほか現在における自家用自動車の普及状況等を考慮すれば、本件自動車はXの日常生活に必要なものとして密接に関連しているので、生活に通常必要な動産(法9条1項9号、令25条)に該当するものと解するのが相当である。そして、自動車が令25条各号にあげられた資産に該当しないことは明らかであるから、Xの本件自動車の譲渡による損失の金額は、法9条2項1号に基づかないものとみなされることになる。したがつて、損益通算の規定(法69条)の適用の有無につき判断するまでもなく右損失の金額を給与所得金額から控除することはできないといわなければならない。
また、仮に本件自動車が前記認定事実のもとではXの生活に通常必要でない動産に該当するものとしても、法69条2項、令200条により譲渡損失の金額は生じなかつたものとみなされることとなるから、譲渡損失の金額を給与所得の金額から控除すべき旨のXの主張は、その余の点について判断するまでもなくいずれにしても採用することはできない。」
(2)大阪高判昭和63年9月27日判時1300号47頁
「認定事実によると、本件自動車は給与所得者であるXが保有し、その生活の用に供せられた動産であって、供用範囲はレジャーのほか、通勤及び勤務先における業務にまで及んでいると言うことができる。」
「ところで、右のうち、自動車をレジャーの用に供することが生活に通常必要なものと言うことができないことは多言を要しないところであるが、自動車を勤務先における業務の用に供することは雇用契約の性質上使用者の負担においてなされるべきことであって、雇用契約における定め等特段の事情の認められない本件においては、被用者であるXにおいて業務の用に供する義務があったと言うことはできず、本件自動車を高砂駅・三宮駅間の通勤の用に供したことについても、その区間の通勤定期券購入代金が使用者によって全額支給されている以上、Xにおいて本来そうする必要はなかったものであって、右いずれの場合も生活に通常必要なものとしての自動車の使用ではないと言わざるを得ない。そうすると、本件自動車が生活に通常必要なものとしてその用に供されたと見られるのは、Xが通勤のため自宅・高砂駅間において使用した場合のみであり、それは本件自動車の使用全体のうち僅かな割合を占めるにすぎないから、本件自動車はその使用の態様よりみて生活に通常必要でない資産に該当するものと解するのが相当である。
そうだとすれば、仮にX主張の譲渡損失が生じたとしても、それは、所得税法(原判決と同じく以下法という。)69条2項にいう生活に通常必要でない資産に係る所得の計算上生じた損失の金額に該当するから、同条1項による他の各種所得の金額との損益通算は認められないことになる。なお、同条2項は、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除することを認めており、これを受けて所得税法施行令(以下原判決と同じく令という。)200条があり、同条は競争馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は当該競争馬の保有に係る雑所得の金額から控除すると定めているが、本件がこれに該当しないことは言うまでもない。なお、本件は資産の譲渡による利益そのものがない事案であるから、法33条3項本文括弧書き(他の資産の譲渡益からの控除)の適用もない。」
「Xは、主位的主張として、給与所得者が保有し、その生活の用に供せられる動産は税法上『生活に通常必要な動産』と『生活に通常必要でない資産』の二種の分類に尽きるものではなく、他に法33条1項の予定する『一般資産』とでも呼ばれるべきものが分類され、本件自動車は前二種のいずれにも該当するものではなく、この『一般資産』に該当するものであり、その譲渡損失については法六九条一項によりXの給与所得の金額から控除すべきものとする。
しかし、法・令は、給与所得者が保有し、その生活の用に供する動産については、『生活に通常必要な動産』(法9条1項9号、令25条)と『生活に通常必要でない資産(動産)』(法62条1項、令178条1項3号)の二種に分類する構成をとり、前者については譲渡による所得を非課税とするとともに譲渡による損失もないものとみなし、後者については原則どおり譲渡による所得に課税するとともに、譲渡による損失については特定の損失と所得との間でのみ控除を認めているものと解するのが相当であって、『一般資産』のような第三の資産概念を持ち込む解釈には賛同することができない。したがって、右Xの主位的主張は実定法上の根拠を欠き失当であり、(後略)」
(3)最二小判平成2年3月23日判時1354号59頁
「所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、本件自動車の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上損失の金額が生じたとしても、これを損益通算の対象とならないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。」