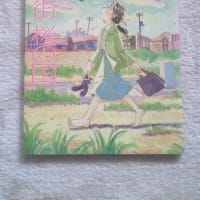blog転居移行中!
http://psalm098.blogspot.jp/
お手数ですが、ブックマークの方は、変更を願います。
-----
今生きている方々、全員に読んで欲しいと願うほど、実に明確な本だった。特に、家族に要介護者がいたり、病者・要介護高齢者にかかわる職業の方々にはぜひとも読んで欲しい。
図書館にも蔵書していると思われるが、予約数でいっぱいのはず。新書で安いので、購入したほうがいいかもしれない。
著者は、京都大学卒業、医者となり、現在は特養の医者をしている。もう、高齢者の域だが、考え方は独特の価値観を持つ。
本書の内容をざっくりと説明すると、死生観の構築である。
加えて、医療の不手際の指摘。その医療と、この国の人びとはどのようにかかわりを持つか=距離感の取り方、を著したものである。
「はじめに」のところで、すでに、blogするには内容が濃すぎる。
○医者には序列がある。大学病院の医者が頂点で、以下、国立病院→日赤→済生会→県立・市立の「税立病院」と続き、次が、民間の大病院→中小病院→一番下が町医者(開業医)→その下に老人ホーム等福祉施設の医者。
もう、ここで、すでに、コメントしたい。
医者はヒエラルキーによって成り立っている。それはまるで大会社のようだ。同じ「医者」を名乗っていても、確実に序列が生まれている。ところが、大学病院の医者は一番最下層の「町医者(開業医)、老人ホーム等福祉施設の医者」より「腕が良くて、病気のことは何でも知っている。絶対に治してくれる」と思ったら大間違いである。逆もある(経験上、開業医さんの方が、レベルが高い。特に在宅医療専門の医師はピンキリではあるものの、少なくとも「生活」を視点に、医療を行ってくれる)。
実にくだらない世界でしょ?
以下、引用を継続。
○病院では最後まで、何かと処置をする。いや、しなければならないところが「病院」。よって、「自然死」はありえない。在宅における死も、ふつうは、病院医療を引き継ぐ(在宅酸素とかリハビリとか投薬とか)。よって、ほとんど「自然死」はない。
○また、医者も、何もしないことには耐えられない。しかし、それは、「穏やかに死ぬのを邪魔する行為」なのだ。
○よって、ほとんどの医者は「自然死」を知らない。人間が自然に死んでいく姿を見たことがない。だから「死ぬのにも医療の手助けが必要」と信仰している。
○「死」という自然な営みは、本来穏やかで安らかだったはず。医療が濃厚に関与することで、より悲惨で、より非人間的なものに変貌させてしまった。世の中で、一番の怖がりは医者だろう。それは、悲惨な死ばかりを目の当たりにしてきたせいでもある。
病院での死が、如何に悲惨であるか、そして自然死をするためには、この国では結構大変なことがわかる本書です。
あなたは、苦しんで死にたいですか?それとも、安らかにこの世を去りたいですか?
共に考えて生きましょう。
こんな感じで、おそらく長期連載をします。
http://psalm098.blogspot.jp/
お手数ですが、ブックマークの方は、変更を願います。
-----
今生きている方々、全員に読んで欲しいと願うほど、実に明確な本だった。特に、家族に要介護者がいたり、病者・要介護高齢者にかかわる職業の方々にはぜひとも読んで欲しい。
図書館にも蔵書していると思われるが、予約数でいっぱいのはず。新書で安いので、購入したほうがいいかもしれない。
著者は、京都大学卒業、医者となり、現在は特養の医者をしている。もう、高齢者の域だが、考え方は独特の価値観を持つ。
本書の内容をざっくりと説明すると、死生観の構築である。
加えて、医療の不手際の指摘。その医療と、この国の人びとはどのようにかかわりを持つか=距離感の取り方、を著したものである。
「はじめに」のところで、すでに、blogするには内容が濃すぎる。
○医者には序列がある。大学病院の医者が頂点で、以下、国立病院→日赤→済生会→県立・市立の「税立病院」と続き、次が、民間の大病院→中小病院→一番下が町医者(開業医)→その下に老人ホーム等福祉施設の医者。
もう、ここで、すでに、コメントしたい。
医者はヒエラルキーによって成り立っている。それはまるで大会社のようだ。同じ「医者」を名乗っていても、確実に序列が生まれている。ところが、大学病院の医者は一番最下層の「町医者(開業医)、老人ホーム等福祉施設の医者」より「腕が良くて、病気のことは何でも知っている。絶対に治してくれる」と思ったら大間違いである。逆もある(経験上、開業医さんの方が、レベルが高い。特に在宅医療専門の医師はピンキリではあるものの、少なくとも「生活」を視点に、医療を行ってくれる)。
実にくだらない世界でしょ?
以下、引用を継続。
○病院では最後まで、何かと処置をする。いや、しなければならないところが「病院」。よって、「自然死」はありえない。在宅における死も、ふつうは、病院医療を引き継ぐ(在宅酸素とかリハビリとか投薬とか)。よって、ほとんど「自然死」はない。
○また、医者も、何もしないことには耐えられない。しかし、それは、「穏やかに死ぬのを邪魔する行為」なのだ。
○よって、ほとんどの医者は「自然死」を知らない。人間が自然に死んでいく姿を見たことがない。だから「死ぬのにも医療の手助けが必要」と信仰している。
○「死」という自然な営みは、本来穏やかで安らかだったはず。医療が濃厚に関与することで、より悲惨で、より非人間的なものに変貌させてしまった。世の中で、一番の怖がりは医者だろう。それは、悲惨な死ばかりを目の当たりにしてきたせいでもある。
病院での死が、如何に悲惨であるか、そして自然死をするためには、この国では結構大変なことがわかる本書です。
あなたは、苦しんで死にたいですか?それとも、安らかにこの世を去りたいですか?
共に考えて生きましょう。
こんな感じで、おそらく長期連載をします。