2005年に本家アニメの声優陣交替・新シリーズ開始を
記念して描かれたといいますが未だ色々火種がくすぶっている,
「実はのび太が発明者」版“ドラえもん最終話”ようやく見ました。
感想としては,よく出来てますね。
すじ自体はそれを書いたブログで読んで知っていたのと
やたら「泣けた」という感想が飛び交っているため
ちょっと構えて読んだせいもあって
泣きはしませんでしたが,本当によくできている。
突然動かなくなったドラえもん,未来の技術で直してもらおうにも
なぜか未来の人間は関与を禁じられドラミちゃんも手出しができない。
のび太は一念発起して勉学に励み,世界的なロボット工学の第一人者に。
そしてついにドラえもんの修理に成功,しずかちゃんの見守る中,
「のび太君、宿題終わったの」と目覚めたドラえもんと抱き合う…。
話自体はよくできているし,絵も原作のタッチを忠実に押さえてる。
模写っちゃ模写だけど,変に自分のものにしていないところ
すんなり入っていけますしね。
身内で楽しむこと,ネットで公開すること…くらいは
いいんじゃないかなぁと思いますけどね。
ていうか,プロの漫画家がそれぞれの『ドラえもん』を描く
トリビュート本なんて企画もありうるわけで,もし
それが実現するならその中に入れてもいいくらいのもんじゃ
ないでしょうかね。
2005年に秋田書店の企画で展開された『ブラック・ジャック』のトリビュート版『ブラック・ジャックalive』『ブラック・ジャックM』の中にはひどいのもありましたしね…。
私はここ数年全然見ていませんけれど,現在のアニメ『ドラえもん』にしても原作のクオリティを相当貶めているという話も聞きますし(個人的には,十年以上前の時点でもオチを改悪してがっかりした記憶がありますけどね。日曜朝にやってた時代はあまりそんな記憶はないですけど…一度,のび太の声が変わった記憶があるんですけど気のせいかなぁ??)
少なくとも20年くらい前に広まった
「のび太植物状態説」
「サザエさん一家,海(海生生物)に還る」
類の都市伝説に比べればよっぽど健康的で心温まる話ですよ。
 読んでよかったという人が多いんじゃないですかね。
読んでよかったという人が多いんじゃないですかね。
まぁ1万冊以上も売り上げて儲けてしまった(何百万円 )こと,
)こと,
「これが最終回」といかにも本物だと勘違いしてしまうバカ人が
出てきだして,本物のイメージに影響を与えかねなくなってきた
という2つが問題といえるでしょうかね。
痛いニュースでは,この同人作者にネット日記(さるさる日記は
ブログというよりは自分BBSとでもいうべきものでしょう)で
噛みついたアシスタントが「お前こそ勝手に藤子(F)先生の遺志を
代弁するな 」と逆に血祭りに上がってますけど
」と逆に血祭りに上がってますけど
誰もが「自分のもの」という思いを持っていて,ちょっとした弾みで
暴走させてしまいかねない国民的名作の宿命,というか
罪なところですね。
下に上げたように,2000年に公開された香取慎吾くん主演の
映画『ジュブナイル』この「のび太が発明者説」の元ストーリーを
下敷きにして作られた作品。このことは当初から公言されており
小学館も藤子プロも公認。(寡聞にて知らなかったヨまったく)
■関連サイト
 【知はうごく】「模倣が生む才能」著作権攻防(6)-3(産経新聞2/1)
【知はうごく】「模倣が生む才能」著作権攻防(6)-3(産経新聞2/1)
 “作者”の田嶋安恵氏(男性説あり)のサイトは見つかりませんでしたけど
“作者”の田嶋安恵氏(男性説あり)のサイトは見つかりませんでしたけど
検索すると,フラッシュ版が本当にそこら中に上げられてますね。
俺様イズムとか爆笑オッシャとか。
 ウィキペディアではけっこう詳しい解説がなされていますね。
ウィキペディアではけっこう詳しい解説がなされていますね。
→田嶋安恵
田嶋 安恵(たじま やすえ)は、日本の漫画家。女性。
代表作はボードゲームがテーマの作品「アクア・ステップ・アップ」。
成年コミック作家でもあり、同人作家(サークル「GA・FAKE」代表)でもある。
2005年に発表した「ドラえもん最終話」では、田嶋・T・安恵という
ペンネームを使用。
ちょ・・・・・・『ドラえもん最終話』同人誌,20ページって。
実質,この16頁の作品で1冊仕上がっちゃってんだ。
同人「誌」なのか?それは。
ヤフオクみたら1万数千円とか値段ついてるし。
 ドラえもんの最終回
ドラえもんの最終回
本物の最終話も3バージョンあったとは!(TC第6巻収録のもの以前の2話は
単行本未収録。『小学4年生』単独掲載時,読者は年度末で5年生に進んで
しまうために3月号で「最終話」を載せる必要があった。そのうちの1本が
日テレ版アニメの最終話に使われた)
都市伝説の最終話もそれぞれのバージョンについて
いきさつなど解説されてます。
 映画 《ジュブナイル》 と 『ドラえもん』~
映画 《ジュブナイル》 と 『ドラえもん』~
映画『ジュブナイル』山崎貴監督 インタビュー
「影響を受けてるんじゃなくて、原作と言ってもいいんです。」
「藤子先生に捧ぐ」と入れさせてくださいと藤子プロにお願いしたら、
それは是非と言ってくださったのでクレジットを入れることができ
結局小学館もスポンサーにつき,びびっていた“原作者"の名前も
スペシャルサンクスで入れることができた…と。
なんかええ話になっとるやんかw。
********************
この駄文を読んで,同感・面白かった・参考になったという方は
→クリック♪(人気ブログランキングにジャンプします。
2/11現在,テレビラジオ部門40位。救援お願いします…
もしくは ブログランキング にほんブログ村
ブログランキング にほんブログ村 ブログ村では8位!
ブログ村では8位!
ベスト10復帰いつ以来だろう…ありがとうございマス。
********************
記念して描かれたといいますが未だ色々火種がくすぶっている,
「実はのび太が発明者」版“ドラえもん最終話”ようやく見ました。
感想としては,よく出来てますね。
すじ自体はそれを書いたブログで読んで知っていたのと
やたら「泣けた」という感想が飛び交っているため
ちょっと構えて読んだせいもあって
泣きはしませんでしたが,本当によくできている。
突然動かなくなったドラえもん,未来の技術で直してもらおうにも
なぜか未来の人間は関与を禁じられドラミちゃんも手出しができない。
のび太は一念発起して勉学に励み,世界的なロボット工学の第一人者に。
そしてついにドラえもんの修理に成功,しずかちゃんの見守る中,
「のび太君、宿題終わったの」と目覚めたドラえもんと抱き合う…。
話自体はよくできているし,絵も原作のタッチを忠実に押さえてる。
模写っちゃ模写だけど,変に自分のものにしていないところ
すんなり入っていけますしね。
身内で楽しむこと,ネットで公開すること…くらいは
いいんじゃないかなぁと思いますけどね。
ていうか,プロの漫画家がそれぞれの『ドラえもん』を描く
トリビュート本なんて企画もありうるわけで,もし
それが実現するならその中に入れてもいいくらいのもんじゃ
ないでしょうかね。
 |  |
私はここ数年全然見ていませんけれど,現在のアニメ『ドラえもん』にしても原作のクオリティを相当貶めているという話も聞きますし(個人的には,十年以上前の時点でもオチを改悪してがっかりした記憶がありますけどね。日曜朝にやってた時代はあまりそんな記憶はないですけど…一度,のび太の声が変わった記憶があるんですけど気のせいかなぁ??)
少なくとも20年くらい前に広まった
「のび太植物状態説」
「サザエさん一家,海(海生生物)に還る」
類の都市伝説に比べればよっぽど健康的で心温まる話ですよ。
 読んでよかったという人が多いんじゃないですかね。
読んでよかったという人が多いんじゃないですかね。まぁ1万冊以上も売り上げて儲けてしまった(何百万円
 )こと,
)こと,「これが最終回」といかにも本物だと勘違いしてしまう
出てきだして,本物のイメージに影響を与えかねなくなってきた
という2つが問題といえるでしょうかね。
痛いニュースでは,この同人作者にネット日記(さるさる日記は
ブログというよりは自分BBSとでもいうべきものでしょう)で
噛みついたアシスタントが「お前こそ勝手に藤子(F)先生の遺志を
代弁するな
 」と逆に血祭りに上がってますけど
」と逆に血祭りに上がってますけど誰もが「自分のもの」という思いを持っていて,ちょっとした弾みで
暴走させてしまいかねない国民的名作の宿命,というか
罪なところですね。
下に上げたように,2000年に公開された香取慎吾くん主演の
映画『ジュブナイル』この「のび太が発明者説」の元ストーリーを
下敷きにして作られた作品。このことは当初から公言されており
小学館も藤子プロも公認。(寡聞にて知らなかったヨまったく)
■関連サイト
 【知はうごく】「模倣が生む才能」著作権攻防(6)-3(産経新聞2/1)
【知はうごく】「模倣が生む才能」著作権攻防(6)-3(産経新聞2/1)  “作者”の田嶋安恵氏(男性説あり)のサイトは見つかりませんでしたけど
“作者”の田嶋安恵氏(男性説あり)のサイトは見つかりませんでしたけど検索すると,フラッシュ版が本当にそこら中に上げられてますね。
俺様イズムとか爆笑オッシャとか。
 | アクア・ステップ・アップ (1)ラプンツエルマーメイドレインDual Symphony |
 ウィキペディアではけっこう詳しい解説がなされていますね。
ウィキペディアではけっこう詳しい解説がなされていますね。→田嶋安恵
田嶋 安恵(たじま やすえ)は、日本の漫画家。女性。
代表作はボードゲームがテーマの作品「アクア・ステップ・アップ」。
成年コミック作家でもあり、同人作家(サークル「GA・FAKE」代表)でもある。
2005年に発表した「ドラえもん最終話」では、田嶋・T・安恵という
ペンネームを使用。
ちょ・・・・・・『ドラえもん最終話』同人誌,20ページって。
実質,この16頁の作品で1冊仕上がっちゃってんだ。
同人「誌」なのか?それは。
ヤフオクみたら1万数千円とか値段ついてるし。
 ドラえもんの最終回
ドラえもんの最終回本物の最終話も3バージョンあったとは!(TC第6巻収録のもの以前の2話は
単行本未収録。『小学4年生』単独掲載時,読者は年度末で5年生に進んで
しまうために3月号で「最終話」を載せる必要があった。そのうちの1本が
日テレ版アニメの最終話に使われた)
都市伝説の最終話もそれぞれのバージョンについて
いきさつなど解説されてます。
 映画 《ジュブナイル》 と 『ドラえもん』~
映画 《ジュブナイル》 と 『ドラえもん』~映画『ジュブナイル』山崎貴監督 インタビュー
「影響を受けてるんじゃなくて、原作と言ってもいいんです。」
「藤子先生に捧ぐ」と入れさせてくださいと藤子プロにお願いしたら、
それは是非と言ってくださったのでクレジットを入れることができ
結局小学館もスポンサーにつき,びびっていた“原作者"の名前も
スペシャルサンクスで入れることができた…と。
なんかええ話になっとるやんかw。
********************
この駄文を読んで,同感・面白かった・参考になったという方は
→クリック♪(人気ブログランキングにジャンプします。
2/11現在,テレビラジオ部門40位。救援お願いします…
もしくは
 ブログランキング にほんブログ村
ブログランキング にほんブログ村 ブログ村では8位!
ブログ村では8位!ベスト10復帰いつ以来だろう…ありがとうございマス。
********************
 | ドラえもん (45)藤子・F・不二雄/小学館実質最終話となった『ガラパ星から来た男』は映画版なみのスケールと劇場公開の制約に縛られないシュールさと毒の鋭さで評価が高い。 |
 |
 |
 |
 |
| マンガと著作権―パロディと引用と同人誌と米沢 嘉博コミケット | ドラことば~心に響くドラえもん名言集小学館 | 映画ドラミちゃん ミニドラSOS!!!/帰ってきたドラえもん/ザ・ドラえもんズ ムシムシぴょんぴょん大作戦!ポニーキャニオン | ジュブナイルメディアファクトリー |















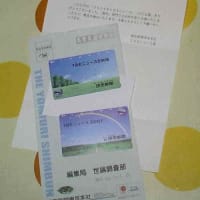
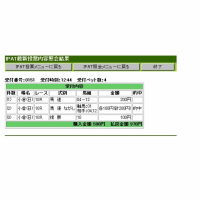






もう『ドラえもん』に対して興味が失せたのが15年以上も前ですから、最終話を読みたいという気持ちは特にないのですが、こういった同人誌に著作権を絡める事に興味があります。ただ、著作権自体あまりよく分かってないのですが(爆)。
今回の、小学館の態度は、ちょっと横暴ではないかと思います。じゃあ、今まで『ドラえもん』の同人誌を描いた人の収入は、みんな小学館の物になってしまうのかと…。許可云々言ってますが、こういう同人誌って、許可を得て作っている人って、少ないかなぁと思うんです(こういった問題は素人ですので、トンチンカンな事を言っているかも知れません)。
「道徳の教材にして」と言われるまでに達したこの人気、描いた本人は、どう思っているのでしょうか?
ネットでも取りあげられ,まとめている人も結構いらしゃいましたね。
今回のケースでいえば,産経新聞の特集を取材した記者のブログによると,
出版社側も,(1)多すぎる同人たちをいちいち帰省する手間は事実上不可能
(2)数百部程度なら著作者の金銭的損害も高が知れている
(3)同人の活動が原作の人気を裏で支えている側面も否定できない
などの理由から,見て見ぬふりをしているというのが
実情だそうです。
今回特に問題になったのは
(1)同人作者が既に商業デビューしているプロ
(2)冊数が万を超え,数百万~1千万の売上げを出し無視できるレベルではない
(3)この同人本がオリジナルとそっくりのデザインの表紙で書店にも並び,
(「最終回がない」ことが前提の)本物への世間の認識を崩す
といった理由によるものであろうとのことでした。
また,別サイト(ブログ)によると,同じ小学館でも
名探偵コナンの場合「世界観を崩さない悪意のないものならOK」
金色のガッシュ27巻では作者が同人誌をもらって嬉しかったと書いている
などの例があり,小学館だから画一的・一方的に
同人を敵視し潰そうとしてる訳ではないようです。
なんといっても藤本先生が亡くなられていることが
(最終回話の乱立にせよ,権利を主張する連中の横暴にせよ)
話をややこしくしているんですよね…。
手塚先生の作品のように皆,それぞれの愛をもって
ともに認め合いながら歩めないのか
本当に残念です。
ドラえもんネタでトラバが来るとは思ってなかったので多少びっくりしました。(^_^;)
同人誌と著作権の関係は難しいです。
個人で楽しむ分なら著作権には触れません。が、身内で楽しむ限り著作権には抵触する関係にあるでしょう。ただ、どこから著作権「侵害」の程度に至るのかはっきりしません。
『今回のドラえもん最終回』同人誌は、絵が似ている程度を超えて正確に模写していること、業として販売していること、そして大きい要素は、内容が最終回であり、まだ終了していない『ドラえもん』を終了させたと錯覚させることで、著作権侵害が認められたんじゃないかと思います。
著作権侵害の限界があいまいなままだと、同人誌などの漫画文化の裾野が広がらなくなって、かえって発展に支障が出ないか心配します。
大局的な見地から著作権のあり方を定めて欲しいものですね。
トラバありがとうございました。
私も取材の際に、真っ先にウィキペディアを読みました。
それにしても、ウィキペディア日本版は、アニメや漫画関係のネタは異様に充実していますねw
同人誌を著作権法的にどう位置づけるかは、簡単に答が出ない問題でしょう。
現在のようにグレーゾーンのまま推移する中で、著作権をめぐる環境が少しずつ変わっていくのを待つしかないように思えます。
> 誰もが「自分のもの」という思いを持っていて,ちょっとした弾みで
暴走させてしまいかねない国民的名作の宿命,というか
罪なところですね。
同時に「同じ作品を読んでも、人によって作品解釈は異なる」という認識の薄い方の多さを、再確認させてくれる事件でもあったと思います。
自分とは違う解釈やそこから生まれる作品も「アリ」と考えられる人が増えないと、同人誌問題はこじれたままのような気がします。
まさに今回の問題はそこにあるでしょうね。
下にコメントを下さっている(赤い帽子の)小人さんが
まとめておられるように
http://kobitosan.iza.ne.jp/blog/entry/115592/
「ネットで流すなら利益を得ない・独占しない
同人誌で出すならオリジナル(の画風・アイデア)で」
という暗黙のルールを悉く破った
(それだけに読者に訴えかける魅力も破壊的に強かった)
禁断の“作品"と言えるでしょうね。
> ドラえもんネタでトラバが来るとは思ってなかったので
> 多少びっくりしました。(^_^;)
ご専門の法律・試験のテーマからはやや外れた話題でしたが
こういう題材のほうが逆に検索でやってくる人が
多かったりするんですよね。
■産経新聞・知的財産取材班 上野記者様
直々にTB・コメントいただき恐縮です。
著作権に関する記事やブログで書かれた見解については私も賛成で(松本センセイにも困ったものです),理屈ばかりこね回して訳のわからない記事を書くマスコミが多い中,地に足が着いている感じですごく親近感を覚えました。これからも益々の御活躍を期待いたします。
本当にウィキは一体誰が書いているのやらと思うくらい詳しいですね。
はてなも,ネットの話のごく一部の話題(例えばバトンの由来とか)に限ると「なぜそんな事を知っている?!」と驚くくらい,現代用語の基礎知識が頼るくらいすごかったりします。
■小人@にうすいぢり さん
記者ブログへのTBから今回の問題に関する記事(前)→(後)と
読ませていただきましたけど,同人・Webでの不文律を
「まさにその通り」という明快な形でまとめられていて
非常にすっきりと腑に落ちました。
> 自分とは違う解釈やそこから生まれる作品も「アリ」
> と考えられる人が増えないと、同人誌問題はこじれたままのような気がします。
この話は,2次創作に対する著作権者側の不寛容性に
ついて言われているのでしょうか?(違う意図でしたらすみません。
ちょっと今回の田嶋T安恵問題とは方向が違うようですし
作成者または読者,どちらの方向について述べられているのかなと思いまして。)
よくフランスではパロディは法律で認められているとか
いいますし,ちょっとした引用やパロディ・二次創作なら自由にさせてほしいってのは思いますね。
現状で黙認されているグレーゾーンの認識が
(産経記者さんも指摘されているように線引きがはっきりしていない
点が悩ましいところですが)落としどころなのかなという気はします。
> この話は,2次創作に対する著作権者側の不寛容性に
ついて言われているのでしょうか?
権利者と読者側の両方です。重きを置いているのは読者側ですが。
パロディー同人誌の愛好者以外の方は「同じ作品に触れても、内容を理解する段階で個人の体験などが反映されているので、それぞれに作品解釈が違う」という認識の薄い場合が多いように感じます。
パロディー作品は、個々の解釈から物語を生み出すものですから、どんなに素晴らしい作品であっても「自分の解釈と違うことが許せない、その作品を無視することも出来ない」タイプの方が必ず現れます。
D.D.さまが例に挙げられた「公認のトリビュート作品」の場合は、編集者が原作から離れすぎた解釈や設定を補正することも、パラレルワールドであることを予め読者に認識させることが可能です。
(編集部がクッションになるわけですね)
この部分がアマチュア作品との大きな違いであり、上記のようなコントロールが不可能なことが、アマチュアのパロディー作品を権利者側が野放しに出来ない理由でもあると考えています。
> 現状で黙認されているグレーゾーンの認識が
(産経記者さんも指摘されているように線引きがはっきりしていない
点が悩ましいところですが)落としどころなのかなという気はします。
<オフレコ>不倫と同じように、完全に認められてない点が、背徳感があってイイという考え方も…</オフレコ>
おぉう,なるほど。
え~,例えば,読者の中には某アシ氏のような「許せない」キレキャラも
いらっしゃるとか,そういうことでしょうかね。
(あの人は内容の解釈以前に,勝手に描いてそれが
評判になっているのが許せないという心情が露骨ですから
小人さんが想定している読者の方はほかにいろいろ
直接身近とかにいらっしゃるのかなとも読み取りました
…ということでよいでしょうか??)
→公認のトリビュート本は編集側がクッションになって
→読者に別物であると認識させることが可能の件
これはこれで,田嶋T安恵本でも,表紙を黒1色刷りにするとか
大きく「藤子プロとは関係ありません」(「非公認」と書くと逆に
公認とまぎらわしい)と書くとかして回避できたのでは…
とああいえばこういうで線が引けないという解釈も。
※店頭売りをしてあの表紙ですから,やっぱ何度考えても
アウトですね。この件は。
ただ,僕もこのブログでエイプリルフールのウソ記事を書いたとき
エイプリルフールだという断り書きをどうしても
目立たなく書こうとしてしまった記憶がありますから
デザインは極力本家に似せて,作者名とか出版社名さえ
自分たちの名前にしておけば(本物じゃないことは)わかるだろうと
した気持ちもわからなくはないです。
→<オフレコ>の件
激しく々意ですw
本当にお恥ずかしい。
気づかせてくださって有難うございました。