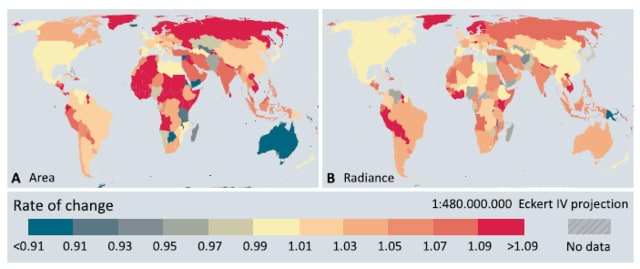「ヒアリに刺されると死ぬことがある」と恐怖で語られた2017年。
詳しく見ると、ヒアリで恐いのは毒ではなく、アナフィラキシー。
これは蜂に刺されるときと似ています。
蜂に刺されると、その毒で誰でも腫れて痛いですね。
しかし、重症化してアナフィラキシー・ショックを起こし命に関わるのはほんの一部の人です。
これは、ハチ毒に対してアレルギーがあるかどうかにより決定すること。
ヒアリでも、その毒で誰でも痛い思いをするようです。
しかし、重症化してアナフィラキシー・ショックを起こし命に関わるのはほんの一部。
蜂と同じく、ヒアリ毒に対するアレルギーの有無で重症化するかどうかが決まります。
ハチ毒に対するアレルギーは林業に携わる人に多い傾向があります。
何回も刺されてアレルギーを獲得するのです(感作といいます)。
という内容の記事を紹介します;
■ ヒアリ、正しく恐れて 救急医のサイト、閲覧20万超
(2018年01月03日 朝日新聞デジタル)
毒を持つ南米原産のヒアリが全国各地で見つかるなか、救急医が「正しい知識を持ってほしい」と毒の症状や治療法を紹介したサイトが20万回以上閲覧されている。
サイト「医療者のための正しく恐れるヒアリ学」は、名古屋掖済会(えきさいかい)病院救命救急センターの安藤裕貴医師(39)が作成した。「ヒアリに刺された時は冷やす」といった対処法や、刺された時に起きうる急激なアレルギー反応で、死に至る可能性もある「アナフィラキシーショック」についての基礎知識にも触れている。
また、ヒアリ生息域の住人の約5割が年に1回刺されている米国内の現状などを紹介。医療関係者向けだが、専門知識のない人でもわかる内容だ。研究が進んでいる米国の論文約20本を読み込み、最新の情報をまとめた。安藤医師は「ヒアリの毒に致死性があるという誤ったイメージが先行しているが、毒そのもので死ぬことはない。気をつけるのはアナフィラキシーのほう。刺されたらどうなるのかという情報が少なかった」と話す。
環境省によると、ヒアリは昨年5月に兵庫県尼崎市で国内で初めて確認された。その後、浜松市や広島県呉市でもみつかり、12月25日までに12都府県で26事例が確認された。冬場は動きが鈍るが、暖かい土の中などで越冬し、春先に再び活動が活発になるとみられ、サイトが役に立ちそうだ。
安藤医師は「必要以上に恐れず、不安を和らげることにつながれば」とサイト作成の理由を語った。
上記サイトを見てみました。
ほほう、と頷いた箇所を列記します。
・ヒアリ生息地の住人の51%は1年に1回刺されている。
・ヒアリによるアナフィラキシーの発生頻度は7%(?)。
・「ヒアリに刺される」はお尻から出る針で刺されること。口で噛むのではない。
・一般的な局所症状は、刺された瞬間痛みが走り、1時間以内に腫れてきて、12時間以内に小さな膿疱ができ、大きな紅斑になって(17-56%)24-72時間続く、蕁麻疹が出ることもある。
・アナフィラキシーのほとんどは、刺されて15分以内(遅くとも1時間以内)に発症する。
・ハチ毒と交差反応性がある。
この中で気になった項目は「ハチ毒と交差反応性あり」。
ハチアレルギー患者では、初めて刺されたときはまだアレルギー体質になっていないのでアナフィラキシーなど強い反応は起こらないとされています。
だから、ヒアリも初めて刺された時に重症化することはない、と考えていましたが、ハチ毒と交差反応性があるとなると話は別。
ハチアレルギー患者さんは、初めてヒアリに刺されたときも同様の症状が出る可能性があるということになります(要注意!)。
詳しく見ると、ヒアリで恐いのは毒ではなく、アナフィラキシー。
これは蜂に刺されるときと似ています。
蜂に刺されると、その毒で誰でも腫れて痛いですね。
しかし、重症化してアナフィラキシー・ショックを起こし命に関わるのはほんの一部の人です。
これは、ハチ毒に対してアレルギーがあるかどうかにより決定すること。
ヒアリでも、その毒で誰でも痛い思いをするようです。
しかし、重症化してアナフィラキシー・ショックを起こし命に関わるのはほんの一部。
蜂と同じく、ヒアリ毒に対するアレルギーの有無で重症化するかどうかが決まります。
ハチ毒に対するアレルギーは林業に携わる人に多い傾向があります。
何回も刺されてアレルギーを獲得するのです(感作といいます)。
という内容の記事を紹介します;
■ ヒアリ、正しく恐れて 救急医のサイト、閲覧20万超
(2018年01月03日 朝日新聞デジタル)
毒を持つ南米原産のヒアリが全国各地で見つかるなか、救急医が「正しい知識を持ってほしい」と毒の症状や治療法を紹介したサイトが20万回以上閲覧されている。
サイト「医療者のための正しく恐れるヒアリ学」は、名古屋掖済会(えきさいかい)病院救命救急センターの安藤裕貴医師(39)が作成した。「ヒアリに刺された時は冷やす」といった対処法や、刺された時に起きうる急激なアレルギー反応で、死に至る可能性もある「アナフィラキシーショック」についての基礎知識にも触れている。
また、ヒアリ生息域の住人の約5割が年に1回刺されている米国内の現状などを紹介。医療関係者向けだが、専門知識のない人でもわかる内容だ。研究が進んでいる米国の論文約20本を読み込み、最新の情報をまとめた。安藤医師は「ヒアリの毒に致死性があるという誤ったイメージが先行しているが、毒そのもので死ぬことはない。気をつけるのはアナフィラキシーのほう。刺されたらどうなるのかという情報が少なかった」と話す。
環境省によると、ヒアリは昨年5月に兵庫県尼崎市で国内で初めて確認された。その後、浜松市や広島県呉市でもみつかり、12月25日までに12都府県で26事例が確認された。冬場は動きが鈍るが、暖かい土の中などで越冬し、春先に再び活動が活発になるとみられ、サイトが役に立ちそうだ。
安藤医師は「必要以上に恐れず、不安を和らげることにつながれば」とサイト作成の理由を語った。
上記サイトを見てみました。
ほほう、と頷いた箇所を列記します。
・ヒアリ生息地の住人の51%は1年に1回刺されている。
・ヒアリによるアナフィラキシーの発生頻度は7%(?)。
・「ヒアリに刺される」はお尻から出る針で刺されること。口で噛むのではない。
・一般的な局所症状は、刺された瞬間痛みが走り、1時間以内に腫れてきて、12時間以内に小さな膿疱ができ、大きな紅斑になって(17-56%)24-72時間続く、蕁麻疹が出ることもある。
・アナフィラキシーのほとんどは、刺されて15分以内(遅くとも1時間以内)に発症する。
・ハチ毒と交差反応性がある。
この中で気になった項目は「ハチ毒と交差反応性あり」。
ハチアレルギー患者では、初めて刺されたときはまだアレルギー体質になっていないのでアナフィラキシーなど強い反応は起こらないとされています。
だから、ヒアリも初めて刺された時に重症化することはない、と考えていましたが、ハチ毒と交差反応性があるとなると話は別。
ハチアレルギー患者さんは、初めてヒアリに刺されたときも同様の症状が出る可能性があるということになります(要注意!)。