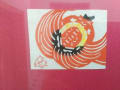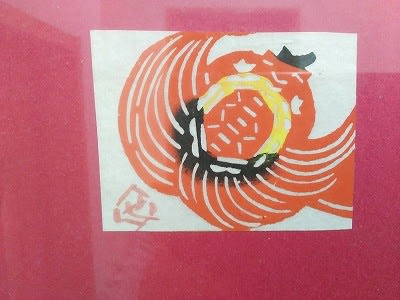ここ何回か、故玩館内部のガラスを紹介してきました。
今回と次回は、ステンドグラス(色付き)です。
今回は、故玩館そのものではなく、居住部や故玩館と居住部を繋ぐ通路脇のステンドグラスです。
いずれも、故玩館大改修の以前に設えた物です。
今回のステンドグラスは、3か所です。
まず、私たちの居住建物のLDです。

上方の横長押は、アコーディオンカーテンの名残です(昔、流行った(^^;)。もう、築45年になります。リフォームをしたとき、大工さんに取り付けてもらいました。
LDの奥の方にあり、普段、太陽の光があまりはいらないので、南をみても、こんな感じでステンドグラスがほとんどわかりません(^^;
部屋の明かりを強くして反対側から見ると、

それらしく見えます。

29.5㎝x58.5㎝。日本製。昭和。

こちらが、台所から南を見た様子です。
控えめな色使いなので嫌な感じはしませんが、チョッと地味すぎ?(^^;
次のステンドグラスは、玄関を入ってすぐ、故玩館へ通じる通路の始まりの場所です。20年ほど前に増築しました。
向こう側は、一応、家事室となっています。修理、修復などの作業や資料置場として使っています。
その間仕切りの戸に、建具屋に頼んでステンドグラスを入れました。

昼間は玄関口が明るいので、ほとんど目立ちません。
夜、中で作業のため電気をつけると、

こんな感じになります。

19.0㎝x48.3㎝x2枚。英国製。20世紀。


設えてみてわかったのですが、日本の家屋(多少洋風でも)に本場、イギリスのステンドグラスはしっくりこないようです。特に、赤ガラスが入っていると、少しの間は綺麗ですが、いつも見ているとだんだん嫌気がさしてきます'(^^;
ここから階段を上がって故玩館へ行きます。
通路の右脇は、先日のブログで紹介したように洗面所になっています。

ここは光をひろう可能性の無い場所です。そこに、イギリスのステンドグラスが入っています。光が少ないことが幸いしてか、赤ガラスも違和感がありません(^.^)
洗面所の反対側は、トイレです。3か所目のステンドグラスがここにあります。

でも、ちょっと見た限りそれらしき物はどこにも・・・
このトイレ、広めなのです。広いのは良いのですが、少々落ち着きません。まあ、二人同時に入ることは無いにしても、何となく落ち着かないのです。
そこで、大と小の間を、間仕切りしました。

そして、そこへステンドグラスを入れました。

少の方・・・左に明るい解放感。

大の方はこんな感じ。


ぼやーと霞んでいるのが良いですね。

35.5㎝x78.9㎝。日本製。昭和。
赤ガラスを排して、紫、黄、青の配置が絶妙です。
次回のブログも含め、これまでステンドグラスをあちこちに使ってきました。どれも今一歩でした。が、この品だけは、我ながらうまくいったと思える成功例です。ステンドグラスを取り付けた大工さんや故玩館来訪者にほめていただいています(^.^)