久しぶりの面白古文書です。
ひねったお題はないのですが、やはり赤(不明)が出ました。読者諸氏のあたたかいサポートをお願いします(^.^)
右欄(東)と左蘭(西)の見立てが対応している(全部ではない)ので、右、左を対照させて載せます。

17.6cm x 22.9cm 。江戸時代後期(天保年間)。

重言見立
為御心得(おんこころえのため)
行司
半紙の紙
実子の子
施(ほどこし)の施行
重宝な宝

頭取
長町の長サ
厳(きびし)い厳(せつ、折?)かん
御ごぞさ(御御造作) 御造作:お手間、苦労
勧進元
大キな大佛
唐(から)の唐人

右:
大関 御御堂様
関脇 用水の水
小結 大キイ大名
前頭 山中(やまなか)の山中(さんちゅう)
前頭 勝負(かちまけ)の勝負附(しょうぶづけ) 勝負附:勝負の結果を書いたもの。
前頭 美しい美女
前頭 歩(かち)歩行(あるく) 歩(かち):徒歩
前頭 舟の船頭
前頭 赤いひぢりめん
左:
大関 神前の前
関脇 新米(しんまい)の米
小結 風呂屋のふろ
前頭 昼中(ひるなか)の白中(はくちゅう)
前頭 借銭(しゃくせん)の借(かり)
前頭 寺子の子
前頭 城下した
前頭 家内の内(うち) 家内:家屋の中
前頭 正月の月

右:
同 御神酒の酒
同 実子の子
同 小さい小おんな
同 すて子の子
同 何日(いつか)の日
同 抜身ヲ抜く
同 燈明を燈(とも)す
同 行列で行(いく)
同 ふり袖のそで
同 乗ものにのる
同 白髪の髪
左:
同 新酒のさけ
持びょう(病)持(もち)
同 大井川の川
月夜のばん(晩)
珍しい珍ぶつ(物)
巻物の一チ巻
同 流行が流行(はやる)
日雇に雇(やとわ)れ
同 下(しも)へ下(くだ)る
目のミへぬ目くら
同 つめたひ冷めし
遠い遠方
右:
同 都合(つごう)合(あわ)して
同 そろばんの名さん(算)
同 うたいうたう(謡い謡う)
同 さいせん(賽銭)の銭
同 黒いびんろうじ(檳榔子) 檳榔子:檳榔子の実で布を黒色に染めた。黒色は檳榔子黒とも言った。
同 ももだにのもも(桃谷の桃)
晴天の日より(和)
同 今の当世風
赤いしょうじょう(猩々)
寺のぼうさん
世ハ人 干物(かんぶつ)物(もの)
叡山の山
左:
同 夫ふ(夫婦)の二人づれ
明朝そうちょう(早朝)
同 寺丁のてら 丁<=>町
こち(東風)風がふく
同 〇水の水かミ
耳がつんぼ
同 こわいこわめし(強飯) 強い:元々は古語(女房言葉)、「固い」の意、現在も広く使用。
新しい新たく(宅)
信のゝおしな(信濃のお品?)
世ハ人
くさいへ(臭い屁)
穴(くさ)の穴(あな)













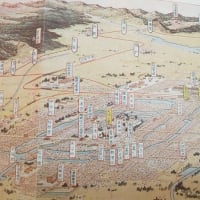




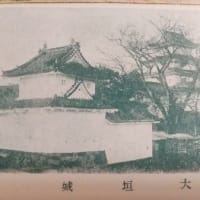
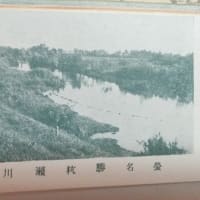
二つ目と三つめは見えにくいです。
番付も持っていらっしゃるなんて、、、
すごいですね。
大型本で、番付を集めたものがありますが、この番付は特に面白い内容ですね。
興味深い資料を公開してくださいまして、ありがとうございます。
言葉遊びみたいな感じですかね??
今回のものは前のものより読みやすいように感じました。かながふっているのがありがたいです。
毎回思うのですが200年前でもまるで外国語です笑(^^)
番付けには、実に色々なものがありますね。そのなかで、なるべくウィットに富んだものを探しては、紹介してきました。あらかたは済みました。絵解きが残ってますが、メチャクチャに難しいので、もう少し言葉遊びや生活面白百科を続けます(^^;
重言なんて、一番簡単な言葉遊びですが、当時の人たちもきっと「馬から落ちて落馬した」などと言って、ワイワイやっていたかと思うと、江戸時代がグッと近づきますね。
当時は、このようなもので、言葉遊びというか、言葉の勉強もしていたのでしょうか(^-^*)
はじめに見えたのは其時だったのですが、
疎水
というのも考えていました。
間違ったことを書き込み申し訳ございませんでした。
後の二ヶ所の文字は、私は目の調子が悪く見えていません。
いずれにせよ、面白い番付があるものですね。