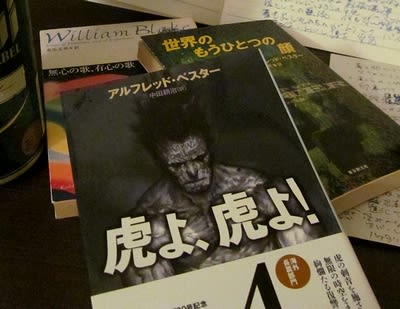2000年代(2000年~2009年)の海外SF短編を集めた年代別アンソロジーが、約20年ぶりに刊行されました。
編者は近年の海外SF紹介に目覚ましい活躍を見せる当代きっての敏腕レビュアー、橋本輝幸氏。
さて時代も編者も変わった新時代のアンソロジー、どんな作品が収録されているのでしょうか。

【エレン・クレイジャズ「ミセス・ゼノンのパラドックス」】
時代も場所も定かでないカフェで交わされる二人のミセスの会話が、ケーキをいかに分割するかという議論から
量子力学的な極限状況へとエスカレートする話。
昔ながらのSFホラ話の系譜に連なる掌編ですが、細かく読むと有名な「無限分割」のパラドックス以外にも
「場所のパラドックス」が出てきたり(カフェの場所が不確定なのはそのため)、パラドックスが解消されたら
ワームホールが生成されるなど、ゼノンのパラドックスに関する考察を多面的に取り入れた作品のようです。
でも詳細までは理解できてないので、詳しい人の解説が欲しいところ。
【ハンヌ・ライアニエミ「懐かしき主人の声(ヒズ・マスターズ・ボイス)】
知性化された犬と猫が拉致された御主人を奪回すべく、ハイテク装備をまとって奮闘する。
タイトルに象徴されるギャグめいたアイデアと頻出するガジェットに造語、そしてペットの主人愛が印象に残りますが、
知性化の功罪や人権の在り方、ディストピアといった深刻な問題の是非には触れずにひたすらカッコよさで押す物語。
昔ならサイバーパンクの亜流と言われそうで、ポスト・サイバーパンクというよりファッション・サイバーパンクっぽい。
ド派手なセンスを誇示する作風をクールと見るか、それともケバいと見るかは好みによりそうですね。
このキッチュな感覚こそSFだぜ!という人はすごく好きそうだけど、2000年代の看板を背負うには少々食い足りないかな。
【ダリル・グレゴリイ「第二人称現在形」】
意識は行動の後付けとして存在するものだとしたら、意識を遮断するドラッグで自我を失った肉体に後から生じたのは
いったい誰の人格なのか?
多重人格やクローニングなどで複数の自己と対峙する「私は誰?」的な物語は前からあったものの、
本作からは「私はみんなの思うような私じゃない!」という切実な叫びが感じられます。
自己同一性について疑問を抱える多くの人たちには特に強く響くでしょう。
さらに経済的・社会的に自立していないティーンエイジャーを主人公に据えたことによって、
親子関係や家族のかたちを問い直す普遍的な物語としても読めるのがうまいところ。
でも別人であろうと意識があるなら、それはもう哲学的ゾンビじゃないのでは?というモヤモヤ感もあり。
もしこれを日本に置き換えたら、むしろ会社や家族から逃げ出したい大人の間でドラッグが大流行するだろうし、
そうした人々を社会復帰させる仕事を描いたSFのほうが売れるかもしれません。
あと鈴木俊隆師の名前は直すべきだけど、増刷は難しそうなんだっけ……。
【劉慈欣「地火」】
炭鉱夫の父をじん肺で失った主人公は技術者となり、採掘によらず石炭をエネルギー化する技術を開発した。
しかしその実験は人間の想像を超えた大事故を引き起こす。
劉の強みは現実に存在する中央集権的国家の圧力を背景に、その中で生きざるを得ない個人の葛藤を鮮やかに描く点でしょう。
そんな社会における科学とは国家と人民の輝かしい未来を創るものであり、同時に立身出世の道具でもあります。
この素朴ともいえる科学観をめぐって理想と俗っぽさの間を揺れ動く登場人物たちの姿は、少し古いSFでよく見たタイプ。
1950年代から60年代の英米では社会批評を書くためにSFが用いられましたが、「地火」を含めた劉の作品には
その頃の作品に感じた生真面目さと未来志向、そして破天荒な描写を躊躇しない蛮勇があります。
いわば一周回ったところに中国SFブームが来たのかな……という印象もありますね。
でも最先端SFの多くが個の問題を書くことに執着する中で、国家や社会といった「大きな問題」を取り上げた作風が
広く支持されるのは、なかなか興味深いです。
本作は2000年の発表ですが、大惨事を食い止めようと奮闘する人々の姿やその先の展開は我が国の原発事故に驚くほど似ています。
作中で「空は落ちない」という格言を叫んで動揺を収めようとする人物が出てきますが、空だって落ちるときには落ちるということを
2020年に生きてる我々は既に経験済なんですよね……。
最後の章はとってつけたようでいかにも政府のプロパガンダ的ですが、記述をよく読むと年代の異動や事実の隠ぺいが示唆されています。
ここに情報操作や歴史修正主義に対する著者からの異議が隠されていると思いました。
【コリイ・ドクトロウ「シスアドが世界を支配するとき」】
リアルとネットの双方で発生した大規模テロは全世界を一瞬にして崩壊させた。
職場のクリーンルームで死を免れたシステムエンジニアは同僚と共に世界各地の同業者と連絡を取り合い、
新たな世界秩序の構築を目指して奮闘する。
2006年という発表時期は同時多発テロの余波も強く残っており、この翌年には事件の影響を強く感じさせる
『ユダヤ警官同盟』が発表されて話題を集めました。
アメリカの隣国であるカナダにとっても「明日世界が終わるかもしれない」という不安と隣り合わせだったはずで、
そうした危機感が作中のリアルな描写に表れているのでしょう。
バイオ兵器やサイバー攻撃との複合テロというビジョンは、世界の破滅なら核攻撃というそれまでの固定観念を覆したとも言えそう。
姿こそ出てこないものの、危機的な状況のグーグルを束ねる女性リーダーも主人公の男性SEよりキャラが立ってました。
それにしても、システム復旧に出動した管理者が世界中に生き残っているという設定はいささか楽天的じゃないかな。
リアルが滅んでもネット世界は生き延びるから、我々はそこを守って民主的に運営しなきゃ!みたいな感覚もちょっとなあ。
これでは21世紀のギーク版「コージー・カタストロフ」じゃないの?という不満も感じました。
【チャールズ・ストロス「コールダー・ウォー」】
ソ連が崩壊しなかった世界、冷戦は悪化の一途を辿り、東側は核を超える兵器として超次元の存在を利用する計画を進めていた。
これを阻止すべく西側諜報員も動き出すが、はたしてその結末は。
宇宙開発が進まなかった世界なので大陸間弾道弾も無さそう……といった側面からも考察できそうな作品。
異世界から来た邪神を大量殺戮兵器に使うという発想は宗教対立による世界紛争へのアンチテーゼであり、
核兵器の原料にウラヌスやプルートーといった神の名が使われていることへの皮肉かもしれません。
そして「残虐行為記録保管所」のタイトルがバラードに由来するように、その原型とも思われる本作では
かつてバラードが多用した、いくつもの断章を重ねていく「濃縮小説」の手法が用いられています。
さらに邪神との接触がWWⅡのナチス・ドイツから連綿と続くものであると示されることで、
本作もまた大量殺戮の時代における「残虐行為展覧会」を狙ったのではないかとも感じますね。
【N・K・ジェミシン「可能性はゼロじゃない」】
「ありそうもない出来事が次々と発生する」という怪現象に見舞われたニューヨークでは、確立的に低い事件も日常茶飯事。
そして住人たちは効くかどうかもわからないお守りに身を固め、毎日を懸命にやり過ごす。
マンハッタンを舞台にしていることから同時多発テロを直接的に示唆する作品なのは間違いないですが、
かつて地下鉄サリン事件や東日本大震災と原発事故を経験し、いま新型コロナウイルス禍のど真ん中で暮らす
われわれ日本人にとっても、大変身につまされる話です。
統計学的にまれな出来事が立て続けに起きるという設定はハインラインの名作「大当たりの年」を思わせますが、
あちらが幕切れに破滅の気配を漂わせるのに比べると「可能性はゼロじゃない」の終わりには希望が感じられます。
たぶんこの希望こそ、著者が書きたかったものじゃないかな。
何の変哲もない日々が突然断ち切られる不安、「いつ何が起こるかわからない」という不穏さが毎日の生活にも影を落とす世界。
でもそれこそ人生本来の姿なのではないか?という逆説を問いかけることで、ジェミシンは毎日を生きることの幸福と不思議さを、
SFならではの表現で見事に書ききったと思います。
「不確実性の時代」を生きる人々の不安と葛藤をユーモアも交えて描きつつ、その生活に寄り添うことで一種の人間賛歌にもなっており、
2000年代を最もよく象徴する傑作のひとつだと思います。
【グレッグ・イーガン「暗黒整数」】
異なる数学を基盤とした世界同士の接触が破滅の危機をもたらした「ルミナス」の物語から10年後。
異世界への新たな干渉が発生し、かつて事件の解決に関わった数学者たちは再び世界を救うため行動を起こす。
鍵となる暗黒整数の理屈はよくわからなくても、別世界の数学が入り込むことで世界全体にエラーが生じてしまうと考えれば、
とにかく世界ヤバい!という雰囲気はなんとなくつかめるはず。
「ルミナス」には2000年問題への目くばせが感じられましたが、「暗黒整数」は同時多発テロ以後も世界を揺るがし続ける
「異なる原理によって成立する二つの世界」の交わらなさを、数学原理に託しながらも比較的ストレートに書いています。
そして前作ではまだ対話の余地もあった異世界との交流は、本作でほろ苦い結末を迎えます。
これこそ前作から10年の刻を経た世界の変化を如実に示すものでしょう。
90年代傑作選からの続き物として本作が選ばれたのも、実はこの変化を見せるためだったりとか……?
【アレステア・レナルズ「ジーマ・ブルー」】
強化された身体で真空からガス惑星までを踏破し、宇宙空間に巨大な前衛芸術を構築する謎の芸術家ジーマ。
その作品に使用されるトレードマークの色「ジーマ・ブルー」には、彼の秘められた生涯との深い関係があった。
NETFLIXで発表されたアニメシリーズ「ラブ、デス&ロボット」で映像化された一編。
その原作を収録する企画によって、2000年代以降の年代別傑作選が出版できる道が開けたとも考えられます。
意識と記憶を論じることで美の意味を問い直す物語は、インスタグラムやライフログという形で全ての行動を記録すること、
あるいはコンシェルジュAIに決定権を委ねることが孕む問題点を経由し、やがてはポストヒューマンを超えたポストライフ、
すなわち人生の仕舞い方へと行きつきます。
そのときジーマの正体は既に重要ではなく、聞き手は彼を通じて「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」
という根源的なテーマを突き付けられるのです。
全体を見ると、年代別傑作選の収録作にヒューゴー賞もネビュラ賞も含まれてないのはこれが初めてですね。
とはいえ両賞の価値がまるでなくなったというわけでもなく、コニー・ウィリスやテッド・チャン、ケリー・リンクら、
主要な賞の常連組については既に作家別の単行本が出ています。
でもSFマガジン2020年6月号でらっぱ亭さんが「零號琴にも通底する」と評したユージイ・フォスターのネビュラ賞受賞作
"Sinner, Baker, Fabulist, Priest; Red Mask, Black Mask, Gentleman, Beast"はこの機会に訳して欲しかった。
個々の作品だけ見れば出来栄えに偏りも感じるし、80年代や90年代の傑作選に比べると「マスターピース」と呼ぶには
ちょっと弱いかなという印象もあります。
それでも全体を通読して「よいセレクトだなあ」と思えるのは、収録作が互いに共通のテーマを持っているからでしょう。
例えばそれは同時多発テロ以後の不確定な世界、戦争への不安、意識や自己同一性への疑い、ポストヒューマニズム志向であり、
読者は読み進めるうちにこれらのテーマを異なる作品から繰り返し読み取って、その時代の輪郭をイメージできるわけです。
このあたりは編者の選択眼が光るところですね。
過剰に技巧的だったりSFとFTの境界にあるような作品もないので、SFになじみのない人が手に取るにもよいでしょう。
21世紀最初の10年をまとめたショーケースとしては粒のそろったアンソロジーだと思います。
その一方、2000年代前後に頭角を現した、あるいは時代を象徴する作家に絞ろうとするあまり、
それ以前からのベテランが引き続き活躍していることを示す作品が入ってないのは少し残念です。
かつて80年代SF傑作選にもゼラズニイやジョアナ・ラスの新作が収録されていたように、
2000年代に日本で再評価が進んだベテラン作家の新作も採って欲しかった。
例えば2004年に『ケルベロス第五の首』 2006年に『デス博士の島その他の物語』が単行本として出版され、
一気に再評価が進んだジーン・ウルフには、SFマガジン掲載時に話題を呼んだ2002年の作品「風来」があります。
またSFマガジン2021年1月号では中村融氏がエッセイのアンソロジー収録を提案していますが、これを踏まえて
やはり2000年代に『奇術師』『双生児』が評判となったクリストファー・プリーストの「戦争読書録」を入れるとか。
あるいは日本で編まれることを念頭に、原爆の代わりに巨大怪獣映画を作って太平洋戦争を終わらせようとする珍作戦を
スーツアクターの視点から描いた、ジェイムズ・モロウ「ヒロシマをめざしてのそのそと」を収録するとか。
本来なら作家別作品集が出れば一番よいけれど、まず見込みがないモロウなどはこうした機会に残して欲しかったですね。
橋本氏もnoteで語ったとおり、年代別アンソロジーにはSFマガジンに収録されたきり書籍化されていない作品を
もう一度世に出す役割もあると思います。
しかし10年分を1冊にまとめるのはさすがに紙幅が足りないとすれば、早川書房にはそろそろ往年の名アンソロジー
『SFマガジン・ベスト』の再始動なども期待したいところですが。
編者は近年の海外SF紹介に目覚ましい活躍を見せる当代きっての敏腕レビュアー、橋本輝幸氏。
さて時代も編者も変わった新時代のアンソロジー、どんな作品が収録されているのでしょうか。

【エレン・クレイジャズ「ミセス・ゼノンのパラドックス」】
時代も場所も定かでないカフェで交わされる二人のミセスの会話が、ケーキをいかに分割するかという議論から
量子力学的な極限状況へとエスカレートする話。
昔ながらのSFホラ話の系譜に連なる掌編ですが、細かく読むと有名な「無限分割」のパラドックス以外にも
「場所のパラドックス」が出てきたり(カフェの場所が不確定なのはそのため)、パラドックスが解消されたら
ワームホールが生成されるなど、ゼノンのパラドックスに関する考察を多面的に取り入れた作品のようです。
でも詳細までは理解できてないので、詳しい人の解説が欲しいところ。
【ハンヌ・ライアニエミ「懐かしき主人の声(ヒズ・マスターズ・ボイス)】
知性化された犬と猫が拉致された御主人を奪回すべく、ハイテク装備をまとって奮闘する。
タイトルに象徴されるギャグめいたアイデアと頻出するガジェットに造語、そしてペットの主人愛が印象に残りますが、
知性化の功罪や人権の在り方、ディストピアといった深刻な問題の是非には触れずにひたすらカッコよさで押す物語。
昔ならサイバーパンクの亜流と言われそうで、ポスト・サイバーパンクというよりファッション・サイバーパンクっぽい。
ド派手なセンスを誇示する作風をクールと見るか、それともケバいと見るかは好みによりそうですね。
このキッチュな感覚こそSFだぜ!という人はすごく好きそうだけど、2000年代の看板を背負うには少々食い足りないかな。
【ダリル・グレゴリイ「第二人称現在形」】
意識は行動の後付けとして存在するものだとしたら、意識を遮断するドラッグで自我を失った肉体に後から生じたのは
いったい誰の人格なのか?
多重人格やクローニングなどで複数の自己と対峙する「私は誰?」的な物語は前からあったものの、
本作からは「私はみんなの思うような私じゃない!」という切実な叫びが感じられます。
自己同一性について疑問を抱える多くの人たちには特に強く響くでしょう。
さらに経済的・社会的に自立していないティーンエイジャーを主人公に据えたことによって、
親子関係や家族のかたちを問い直す普遍的な物語としても読めるのがうまいところ。
でも別人であろうと意識があるなら、それはもう哲学的ゾンビじゃないのでは?というモヤモヤ感もあり。
もしこれを日本に置き換えたら、むしろ会社や家族から逃げ出したい大人の間でドラッグが大流行するだろうし、
そうした人々を社会復帰させる仕事を描いたSFのほうが売れるかもしれません。
あと鈴木俊隆師の名前は直すべきだけど、増刷は難しそうなんだっけ……。
【劉慈欣「地火」】
炭鉱夫の父をじん肺で失った主人公は技術者となり、採掘によらず石炭をエネルギー化する技術を開発した。
しかしその実験は人間の想像を超えた大事故を引き起こす。
劉の強みは現実に存在する中央集権的国家の圧力を背景に、その中で生きざるを得ない個人の葛藤を鮮やかに描く点でしょう。
そんな社会における科学とは国家と人民の輝かしい未来を創るものであり、同時に立身出世の道具でもあります。
この素朴ともいえる科学観をめぐって理想と俗っぽさの間を揺れ動く登場人物たちの姿は、少し古いSFでよく見たタイプ。
1950年代から60年代の英米では社会批評を書くためにSFが用いられましたが、「地火」を含めた劉の作品には
その頃の作品に感じた生真面目さと未来志向、そして破天荒な描写を躊躇しない蛮勇があります。
いわば一周回ったところに中国SFブームが来たのかな……という印象もありますね。
でも最先端SFの多くが個の問題を書くことに執着する中で、国家や社会といった「大きな問題」を取り上げた作風が
広く支持されるのは、なかなか興味深いです。
本作は2000年の発表ですが、大惨事を食い止めようと奮闘する人々の姿やその先の展開は我が国の原発事故に驚くほど似ています。
作中で「空は落ちない」という格言を叫んで動揺を収めようとする人物が出てきますが、空だって落ちるときには落ちるということを
2020年に生きてる我々は既に経験済なんですよね……。
最後の章はとってつけたようでいかにも政府のプロパガンダ的ですが、記述をよく読むと年代の異動や事実の隠ぺいが示唆されています。
ここに情報操作や歴史修正主義に対する著者からの異議が隠されていると思いました。
【コリイ・ドクトロウ「シスアドが世界を支配するとき」】
リアルとネットの双方で発生した大規模テロは全世界を一瞬にして崩壊させた。
職場のクリーンルームで死を免れたシステムエンジニアは同僚と共に世界各地の同業者と連絡を取り合い、
新たな世界秩序の構築を目指して奮闘する。
2006年という発表時期は同時多発テロの余波も強く残っており、この翌年には事件の影響を強く感じさせる
『ユダヤ警官同盟』が発表されて話題を集めました。
アメリカの隣国であるカナダにとっても「明日世界が終わるかもしれない」という不安と隣り合わせだったはずで、
そうした危機感が作中のリアルな描写に表れているのでしょう。
バイオ兵器やサイバー攻撃との複合テロというビジョンは、世界の破滅なら核攻撃というそれまでの固定観念を覆したとも言えそう。
姿こそ出てこないものの、危機的な状況のグーグルを束ねる女性リーダーも主人公の男性SEよりキャラが立ってました。
それにしても、システム復旧に出動した管理者が世界中に生き残っているという設定はいささか楽天的じゃないかな。
リアルが滅んでもネット世界は生き延びるから、我々はそこを守って民主的に運営しなきゃ!みたいな感覚もちょっとなあ。
これでは21世紀のギーク版「コージー・カタストロフ」じゃないの?という不満も感じました。
【チャールズ・ストロス「コールダー・ウォー」】
ソ連が崩壊しなかった世界、冷戦は悪化の一途を辿り、東側は核を超える兵器として超次元の存在を利用する計画を進めていた。
これを阻止すべく西側諜報員も動き出すが、はたしてその結末は。
宇宙開発が進まなかった世界なので大陸間弾道弾も無さそう……といった側面からも考察できそうな作品。
異世界から来た邪神を大量殺戮兵器に使うという発想は宗教対立による世界紛争へのアンチテーゼであり、
核兵器の原料にウラヌスやプルートーといった神の名が使われていることへの皮肉かもしれません。
そして「残虐行為記録保管所」のタイトルがバラードに由来するように、その原型とも思われる本作では
かつてバラードが多用した、いくつもの断章を重ねていく「濃縮小説」の手法が用いられています。
さらに邪神との接触がWWⅡのナチス・ドイツから連綿と続くものであると示されることで、
本作もまた大量殺戮の時代における「残虐行為展覧会」を狙ったのではないかとも感じますね。
【N・K・ジェミシン「可能性はゼロじゃない」】
「ありそうもない出来事が次々と発生する」という怪現象に見舞われたニューヨークでは、確立的に低い事件も日常茶飯事。
そして住人たちは効くかどうかもわからないお守りに身を固め、毎日を懸命にやり過ごす。
マンハッタンを舞台にしていることから同時多発テロを直接的に示唆する作品なのは間違いないですが、
かつて地下鉄サリン事件や東日本大震災と原発事故を経験し、いま新型コロナウイルス禍のど真ん中で暮らす
われわれ日本人にとっても、大変身につまされる話です。
統計学的にまれな出来事が立て続けに起きるという設定はハインラインの名作「大当たりの年」を思わせますが、
あちらが幕切れに破滅の気配を漂わせるのに比べると「可能性はゼロじゃない」の終わりには希望が感じられます。
たぶんこの希望こそ、著者が書きたかったものじゃないかな。
何の変哲もない日々が突然断ち切られる不安、「いつ何が起こるかわからない」という不穏さが毎日の生活にも影を落とす世界。
でもそれこそ人生本来の姿なのではないか?という逆説を問いかけることで、ジェミシンは毎日を生きることの幸福と不思議さを、
SFならではの表現で見事に書ききったと思います。
「不確実性の時代」を生きる人々の不安と葛藤をユーモアも交えて描きつつ、その生活に寄り添うことで一種の人間賛歌にもなっており、
2000年代を最もよく象徴する傑作のひとつだと思います。
【グレッグ・イーガン「暗黒整数」】
異なる数学を基盤とした世界同士の接触が破滅の危機をもたらした「ルミナス」の物語から10年後。
異世界への新たな干渉が発生し、かつて事件の解決に関わった数学者たちは再び世界を救うため行動を起こす。
鍵となる暗黒整数の理屈はよくわからなくても、別世界の数学が入り込むことで世界全体にエラーが生じてしまうと考えれば、
とにかく世界ヤバい!という雰囲気はなんとなくつかめるはず。
「ルミナス」には2000年問題への目くばせが感じられましたが、「暗黒整数」は同時多発テロ以後も世界を揺るがし続ける
「異なる原理によって成立する二つの世界」の交わらなさを、数学原理に託しながらも比較的ストレートに書いています。
そして前作ではまだ対話の余地もあった異世界との交流は、本作でほろ苦い結末を迎えます。
これこそ前作から10年の刻を経た世界の変化を如実に示すものでしょう。
90年代傑作選からの続き物として本作が選ばれたのも、実はこの変化を見せるためだったりとか……?
【アレステア・レナルズ「ジーマ・ブルー」】
強化された身体で真空からガス惑星までを踏破し、宇宙空間に巨大な前衛芸術を構築する謎の芸術家ジーマ。
その作品に使用されるトレードマークの色「ジーマ・ブルー」には、彼の秘められた生涯との深い関係があった。
NETFLIXで発表されたアニメシリーズ「ラブ、デス&ロボット」で映像化された一編。
その原作を収録する企画によって、2000年代以降の年代別傑作選が出版できる道が開けたとも考えられます。
意識と記憶を論じることで美の意味を問い直す物語は、インスタグラムやライフログという形で全ての行動を記録すること、
あるいはコンシェルジュAIに決定権を委ねることが孕む問題点を経由し、やがてはポストヒューマンを超えたポストライフ、
すなわち人生の仕舞い方へと行きつきます。
そのときジーマの正体は既に重要ではなく、聞き手は彼を通じて「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」
という根源的なテーマを突き付けられるのです。
全体を見ると、年代別傑作選の収録作にヒューゴー賞もネビュラ賞も含まれてないのはこれが初めてですね。
とはいえ両賞の価値がまるでなくなったというわけでもなく、コニー・ウィリスやテッド・チャン、ケリー・リンクら、
主要な賞の常連組については既に作家別の単行本が出ています。
でもSFマガジン2020年6月号でらっぱ亭さんが「零號琴にも通底する」と評したユージイ・フォスターのネビュラ賞受賞作
"Sinner, Baker, Fabulist, Priest; Red Mask, Black Mask, Gentleman, Beast"はこの機会に訳して欲しかった。
個々の作品だけ見れば出来栄えに偏りも感じるし、80年代や90年代の傑作選に比べると「マスターピース」と呼ぶには
ちょっと弱いかなという印象もあります。
それでも全体を通読して「よいセレクトだなあ」と思えるのは、収録作が互いに共通のテーマを持っているからでしょう。
例えばそれは同時多発テロ以後の不確定な世界、戦争への不安、意識や自己同一性への疑い、ポストヒューマニズム志向であり、
読者は読み進めるうちにこれらのテーマを異なる作品から繰り返し読み取って、その時代の輪郭をイメージできるわけです。
このあたりは編者の選択眼が光るところですね。
過剰に技巧的だったりSFとFTの境界にあるような作品もないので、SFになじみのない人が手に取るにもよいでしょう。
21世紀最初の10年をまとめたショーケースとしては粒のそろったアンソロジーだと思います。
その一方、2000年代前後に頭角を現した、あるいは時代を象徴する作家に絞ろうとするあまり、
それ以前からのベテランが引き続き活躍していることを示す作品が入ってないのは少し残念です。
かつて80年代SF傑作選にもゼラズニイやジョアナ・ラスの新作が収録されていたように、
2000年代に日本で再評価が進んだベテラン作家の新作も採って欲しかった。
例えば2004年に『ケルベロス第五の首』 2006年に『デス博士の島その他の物語』が単行本として出版され、
一気に再評価が進んだジーン・ウルフには、SFマガジン掲載時に話題を呼んだ2002年の作品「風来」があります。
またSFマガジン2021年1月号では中村融氏がエッセイのアンソロジー収録を提案していますが、これを踏まえて
やはり2000年代に『奇術師』『双生児』が評判となったクリストファー・プリーストの「戦争読書録」を入れるとか。
あるいは日本で編まれることを念頭に、原爆の代わりに巨大怪獣映画を作って太平洋戦争を終わらせようとする珍作戦を
スーツアクターの視点から描いた、ジェイムズ・モロウ「ヒロシマをめざしてのそのそと」を収録するとか。
本来なら作家別作品集が出れば一番よいけれど、まず見込みがないモロウなどはこうした機会に残して欲しかったですね。
橋本氏もnoteで語ったとおり、年代別アンソロジーにはSFマガジンに収録されたきり書籍化されていない作品を
もう一度世に出す役割もあると思います。
しかし10年分を1冊にまとめるのはさすがに紙幅が足りないとすれば、早川書房にはそろそろ往年の名アンソロジー
『SFマガジン・ベスト』の再始動なども期待したいところですが。