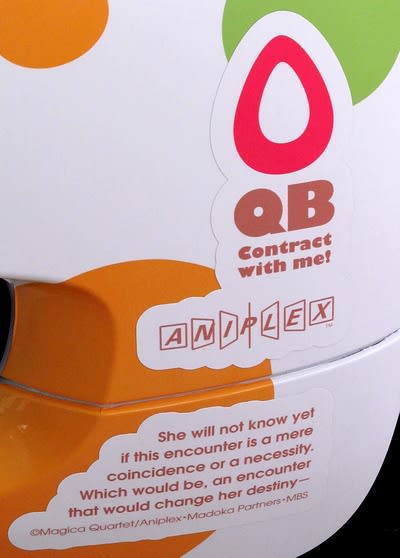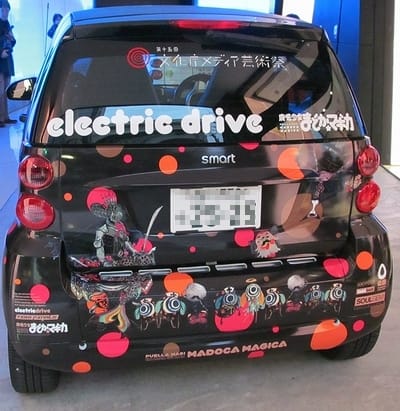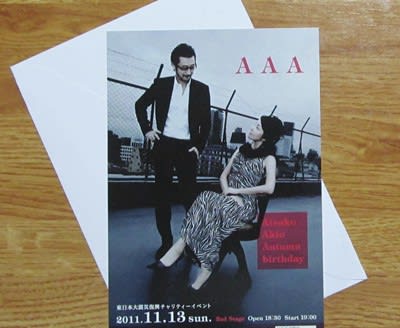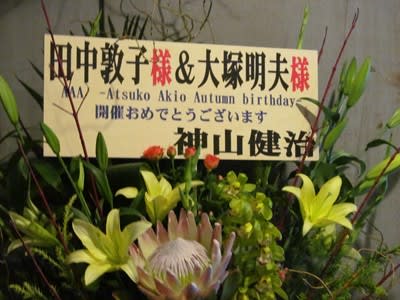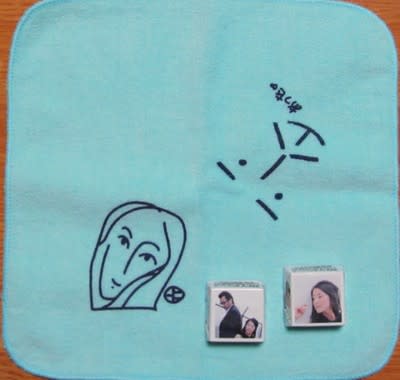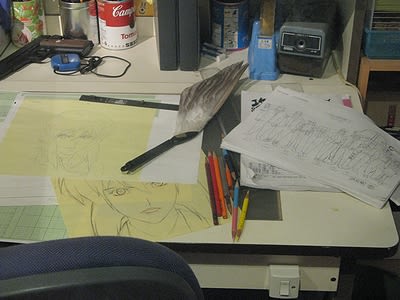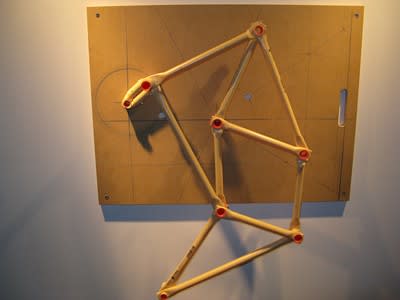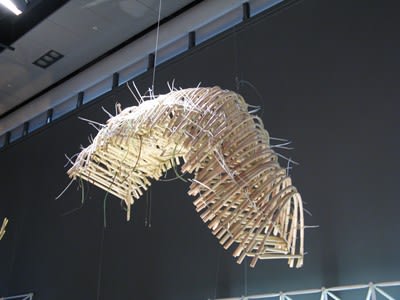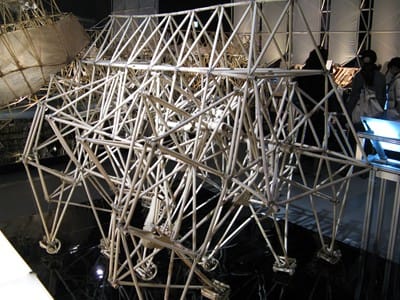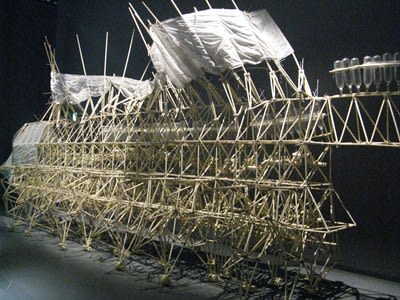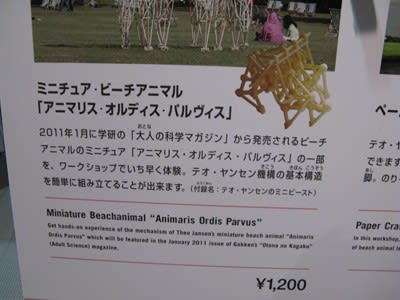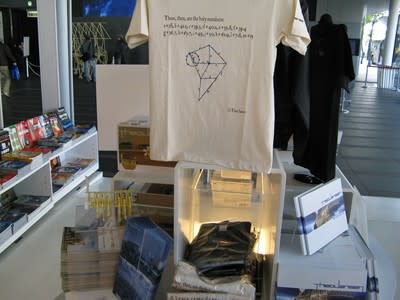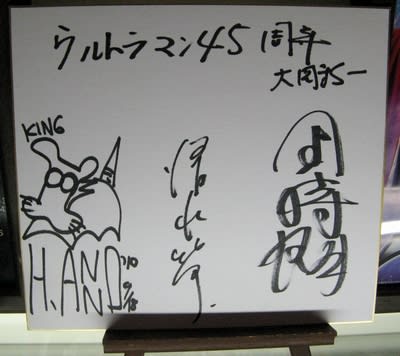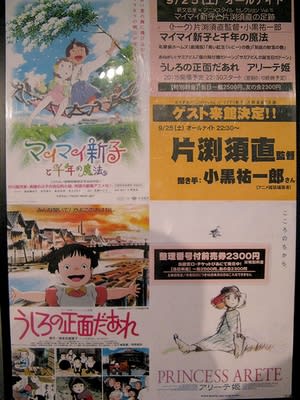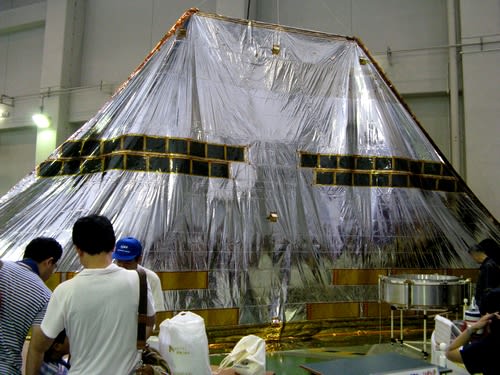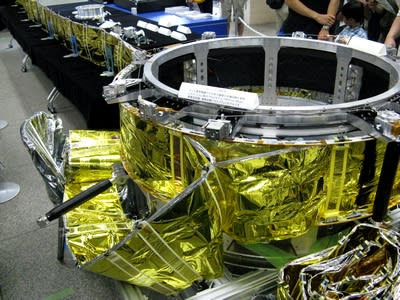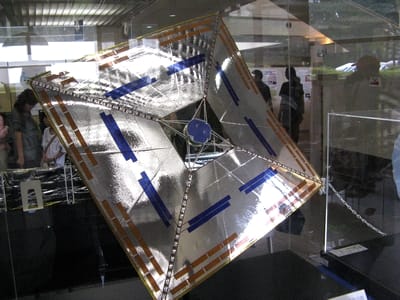今年はSFセミナーに行かなかったのでナマのSF話に飢えていた私ですが、5/10という絶好のタイミングで
<池澤春菜&堺三保のSFなんでも箱 #7>が開催されるとの情報をキャッチ。
しかも今回のサブタイトルは「ウルフ!ウルフ! ウルフ! 大事なことなので三回言ってみました。」
私がラファティと並んで偏愛するジーン・ウルフを取り上げるとくれば、これは参加するしかない!
会場のLive Wire Biri-Biri酒場に到着してみたら、なんと真裏の建物が教会でした。
これはますますウルフめいてきましたよーと勝手に盛り上がってたら、入場待ちの放克軒博士
(Formerly Known As さあのうず氏)と遭遇、さらに入場後は去年のSFセミナーでお会いした
グリーンフロウさんとも再会、さらに若きウルフ読みの隼瀬茅渟さんとも感動の初対面を果たし、
スタート前からテンション上がりまくり。
やっぱりこういうイベントで知り合いがいるってのは心強いもんです。
会場に入ると、店の奥でギターを爪弾くダンディな男性とその向かいで静かに本を読む男性の姿が。
ギターを弾いているのはミュージシャンにして作家・翻訳家・歌人であり、1月にウルフの『ピース』を
共訳された西崎憲さん、その向かいで『ピース』を読んでいたのは、『ケルベロス第五の首』などを訳された、
映画評論家にして特殊翻訳家の柳下毅一郎さんでした。
こっち側だけ見るとまるで文壇バーっぽい感じですが、部屋の反対側では野球帽をかぶった堺三保さんが、
パソコンとにらめっこしながらアメリカ滞在中の池澤春菜さんとの通信を確立しようと苦心する姿があって、
こっちは秋葉原のネットカフェを思わせる雰囲気。
さすがはウルフイベント(?)、なんだかひとつの室内で時空のねじれが起きているみたいで面白かったです。
今回はアメリカ短期留学中の池澤さんに代わって、ゲストの二人が進行役の堺さんをサポートしつつ、
ジーン・ウルフの謎と魅力に迫ろうという企画です。
20人くらいのお客さんの中にはSF関係の編集者も見受けられ、さらには前回のゲストだった宮内悠介さんも
来場されるなど、来場者側も相当に濃い感じでした。
なお、池澤さんは滞在先からのネット中継による参加ですが、その滞在先がワシントンDC…。
そこって「アメリカの七夜」の舞台じゃないですか!
せっかくなので誰かそのことについて池澤さんに振らないかなーと思ってたのですが、
最後まで話題に出なかったのが残念でした。
さて、前半は西崎憲さんの経歴をたどる形で、ミュージシャンから翻訳家へ、さらに小説家へと
歩みを進めてきたことについてのお話を伺いました。
ミュージシャンを目指して上京し、やがてアイドルに曲を提供するまでに至ったものの、
思い通りにいかない部分もあって挫折感を感じたこともあったそうで、そんな時期にもともと好きだった
怪奇小説やミステリを訳す機会を得て、翻訳家の道へと進むことになったそうです。
それ以前にコッパードの翻訳ファンジンを出そうとして果たせなかった事はあったものの、
本格的に英語を勉強したのは20代半ばを過ぎてからということで、西崎さんいわく
「がんばれば誰でもウルフを訳せるようになります!(にっこり)」
これを聞いた語学留学中の池澤さんと、観客一同の動揺っぷりたるや・・・。
ちなみに西崎さんは声優の野中藍さんのファーストアルバムにも編曲で参加されてますが、
その野中さんの初主演アニメ『宇宙のステルヴィア』でSF設定と脚本を担当されたのが、
本日の進行役である堺三保さんなのです。遠いようで近いのが人の縁ですねー。
そしてアメリカからネット経由で曲のオファーをする池澤さんに、西崎さんから
「曲も作りますし、バックでギターも弾きますよ」との力強い答えが。
もしこの組み合わせが実現したら、ぜひSF大会でライブをやってもらわなくては!
音楽と翻訳が楽しくて小説を書くことは考えていなかった西崎さんですが、ある日夢に出てきた女性から
「賞に応募しなさい」とお告げがあり、ちょうど募集していたファンタジーノベル大賞に応募するべく
1ヶ月で300枚を書き上げたのが『世界の果ての庭』。
これが受賞作となって小説家としてもデビューし、今に至るということです。
最初は体力的な要因等で長編が書けないと思い、デビュー作は連作短編という形になりましたが、
受賞後に担当編集者の勧めで長編も書くようになったとのこと。
堺さんからの「怪奇小説が好きなわりに、小説ではそういう作品を書かないですね」との質問には
「怪奇を単なる道具にしたくないという気持ちがある。自分としては雰囲気、atmosphereを大事にしたい。
(読者が)忘れないようなものを訳したい、書きたいと思ってます。」と回答されてました。
1作目はダンセイニ風の異世界、2作目は架空の日本という風に作風を変えたのは意識してのもので、さらに
「ファンタジーの楽しみを単なる素材にしたくない、(物語世界が)現実と強力につながっているほうがいい。」
とのお話も。
『蕃東国物語』のラストについては「現実でも予想外のことが起きるものですから」と語り、
『ゆみに町ガイドブック』に見られるアンチクライマックスについては「クライマックスという概念はなくて、
例えばラヴェルのボレロのように“曲の始まる前から音楽が演奏され、曲が終わった後も演奏が続いている”
というような、始まりも終わりもないものが好き」とのお話がありました。
今後のお仕事では、入手難で古書価がうなぎのぼりのコッパード『郵便局の蛇』が待望の文庫化、さらに
ウェブ連載で高校生を主人公にしたジュブナイル(三鷹に渓谷があったり、民間信仰が色濃く残っている
パラレルワールドの東京で、物語の解析をする資格が存在するという設定)が始まるそうです。
他には『蕃東国物語』の続編や、55人の海外作家を集めた怪奇小説アンソロジーの企画も進行中とのこと。
後半は西崎さんが訳した『ピース』を中心に、「ジーン・ウルフはこう読め(るかも)」という内容のお話。
西崎さんが『ピース』を訳したのは、国書刊行会の樽本さんからの依頼によるものだそうで、会場に来ていた
御本人によると「ウルフを頼める人は少なくて、宮脇孝夫さんや西崎憲さんくらいに限られる。宮脇さんには
『ジーン・ウルフの記念日の本』を頼んであるので、『ピース』は西崎さんにお願いした。」
という事情だそうです。
(そういえば2012年11月にファン交で樽本さんに聞いた『記念日の本』の話を
「宮脇さんの担当作品待ち」とツイートした記憶が・・・あれからもう1年半が経ちました。)
このとき『ピース』以外に候補として挙がったのが「Castleview」「Free Live Free」「There Are Doors」で、
西崎さんが4作を読み比べたときに「一番地味だけど、深そうに見えた」のが『ピース』だそうです。
堺さんからは「ウルフを読んでると、常に裏を読まなければいけない気がしてしんどい。『新しい太陽の書』は
長いのでさすがにほとんどの謎が説明されるけど、『アメリカの七夜』なんてさっぱりわからない。『ピース』も
4回挑戦したけど90ページくらいで挫折した。解説を読んでから最後の30ページくらいを読んでみたけど、
ますますわからなくなった。」と告白があり、これには柳下さんと西崎さんから「100ページまでがつらい。
第三章の「錬金術師」はすごくおもしろいから。」とアドバイスがあり、それをネット経由で聞いた池澤さんが
「帰国したら三章から読みます!」と冗談交じりに答えてました。
さらに柳下さんが「デス博士の島その他の物語」のラスト一節を朗読、私の隣ではデス博士ならぬ放克軒博士が
感極まってすすり泣く(ちょっと誇張)という一幕も。
柳下さんからは「好きな本は読み終えたくない、いつまでも読んでいたい。」、西崎さんからは
「本なんて人生で数冊読めばいい程度なのに、チェーンスモーキングのように何冊も読み続けてしまう。
それは1冊の本を切れ目なく読み続けているようなもので、つまりは終わらない本を読みたいのではないか。」
という言葉で、ウルフの作風に魅了される心理が語られました。
これに堺さんが「切れ目のない話は苦手」と返し、柳下さんは「語りの層が何層もあって、主人公の回想が
そのときその場面で読んでいた本の中の物語として語られている。こうして物語の中の物語を読み続けることが
できる。『ピース』は謎解きではない。ジーン・ウルフに謎はないんですよ。」と答えます。
ここで池澤さんがエンデの『はてしない物語』を引き合いに出して「はてしない物語なんだーと思って読んだら、
果てがあってガッカリした!」と絶妙な例えを放り込み、これには聴衆みんなが「なるほどー」と納得の表情。
西崎さんは再びボレロの例を引いて「(冒頭の)木が倒れる前から、物語は存在する」という視点を提示。
柳下さんの「回想は回想だけど、死者の回想にも見える」という指摘については、どちらでもいいのではとの
読み方を示しました。
柳下さんがウィアの家を「記憶の館」であると説明した際には、横に座っていた隼瀬さんが『ハンニバル』の
記憶の宮殿だ!と反応。
これを聞きながら私は「主人公の回想が、読んでいた本と紐付けられている」という点とも共通性がありそうだ…
なんてことを考えてました。
ウルフを訳すことについて、西崎さんからは「翻訳には英文の解釈と小説の解釈の二つがあって、まず文法上で
正しく訳してから、小説としての翻訳にする。『ピース』は時制が厄介な上に話の中の話が出てきて小説として
訳すことが難しいので、英文として正しく訳すよう心掛けた。」と説明があり、さらに「いくら難解といっても、
出てくる風景や道具立ては普通のもの。例えば三人で陶器の卵を買いに行く場面など、ビジュアル的に見れば
映画を観るように読める。」とアドバイス。
これを受けて柳下さんは『新しい太陽の書』で「剣舞の塔」が実は宇宙船だったとわかる場面について、
「アポロ宇宙船の写真が飾られている場面でそれがはっきりするけれど、それまでに飛び飛びに置かれたシーンが
ぱっとつながるおもしろさがある。ひとつ見つかると次から次へと見つかっていく。」と、ウルフ作品における
読みどころを説明してくれました。
お茶のポットに持ち主の顔が浮かぶエピソードもいいねーという話題になったので、お茶とくればやっぱり
池澤さんからひとこと・・・と思ったのですが、この期待は叶いませんでした。
最後に両ウルフ訳者よりジーン・ウルフのマイベスト作品を紹介してもらったところ、順当に
『ケルベロス第五の首』と『ピース』が挙がりましたが、柳下さんは未訳のヤングアダルト作品
『The Devil in a Forest』がわかりやすくていいとも話してました。
柳下さんはウールス・サイクルからのスピンアウト作品"The Book of the Long Sun"と
"The Book of the Short Sun"も好きで、特に前者は訳してみたいとのこと。
(実はこのシリーズ、別のウルフ作品とも関係がありそうなんですよね・・・。)
今後のお仕事告知では、柳下さんが手がけたアラン・ムーアのスーパーヒロイン物『プロメテア』の1巻が
5月末に発売。
巻を追うごとに異常さが増して行き、最終巻は本の構成そのものがとんでもないことになるそうなので、
みなさん買いましょう!(私はもちろん予約済みです~。)
西崎さんはSF寄りの作品として、魔術的なマイクロフォンをめぐる物語(シナトラがレコーディングに使い、
それが南米に渡って革命の演説に使われ、やがて争奪戦が繰り広げられる)を構想しているそうで、これも
相当おもしろい作品になりそうです。
そして国書の樽本さんからは、2年前のSFセミナーで話が出た2部作『ウィザード』と『ナイト』が今年中に
(分冊で)刊行予定との話が・・・これが実現すれば、ジーン・ウルフの本が1年で3冊出るという快挙!
しかも全部が国書の本!これは樽本さんに(『記念日の本』も含めて)がんばっていただきたいものです。
イベント終了後は来場者の半分くらいが残って、西崎・柳下両氏を囲んでの懇親会に突入しましたが、
卓の両端と真ん中で別々の話題を話していたので、全体を聞き取ることはできませんでした。
自分が聴いて記憶に残っている話題を箇条書きにすると、次のとおりです。
・(名称は変えてあるけど)『屍食教典儀』や『ネクロノミコン』が登場するあたりは、ウルフというより
クトゥルフ物。さすが『ラヴクラフトの遺産』に短編を寄稿しただけのことはある。
・セヴェリアンの仮面と黒マントという姿は、アニメ『DARKER THAN BLACK 黒の契約者』に引き継がれたのでは?
との意見から、続編『流星の双子』のラストはケルベロスのオマージュだろうという話にまで発展。
・キャロル・エムシュウィラーの「順応性」が早い時期にSFMに載ってるのはすごい。
せっかくだから700号記念で取り上げて欲しかった。
・小畑健の描くセヴェリアンは優男すぎる、ウルフのイメージはもっとマッチョなはずという声に対し、
2巻のセクラと3巻のテルミヌス・エストはカッコいいという擁護の声もあり。
(どんないきさつで小畑さんに頼んだのか、会場内にいた早川の方に聞けばよかった・・・。)
・ディッシュの評論集『On SF』(邦題『SFの気恥ずかしさ』)も今年中に国書から出る予定。
・プリーストの『夢幻諸島から』は単体で読むより、他のシリーズ作品とあわせて読みたい。
あと『逆転世界』はやっぱり面白い。
・ディックとラファティとウルフを読むとモテる説。
・『ピース』は他のウルフ作品に比べると読みやすい。ひとつの理由として、西崎さんの
柔らかい語り口のおかげではないか。
いろんな人の話が入り混じっているので、個々の発言者については勘弁してください~。
さて、次回の「SFなんでも箱」のゲストは、幻想小説研究家・翻訳家の中野善夫氏です。
お題はダンセイニか、はたまたヴァーノン・リーか?乞うご期待!
<池澤春菜&堺三保のSFなんでも箱 #7>が開催されるとの情報をキャッチ。
しかも今回のサブタイトルは「ウルフ!ウルフ! ウルフ! 大事なことなので三回言ってみました。」
私がラファティと並んで偏愛するジーン・ウルフを取り上げるとくれば、これは参加するしかない!
会場のLive Wire Biri-Biri酒場に到着してみたら、なんと真裏の建物が教会でした。
これはますますウルフめいてきましたよーと勝手に盛り上がってたら、入場待ちの放克軒博士
(Formerly Known As さあのうず氏)と遭遇、さらに入場後は去年のSFセミナーでお会いした
グリーンフロウさんとも再会、さらに若きウルフ読みの隼瀬茅渟さんとも感動の初対面を果たし、
スタート前からテンション上がりまくり。
やっぱりこういうイベントで知り合いがいるってのは心強いもんです。
会場に入ると、店の奥でギターを爪弾くダンディな男性とその向かいで静かに本を読む男性の姿が。
ギターを弾いているのはミュージシャンにして作家・翻訳家・歌人であり、1月にウルフの『ピース』を
共訳された西崎憲さん、その向かいで『ピース』を読んでいたのは、『ケルベロス第五の首』などを訳された、
映画評論家にして特殊翻訳家の柳下毅一郎さんでした。
こっち側だけ見るとまるで文壇バーっぽい感じですが、部屋の反対側では野球帽をかぶった堺三保さんが、
パソコンとにらめっこしながらアメリカ滞在中の池澤春菜さんとの通信を確立しようと苦心する姿があって、
こっちは秋葉原のネットカフェを思わせる雰囲気。
さすがはウルフイベント(?)、なんだかひとつの室内で時空のねじれが起きているみたいで面白かったです。
今回はアメリカ短期留学中の池澤さんに代わって、ゲストの二人が進行役の堺さんをサポートしつつ、
ジーン・ウルフの謎と魅力に迫ろうという企画です。
20人くらいのお客さんの中にはSF関係の編集者も見受けられ、さらには前回のゲストだった宮内悠介さんも
来場されるなど、来場者側も相当に濃い感じでした。
なお、池澤さんは滞在先からのネット中継による参加ですが、その滞在先がワシントンDC…。
そこって「アメリカの七夜」の舞台じゃないですか!
せっかくなので誰かそのことについて池澤さんに振らないかなーと思ってたのですが、
最後まで話題に出なかったのが残念でした。
さて、前半は西崎憲さんの経歴をたどる形で、ミュージシャンから翻訳家へ、さらに小説家へと
歩みを進めてきたことについてのお話を伺いました。
ミュージシャンを目指して上京し、やがてアイドルに曲を提供するまでに至ったものの、
思い通りにいかない部分もあって挫折感を感じたこともあったそうで、そんな時期にもともと好きだった
怪奇小説やミステリを訳す機会を得て、翻訳家の道へと進むことになったそうです。
それ以前にコッパードの翻訳ファンジンを出そうとして果たせなかった事はあったものの、
本格的に英語を勉強したのは20代半ばを過ぎてからということで、西崎さんいわく
「がんばれば誰でもウルフを訳せるようになります!(にっこり)」
これを聞いた語学留学中の池澤さんと、観客一同の動揺っぷりたるや・・・。
ちなみに西崎さんは声優の野中藍さんのファーストアルバムにも編曲で参加されてますが、
その野中さんの初主演アニメ『宇宙のステルヴィア』でSF設定と脚本を担当されたのが、
本日の進行役である堺三保さんなのです。遠いようで近いのが人の縁ですねー。
そしてアメリカからネット経由で曲のオファーをする池澤さんに、西崎さんから
「曲も作りますし、バックでギターも弾きますよ」との力強い答えが。
もしこの組み合わせが実現したら、ぜひSF大会でライブをやってもらわなくては!
音楽と翻訳が楽しくて小説を書くことは考えていなかった西崎さんですが、ある日夢に出てきた女性から
「賞に応募しなさい」とお告げがあり、ちょうど募集していたファンタジーノベル大賞に応募するべく
1ヶ月で300枚を書き上げたのが『世界の果ての庭』。
これが受賞作となって小説家としてもデビューし、今に至るということです。
最初は体力的な要因等で長編が書けないと思い、デビュー作は連作短編という形になりましたが、
受賞後に担当編集者の勧めで長編も書くようになったとのこと。
堺さんからの「怪奇小説が好きなわりに、小説ではそういう作品を書かないですね」との質問には
「怪奇を単なる道具にしたくないという気持ちがある。自分としては雰囲気、atmosphereを大事にしたい。
(読者が)忘れないようなものを訳したい、書きたいと思ってます。」と回答されてました。
1作目はダンセイニ風の異世界、2作目は架空の日本という風に作風を変えたのは意識してのもので、さらに
「ファンタジーの楽しみを単なる素材にしたくない、(物語世界が)現実と強力につながっているほうがいい。」
とのお話も。
『蕃東国物語』のラストについては「現実でも予想外のことが起きるものですから」と語り、
『ゆみに町ガイドブック』に見られるアンチクライマックスについては「クライマックスという概念はなくて、
例えばラヴェルのボレロのように“曲の始まる前から音楽が演奏され、曲が終わった後も演奏が続いている”
というような、始まりも終わりもないものが好き」とのお話がありました。
今後のお仕事では、入手難で古書価がうなぎのぼりのコッパード『郵便局の蛇』が待望の文庫化、さらに
ウェブ連載で高校生を主人公にしたジュブナイル(三鷹に渓谷があったり、民間信仰が色濃く残っている
パラレルワールドの東京で、物語の解析をする資格が存在するという設定)が始まるそうです。
他には『蕃東国物語』の続編や、55人の海外作家を集めた怪奇小説アンソロジーの企画も進行中とのこと。
後半は西崎さんが訳した『ピース』を中心に、「ジーン・ウルフはこう読め(るかも)」という内容のお話。
西崎さんが『ピース』を訳したのは、国書刊行会の樽本さんからの依頼によるものだそうで、会場に来ていた
御本人によると「ウルフを頼める人は少なくて、宮脇孝夫さんや西崎憲さんくらいに限られる。宮脇さんには
『ジーン・ウルフの記念日の本』を頼んであるので、『ピース』は西崎さんにお願いした。」
という事情だそうです。
(そういえば2012年11月にファン交で樽本さんに聞いた『記念日の本』の話を
「宮脇さんの担当作品待ち」とツイートした記憶が・・・あれからもう1年半が経ちました。)
このとき『ピース』以外に候補として挙がったのが「Castleview」「Free Live Free」「There Are Doors」で、
西崎さんが4作を読み比べたときに「一番地味だけど、深そうに見えた」のが『ピース』だそうです。
堺さんからは「ウルフを読んでると、常に裏を読まなければいけない気がしてしんどい。『新しい太陽の書』は
長いのでさすがにほとんどの謎が説明されるけど、『アメリカの七夜』なんてさっぱりわからない。『ピース』も
4回挑戦したけど90ページくらいで挫折した。解説を読んでから最後の30ページくらいを読んでみたけど、
ますますわからなくなった。」と告白があり、これには柳下さんと西崎さんから「100ページまでがつらい。
第三章の「錬金術師」はすごくおもしろいから。」とアドバイスがあり、それをネット経由で聞いた池澤さんが
「帰国したら三章から読みます!」と冗談交じりに答えてました。
さらに柳下さんが「デス博士の島その他の物語」のラスト一節を朗読、私の隣ではデス博士ならぬ放克軒博士が
感極まってすすり泣く(ちょっと誇張)という一幕も。
柳下さんからは「好きな本は読み終えたくない、いつまでも読んでいたい。」、西崎さんからは
「本なんて人生で数冊読めばいい程度なのに、チェーンスモーキングのように何冊も読み続けてしまう。
それは1冊の本を切れ目なく読み続けているようなもので、つまりは終わらない本を読みたいのではないか。」
という言葉で、ウルフの作風に魅了される心理が語られました。
これに堺さんが「切れ目のない話は苦手」と返し、柳下さんは「語りの層が何層もあって、主人公の回想が
そのときその場面で読んでいた本の中の物語として語られている。こうして物語の中の物語を読み続けることが
できる。『ピース』は謎解きではない。ジーン・ウルフに謎はないんですよ。」と答えます。
ここで池澤さんがエンデの『はてしない物語』を引き合いに出して「はてしない物語なんだーと思って読んだら、
果てがあってガッカリした!」と絶妙な例えを放り込み、これには聴衆みんなが「なるほどー」と納得の表情。
西崎さんは再びボレロの例を引いて「(冒頭の)木が倒れる前から、物語は存在する」という視点を提示。
柳下さんの「回想は回想だけど、死者の回想にも見える」という指摘については、どちらでもいいのではとの
読み方を示しました。
柳下さんがウィアの家を「記憶の館」であると説明した際には、横に座っていた隼瀬さんが『ハンニバル』の
記憶の宮殿だ!と反応。
これを聞きながら私は「主人公の回想が、読んでいた本と紐付けられている」という点とも共通性がありそうだ…
なんてことを考えてました。
ウルフを訳すことについて、西崎さんからは「翻訳には英文の解釈と小説の解釈の二つがあって、まず文法上で
正しく訳してから、小説としての翻訳にする。『ピース』は時制が厄介な上に話の中の話が出てきて小説として
訳すことが難しいので、英文として正しく訳すよう心掛けた。」と説明があり、さらに「いくら難解といっても、
出てくる風景や道具立ては普通のもの。例えば三人で陶器の卵を買いに行く場面など、ビジュアル的に見れば
映画を観るように読める。」とアドバイス。
これを受けて柳下さんは『新しい太陽の書』で「剣舞の塔」が実は宇宙船だったとわかる場面について、
「アポロ宇宙船の写真が飾られている場面でそれがはっきりするけれど、それまでに飛び飛びに置かれたシーンが
ぱっとつながるおもしろさがある。ひとつ見つかると次から次へと見つかっていく。」と、ウルフ作品における
読みどころを説明してくれました。
お茶のポットに持ち主の顔が浮かぶエピソードもいいねーという話題になったので、お茶とくればやっぱり
池澤さんからひとこと・・・と思ったのですが、この期待は叶いませんでした。
最後に両ウルフ訳者よりジーン・ウルフのマイベスト作品を紹介してもらったところ、順当に
『ケルベロス第五の首』と『ピース』が挙がりましたが、柳下さんは未訳のヤングアダルト作品
『The Devil in a Forest』がわかりやすくていいとも話してました。
柳下さんはウールス・サイクルからのスピンアウト作品"The Book of the Long Sun"と
"The Book of the Short Sun"も好きで、特に前者は訳してみたいとのこと。
(実はこのシリーズ、別のウルフ作品とも関係がありそうなんですよね・・・。)
今後のお仕事告知では、柳下さんが手がけたアラン・ムーアのスーパーヒロイン物『プロメテア』の1巻が
5月末に発売。
巻を追うごとに異常さが増して行き、最終巻は本の構成そのものがとんでもないことになるそうなので、
みなさん買いましょう!(私はもちろん予約済みです~。)
西崎さんはSF寄りの作品として、魔術的なマイクロフォンをめぐる物語(シナトラがレコーディングに使い、
それが南米に渡って革命の演説に使われ、やがて争奪戦が繰り広げられる)を構想しているそうで、これも
相当おもしろい作品になりそうです。
そして国書の樽本さんからは、2年前のSFセミナーで話が出た2部作『ウィザード』と『ナイト』が今年中に
(分冊で)刊行予定との話が・・・これが実現すれば、ジーン・ウルフの本が1年で3冊出るという快挙!
しかも全部が国書の本!これは樽本さんに(『記念日の本』も含めて)がんばっていただきたいものです。
イベント終了後は来場者の半分くらいが残って、西崎・柳下両氏を囲んでの懇親会に突入しましたが、
卓の両端と真ん中で別々の話題を話していたので、全体を聞き取ることはできませんでした。
自分が聴いて記憶に残っている話題を箇条書きにすると、次のとおりです。
・(名称は変えてあるけど)『屍食教典儀』や『ネクロノミコン』が登場するあたりは、ウルフというより
クトゥルフ物。さすが『ラヴクラフトの遺産』に短編を寄稿しただけのことはある。
・セヴェリアンの仮面と黒マントという姿は、アニメ『DARKER THAN BLACK 黒の契約者』に引き継がれたのでは?
との意見から、続編『流星の双子』のラストはケルベロスのオマージュだろうという話にまで発展。
・キャロル・エムシュウィラーの「順応性」が早い時期にSFMに載ってるのはすごい。
せっかくだから700号記念で取り上げて欲しかった。
・小畑健の描くセヴェリアンは優男すぎる、ウルフのイメージはもっとマッチョなはずという声に対し、
2巻のセクラと3巻のテルミヌス・エストはカッコいいという擁護の声もあり。
(どんないきさつで小畑さんに頼んだのか、会場内にいた早川の方に聞けばよかった・・・。)
・ディッシュの評論集『On SF』(邦題『SFの気恥ずかしさ』)も今年中に国書から出る予定。
・プリーストの『夢幻諸島から』は単体で読むより、他のシリーズ作品とあわせて読みたい。
あと『逆転世界』はやっぱり面白い。
・ディックとラファティとウルフを読むとモテる説。
・『ピース』は他のウルフ作品に比べると読みやすい。ひとつの理由として、西崎さんの
柔らかい語り口のおかげではないか。
いろんな人の話が入り混じっているので、個々の発言者については勘弁してください~。
さて、次回の「SFなんでも箱」のゲストは、幻想小説研究家・翻訳家の中野善夫氏です。
お題はダンセイニか、はたまたヴァーノン・リーか?乞うご期待!