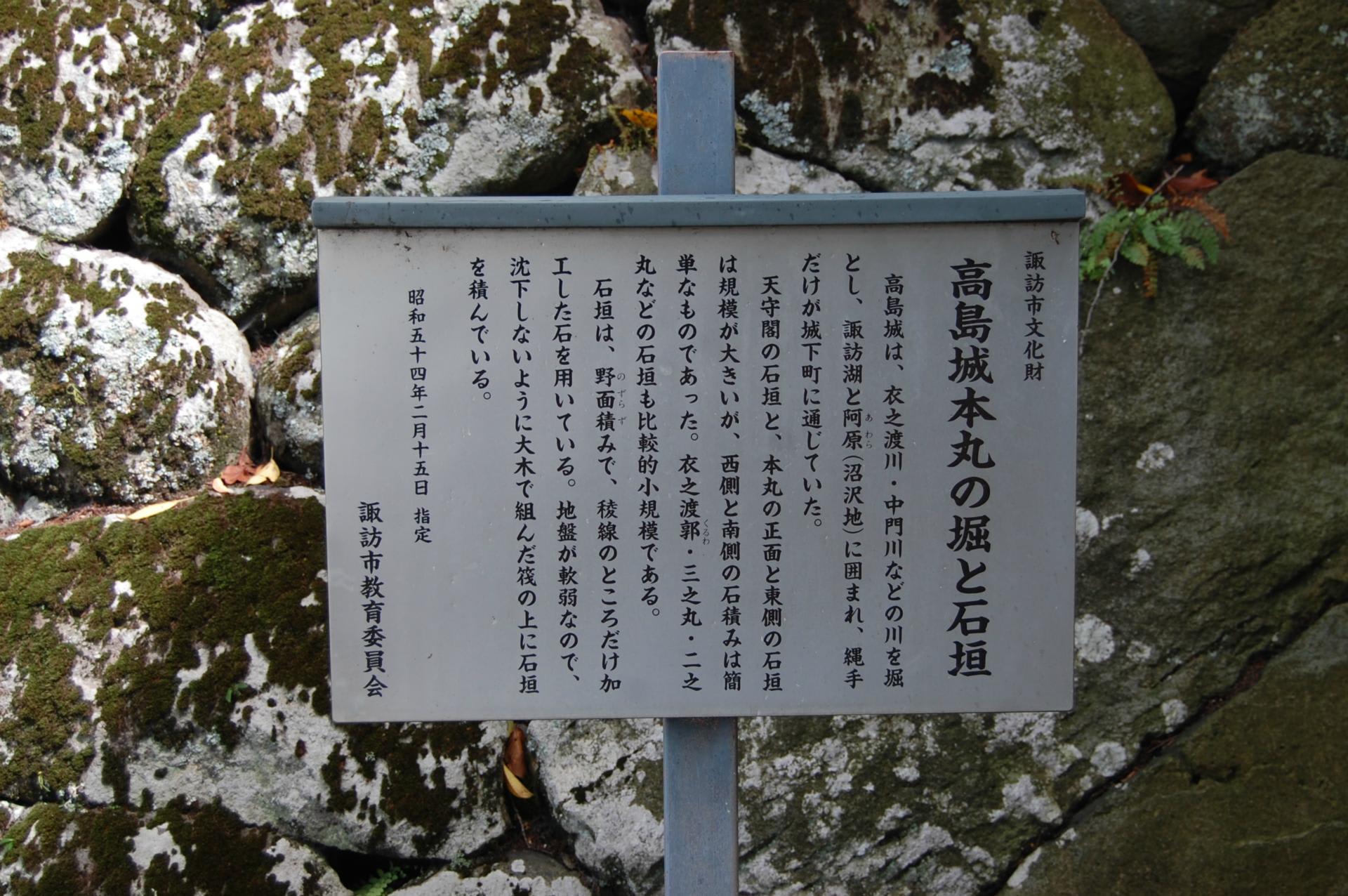18きっぷで信州の古城、上田城と小諸城を目指しました。

高崎から信越線の電車に乗り換えます。

新幹線の開通に伴って横川から先は廃線となりました。高崎と横川を結び、群馬県内だけを走る路線ですが、信越線という名称はそのままです。

横川駅の改札口。今も「峠の釜めし」の売店はあります。

横川・軽井沢間は代替バスが運行。1月にスキーバスの事故があった碓氷バイパスを通行します。

軽井沢に到着。新幹線開業によって新設された駅舎です。

第三セクター鉄道・しなの鉄道の改札口

しなの鉄道の赤い電車。真田の赤備えか?

上田市の観光看板

中央奥に軽井沢の旧駅舎

軽井沢駅舎記念館の展示車両。EF63形電気機関車

アプト式電気機関車EC40形

湘南カラーの車両

車窓から見える浅間山

小諸で水色の車両に乗り換え

上田駅に到着。しなの鉄道・上田駅の入口です。

赤備えの甲冑レプリカ


上田駅

駅前の商業ビル。駅前通りが市街地へまっすぐに伸びています。

河岸段丘、崖下の道。当時、上田城の真下を千曲川が流れていました。このあたりを尼ヶ淵といい、上田城は別名、尼ヶ淵城と呼ばれました。

文化講演会のポスター。童門冬二氏(作家)、八名信夫氏(俳優)、真田徹氏(仙台真田家14代当主)。

二の丸堀



二の丸橋


大河ドラマ館

真田十勇士ウォーキングマップ


東虎口櫓門。右に北櫓、左は南櫓

東虎口の空堀

千曲川の方向。今は新幹線、しなの鉄道が通っています。

東虎口の北側の本丸堀

真田石。真田信之が松代移封の際に運ぼうとしたが動かないために諦めたという巨石。

南櫓

千曲川方向

南櫓の内部

南櫓の内部。甲冑

信之の奥方・小松姫は旅の途中の鴻巣宿にて死亡。亡骸を上田へ運んだという駕籠

上田城の模型。左側が千曲川です。

空堀

渡櫓

南櫓

火縄銃

北櫓

北櫓内部


本丸跡の真田神社

赤備えの兜

真田神社の本殿

真田井戸。城外へ通じる抜け穴となっていたそうです。

西櫓

西櫓内部



山本鼎記念館標柱石。山本鼎は大正・昭和前期に活躍した画家です。山本鼎記念館がこの地にありましたが、2014年に上田市美術館が開館、山本作品は新しい美術館に移管されました。私は十数年前に見学したかも知れません。

上田市立博物館

初めて人工的にがんを発生させることに成功した病理学者、山極勝三郎のコーナー

上田城の模型。城下に千曲川が迫っている様子がわかります。

上田市立博物館別館

博物館別館入口



平和の鐘


二の丸堀

大河ドラマ館。真田丸便乗キャンペーンにはいささかうんざり。入館はしませんでした。

高崎から信越線の電車に乗り換えます。

新幹線の開通に伴って横川から先は廃線となりました。高崎と横川を結び、群馬県内だけを走る路線ですが、信越線という名称はそのままです。

横川駅の改札口。今も「峠の釜めし」の売店はあります。

横川・軽井沢間は代替バスが運行。1月にスキーバスの事故があった碓氷バイパスを通行します。

軽井沢に到着。新幹線開業によって新設された駅舎です。

第三セクター鉄道・しなの鉄道の改札口

しなの鉄道の赤い電車。真田の赤備えか?

上田市の観光看板

中央奥に軽井沢の旧駅舎

軽井沢駅舎記念館の展示車両。EF63形電気機関車

アプト式電気機関車EC40形

湘南カラーの車両

車窓から見える浅間山

小諸で水色の車両に乗り換え

上田駅に到着。しなの鉄道・上田駅の入口です。

赤備えの甲冑レプリカ


上田駅

駅前の商業ビル。駅前通りが市街地へまっすぐに伸びています。

河岸段丘、崖下の道。当時、上田城の真下を千曲川が流れていました。このあたりを尼ヶ淵といい、上田城は別名、尼ヶ淵城と呼ばれました。

文化講演会のポスター。童門冬二氏(作家)、八名信夫氏(俳優)、真田徹氏(仙台真田家14代当主)。

二の丸堀



二の丸橋


大河ドラマ館

真田十勇士ウォーキングマップ


東虎口櫓門。右に北櫓、左は南櫓

東虎口の空堀

千曲川の方向。今は新幹線、しなの鉄道が通っています。

東虎口の北側の本丸堀

真田石。真田信之が松代移封の際に運ぼうとしたが動かないために諦めたという巨石。

南櫓

千曲川方向

南櫓の内部

南櫓の内部。甲冑

信之の奥方・小松姫は旅の途中の鴻巣宿にて死亡。亡骸を上田へ運んだという駕籠

上田城の模型。左側が千曲川です。

空堀

渡櫓

南櫓

火縄銃

北櫓

北櫓内部


本丸跡の真田神社

赤備えの兜

真田神社の本殿

真田井戸。城外へ通じる抜け穴となっていたそうです。

西櫓

西櫓内部



山本鼎記念館標柱石。山本鼎は大正・昭和前期に活躍した画家です。山本鼎記念館がこの地にありましたが、2014年に上田市美術館が開館、山本作品は新しい美術館に移管されました。私は十数年前に見学したかも知れません。

上田市立博物館

初めて人工的にがんを発生させることに成功した病理学者、山極勝三郎のコーナー

上田城の模型。城下に千曲川が迫っている様子がわかります。

上田市立博物館別館

博物館別館入口



平和の鐘


二の丸堀

大河ドラマ館。真田丸便乗キャンペーンにはいささかうんざり。入館はしませんでした。