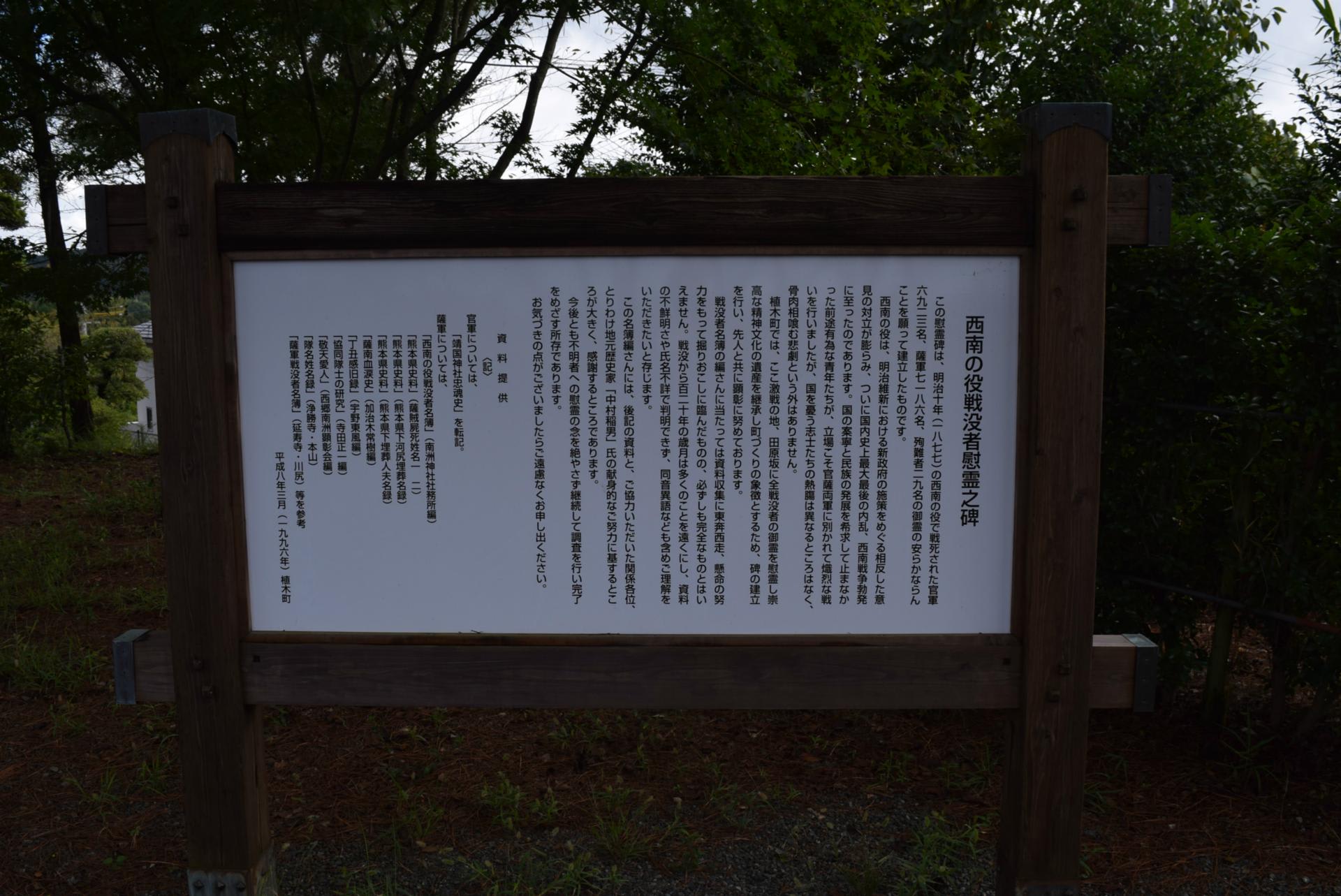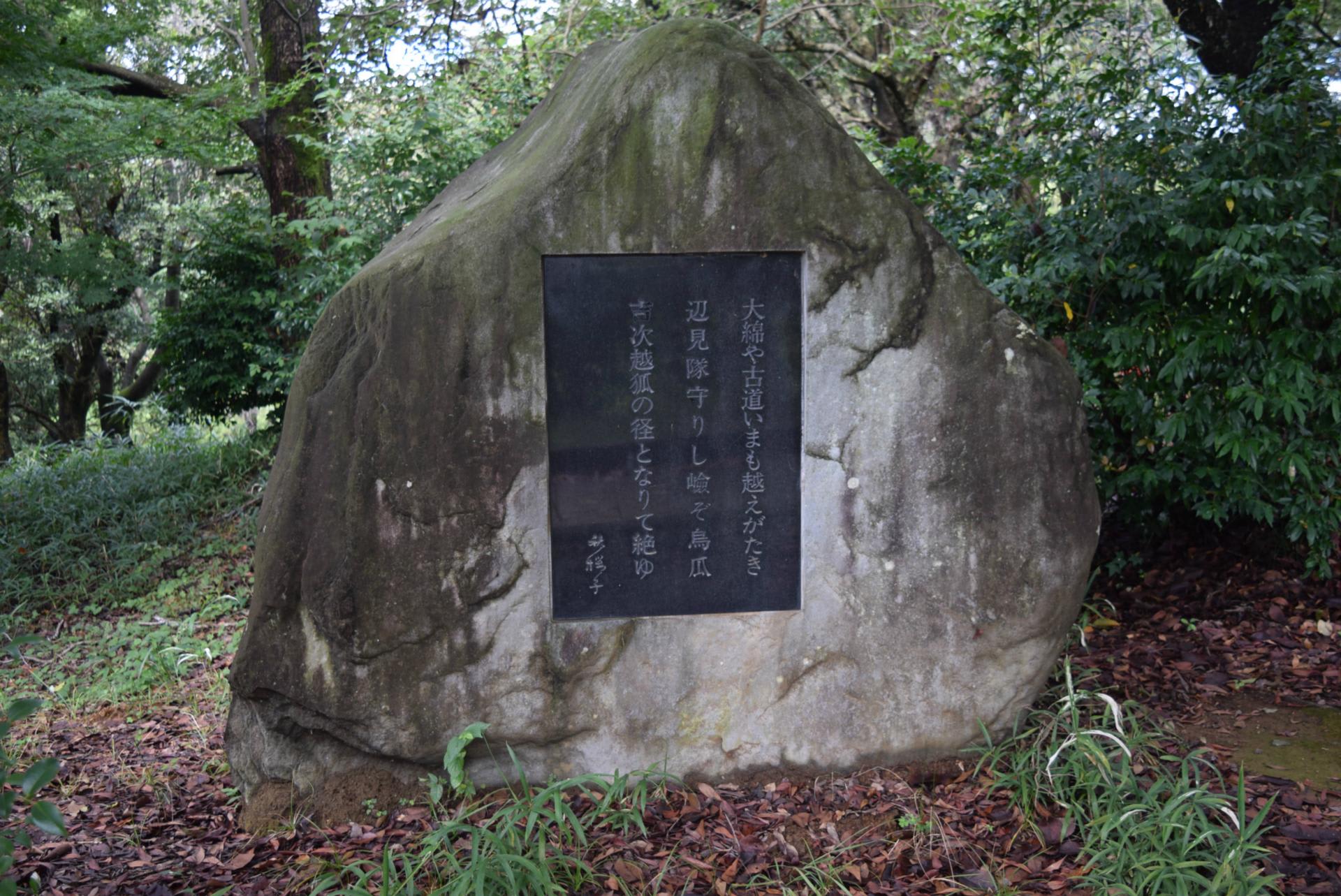府内城三之丸跡に建つアートプラザ。磯崎新が設計、1966年に完成した旧大分県立大分図書館。1998年に大分市が改修しアートプラザとしてオープンしました。
府内城三之丸跡に建つアートプラザ。磯崎新が設計、1966年に完成した旧大分県立大分図書館。1998年に大分市が改修しアートプラザとしてオープンしました。

 3階は磯崎新建築展示室。北九州市立美術館(1974年)
3階は磯崎新建築展示室。北九州市立美術館(1974年) 群馬県立近代美術館(1974年)
群馬県立近代美術館(1974年) ハラ・ミュージアム・アーク(1988年。群馬県)
ハラ・ミュージアム・アーク(1988年。群馬県) 水戸芸術館(1990年)
水戸芸術館(1990年) ロサンゼルス現代美術館(1986年)
ロサンゼルス現代美術館(1986年) 西脇市岡之山美術館(1984年。兵庫県)
西脇市岡之山美術館(1984年。兵庫県)

 奈義町現代美術館(1994年。岡山県)
奈義町現代美術館(1994年。岡山県) 富山県立山博物館(1991年)
富山県立山博物館(1991年)
 ブルックリン美術館(1992年)
ブルックリン美術館(1992年)
 ミュンヘン近代美術館(コンペ落選)
ミュンヘン近代美術館(コンペ落選) シュトゥットガルト現代美術館(コンペ採用も建設計画中止)
シュトゥットガルト現代美術館(コンペ採用も建設計画中止)




 新聞少年像
新聞少年像 大手公園
大手公園
 巨大ソテツ
巨大ソテツ
 伊東ドン・マンショ像(北村西望)
伊東ドン・マンショ像(北村西望) 健ちゃん像(北村西望)
健ちゃん像(北村西望)
 滝廉太郎像(朝倉文夫)
滝廉太郎像(朝倉文夫)
 西洋演劇発祥の地
西洋演劇発祥の地
 坂茂が設計、2014年に完成した大分県立美術館
坂茂が設計、2014年に完成した大分県立美術館




 イサム・ノグチ展を開催中
イサム・ノグチ展を開催中 ノグチがデザインしたAKARI。大部分は撮影禁止です。
ノグチがデザインしたAKARI。大部分は撮影禁止です。





 六郷満山開山1300年の記念展示
六郷満山開山1300年の記念展示 2階
2階

 対面のオアシスひろば21への渡り廊下
対面のオアシスひろば21への渡り廊下 県立美術館の全景
県立美術館の全景


 OASISひろば21内部。iichico総合文化センター、NHK大分、オアシスタワーホテルなどで構成される多目的複合施設
OASISひろば21内部。iichico総合文化センター、NHK大分、オアシスタワーホテルなどで構成される多目的複合施設 大分駅のイルミネーション
大分駅のイルミネーション ザビエル像
ザビエル像 大分駅の改札内です。なんとフローリング床です。
大分駅の改札内です。なんとフローリング床です。 行き先表示版も見やすい。
行き先表示版も見やすい。 トイレの入口はまるでスーパー銭湯の入口のようです。
トイレの入口はまるでスーパー銭湯の入口のようです。 黒川医院の広告パネル
黒川医院の広告パネル









 2018年新春の旅、大分豊後へ向かいます。
2018年新春の旅、大分豊後へ向かいます。 大分空港に着陸。空港からバスで1時間ほどかかって大分駅に来ました。大分空港は国東半島にあって別府・大分からかなり遠いです。
大分空港に着陸。空港からバスで1時間ほどかかって大分駅に来ました。大分空港は国東半島にあって別府・大分からかなり遠いです。 大分駅前の大友宗麟像。豊後は戦国時代、キリシタン大名として有名な大友宗麟が支配しました。
大分駅前の大友宗麟像。豊後は戦国時代、キリシタン大名として有名な大友宗麟が支配しました。

 大分銀行赤レンガ館は修復工事中です。辰野金吾が設計し1913年に完成。
大分銀行赤レンガ館は修復工事中です。辰野金吾が設計し1913年に完成。 府内五番街
府内五番街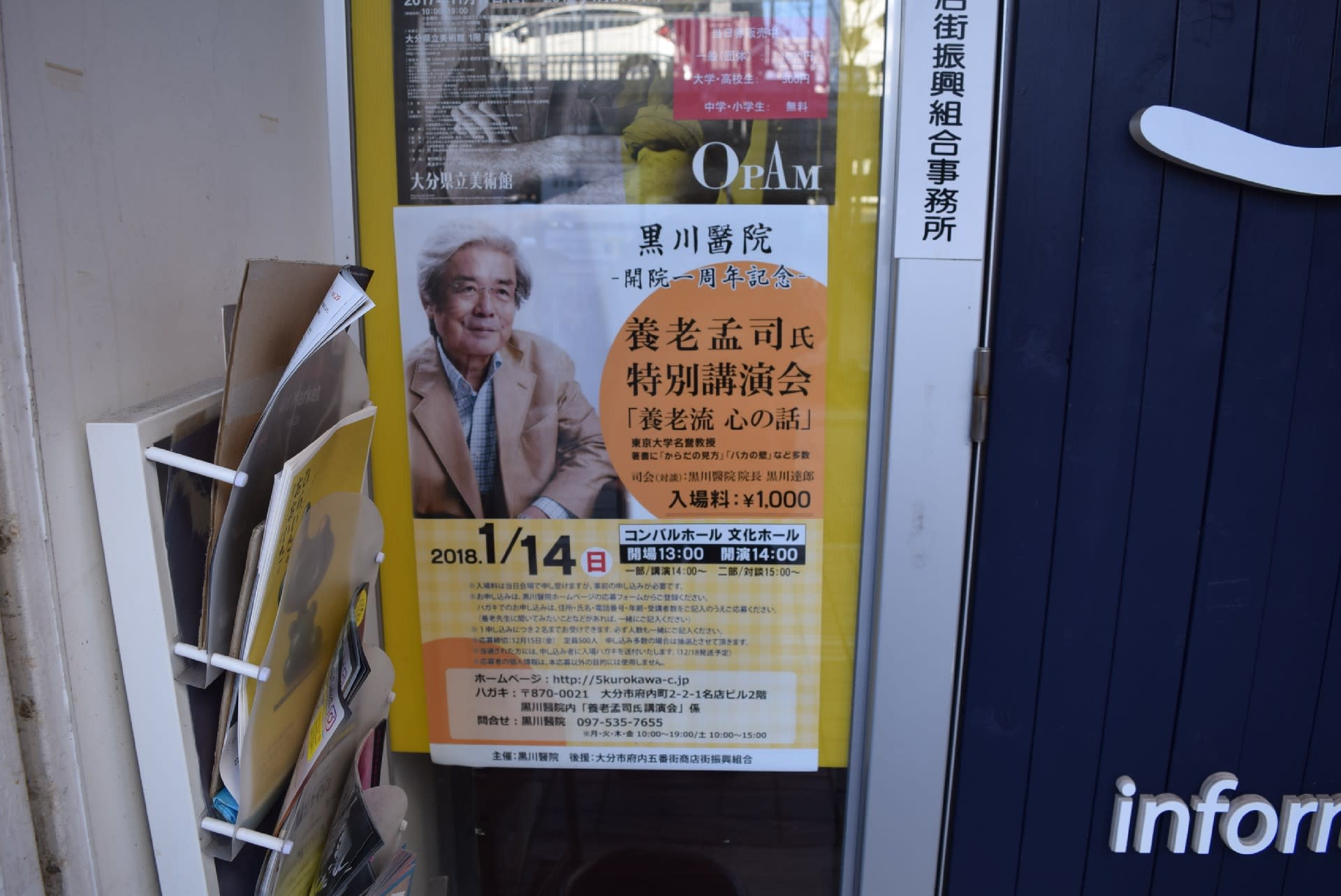 養老孟司講演会のポスター
養老孟司講演会のポスター 講演会を主催する黒川医院が入居する複合ビル
講演会を主催する黒川医院が入居する複合ビル
 西洋医学発祥記念碑。1557年に病院が創設され、ポルトガル人医師のアルメイダによって外科手術も行われました。
西洋医学発祥記念碑。1557年に病院が創設され、ポルトガル人医師のアルメイダによって外科手術も行われました。 大分県教育発祥の地
大分県教育発祥の地
 フランシスコ・ザビエル像。1551年に大分に来て布教を始めました。
フランシスコ・ザビエル像。1551年に大分に来て布教を始めました。 大分府内城。大友宗麟の城です。
大分府内城。大友宗麟の城です。 着到櫓
着到櫓 大手門の堀
大手門の堀 大手門
大手門
 アオサギ
アオサギ

 大手門の石垣
大手門の石垣 仮想天守イルミネーション
仮想天守イルミネーション
 府内城1/70模型
府内城1/70模型





 本丸櫓台
本丸櫓台
 人質櫓
人質櫓 北之丸(現松栄神社)につながる廊下橋
北之丸(現松栄神社)につながる廊下橋

 天守台上
天守台上
 本丸櫓台
本丸櫓台

 天守台石垣
天守台石垣

 人質櫓
人質櫓 東の二階櫓
東の二階櫓

 廊下橋修復工事
廊下橋修復工事


 西之丸角櫓
西之丸角櫓 北之丸の方向
北之丸の方向 駐車場入口
駐車場入口
 廊下橋
廊下橋


 北之丸跡の松栄神社
北之丸跡の松栄神社