「令和日本国憲法草案」について2
※まず、「令和日本国憲法草案」に目を通してみてください。
【令和日本国憲法草案2】 - 夕暮れのフクロウ https://is.gd/76WnJq
その上で、感想、ご批判などをコメント欄にでもいただければさいわいです、
明治憲法以来、日本は成文憲法を中心に法秩序を築いてきました。条文の体系化、法典整備、形式的正統性の尊重は、確かに近代国家の形成において有効に機能しました。しかし、この成文という形式性は、ときに現実の文化・歴史・伝統との乖離を生み、制度の柔軟性と有機性を損なう要因ともなりました。
こうした背景から、先に、提示した「令和日本国憲法草案」は、成文法的な体系を維持しつつも、英国型の不文憲法に見られる運用性の柔軟さや伝統との親和性、さらには伝統的な生活根拠との結合を模索しようとしたものです。
英国における法秩序は、「憲法典」を持ってはいませんが、判例や慣習、制度的伝統などによって支えられています。その柔軟性は、例えば王室と議会、判例と政治慣行、政党制度と慣例などとの調和に顕著であり、書かれたルールに縛られない通融性のある「国家の連続性」と「文化の適応力」を維持してきました。
「令和日本国憲法草案」は、日本においてもこのような「不文的な法制度の柔軟性」を部分的に導入することにより、伝統文化と現代の制度とのあいだの離反や距離を少しでも埋めようという目的をもっています。
「令和日本国憲法草案」の大きな特徴は、成文憲法としての理念的な骨格と、その理念を具体的に展開する「憲法施行法」の制度的な設計との二層構造です。これは、憲法においては抽象的な理念の定式化にとどめ、その具体的な運用や社会制度の設計に関しては、時代・慣習・文化に即した法律によって柔軟に対応する余地をもたせようとしたものです。
この点において、「憲法=理念」「憲法施行法=制度・慣行」という区分は、まさに英米法的な「コモンローと慣習 common law and convention」の思想を日本的に翻案しようとしたものです。
現行日本国憲法の抽象的な「個人主義」は、しばしば伝統的な家族制度や地域共同体との緊張をはらみがちです。「令和日本国憲法草案」は、個人の自由を否定することなく、その自由の前提としての「共同体的基盤」の価値を再発見し、それを制度的に保護し、あるいは再構成しようとするものです。
たとえば、家族に関する規定においては、個人の尊厳と親族的な連帯との調和が求められ、地域においては「市民社会」としての公共性の回復が意図されています。これはいわばヘーゲル的な「人倫(Sittlichkeit)」の回復へと通じるものです。
日本の近代化の過程において、宗教や伝統的慣習は「私的領域」に閉じ込められ、制度的な保護の対象外とされてきました。しかし、精神的で伝統的な共同性は国家の統合原理の一部でもあります。「令和日本国憲法草案」は、これらを「文化的な公共財」として明確に保護し、制度的な承認の枠組みを与えようとするものです。
そのためには、「国家宗教」ではなく、「民族的文化的遺産」としての宗教・儀礼・慣習を、国家が支援する新たな法的な枠組みが求められます。これは「信教の自由」ともちろん矛盾するものではありません。むしろ文化の多様性とその尊厳の尊重を目的とするものです。
「令和日本国憲法草案」の本質は、「理念としての国家(Staat als Idee)」の回復にあります。理念国家とは、もちろん単なる制度の集合体ではなく、文化・伝統・宗教・人倫を制度的に媒介しながら、国民の自己意識を形成するその実体でもあります。ここにおいて、成文憲法の硬直性を超えていくために、不文的な慣習や文化的な実践を「理念国家の現実的な契機」として認識し、それを制度化していくものです。
日本は、明治以来の法典主義を経て、とくに戦後憲法下において今日では国家理念の抽象化と伝統的な民族的な宗教・儀礼・慣習などの制度との乖離がいっそう深刻化しています。「令和日本国憲法草案」は、成文憲法の枠内において不文法的な運用を可能にし、柔軟かつ理念的な国家の再編を目指すものです。
この構想は、単なる制度改革にとどまらず、「文化の自己再生」と「国家の自己意識の再編」をも伴った根源的な国家哲学の刷新を含んでいます。それはまさに、ヘーゲルが『法の哲学』において語った「現実的な理念としての国家」の、 21世紀日本における現代的な再構成の試みでもあります。
「令和日本国憲法草案」について1 - 夕暮れのフクロウ https://is.gd/sauO8A



















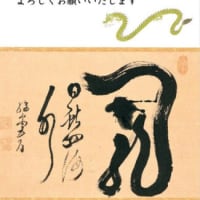
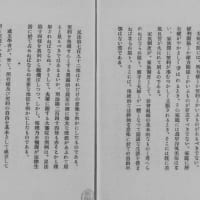







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます