§36
Der Trieb des Menschen nach seinem besondern Dasein, wie die Moral es betrachtet, geht auf die Übereinstimmung des Äußern überhaupt mit seinen inneren Bestimmungen(※1), auf Vergnügen und Glückseligkeit.
第三十六節[衝動と道徳]
人間の特殊な定在におけるその衝動を、道徳の面から見るならば、外的なもの一般と人間の内的な欲求との一致に関わり、満足と幸福 に関係する。
Erläuterung.
説明
Der Mensch hat Triebe d. h. er hat innerliche Bestimmungen in seiner Natur oder nach derjenigen Seite, nach welcher er ein Wirkliches überhaupt (※2)ist. Diese Bestimmungen sind also ein Mangelhaftes, insofern sie nur ein Innerliches sind.
人間は衝動をもつ。すなわち、人間はその生まれつきにおいて、あるいは人間が一般的に生身の存在であるという面において、人間は内的な欲求をもつ。これらの欲求は、したがって、それらが単に内的なものである限りにおいては、欠陥のあるものである。
Sie sind Triebe, insofern sie darauf ausgehen, diesen Mangel aufzuheben d. h. sie fordern ihre Realisierung, die Übereinstimmung des Äußerlichen mit dem Innerlichen.Diese Übereinstimmung ist das Vergnügen. Ihm geht daher eine Reflexion als Vergleichung zwischen dem Innerlichen und Äußerlichen voraus, mag dies von mir oder dem Glücke herrühren.
欲求がこの欠陥を補うことをを目指している限りにおいては、それは衝動である。すなわち、衝動は、外的なものと内的なものとを一致させるようその実現を要求する。これらの一致が満足である。だから、自力によるものか、幸運によるものかにかかわらず、その満足には内的なものと外的なものとを比較する反省が先行する。
Das Vergnügen kann nun aus den mannigfaltigsten Quellen entspringen. Es hängt nicht vom Inhalt ab, sondern betrifft nur die Form, oder es ist das Gefühl eines nur Formellen, nämlich der angegebenen Übereinstimmung. Die Lehre, welche das Vergnügen oder vielmehr die Glückseligkeit zum Zwecke hat, ist Eudämonismus genannt worden.
ところで、その満足はさまざまな源泉から生じうる。それは内容にかかわらず、ただ形式にのみ関係する。あるいは、その満足はただ形だけの感情、すなわち(内的なものと外的なものについて)得られた一致についての感情に関係している。満足あるいはさらに幸福を目的とする教えは「幸福説」とも呼ばれる。
Es ist aber darin unbestimmt, worin man das Vergnügen oder die Glückseligkeit zu suchen habe. Es kann also einen ganz rohen, groben Eudämonismus geben, aber eben so gut einen besseren; nämlich die guten wie die bösen Handlungen können sich auf dies Prinzip gründen.(※3)
しかし、幸福説では、満足や幸福を人間はどこに探求すべきかということについてははっきりしていない。したがって、まったく洗練されない粗雑な幸福説がありうるが、しかし同時にまた、非常に優れた幸福説もありうる。すなわち悪しき行動と同じく善き行動も、幸福説のこれらの原則に基づくことができる。
※1
die Übereinstimmung des Äußern überhaupt mit seinen inneren Bestimmungen
外にあるもの一般と人間の内にある規定との合致。
inneren Bestimmungen は「内的な欲求」と訳した。
人間の内なる欲望は外にあるものによって充足される。
※2
ein Wirkliches überhaupt
現実的なもの一般。要するに生きて活動するもの。
※3
前節において、道徳的行為は、抽象的なものではなくて個々の現実に関わる具体的な行為であることが明らかにされたが、そこにある具体的な生身の人間としては、生まれつき何らかの衝動をもつ。
衝動とは、人間の内的な欲求を外にあるもので充足させようとすることである。衝動の充足は、満足と幸福にかかわる。










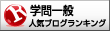








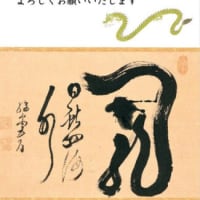
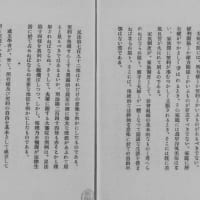







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます