(2006/ゴア・ヴァービンスキー監督/ジョニー・デップ=ジャック・スパロウ、オーランド・ブルーム=ウィル・ターナー、キーラ・ナイトレイ=エリザベス・スワン、ビル・ナイ=デイヴィ・ジョーンズ、ステラン・スカルスガルド=“ブーツストラップ”・ビル・ターナー、ジャック・ダヴェンポート=ノリントン、ケヴィン・マクナリー=ギブス、ナオミ・ハリス=ティア・ダルマ、ジョナサン・プライス=スワン総督、マッケンジー・クルック=ラジェッティ、トム・ホランダー=ベケット卿、リー・アレンバーグ=ピンテル、ジェフリー・ラッシュ=バルボッサ/151分)
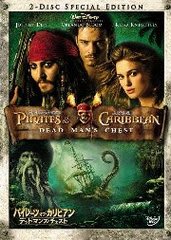 子供がTVCMの大蛸が船をぶっ潰すシーンを見て心待ちにしていた映画。レンタルが始まったので早速借りてきました。前作がまんざらでもなかったオヤジも楽しみにしておりました。
子供がTVCMの大蛸が船をぶっ潰すシーンを見て心待ちにしていた映画。レンタルが始まったので早速借りてきました。前作がまんざらでもなかったオヤジも楽しみにしておりました。
しかしなんですな、シリーズものの2作目というのは、特にこういうアクションアドベンチャー物は、主要な登場人物の紹介は既に済ましているのでその辺の楽しみはないし、後は新規に登場する人物とお話の意外性に頼るしかないので自然ハードルは高くなりますな。しかも今回は、最後が「それでは皆様、次回をお楽しみに~」って感じにクローズしちゃってて、1本の映画としては不完全燃焼してしまうものでありました。
お話は次から次へと新しい局面が出てくるので観てる分には飽きはこない。今回新しく登場した目玉のキャラクターは、半魚人ならぬ半蛸人と形容したくなる幽霊船の船長デイヴィ・ジョーンズ。なにやら、昔活躍したアメリカの人気バンドのボーカルを思い出してしまいますが、こちらはいわゆるクリーチャー。顔が蛸で髭が蛸の足のよう。片脚の義足はエイハブ船長みたいだし、片手はカニの爪になっておりました。
この船長とジャック・スパロウがどういう関係にあるかというと、13年前に海の底に沈んでいたブラックパールをスパロウがジョーンズに引き上げるのを頼んだという事らしい。で、その時にある約束事を交わしていたんだが、ジャックの履行期限が迫り、応じたくないジャックが回避の手段に出るという次第。
大蛸はジョーンズが操る怪物のようで、ジャックには大蛸の危機も迫る。
冒頭では、エリザベスとウィルが新しく赴任した統治者に捕まり、前作でジャックを逃がした罪で投獄される。但し、ジャックの持つコンパスを持ち帰ったら罪を軽減しようという条件に、ウィルはジャックに会いに行くことを許される。ウィルを待っても本当に無罪になるかどうか分からぬと、エリザベスは父親の手で脱獄しウィルに合流しようとする。こうして、また主役の3人が絡み合う。
前作で死んだと思われていたウィルの父親も登場したし、ジョーンズにも曰わくありげな過去話がありそうだし、最終作も観ることになるでしょうが、あっと驚くような展開、頼んますよ~。
▼(ネタバレ注意)
ジョーンズがああいう姿になったのには“失恋の痛手”という原因があったらしい。
死者をよみがえらす力を持っているような、不思議な女ティア・ダルマ。
最後の最後に出てきた、前作で死んだはずのバルボッサ。
大蛸に食われてしまったのか、ジャック・スパロウ。
『やっぱり、第1作がよかったなぁ』って、なるような気もするけど・・・。
▲(解除)
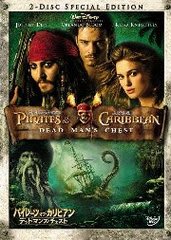 子供がTVCMの大蛸が船をぶっ潰すシーンを見て心待ちにしていた映画。レンタルが始まったので早速借りてきました。前作がまんざらでもなかったオヤジも楽しみにしておりました。
子供がTVCMの大蛸が船をぶっ潰すシーンを見て心待ちにしていた映画。レンタルが始まったので早速借りてきました。前作がまんざらでもなかったオヤジも楽しみにしておりました。しかしなんですな、シリーズものの2作目というのは、特にこういうアクションアドベンチャー物は、主要な登場人物の紹介は既に済ましているのでその辺の楽しみはないし、後は新規に登場する人物とお話の意外性に頼るしかないので自然ハードルは高くなりますな。しかも今回は、最後が「それでは皆様、次回をお楽しみに~」って感じにクローズしちゃってて、1本の映画としては不完全燃焼してしまうものでありました。
お話は次から次へと新しい局面が出てくるので観てる分には飽きはこない。今回新しく登場した目玉のキャラクターは、半魚人ならぬ半蛸人と形容したくなる幽霊船の船長デイヴィ・ジョーンズ。なにやら、昔活躍したアメリカの人気バンドのボーカルを思い出してしまいますが、こちらはいわゆるクリーチャー。顔が蛸で髭が蛸の足のよう。片脚の義足はエイハブ船長みたいだし、片手はカニの爪になっておりました。
この船長とジャック・スパロウがどういう関係にあるかというと、13年前に海の底に沈んでいたブラックパールをスパロウがジョーンズに引き上げるのを頼んだという事らしい。で、その時にある約束事を交わしていたんだが、ジャックの履行期限が迫り、応じたくないジャックが回避の手段に出るという次第。
大蛸はジョーンズが操る怪物のようで、ジャックには大蛸の危機も迫る。
冒頭では、エリザベスとウィルが新しく赴任した統治者に捕まり、前作でジャックを逃がした罪で投獄される。但し、ジャックの持つコンパスを持ち帰ったら罪を軽減しようという条件に、ウィルはジャックに会いに行くことを許される。ウィルを待っても本当に無罪になるかどうか分からぬと、エリザベスは父親の手で脱獄しウィルに合流しようとする。こうして、また主役の3人が絡み合う。
前作で死んだと思われていたウィルの父親も登場したし、ジョーンズにも曰わくありげな過去話がありそうだし、最終作も観ることになるでしょうが、あっと驚くような展開、頼んますよ~。
▼(ネタバレ注意)
ジョーンズがああいう姿になったのには“失恋の痛手”という原因があったらしい。
死者をよみがえらす力を持っているような、不思議な女ティア・ダルマ。
最後の最後に出てきた、前作で死んだはずのバルボッサ。
大蛸に食われてしまったのか、ジャック・スパロウ。
『やっぱり、第1作がよかったなぁ』って、なるような気もするけど・・・。
▲(解除)
・お薦め度【★★=悪くはないけどネ】 











 17世紀のカリブが舞台。部下に船を乗っ取られ、無人島に置き去りにされた悪名高き海賊船の船長ジャック・スパロウにジョニー・デップ。当地を治めている総督の娘エリザベス・スワンにキーラ・ナイトレイ。そして、映画の冒頭で海を漂流しているところを総督の船に拾われる少年ウィル・ターナーの成人後にオーランド・ブルームが扮する。
17世紀のカリブが舞台。部下に船を乗っ取られ、無人島に置き去りにされた悪名高き海賊船の船長ジャック・スパロウにジョニー・デップ。当地を治めている総督の娘エリザベス・スワンにキーラ・ナイトレイ。そして、映画の冒頭で海を漂流しているところを総督の船に拾われる少年ウィル・ターナーの成人後にオーランド・ブルームが扮する。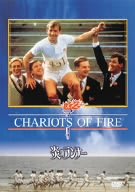 1924年、パリで行われた第8回オリンピックで活躍したイギリス代表選手の話だ。ケンブリッジ大学の負けず嫌いのユダヤ人新入生ハロルド・エイブラハムと、スコットランド人宣教師でラブビーの名ウィング、エリック・リデルのエピソードが主で、エイブラハムはユダヤ人故の偏見に苦しみ、リデルは信仰と国家への忠誠心との間で悩む。どちらも、陸上短距離走の選手だ。
1924年、パリで行われた第8回オリンピックで活躍したイギリス代表選手の話だ。ケンブリッジ大学の負けず嫌いのユダヤ人新入生ハロルド・エイブラハムと、スコットランド人宣教師でラブビーの名ウィング、エリック・リデルのエピソードが主で、エイブラハムはユダヤ人故の偏見に苦しみ、リデルは信仰と国家への忠誠心との間で悩む。どちらも、陸上短距離走の選手だ。 アメリカ西部の田舎町(実はサンフランシスコ近郊という設定)。住宅街を2台のショベルカーがゆっくりと進んでいる。町の住人は何事かと窓の外を覗く。ショベルカーは、町への侵入道路をふさぐように並んで、重いショベルを道路に降ろす。まるでバリケードのように。
アメリカ西部の田舎町(実はサンフランシスコ近郊という設定)。住宅街を2台のショベルカーがゆっくりと進んでいる。町の住人は何事かと窓の外を覗く。ショベルカーは、町への侵入道路をふさぐように並んで、重いショベルを道路に降ろす。まるでバリケードのように。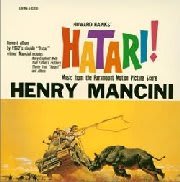 ヘンリー・マンシーニの「♪子象の行進」が忘れられない「ハタリ!」。夕べNHK-BS2で放送していたので懐かしくて録画した。アフリカが舞台の動物相手の仕事をしている人々の話で、内容は忘れてしまっていたが監督がハワード・ホークスだからハズレはないだろうと観てみたら、残念ながら個人的には大ハズレでした。
ヘンリー・マンシーニの「♪子象の行進」が忘れられない「ハタリ!」。夕べNHK-BS2で放送していたので懐かしくて録画した。アフリカが舞台の動物相手の仕事をしている人々の話で、内容は忘れてしまっていたが監督がハワード・ホークスだからハズレはないだろうと観てみたら、残念ながら個人的には大ハズレでした。 ショーンには、かつて結婚を約束していた女性がアフリカの生活になじめずに別れてしまったという過去があり、こと女性に関しては心を開けない男になっていた。
ショーンには、かつて結婚を約束していた女性がアフリカの生活になじめずに別れてしまったという過去があり、こと女性に関しては心を開けない男になっていた。 有名な武術家リー・ムーバイ(ユンファ)が、師匠から受け継いだ名剣を北京に向かうという女弟子ユー・シューリン(ヨー)に預ける。“グリーン・デスティニー”と名付けられたその剣には邪悪なモノを引きつける所があり、世に出回らぬ方がいいと考えたからだ。北京の著名な武術家の屋敷に届けられた名剣は、その夜の内に盗まれる。
有名な武術家リー・ムーバイ(ユンファ)が、師匠から受け継いだ名剣を北京に向かうという女弟子ユー・シューリン(ヨー)に預ける。“グリーン・デスティニー”と名付けられたその剣には邪悪なモノを引きつける所があり、世に出回らぬ方がいいと考えたからだ。北京の著名な武術家の屋敷に届けられた名剣は、その夜の内に盗まれる。
 「原子力潜水艦シービュー号」「宇宙家族ロビンソン」「タイム・トンネル」。子供の頃、これらSFテレビドラマでわくわくさせてくれたプロデューサー、アーウィン・アレンが、「ポセイドン・アドベンチャー(1972)」に続いて作ったパニック超大作だ。前作でもやったはずだが、今回はジョン・ギラーミンと並んでアクション部分の監督としてクレジットに名を連ねている。3時間近くの大作で、出演したスター俳優達も前作を遙かに凌ぐ豪華なものだった。
「原子力潜水艦シービュー号」「宇宙家族ロビンソン」「タイム・トンネル」。子供の頃、これらSFテレビドラマでわくわくさせてくれたプロデューサー、アーウィン・アレンが、「ポセイドン・アドベンチャー(1972)」に続いて作ったパニック超大作だ。前作でもやったはずだが、今回はジョン・ギラーミンと並んでアクション部分の監督としてクレジットに名を連ねている。3時間近くの大作で、出演したスター俳優達も前作を遙かに凌ぐ豪華なものだった。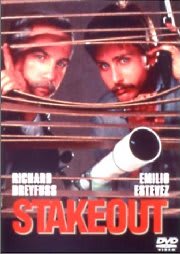 警官殺しなどで服役中のエイダン・クインが従兄弟の手引きで刑務所から脱獄する。FBIはクインが元恋人のマリア(ストー)の所にも来るはずだと、彼女の住んでいるシアトルの警察に張り込みを依頼する。
警官殺しなどで服役中のエイダン・クインが従兄弟の手引きで刑務所から脱獄する。FBIはクインが元恋人のマリア(ストー)の所にも来るはずだと、彼女の住んでいるシアトルの警察に張り込みを依頼する。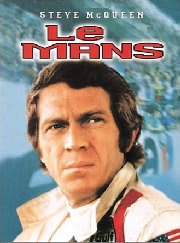 封切り時には見逃していて、74年のリバイバルで観たと思う。それでも30年ぶりの再会だ。
封切り時には見逃していて、74年のリバイバルで観たと思う。それでも30年ぶりの再会だ。
 第一次世界大戦勃発時のアフリカ。
第一次世界大戦勃発時のアフリカ。 ★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)
★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)

