(2018/ピーター・ファレリー監督・共同脚本/ヴィゴ・モーテンセン(=トニー・“リップ”・バレロンガ)、マハーシャラ・アリ(=ドクター・ドナルド・シャーリー)、リンダ・カーデリーニ(=ドロレス・バレロンガ)、ディミテル・D・マリノフ、マイク・ハットン/130分)
 実話が元ネタだそうです。
実話が元ネタだそうです。
1962年のアメリカ、ニューヨーク。
ブロンクスで暮らすイタリア系アメリカ人のトニーはナイトクラブ「コパカバーナ」で用心棒をしていたが、店が改装の為に数か月閉店することになりその間無職になった。店の担当者が探してくれた仕事はカーネギーホールの上階に住む天才黒人ピアニスト、ドクター・ドン・シャーリーのツアーの運転手だった。ブロンクスの親戚仲間と同じくトニーも黒人を毛嫌いしていたが、仕事となれば割り切れる彼は自分の希望を全てのませてその仕事を獲得した。
ツアーは中西部を出発してディープサウス(深南部)の各州を8週間をかけて廻るモノで、ロシア人のチェロとベースを加えたトリオ編成だった。現在よりも黒人差別の激しい南部アメリカでのツアーはトニーの予想通り危険と隣り合わせのものだった・・・。
人種差別を批判する映画ですが、それよりも正反対の生き方をする男同士にだんだんと相手に対するリスペクトが生まれ、最後には友情で繋がるようになるまでが落ち着いた語り口で綴られた作品でした。
ロード・ムーヴィーであり、序盤は二人の人生観の違いからくる軋轢が軽く描かれ、ツアーが南部に入るにしたがってトニーが知らなかった黒人差別の実態が段々と露わになっていく構成が秀逸です。
トニーが愛妻に頼まれて旅先で書く手紙のエピソードがエピローグ(クリスマス・イヴ!)に効いてきてウルウルしてしまいました。
「ヒストリー・オブ・バイオレンス」のヴィゴ・モーテンセンがちょっぴり太めの体型に変貌して、がさつだけど人情に篤いイタリアンを演じて各賞で主演男優賞にノミネートされております。
品位を尊重するピアニストを演じたマハーシャラ・アリはアカデミー賞で助演男優賞を受賞したそうです。
尚、タイトルの「グリーンブック」とは黒人が利用できる施設を記した旅行ガイドブックのことだそうです。
 実話が元ネタだそうです。
実話が元ネタだそうです。1962年のアメリカ、ニューヨーク。
ブロンクスで暮らすイタリア系アメリカ人のトニーはナイトクラブ「コパカバーナ」で用心棒をしていたが、店が改装の為に数か月閉店することになりその間無職になった。店の担当者が探してくれた仕事はカーネギーホールの上階に住む天才黒人ピアニスト、ドクター・ドン・シャーリーのツアーの運転手だった。ブロンクスの親戚仲間と同じくトニーも黒人を毛嫌いしていたが、仕事となれば割り切れる彼は自分の希望を全てのませてその仕事を獲得した。
ツアーは中西部を出発してディープサウス(深南部)の各州を8週間をかけて廻るモノで、ロシア人のチェロとベースを加えたトリオ編成だった。現在よりも黒人差別の激しい南部アメリカでのツアーはトニーの予想通り危険と隣り合わせのものだった・・・。
*
人種差別を批判する映画ですが、それよりも正反対の生き方をする男同士にだんだんと相手に対するリスペクトが生まれ、最後には友情で繋がるようになるまでが落ち着いた語り口で綴られた作品でした。
ロード・ムーヴィーであり、序盤は二人の人生観の違いからくる軋轢が軽く描かれ、ツアーが南部に入るにしたがってトニーが知らなかった黒人差別の実態が段々と露わになっていく構成が秀逸です。
トニーが愛妻に頼まれて旅先で書く手紙のエピソードがエピローグ(クリスマス・イヴ!)に効いてきてウルウルしてしまいました。
「ヒストリー・オブ・バイオレンス」のヴィゴ・モーテンセンがちょっぴり太めの体型に変貌して、がさつだけど人情に篤いイタリアンを演じて各賞で主演男優賞にノミネートされております。
品位を尊重するピアニストを演じたマハーシャラ・アリはアカデミー賞で助演男優賞を受賞したそうです。
尚、タイトルの「グリーンブック」とは黒人が利用できる施設を記した旅行ガイドブックのことだそうです。
・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】

(2017/マーク・ウェブ監督/クリス・エヴァンス(=フランク)、マッケナ・グレイス(=メアリー)、リンゼイ・ダンカン(=イヴリン)、ジェニー・スレイト(ボニー)、オクタヴィア・スペンサー(=ロバータ)/101分)
<ギフテッド(Gifted)とは、先天的に顕著に高い知性と共感的理解、倫理観、正義感、博愛精神のいずれかを持っている人のこと。知的才能。これらの定義は世間的な成功を収める、収めないに関わらない。また、目立つことを避けようと故意ないし無意識的に怠け者や優秀でない者、天然な性格を演じることで社会に溶け込もうとする傾向が報告されており、現代社会における発見は困難で、診断には高度な専門知識を必要とする。参考知能指数は130以上。過集中、突発的な言動、早口など、ADHDと共通する特徴があり誤解されやすい>(ウィキペディアより)
つまり彼らは神様から類まれなる才能というか資質を授けられた、贈られた人なのである。
何かのDVDを観た時の予告編の中にあって、観たいと思っていた作品だった。
 幼い娘とシングル・ファーザーのお話と思って観ていたら、姉の忘れ形見の姪を育てる男と、その天才的頭脳を持った少女とのハート・ウォ-ミングなドラマでありました。
幼い娘とシングル・ファーザーのお話と思って観ていたら、姉の忘れ形見の姪を育てる男と、その天才的頭脳を持った少女とのハート・ウォ-ミングなドラマでありました。
少女が七歳になったので学校に通わなくてはならなくなるが、たちまちその特異な能力に気付かれ、やがて少女の母方の祖母がやってきて孫娘の親権を息子と争うという裁判劇の要素も入ってくる。
祖母は孫娘がギフテッドであることを知っており、彼女に相応しい環境で育てるべきだと主張するが、息子は姪をあくまでも普通の少女らしい環境に置きたいと思っている。
何故祖母は裁判を起こしてまでも孫娘を息子から奪おうとするのか?
何故息子は母親の要望を断って姪を普通の学校に通わせようとするのか?
実は少女の母親も天才的数学者でありフィールズ賞やノーベル賞を獲得するかもしれないと期待された女性だった。しかし彼女はまだ赤ん坊の娘を弟に託して自殺をしたのだ。
何故彼女は死んでしまったのか?
裁判の過程で彼ら家族の歴史や関係性が明らかになって行く所も面白いし、最後にどんでん返しの様に明かされる姉の秘密に祖母は涙する。
天才少女メアリーに扮したマッケナ・グレイスが可愛い。
<ギフテッド(Gifted)とは、先天的に顕著に高い知性と共感的理解、倫理観、正義感、博愛精神のいずれかを持っている人のこと。知的才能。これらの定義は世間的な成功を収める、収めないに関わらない。また、目立つことを避けようと故意ないし無意識的に怠け者や優秀でない者、天然な性格を演じることで社会に溶け込もうとする傾向が報告されており、現代社会における発見は困難で、診断には高度な専門知識を必要とする。参考知能指数は130以上。過集中、突発的な言動、早口など、ADHDと共通する特徴があり誤解されやすい>(ウィキペディアより)
つまり彼らは神様から類まれなる才能というか資質を授けられた、贈られた人なのである。
何かのDVDを観た時の予告編の中にあって、観たいと思っていた作品だった。
*
 幼い娘とシングル・ファーザーのお話と思って観ていたら、姉の忘れ形見の姪を育てる男と、その天才的頭脳を持った少女とのハート・ウォ-ミングなドラマでありました。
幼い娘とシングル・ファーザーのお話と思って観ていたら、姉の忘れ形見の姪を育てる男と、その天才的頭脳を持った少女とのハート・ウォ-ミングなドラマでありました。少女が七歳になったので学校に通わなくてはならなくなるが、たちまちその特異な能力に気付かれ、やがて少女の母方の祖母がやってきて孫娘の親権を息子と争うという裁判劇の要素も入ってくる。
祖母は孫娘がギフテッドであることを知っており、彼女に相応しい環境で育てるべきだと主張するが、息子は姪をあくまでも普通の少女らしい環境に置きたいと思っている。
何故祖母は裁判を起こしてまでも孫娘を息子から奪おうとするのか?
何故息子は母親の要望を断って姪を普通の学校に通わせようとするのか?
実は少女の母親も天才的数学者でありフィールズ賞やノーベル賞を獲得するかもしれないと期待された女性だった。しかし彼女はまだ赤ん坊の娘を弟に託して自殺をしたのだ。
何故彼女は死んでしまったのか?
裁判の過程で彼ら家族の歴史や関係性が明らかになって行く所も面白いし、最後にどんでん返しの様に明かされる姉の秘密に祖母は涙する。
天才少女メアリーに扮したマッケナ・グレイスが可愛い。
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】

(2018/ペアニル・フィシャー・クリステンセン監督・共同脚本/アルバ・アウグスト(=アストリッド)、マリア・ボネヴィー(=母ハンナ)、トリーヌ・ディルホム(=里親マリー)、マグヌス・クレッペル(=父サムエル)、ヘンリク・ラファエルソン(=編集長ブロムベルイ)/123分)

 2018年のスウェーデン映画「リンドグレーン」を観る。「長くつ下のピッピ」でお馴染みの世界的な児童文学作家アストリッド・リンドグレーンを題材にした作品だ。
2018年のスウェーデン映画「リンドグレーン」を観る。「長くつ下のピッピ」でお馴染みの世界的な児童文学作家アストリッド・リンドグレーンを題材にした作品だ。
子供の頃に多分「ピッピ」も読んだはずだが、僕の頭に残っているのは「やかまし村」とか「名探偵カッレ君」のシリーズだった。それと「ラスムス君」とか。
小学生時分の愛読書を聞かれたらSFと共に「シートン動物記」や「ファーブル昆虫記」、そしてジャック・ロンドンの動物モノを挙げる僕だが、一方でリンドグレーンにも愛着があった。
なので2年前にこの映画の事を知った時には必ず見ようと思っていた。リンドグレーンの人となりを殆ど知らなかったからだが、内容は僕が期待していた創作の秘密のようなものではなかった。
原題が【UNGA ASTRID】。英語で表記すると【YOUNG ASTRID】。つまり若き日のアストリッドを描いた作品なのだ。
映画配給会社は「若きアストリッド」では知名度に問題有りと思ったんでしょう、ただの「リンドグレーン」とした。本当は結婚してリンドグレーン姓になる前の彼女を描いているのにね。
 オープニングは年老いたアストリッドが書斎で子供達から届いたファンレターを開封して読んでいるシーンで、屋内から窓側に向けたカメラに映る彼女がシルエットの様に描かれていて素敵だった。
オープニングは年老いたアストリッドが書斎で子供達から届いたファンレターを開封して読んでいるシーンで、屋内から窓側に向けたカメラに映る彼女がシルエットの様に描かれていて素敵だった。
折々にその手紙が子供の声でナレーションされているのも雰囲気がある。時にエピソードとリンクしていると感じるものもあった。
 ただねぇ。16歳から20代前半の数年間の彼女の人生を描いているわけだけど、上にも書いたように創作の秘密とか起源のようなエピソードではなかった気がするんだよね。
ただねぇ。16歳から20代前半の数年間の彼女の人生を描いているわけだけど、上にも書いたように創作の秘密とか起源のようなエピソードではなかった気がするんだよね。
確かに波乱万丈な数年間だし彼女の苦労がその後の糧になっただろう事は容易に想像できるけど、その対処の仕方に彼女なりの聡明さとか意外さみたいなモノは無かった。
両親とのエピソードも物語の軸になりそうなものだったのに、今一つつっこんだ描写ではなかったね。もう少し感動的なウェットな描き方でも良かったと思うけどなぁ。
 ウィキペディアには<スウェーデンの南東部のヴィンメルビューで4人兄弟の長女として生まれた。田園地帯の小さな牧場で家族と共に過ごした幸福な子供時代の経験が作品の下敷きになっている>と書いてあるが、映画は全然違う様相だった。
ウィキペディアには<スウェーデンの南東部のヴィンメルビューで4人兄弟の長女として生まれた。田園地帯の小さな牧場で家族と共に過ごした幸福な子供時代の経験が作品の下敷きになっている>と書いてあるが、映画は全然違う様相だった。
女流作家の性格は大体がお転婆で常識にとらわれない奔放なものと言うのが通り相場だが、アストリッドもそういう風に描かれていた。
敬虔なクリスチャンの農業家庭に生まれるも、毎週の教会通いも彼女にとっては退屈でしかない。父親は静かに見守ってくれるが母親にはいつも小言を頂戴するお姉ちゃんだった。
16歳の時に友人の父親がオーナーで編集長でもある新聞社に雇われ、その文才を褒められた事から急接近、男女の関係になり赤ん坊を身ごもってしまう。
地域の人に知られることは出来ないと、ストックホルムで秘書の学校に通いながら赤ん坊を産む。
編集長には妻がいるので離婚裁判の終結を待って結婚するつもりだったが、長引いたのでアストリッドは赤ん坊を隣国デンマークの里親に預ける事にするのだが・・・。
というようなお話でね。
父親くらいの年齢差の男との情事が苦労の発端だけど、どちらかというと彼女の方が積極的だったし、その若気の至り感も何処かで観たような気がするし、そんなに興味惹かれるものでもなかったな。
▼(ネタバレ注意)
なんやかやと裁判は長引き、赤ん坊はどんどん大きくなる。
編集長は姦通罪に問われるもわずかな罰金でやっとのことで離婚が出来るようになるが、それを告げる彼のあっけらかんとしたモノ言いにアストリッドはカチンと来てしまう。
先の見通しを厳しく見積もっていたにしても、母子離れ離れで暮らさざるを得なかったアストリッドには、彼が将来的に信用できない伴侶に見えたのでしょう。
こうしていよいよシングルマザーとして子育てと仕事の両立に立ち向かうわけだが、いざ引き取った我が子は既に里親に懐いていてなかなか自分に馴染んでくれないというさもありなんというシチュエーションにもなっていくわけです。
▲(解除)
 allcinemaの解説によると、<19歳で予期せぬ妊娠をしてしまう>と書いてある。
allcinemaの解説によると、<19歳で予期せぬ妊娠をしてしまう>と書いてある。
全体的にもそうだけど、時の流れがよく分からないのが難点だよね。
北欧の映画らしい厳しくも美しい自然の描写に合わすように、手持ちカメラによる観照的な描き方は理解できるが、人物像が表層的だったね。
なのでお薦め度は★二つ半。
 自分に懐かない我が子が病気になり、看病する間に添い寝をして物語を話してきかすというシーンが一番観たかったエピソードかも知れない。
自分に懐かない我が子が病気になり、看病する間に添い寝をして物語を話してきかすというシーンが一番観たかったエピソードかも知れない。

 2018年のスウェーデン映画「リンドグレーン」を観る。「長くつ下のピッピ」でお馴染みの世界的な児童文学作家アストリッド・リンドグレーンを題材にした作品だ。
2018年のスウェーデン映画「リンドグレーン」を観る。「長くつ下のピッピ」でお馴染みの世界的な児童文学作家アストリッド・リンドグレーンを題材にした作品だ。子供の頃に多分「ピッピ」も読んだはずだが、僕の頭に残っているのは「やかまし村」とか「名探偵カッレ君」のシリーズだった。それと「ラスムス君」とか。
小学生時分の愛読書を聞かれたらSFと共に「シートン動物記」や「ファーブル昆虫記」、そしてジャック・ロンドンの動物モノを挙げる僕だが、一方でリンドグレーンにも愛着があった。
なので2年前にこの映画の事を知った時には必ず見ようと思っていた。リンドグレーンの人となりを殆ど知らなかったからだが、内容は僕が期待していた創作の秘密のようなものではなかった。
原題が【UNGA ASTRID】。英語で表記すると【YOUNG ASTRID】。つまり若き日のアストリッドを描いた作品なのだ。
映画配給会社は「若きアストリッド」では知名度に問題有りと思ったんでしょう、ただの「リンドグレーン」とした。本当は結婚してリンドグレーン姓になる前の彼女を描いているのにね。
 オープニングは年老いたアストリッドが書斎で子供達から届いたファンレターを開封して読んでいるシーンで、屋内から窓側に向けたカメラに映る彼女がシルエットの様に描かれていて素敵だった。
オープニングは年老いたアストリッドが書斎で子供達から届いたファンレターを開封して読んでいるシーンで、屋内から窓側に向けたカメラに映る彼女がシルエットの様に描かれていて素敵だった。折々にその手紙が子供の声でナレーションされているのも雰囲気がある。時にエピソードとリンクしていると感じるものもあった。
 ただねぇ。16歳から20代前半の数年間の彼女の人生を描いているわけだけど、上にも書いたように創作の秘密とか起源のようなエピソードではなかった気がするんだよね。
ただねぇ。16歳から20代前半の数年間の彼女の人生を描いているわけだけど、上にも書いたように創作の秘密とか起源のようなエピソードではなかった気がするんだよね。確かに波乱万丈な数年間だし彼女の苦労がその後の糧になっただろう事は容易に想像できるけど、その対処の仕方に彼女なりの聡明さとか意外さみたいなモノは無かった。
両親とのエピソードも物語の軸になりそうなものだったのに、今一つつっこんだ描写ではなかったね。もう少し感動的なウェットな描き方でも良かったと思うけどなぁ。
 ウィキペディアには<スウェーデンの南東部のヴィンメルビューで4人兄弟の長女として生まれた。田園地帯の小さな牧場で家族と共に過ごした幸福な子供時代の経験が作品の下敷きになっている>と書いてあるが、映画は全然違う様相だった。
ウィキペディアには<スウェーデンの南東部のヴィンメルビューで4人兄弟の長女として生まれた。田園地帯の小さな牧場で家族と共に過ごした幸福な子供時代の経験が作品の下敷きになっている>と書いてあるが、映画は全然違う様相だった。女流作家の性格は大体がお転婆で常識にとらわれない奔放なものと言うのが通り相場だが、アストリッドもそういう風に描かれていた。
敬虔なクリスチャンの農業家庭に生まれるも、毎週の教会通いも彼女にとっては退屈でしかない。父親は静かに見守ってくれるが母親にはいつも小言を頂戴するお姉ちゃんだった。
16歳の時に友人の父親がオーナーで編集長でもある新聞社に雇われ、その文才を褒められた事から急接近、男女の関係になり赤ん坊を身ごもってしまう。
地域の人に知られることは出来ないと、ストックホルムで秘書の学校に通いながら赤ん坊を産む。
編集長には妻がいるので離婚裁判の終結を待って結婚するつもりだったが、長引いたのでアストリッドは赤ん坊を隣国デンマークの里親に預ける事にするのだが・・・。
というようなお話でね。
父親くらいの年齢差の男との情事が苦労の発端だけど、どちらかというと彼女の方が積極的だったし、その若気の至り感も何処かで観たような気がするし、そんなに興味惹かれるものでもなかったな。
▼(ネタバレ注意)
なんやかやと裁判は長引き、赤ん坊はどんどん大きくなる。
編集長は姦通罪に問われるもわずかな罰金でやっとのことで離婚が出来るようになるが、それを告げる彼のあっけらかんとしたモノ言いにアストリッドはカチンと来てしまう。
先の見通しを厳しく見積もっていたにしても、母子離れ離れで暮らさざるを得なかったアストリッドには、彼が将来的に信用できない伴侶に見えたのでしょう。
こうしていよいよシングルマザーとして子育てと仕事の両立に立ち向かうわけだが、いざ引き取った我が子は既に里親に懐いていてなかなか自分に馴染んでくれないというさもありなんというシチュエーションにもなっていくわけです。
▲(解除)
 allcinemaの解説によると、<19歳で予期せぬ妊娠をしてしまう>と書いてある。
allcinemaの解説によると、<19歳で予期せぬ妊娠をしてしまう>と書いてある。全体的にもそうだけど、時の流れがよく分からないのが難点だよね。
北欧の映画らしい厳しくも美しい自然の描写に合わすように、手持ちカメラによる観照的な描き方は理解できるが、人物像が表層的だったね。
なのでお薦め度は★二つ半。
 自分に懐かない我が子が病気になり、看病する間に添い寝をして物語を話してきかすというシーンが一番観たかったエピソードかも知れない。
自分に懐かない我が子が病気になり、看病する間に添い寝をして物語を話してきかすというシーンが一番観たかったエピソードかも知れない。・お薦め度【★★=悪くはないけどネ】 

(2004/ヴィム・ヴェンダース監督・共同脚本/ジョン・ディール(=ポール)、ミシェル・ウィリアムズ(=ラナ)、ウェンデル・ピアース(=ヘンリー)、リチャード・エドソン(=ジミー)、バート・ヤング(=シャーマン)、ショーン・トーブ(=ハッサン)/124分)
 「パリ、テキサス (1984)」しか観てないヴィム・ヴェンダースだけど「ベルリン・天使の詩 (1987)」とか「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ (1999)」とか前から観たいと思っている作品もあって、改めてデータを見てみると「アメリカの友人 (1977)」とか「都会のアリス (1974)」、「アメリカ、家族のいる風景 (2005)」なんていう知っているタイトルも沢山あることが分かった。こりゃのんびりしてられんな。
「パリ、テキサス (1984)」しか観てないヴィム・ヴェンダースだけど「ベルリン・天使の詩 (1987)」とか「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ (1999)」とか前から観たいと思っている作品もあって、改めてデータを見てみると「アメリカの友人 (1977)」とか「都会のアリス (1974)」、「アメリカ、家族のいる風景 (2005)」なんていう知っているタイトルも沢山あることが分かった。こりゃのんびりしてられんな。
何となくジム・ジャームッシュと同じゆるい系のイメージなんだけど、どちらもドイツの血が入ってるんだね。
 何年も前に買ったレンタル落ちDVDの鑑賞。
何年も前に買ったレンタル落ちDVDの鑑賞。
監督の名前だけで買ったはずでストーリーは知らないと思っていたが、MYブログを検索したら2005年に<ヴェンダースの新作>として記事にしていた。有田芳生氏のHP内にある日記に試写会後の感想として面白かったと紹介されていて、コレは覚えておこうと書いていたのだ。5年前に買ったとしても記事からは十年は経っているんだが、完全に忘れてたネ。
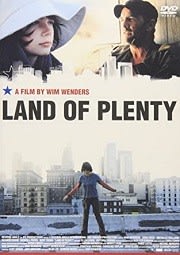 9.11事件から2年後のカリフォルニアが舞台。
9.11事件から2年後のカリフォルニアが舞台。
主人公は二人。それぞれのエピソードが冒頭から並行して語られていって、中盤からは二人のロードムーヴィーとなって行く。
まずは元グリーンベレーの中年男ポール・ジェフリーズ。
監視用機器を装備した中古のバンに乗って街中を巡回、監視するのが日課となっているポール。日課というよりは生粋の愛国者としてソレが使命だと思っている男だ。ベトナム戦争時代の枯葉剤の影響であちこち激痛が走ったりするが弱音は吐かない。ターバンを巻いた男を見れば怪しいアラブ人として追跡したり、定期的に川の水を採取して生物化学兵器や爆弾製造の兆候がないかを調べたりもする。
分析をしてくれるのはポールよりちょっと若いジミー。ポールを“曹長”と呼んでいるが戦時中からの知り合いなんだろうか。真面目でどこか心根の優しさが滲み出ているタイプの男だ。
2001年の9.11後、アメリカにはポールのような男性が増えたに違いないよね。ヒステリックな事件も起きてたように記憶する。今はコロナの影響でアジア人が憎悪の対象だけど。
もう一人の主人公はラナという二十歳の少女。名字はスウェンソン。
父親は宣教師で両親に連れられてアフリカや中近東で暮らしてきたが、母親が病死し、その母親の薦めでアメリカに住む伯父を探しにやって来たのだ。母親からの手紙を渡す目的もある。およそ十年ぶりの帰国だ。
冒頭でテルアビブからロスの空港に到着。迎えてくれたのはロスの貧民街で伝道と慈善活動をしている宣教師のヘンリー。ラナが小さい頃から知っているので今回の帰国の手配をしてくれたのだ。アメリカでホームレスの数が一番多いと言われるカリフォルニアで、彼らを救おうとしているヘンリーの手伝いをしながら伯父を探すことになる。ほぼリュック一つが全財産だがノートパソコンさえあれば世界中の情報が手に入り地球の裏側の人とも話が出来る。パレスチナの友人ともチャットが出来るラナなのだ。
ラナが探している母親の兄がポールであることは予想がつき、割と早い段階で明らかになるもコンタクトはスムースではなかった。ポールは勝手に私設米国防衛隊の隊長を任じているが、テロリストからも監視をされているかも知れないという意識があるからだ。
母親に聞いた住所でラナはジミーに出会い、彼に聞いた伯父の携帯番号に伝道所から電話するもポールは出ない。改めて後に公衆電話からその番号に掛けてくるのだ。誰が盗聴しているか分からない、ポールはそう思っている。僕には少し滑稽にみえるポールだが、ラナは勿論真剣に対応する。
『名前は?』
『ラナ、ラナ・スウェンソン』
ポールは伝道所の情報を聞いてきた男を装っていたが、ラナの名前を聞いた後の少しの沈黙にラナは彼が伯父であると気付く。
『ポール伯父さん』
用事があればまた掛けると言いながらポールは電話を一方的に切る。
翌日、ラナの様子を見ようとポールは伝道所の給食部屋にやって来るが、そこで数日前から監視対象にしている一人のアラブ人に遭遇する。洗剤メーカーの箱を抱えて街をうろついていた男だ。バンから男を監視するポール。
夜になり、ターバンを巻いた男は伝道所のすぐ近くの路上に段ボールを組み立て、数人の男達とドラム缶で火を焚きながら暖をとっていた。
すると、ポールのバンの反対側から一台の黒い大きな車がやって来て、ホームレスの段ボールに火を放ち、ポールが監視していたアラブ人に弾丸を打ち込んだ。あっという間の出来事だった。
ラナやヘンリー達が伝道所から出て来てアラブ人を介抱しようとしたが、男はポールの腕の中で死に絶えた。『トロナ』という言葉を残して。
ここまでで上映時間約45分。
その後、ジミーの調査で「トロナ」とはソルトレイクの近くの町の名前である事が分かり、警察で被害者の名がハッサン・アフメッドである事を聞いたラナがネットで「トロナのアフメッド」で検索して、親族らしき人物がトロナに一人いる事が分かった。
家族に遺体を引き渡したいラナはポールに遺体を運ぶことを頼む。ラナ曰く、「トロナ」に行けばテロリストの様子が知れるかもしれないし、遺体を運ぶのだから怪しまれない。
こうして、二人の短い旅が始まる・・・。
 お薦め度は★三つ。
お薦め度は★三つ。
まるで“ごっこ”に見えなくもないポールのエピソードだけど、当時のアメリカ人の焦燥というか9.11のトラウマというか、ただ笑って済ますわけにはいかないモノを感じるんだよね。そして、雑に見えながらエピソードが無駄なく繋がっていくのも良い。
音楽の使い方も現代風で、時にミュージックビデオの様に見えるシーンもあり流石“ゆるい系“という感じでした。
後半は二人のロード・ムーヴィーになるって書いたけど、ラナに関していえば最初からずっとそうなんだよね。
 特典映像によると全編デジタルカメラでの撮影で、俳優陣からすると小さなカメラだし、準備の時間も要らないので演技に集中できたらしい。監督においてはフィルム撮影のような物理的な制限を気にしなくてよく、NGにも誰もイラつかなかったとの事。ヴェンダース曰く、小さいので殆ど手持ちでの撮影だったがドキュメンタリー風にはならずに映画らしく仕上がった。
特典映像によると全編デジタルカメラでの撮影で、俳優陣からすると小さなカメラだし、準備の時間も要らないので演技に集中できたらしい。監督においてはフィルム撮影のような物理的な制限を気にしなくてよく、NGにも誰もイラつかなかったとの事。ヴェンダース曰く、小さいので殆ど手持ちでの撮影だったがドキュメンタリー風にはならずに映画らしく仕上がった。
撮影監督はフランツ・ルスティヒ。
 ジョン・ディールは「ジュラシック・パークⅢ」に出てたとの事。多分捜索隊の護衛の役だったと思うが覚えてない。
ジョン・ディールは「ジュラシック・パークⅢ」に出てたとの事。多分捜索隊の護衛の役だったと思うが覚えてない。
ミシェル・ウィリアムズは「ブロークバック・マウンテン」でお逢いしましたな。
「ロッキー」シリーズのエイドリアンの兄貴でお馴染みのバート・ヤングは伝道所の管理人の役でした。
▼(ネタバレ注意)
トロナの調査の結果はポールの完全なる見当違い。己の勘の鈍ったことにショックを受けたポールはトロナのモーテルで酔いつぶれ、ラナに介抱される。
ハッサンの葬儀の間、ポールはラナの母親、つまり妹からの手紙を読む。
かつて考え方の違いで仲違いした兄妹だったが、余命幾ばくも無くなった妹は兄に自分が幼く間違っていた事を誤り、残していく娘の事を託す。ラナには宣教師の父親がいるが、その妻からすると娘の将来を託すには頼りなかったらしい。
ラナは9.11の時に中東にいて、周りのアラブの人々が歓声をあげていた事にショックを受けたと話す。アメリカやアメリカ人を嫌う人々が世界にはいるのだ。
9.11でツインタワーで亡くなった一般市民は3000人以上。彼らはテロリスト達への報復を望んでいるだろうか?
ラストシーンは、バンでニューヨークに向かうポールとラナの姿。そしてグランドゼロを見下ろす彼らの姿でした。
余談ですがポールの携帯の受信音はアメリカ国歌でした(笑)
▲(解除)
[05.14 追記]
昨日監督の解説付きバージョンを観たらジミーもベトナム帰還兵という事でした。そしてポールとジミーの家は隣同士だけど、ポールはバンに寝泊まりしてるとの事。
また、携帯のアメリカ国歌は標準で付いていたそう。なるほど。
 「パリ、テキサス (1984)」しか観てないヴィム・ヴェンダースだけど「ベルリン・天使の詩 (1987)」とか「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ (1999)」とか前から観たいと思っている作品もあって、改めてデータを見てみると「アメリカの友人 (1977)」とか「都会のアリス (1974)」、「アメリカ、家族のいる風景 (2005)」なんていう知っているタイトルも沢山あることが分かった。こりゃのんびりしてられんな。
「パリ、テキサス (1984)」しか観てないヴィム・ヴェンダースだけど「ベルリン・天使の詩 (1987)」とか「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ (1999)」とか前から観たいと思っている作品もあって、改めてデータを見てみると「アメリカの友人 (1977)」とか「都会のアリス (1974)」、「アメリカ、家族のいる風景 (2005)」なんていう知っているタイトルも沢山あることが分かった。こりゃのんびりしてられんな。何となくジム・ジャームッシュと同じゆるい系のイメージなんだけど、どちらもドイツの血が入ってるんだね。
 何年も前に買ったレンタル落ちDVDの鑑賞。
何年も前に買ったレンタル落ちDVDの鑑賞。監督の名前だけで買ったはずでストーリーは知らないと思っていたが、MYブログを検索したら2005年に<ヴェンダースの新作>として記事にしていた。有田芳生氏のHP内にある日記に試写会後の感想として面白かったと紹介されていて、コレは覚えておこうと書いていたのだ。5年前に買ったとしても記事からは十年は経っているんだが、完全に忘れてたネ。
*
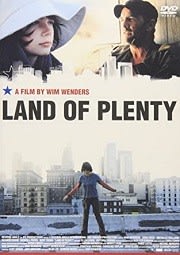 9.11事件から2年後のカリフォルニアが舞台。
9.11事件から2年後のカリフォルニアが舞台。主人公は二人。それぞれのエピソードが冒頭から並行して語られていって、中盤からは二人のロードムーヴィーとなって行く。
まずは元グリーンベレーの中年男ポール・ジェフリーズ。
監視用機器を装備した中古のバンに乗って街中を巡回、監視するのが日課となっているポール。日課というよりは生粋の愛国者としてソレが使命だと思っている男だ。ベトナム戦争時代の枯葉剤の影響であちこち激痛が走ったりするが弱音は吐かない。ターバンを巻いた男を見れば怪しいアラブ人として追跡したり、定期的に川の水を採取して生物化学兵器や爆弾製造の兆候がないかを調べたりもする。
分析をしてくれるのはポールよりちょっと若いジミー。ポールを“曹長”と呼んでいるが戦時中からの知り合いなんだろうか。真面目でどこか心根の優しさが滲み出ているタイプの男だ。
2001年の9.11後、アメリカにはポールのような男性が増えたに違いないよね。ヒステリックな事件も起きてたように記憶する。今はコロナの影響でアジア人が憎悪の対象だけど。
もう一人の主人公はラナという二十歳の少女。名字はスウェンソン。
父親は宣教師で両親に連れられてアフリカや中近東で暮らしてきたが、母親が病死し、その母親の薦めでアメリカに住む伯父を探しにやって来たのだ。母親からの手紙を渡す目的もある。およそ十年ぶりの帰国だ。
冒頭でテルアビブからロスの空港に到着。迎えてくれたのはロスの貧民街で伝道と慈善活動をしている宣教師のヘンリー。ラナが小さい頃から知っているので今回の帰国の手配をしてくれたのだ。アメリカでホームレスの数が一番多いと言われるカリフォルニアで、彼らを救おうとしているヘンリーの手伝いをしながら伯父を探すことになる。ほぼリュック一つが全財産だがノートパソコンさえあれば世界中の情報が手に入り地球の裏側の人とも話が出来る。パレスチナの友人ともチャットが出来るラナなのだ。
ラナが探している母親の兄がポールであることは予想がつき、割と早い段階で明らかになるもコンタクトはスムースではなかった。ポールは勝手に私設米国防衛隊の隊長を任じているが、テロリストからも監視をされているかも知れないという意識があるからだ。
母親に聞いた住所でラナはジミーに出会い、彼に聞いた伯父の携帯番号に伝道所から電話するもポールは出ない。改めて後に公衆電話からその番号に掛けてくるのだ。誰が盗聴しているか分からない、ポールはそう思っている。僕には少し滑稽にみえるポールだが、ラナは勿論真剣に対応する。
『名前は?』
『ラナ、ラナ・スウェンソン』
ポールは伝道所の情報を聞いてきた男を装っていたが、ラナの名前を聞いた後の少しの沈黙にラナは彼が伯父であると気付く。
『ポール伯父さん』
用事があればまた掛けると言いながらポールは電話を一方的に切る。
翌日、ラナの様子を見ようとポールは伝道所の給食部屋にやって来るが、そこで数日前から監視対象にしている一人のアラブ人に遭遇する。洗剤メーカーの箱を抱えて街をうろついていた男だ。バンから男を監視するポール。
夜になり、ターバンを巻いた男は伝道所のすぐ近くの路上に段ボールを組み立て、数人の男達とドラム缶で火を焚きながら暖をとっていた。
すると、ポールのバンの反対側から一台の黒い大きな車がやって来て、ホームレスの段ボールに火を放ち、ポールが監視していたアラブ人に弾丸を打ち込んだ。あっという間の出来事だった。
ラナやヘンリー達が伝道所から出て来てアラブ人を介抱しようとしたが、男はポールの腕の中で死に絶えた。『トロナ』という言葉を残して。
ここまでで上映時間約45分。
その後、ジミーの調査で「トロナ」とはソルトレイクの近くの町の名前である事が分かり、警察で被害者の名がハッサン・アフメッドである事を聞いたラナがネットで「トロナのアフメッド」で検索して、親族らしき人物がトロナに一人いる事が分かった。
家族に遺体を引き渡したいラナはポールに遺体を運ぶことを頼む。ラナ曰く、「トロナ」に行けばテロリストの様子が知れるかもしれないし、遺体を運ぶのだから怪しまれない。
こうして、二人の短い旅が始まる・・・。
*
 お薦め度は★三つ。
お薦め度は★三つ。まるで“ごっこ”に見えなくもないポールのエピソードだけど、当時のアメリカ人の焦燥というか9.11のトラウマというか、ただ笑って済ますわけにはいかないモノを感じるんだよね。そして、雑に見えながらエピソードが無駄なく繋がっていくのも良い。
音楽の使い方も現代風で、時にミュージックビデオの様に見えるシーンもあり流石“ゆるい系“という感じでした。
後半は二人のロード・ムーヴィーになるって書いたけど、ラナに関していえば最初からずっとそうなんだよね。
 特典映像によると全編デジタルカメラでの撮影で、俳優陣からすると小さなカメラだし、準備の時間も要らないので演技に集中できたらしい。監督においてはフィルム撮影のような物理的な制限を気にしなくてよく、NGにも誰もイラつかなかったとの事。ヴェンダース曰く、小さいので殆ど手持ちでの撮影だったがドキュメンタリー風にはならずに映画らしく仕上がった。
特典映像によると全編デジタルカメラでの撮影で、俳優陣からすると小さなカメラだし、準備の時間も要らないので演技に集中できたらしい。監督においてはフィルム撮影のような物理的な制限を気にしなくてよく、NGにも誰もイラつかなかったとの事。ヴェンダース曰く、小さいので殆ど手持ちでの撮影だったがドキュメンタリー風にはならずに映画らしく仕上がった。撮影監督はフランツ・ルスティヒ。
 ジョン・ディールは「ジュラシック・パークⅢ」に出てたとの事。多分捜索隊の護衛の役だったと思うが覚えてない。
ジョン・ディールは「ジュラシック・パークⅢ」に出てたとの事。多分捜索隊の護衛の役だったと思うが覚えてない。ミシェル・ウィリアムズは「ブロークバック・マウンテン」でお逢いしましたな。
「ロッキー」シリーズのエイドリアンの兄貴でお馴染みのバート・ヤングは伝道所の管理人の役でした。
▼(ネタバレ注意)
トロナの調査の結果はポールの完全なる見当違い。己の勘の鈍ったことにショックを受けたポールはトロナのモーテルで酔いつぶれ、ラナに介抱される。
ハッサンの葬儀の間、ポールはラナの母親、つまり妹からの手紙を読む。
かつて考え方の違いで仲違いした兄妹だったが、余命幾ばくも無くなった妹は兄に自分が幼く間違っていた事を誤り、残していく娘の事を託す。ラナには宣教師の父親がいるが、その妻からすると娘の将来を託すには頼りなかったらしい。
ラナは9.11の時に中東にいて、周りのアラブの人々が歓声をあげていた事にショックを受けたと話す。アメリカやアメリカ人を嫌う人々が世界にはいるのだ。
9.11でツインタワーで亡くなった一般市民は3000人以上。彼らはテロリスト達への報復を望んでいるだろうか?
ラストシーンは、バンでニューヨークに向かうポールとラナの姿。そしてグランドゼロを見下ろす彼らの姿でした。
余談ですがポールの携帯の受信音はアメリカ国歌でした(笑)
▲(解除)
[05.14 追記]
昨日監督の解説付きバージョンを観たらジミーもベトナム帰還兵という事でした。そしてポールとジミーの家は隣同士だけど、ポールはバンに寝泊まりしてるとの事。
また、携帯のアメリカ国歌は標準で付いていたそう。なるほど。
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 

(2009/ジョン・リー・ハンコック監督・脚本/サンドラ・ブロック、クィントン・アーロン、ティム・マッグロウ、リリー・コリンズ、ジェイ・ヘッド、レイ・マッキノン、キャシー・ベイツ/128分)
ジョン・リー・ハンコックの名前に見覚えがあったのでMYブログを確認したら、「オールド・ルーキー」の監督だった。「オールド・ルーキー」は高校教師が一度はあきらめたメジャーリーガーに再挑戦するという実話が元になった作品だったが、この「しあわせの隠れ場所」も一人のアメリカン・フットボール選手の実話が背景にある。
ハンコックさん、スポーツ系の感動的実話が好きなのかな。
 「しあわせの隠れ場所」を観る。1回目はプロローグのくだりをストーリーの一部と誤解したまま観てしまって、2回目でそれが分かった。冒頭の聞き取り調査のシーンも要るかなぁ?って感じ。ハートフルなお話なので何回かウルウルしたけれど。
「しあわせの隠れ場所」を観る。1回目はプロローグのくだりをストーリーの一部と誤解したまま観てしまって、2回目でそれが分かった。冒頭の聞き取り調査のシーンも要るかなぁ?って感じ。ハートフルなお話なので何回かウルウルしたけれど。
([4月24日] Twitter on 十瑠より)
 アメリカ南部の都市メンフィス。
アメリカ南部の都市メンフィス。
キリスト教系の私立学校を一組の黒人の親子が訪ねてくる。スポーツが得意な息子を転校させたいとやって来たのだが、アメフト部のコーチにはもう一人息子の友だちも連れてきたのでその子も見てくれという。ビッグマイクと呼ばれるその少年は大きな体にも関わらず俊敏な動きをしていてコーチは一瞬で彼に興味を持った。是非とも彼をチームに入れたいと。
ビッグマイク。本名はマイケル・オアー。父親は行方不明、母親も薬物中毒で生活は貧困を極める。そんな彼を案じて友達の父親は時々寝る所を提供してあげていたのだ。
元々成績が思わしくなく転校してきても授業に付いてこれないだろうと見られていたが、建学の精神に則りマイケルは学校に入ることになった。食事も十分ではなく、学校の体育館で開かれる競技会の観戦者が残していったポテトチップスを拾い集めて空腹を紛らわし、着替えのTシャツをコインランドリーで洗っては着替える。
ある寒い夜。マイケルは寒さをしのごうと体育館に向かっていた。格好はいつものよれよれのポロシャツにハーフパンツ。
そこに通りかかったのがテューイ家の車だった。運転していたのはショーン・テューイ、そして同乗者は妻のリー・アンと息子のショーンJr。小ショーンは自称SJ(エスジェイ)。SJもマイケルと同じ学校に通っていて当然彼の事も知っていた。
あまりに寒そうなのでショーンが『どこに行くんだ?』と聞くとマイケルは短く『体育館』と答えた。
一度は行き過ぎたが気になったリー・アンは車を降りてマイケルを呼び止め話しかけた。
『こんな夜に体育館に行って何をするつもり?』
『あそこは暖かいから』
『だからってもう閉まってるわよ。あなた今夜寝る所はあるの?』
『はい』
『嘘は言わないでよ』
マイケルはかぶりを振った。
しばし考えたリー・アンはマイケルを車の後部座席に乗せた。初対面と言っていい体の大きな黒人の少年を家に泊める事にしたのだ。
こうしてマイケルとテューイ家との物語が始まっていく。
「オールド・ルーキー」はアスリートの野球選手が主人公の物語でしたが、これはマイケルよりはリー・アンが主人公ですね。
彼女自身が途中で友人に語るように、彼女がマイケルの人生を変えたのではなく、マイケルが彼女の人生を変えた物語でした。
ということでテューイ家の家族についてもう少し書いておきましょう。
父親のショーンはミシシッピ大出身で大学時代はバスケットボールの花形選手、今は85店のレストランを経営している実業家。
同じ大学でチアリーダーをしていたリー・アンは売れっ子のインテリア・デザイナー。
SJにはお姉ちゃんがいて名前はコリンズ。彼女も同じ学校に通ってて、バレーボールやチアリーディングをしている。
SJは小さいがスポーツが大好きで、後にマイケルのトレーニングをリードしてくれる頼もしい奴であります。
口の重たいマイケルから徐々に彼の人生を聞き出し、今まで知らなかった世界を知っていくリー・アン。
口先だけではない実践的なクリスチャンとしての生き方に目覚めていく感じがして、ジワっとくるシーンが何か所もありましたね。あっ、僕はクリスチャンでもなんでもないですが。
お薦め度は★二つ半。
「オールド・ルーキー」もそうだったけど尺が長いのが欠点かな。エピソードの流れはオカシクないんだけど、例えば有名になったマイケルを色々な大学が勧誘にくるシーン等ありふれてる分余計に長く感じたなぁ。
ただ、若い人達にはユーモアもあるし、★三つ【一見の価値あり】くらいの良いお話だと思います。
他の部分に挿入しても良かったのではないかと思ったプロローグについて。
アメフトは良く知らないので間違っているかもしれませんが、過去のある試合でアメフトの中枢ポジションであるクォーターバックの選手が敵のディフェンスに潰されて大怪我をするシーンで、この衝撃的なプレイによってクォーターバックを守るミッションを持った選手が必要になったという解説なのでした。
この重要なポジションの選手は身体が大きくて俊敏な動きが求められる。マイケルにはその素質と能力があったから求められらたし才能も開花していったわけです。
原題は【THE BLIND SIDE】
<原題の「ブラインドサイド」とは、クォーターバックの利き手逆側の、死角になり易いサイドの事で、右利きクォーターバックの場合は左側である。パスプレイの際、クォーターバックの体は利き手側に向くため(右利きの場合右方向)、逆側は死角になりやすい。よってブラインドサイドのオフェンスタックルは、オフェンスライン内でも特に重要とされ、高い能力が求められる。映画の冒頭ではワシントン・レッドスキンズのジョー・サイズマンがローレンス・テイラーにサックされ再起不能となったプレーが映し出される>とウィキペディアには書かれていました。
映画のテーマを思えば、リッチな白人社会には見えない貧困にあえぐ黒人社会をさしているのではないでしょうかね。
2009年のアカデミー賞では作品賞にノミネート、見事サンドラ・ブロックが主演女優賞に輝きました。
サンドラはゴールデン・グローブ賞、放送映画批評家協会賞でも女優賞を獲得したそうです。
尚、テューイ家の長女コリンズを演じていたリリー・コリンズは、あのフィル・コリンズのお嬢さんらしいです。可愛かったなぁ。
ジョン・リー・ハンコックの名前に見覚えがあったのでMYブログを確認したら、「オールド・ルーキー」の監督だった。「オールド・ルーキー」は高校教師が一度はあきらめたメジャーリーガーに再挑戦するという実話が元になった作品だったが、この「しあわせの隠れ場所」も一人のアメリカン・フットボール選手の実話が背景にある。
ハンコックさん、スポーツ系の感動的実話が好きなのかな。
 「しあわせの隠れ場所」を観る。1回目はプロローグのくだりをストーリーの一部と誤解したまま観てしまって、2回目でそれが分かった。冒頭の聞き取り調査のシーンも要るかなぁ?って感じ。ハートフルなお話なので何回かウルウルしたけれど。
「しあわせの隠れ場所」を観る。1回目はプロローグのくだりをストーリーの一部と誤解したまま観てしまって、2回目でそれが分かった。冒頭の聞き取り調査のシーンも要るかなぁ?って感じ。ハートフルなお話なので何回かウルウルしたけれど。([4月24日] Twitter on 十瑠より)
*
 アメリカ南部の都市メンフィス。
アメリカ南部の都市メンフィス。キリスト教系の私立学校を一組の黒人の親子が訪ねてくる。スポーツが得意な息子を転校させたいとやって来たのだが、アメフト部のコーチにはもう一人息子の友だちも連れてきたのでその子も見てくれという。ビッグマイクと呼ばれるその少年は大きな体にも関わらず俊敏な動きをしていてコーチは一瞬で彼に興味を持った。是非とも彼をチームに入れたいと。
ビッグマイク。本名はマイケル・オアー。父親は行方不明、母親も薬物中毒で生活は貧困を極める。そんな彼を案じて友達の父親は時々寝る所を提供してあげていたのだ。
元々成績が思わしくなく転校してきても授業に付いてこれないだろうと見られていたが、建学の精神に則りマイケルは学校に入ることになった。食事も十分ではなく、学校の体育館で開かれる競技会の観戦者が残していったポテトチップスを拾い集めて空腹を紛らわし、着替えのTシャツをコインランドリーで洗っては着替える。
ある寒い夜。マイケルは寒さをしのごうと体育館に向かっていた。格好はいつものよれよれのポロシャツにハーフパンツ。
そこに通りかかったのがテューイ家の車だった。運転していたのはショーン・テューイ、そして同乗者は妻のリー・アンと息子のショーンJr。小ショーンは自称SJ(エスジェイ)。SJもマイケルと同じ学校に通っていて当然彼の事も知っていた。
あまりに寒そうなのでショーンが『どこに行くんだ?』と聞くとマイケルは短く『体育館』と答えた。
一度は行き過ぎたが気になったリー・アンは車を降りてマイケルを呼び止め話しかけた。
『こんな夜に体育館に行って何をするつもり?』
『あそこは暖かいから』
『だからってもう閉まってるわよ。あなた今夜寝る所はあるの?』
『はい』
『嘘は言わないでよ』
マイケルはかぶりを振った。
しばし考えたリー・アンはマイケルを車の後部座席に乗せた。初対面と言っていい体の大きな黒人の少年を家に泊める事にしたのだ。
こうしてマイケルとテューイ家との物語が始まっていく。
*
「オールド・ルーキー」はアスリートの野球選手が主人公の物語でしたが、これはマイケルよりはリー・アンが主人公ですね。
彼女自身が途中で友人に語るように、彼女がマイケルの人生を変えたのではなく、マイケルが彼女の人生を変えた物語でした。
ということでテューイ家の家族についてもう少し書いておきましょう。
父親のショーンはミシシッピ大出身で大学時代はバスケットボールの花形選手、今は85店のレストランを経営している実業家。
同じ大学でチアリーダーをしていたリー・アンは売れっ子のインテリア・デザイナー。
SJにはお姉ちゃんがいて名前はコリンズ。彼女も同じ学校に通ってて、バレーボールやチアリーディングをしている。
SJは小さいがスポーツが大好きで、後にマイケルのトレーニングをリードしてくれる頼もしい奴であります。
口の重たいマイケルから徐々に彼の人生を聞き出し、今まで知らなかった世界を知っていくリー・アン。
口先だけではない実践的なクリスチャンとしての生き方に目覚めていく感じがして、ジワっとくるシーンが何か所もありましたね。あっ、僕はクリスチャンでもなんでもないですが。
お薦め度は★二つ半。
「オールド・ルーキー」もそうだったけど尺が長いのが欠点かな。エピソードの流れはオカシクないんだけど、例えば有名になったマイケルを色々な大学が勧誘にくるシーン等ありふれてる分余計に長く感じたなぁ。
ただ、若い人達にはユーモアもあるし、★三つ【一見の価値あり】くらいの良いお話だと思います。
他の部分に挿入しても良かったのではないかと思ったプロローグについて。
アメフトは良く知らないので間違っているかもしれませんが、過去のある試合でアメフトの中枢ポジションであるクォーターバックの選手が敵のディフェンスに潰されて大怪我をするシーンで、この衝撃的なプレイによってクォーターバックを守るミッションを持った選手が必要になったという解説なのでした。
この重要なポジションの選手は身体が大きくて俊敏な動きが求められる。マイケルにはその素質と能力があったから求められらたし才能も開花していったわけです。
原題は【THE BLIND SIDE】
<原題の「ブラインドサイド」とは、クォーターバックの利き手逆側の、死角になり易いサイドの事で、右利きクォーターバックの場合は左側である。パスプレイの際、クォーターバックの体は利き手側に向くため(右利きの場合右方向)、逆側は死角になりやすい。よってブラインドサイドのオフェンスタックルは、オフェンスライン内でも特に重要とされ、高い能力が求められる。映画の冒頭ではワシントン・レッドスキンズのジョー・サイズマンがローレンス・テイラーにサックされ再起不能となったプレーが映し出される>とウィキペディアには書かれていました。
映画のテーマを思えば、リッチな白人社会には見えない貧困にあえぐ黒人社会をさしているのではないでしょうかね。
2009年のアカデミー賞では作品賞にノミネート、見事サンドラ・ブロックが主演女優賞に輝きました。
サンドラはゴールデン・グローブ賞、放送映画批評家協会賞でも女優賞を獲得したそうです。
尚、テューイ家の長女コリンズを演じていたリリー・コリンズは、あのフィル・コリンズのお嬢さんらしいです。可愛かったなぁ。
・お薦め度【★★=悪くはないけどネ】 

(1949/ロバート・ロッセン監督・製作・脚本/ブロデリック・クロフォード(=ウィリー・スターク)、ジョン・アイアランド(=ジャック・バーデン)、マーセデス・マッケンブリッジ、ジョーン・ドルー、ジョン・デレク、ポール・フォード、アン・セイモア/109分)

 「オール・ザ・キングスメン (1949)」の2回目を観る。大分前に買っていた中古DVDだ。1回目は超特急で語られるお話に何の感慨も無かったが、今回で流れが感じられた。いつもの事だが、昔の作品は話のスピードが速い。トランプ政権を支えた民衆もあんなもんだったんだろう。変わらねぇな、人の世は。[11月19日]
「オール・ザ・キングスメン (1949)」の2回目を観る。大分前に買っていた中古DVDだ。1回目は超特急で語られるお話に何の感慨も無かったが、今回で流れが感じられた。いつもの事だが、昔の作品は話のスピードが速い。トランプ政権を支えた民衆もあんなもんだったんだろう。変わらねぇな、人の世は。[11月19日]
(↑Twitter on 十瑠 から)
 歳と共にすっかり文章を考えるのが億劫になってきてしまって、2回目の鑑賞からもう1週間以上経っているのにまだ一行も書けてない。このままだと、又ポートレイト問題の連続になってしまうので、気合を入れ直してさっさと書くことにする。今回もツイッター風になるでしょう。
歳と共にすっかり文章を考えるのが億劫になってきてしまって、2回目の鑑賞からもう1週間以上経っているのにまだ一行も書けてない。このままだと、又ポートレイト問題の連続になってしまうので、気合を入れ直してさっさと書くことにする。今回もツイッター風になるでしょう。
 かなり昔から知っていた作品だが、いつからだろう? TVで「ハスラー (1961)」を観た時に淀川さんがロバート・ロッセンの名作として紹介でもしたかな? 少なくとも高校生の頃には知っていたはずだ。「SCREEN」を読んでいたからね。
かなり昔から知っていた作品だが、いつからだろう? TVで「ハスラー (1961)」を観た時に淀川さんがロバート・ロッセンの名作として紹介でもしたかな? 少なくとも高校生の頃には知っていたはずだ。「SCREEN」を読んでいたからね。
だけど今まで未見だった。なにせこの映画、日本初公開は1976年なんだ。76年の9月。多分公開されたのも知らなかったかも。
で、実は76年というのはアラン・J・パクラの名作「大統領の陰謀」の公開と同じ年なんだね。こちらは76年の8月。
思うに、政治物は当たらないはずなのに「大統領の陰謀」がヒットしたんで併せて公開になったんじゃないかな。何しろ「大統領の陰謀」の原題【ALL THE PRESIDENT'S MEN】はこの映画のタイトルを捩ったものだからね。
 「大統領の陰謀」のせいで、今までこの映画も大統領になる男が主人公だと思い込んでいたけれど、実は州知事に当選する男の話だった。但し、お話の主人公はその男を取材する新聞記者ジャック・バーデンだった。狂言回しだな。
「大統領の陰謀」のせいで、今までこの映画も大統領になる男が主人公だと思い込んでいたけれど、実は州知事に当選する男の話だった。但し、お話の主人公はその男を取材する新聞記者ジャック・バーデンだった。狂言回しだな。
架空の地方の田舎町で一人の男が街角で演説をぶっている。郡の予算執行に不正の匂いがすると言うんだが、その演説が町民に人気があると言うのでジャックは上司に命令されて取材に訪れる。案の定、既得権益を守りたい連中が嫌がらせをする場面に遭遇し、ジャックはそれでもへこたれない男に惹かれる。男の名前はウィリー・スターク。
ウィリーには学校の先生をしていた妻のルーシーと養子のトムがいた。
ウィリーは郡の出納官の選挙に立候補するも破れる。それでも彼は妻に助けられながら法律の勉強をし、法学士の資格を得、事務所を開いて住民の為に働くようになる。
新しい州知事の選挙が始まった時、優勢を確かなものにしたい第一候補者の裏ブレーンが、第二候補者の票を分散させようとウィリーを第三の候補者に祭り上げる。選挙中盤でその事を知ったウィリーは怒り、やがて選挙のやり方に目覚めていき、その次の選挙で州知事に立候補、見事当選する。
 さて、ジャックは当初ウィリーの記事を書いていたが新聞社にも既得権益団体の圧力がかかり、やがて上司からもウィリーの記事を止められ、それならばと新聞社を辞める事になる。そして知事候補になった頃にはウィリーの参謀となっていた。
さて、ジャックは当初ウィリーの記事を書いていたが新聞社にも既得権益団体の圧力がかかり、やがて上司からもウィリーの記事を止められ、それならばと新聞社を辞める事になる。そして知事候補になった頃にはウィリーの参謀となっていた。
その頃はジャックはただの狂言回しではなくなる。ジャックの故郷の親類縁者には地元の有力者が居たからだ。恋人の亡父は前知事であり、その兄は優秀な医師、兄妹の叔父は州の裁判所の判事だった。
正義感に燃える政治家としてウィリーを彼らに紹介するジャック。やがて彼らがウィリーの手綱に捕らわれていくとも知らずに。
 1回目の鑑賞では、ありがちなエピソードを並べた薄っぺらい映画だと感じたけど、2回目できちんと流れが出来ていることが分かった。ただ、ウィリーの心変わりというか心境の変化みたいなものが描かれているとはいえず物足りなかった。
1回目の鑑賞では、ありがちなエピソードを並べた薄っぺらい映画だと感じたけど、2回目できちんと流れが出来ていることが分かった。ただ、ウィリーの心変わりというか心境の変化みたいなものが描かれているとはいえず物足りなかった。
結局、彼は最初から地位と権力が狙いの男だったんだと考えるしかないかな。それでもそういう男だったと印象付けるエピソードもショットも乏しかった感がある。
それにしても、この独裁的な権力者は次々と周りの全ての人々を不幸にしていったな。
今ならもっと繊細に描くことも出来るだろうけど、2006年のショーン・ペン主演のリメイク版はどうなんだろう?。
 ロッセンはこの映画で赤狩りの標的にされたみたいだが、映画自体には共産主義を礼賛するようなシーンは無かったと思うけど。
ロッセンはこの映画で赤狩りの標的にされたみたいだが、映画自体には共産主義を礼賛するようなシーンは無かったと思うけど。
 選挙参謀となったジャックがウィリーにこう言ったのが印象的。
選挙参謀となったジャックがウィリーにこう言ったのが印象的。
『大衆を教育しようとするな。泣かせろ、笑わせろ、怒らせろ。彼らの感情を揺すぶるんだ』
 第22回アカデミー賞で、作品賞、主演男優賞(クロフォード)、助演女優賞(マッケンブリッジ)の3部門を獲得したらしい。マッケンブリッジはウィリーの選挙参謀から秘書になる役。
第22回アカデミー賞で、作品賞、主演男優賞(クロフォード)、助演女優賞(マッケンブリッジ)の3部門を獲得したらしい。マッケンブリッジはウィリーの選挙参謀から秘書になる役。
カメラは「俺たちに明日はない」のバーネット・ガフィだった。

 「オール・ザ・キングスメン (1949)」の2回目を観る。大分前に買っていた中古DVDだ。1回目は超特急で語られるお話に何の感慨も無かったが、今回で流れが感じられた。いつもの事だが、昔の作品は話のスピードが速い。トランプ政権を支えた民衆もあんなもんだったんだろう。変わらねぇな、人の世は。[11月19日]
「オール・ザ・キングスメン (1949)」の2回目を観る。大分前に買っていた中古DVDだ。1回目は超特急で語られるお話に何の感慨も無かったが、今回で流れが感じられた。いつもの事だが、昔の作品は話のスピードが速い。トランプ政権を支えた民衆もあんなもんだったんだろう。変わらねぇな、人の世は。[11月19日](↑Twitter on 十瑠 から)
*
 歳と共にすっかり文章を考えるのが億劫になってきてしまって、2回目の鑑賞からもう1週間以上経っているのにまだ一行も書けてない。このままだと、又ポートレイト問題の連続になってしまうので、気合を入れ直してさっさと書くことにする。今回もツイッター風になるでしょう。
歳と共にすっかり文章を考えるのが億劫になってきてしまって、2回目の鑑賞からもう1週間以上経っているのにまだ一行も書けてない。このままだと、又ポートレイト問題の連続になってしまうので、気合を入れ直してさっさと書くことにする。今回もツイッター風になるでしょう。 かなり昔から知っていた作品だが、いつからだろう? TVで「ハスラー (1961)」を観た時に淀川さんがロバート・ロッセンの名作として紹介でもしたかな? 少なくとも高校生の頃には知っていたはずだ。「SCREEN」を読んでいたからね。
かなり昔から知っていた作品だが、いつからだろう? TVで「ハスラー (1961)」を観た時に淀川さんがロバート・ロッセンの名作として紹介でもしたかな? 少なくとも高校生の頃には知っていたはずだ。「SCREEN」を読んでいたからね。だけど今まで未見だった。なにせこの映画、日本初公開は1976年なんだ。76年の9月。多分公開されたのも知らなかったかも。
で、実は76年というのはアラン・J・パクラの名作「大統領の陰謀」の公開と同じ年なんだね。こちらは76年の8月。
思うに、政治物は当たらないはずなのに「大統領の陰謀」がヒットしたんで併せて公開になったんじゃないかな。何しろ「大統領の陰謀」の原題【ALL THE PRESIDENT'S MEN】はこの映画のタイトルを捩ったものだからね。
 「大統領の陰謀」のせいで、今までこの映画も大統領になる男が主人公だと思い込んでいたけれど、実は州知事に当選する男の話だった。但し、お話の主人公はその男を取材する新聞記者ジャック・バーデンだった。狂言回しだな。
「大統領の陰謀」のせいで、今までこの映画も大統領になる男が主人公だと思い込んでいたけれど、実は州知事に当選する男の話だった。但し、お話の主人公はその男を取材する新聞記者ジャック・バーデンだった。狂言回しだな。架空の地方の田舎町で一人の男が街角で演説をぶっている。郡の予算執行に不正の匂いがすると言うんだが、その演説が町民に人気があると言うのでジャックは上司に命令されて取材に訪れる。案の定、既得権益を守りたい連中が嫌がらせをする場面に遭遇し、ジャックはそれでもへこたれない男に惹かれる。男の名前はウィリー・スターク。
ウィリーには学校の先生をしていた妻のルーシーと養子のトムがいた。
ウィリーは郡の出納官の選挙に立候補するも破れる。それでも彼は妻に助けられながら法律の勉強をし、法学士の資格を得、事務所を開いて住民の為に働くようになる。
新しい州知事の選挙が始まった時、優勢を確かなものにしたい第一候補者の裏ブレーンが、第二候補者の票を分散させようとウィリーを第三の候補者に祭り上げる。選挙中盤でその事を知ったウィリーは怒り、やがて選挙のやり方に目覚めていき、その次の選挙で州知事に立候補、見事当選する。
 さて、ジャックは当初ウィリーの記事を書いていたが新聞社にも既得権益団体の圧力がかかり、やがて上司からもウィリーの記事を止められ、それならばと新聞社を辞める事になる。そして知事候補になった頃にはウィリーの参謀となっていた。
さて、ジャックは当初ウィリーの記事を書いていたが新聞社にも既得権益団体の圧力がかかり、やがて上司からもウィリーの記事を止められ、それならばと新聞社を辞める事になる。そして知事候補になった頃にはウィリーの参謀となっていた。その頃はジャックはただの狂言回しではなくなる。ジャックの故郷の親類縁者には地元の有力者が居たからだ。恋人の亡父は前知事であり、その兄は優秀な医師、兄妹の叔父は州の裁判所の判事だった。
正義感に燃える政治家としてウィリーを彼らに紹介するジャック。やがて彼らがウィリーの手綱に捕らわれていくとも知らずに。
 1回目の鑑賞では、ありがちなエピソードを並べた薄っぺらい映画だと感じたけど、2回目できちんと流れが出来ていることが分かった。ただ、ウィリーの心変わりというか心境の変化みたいなものが描かれているとはいえず物足りなかった。
1回目の鑑賞では、ありがちなエピソードを並べた薄っぺらい映画だと感じたけど、2回目できちんと流れが出来ていることが分かった。ただ、ウィリーの心変わりというか心境の変化みたいなものが描かれているとはいえず物足りなかった。結局、彼は最初から地位と権力が狙いの男だったんだと考えるしかないかな。それでもそういう男だったと印象付けるエピソードもショットも乏しかった感がある。
それにしても、この独裁的な権力者は次々と周りの全ての人々を不幸にしていったな。
今ならもっと繊細に描くことも出来るだろうけど、2006年のショーン・ペン主演のリメイク版はどうなんだろう?。
 ロッセンはこの映画で赤狩りの標的にされたみたいだが、映画自体には共産主義を礼賛するようなシーンは無かったと思うけど。
ロッセンはこの映画で赤狩りの標的にされたみたいだが、映画自体には共産主義を礼賛するようなシーンは無かったと思うけど。 選挙参謀となったジャックがウィリーにこう言ったのが印象的。
選挙参謀となったジャックがウィリーにこう言ったのが印象的。『大衆を教育しようとするな。泣かせろ、笑わせろ、怒らせろ。彼らの感情を揺すぶるんだ』
 第22回アカデミー賞で、作品賞、主演男優賞(クロフォード)、助演女優賞(マッケンブリッジ)の3部門を獲得したらしい。マッケンブリッジはウィリーの選挙参謀から秘書になる役。
第22回アカデミー賞で、作品賞、主演男優賞(クロフォード)、助演女優賞(マッケンブリッジ)の3部門を獲得したらしい。マッケンブリッジはウィリーの選挙参謀から秘書になる役。カメラは「俺たちに明日はない」のバーネット・ガフィだった。
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 

(1954/ルネ・クレマン監督・共同脚本/ジェラール・フィリップ、ナターシャ・パリー(=パトリシア)、ヴァレリー・ホブソン(=キャサリン)、マーガレット・ジョンストン(=アン)、ジョーン・グリーンウッド(=ノラ)、ジェルメーヌ・モンテロ(=マルセル)/99分)
ルネ・クレマンと言えば「太陽がいっぱい (1959)」であり「禁じられた遊び (1952)」であり「居酒屋 (1956)」なんですけどね、僕にとっては。
それ以前の、カンヌ国際映画祭で評価された「鉄路の闘い (1946)」、「海の牙 (1947)」、「鉄格子の彼方 (1949)」なんちゅうのもとっても観たいんだけど、未だに逢うことが出来ないのであります。
さて1954年の「しのび逢い」は「禁じられた遊び」と「居酒屋」の間に作られた映画で、タイトルからロマンチックな恋愛モノを想像させますが、実は女たらしのチャラ男が主人公の半コメディっぽいところもある作品なのであります。ま、その事は双葉さんの解説で知ってはいたんですけど、双葉さんの評価が☆四つの傑作だったので随分前に録画していたんです。今回お初にお目にかかりました。
 フランス人青年アンドレ・リポアは母国を嫌い外国で暮らすことを望んでいたけれど、先の大戦が終わった時にイギリスにいた為にそのまま帰国せずロンドンで仕事と住まいを探した。やりたい仕事というものもなく求人のあった商社に勤めたが地道な事をコツコツやるタイプでもなく、給料も前借が常習だったので給料袋には毎度小銭が少し入っているだけだった。そんなアンドレの日々の楽しみは退社後のガールハント。街に出た後には公衆電話ボックスでネクタイを替えて気分を上げるのだった。
フランス人青年アンドレ・リポアは母国を嫌い外国で暮らすことを望んでいたけれど、先の大戦が終わった時にイギリスにいた為にそのまま帰国せずロンドンで仕事と住まいを探した。やりたい仕事というものもなく求人のあった商社に勤めたが地道な事をコツコツやるタイプでもなく、給料も前借が常習だったので給料袋には毎度小銭が少し入っているだけだった。そんなアンドレの日々の楽しみは退社後のガールハント。街に出た後には公衆電話ボックスでネクタイを替えて気分を上げるのだった。
そんな綱渡りのような生活が数年続いた後、アンドレは一人の資産家の娘キャサリンと結婚した。逆玉と言うべきだが、彼の女遊びはやむことはなく、結婚式から数か月後キャサリンはアンドレとの離婚を決心していた。
と、上記したドラマの設定は後々分かることで、映画のオープニングはアンドレが一人の女性と舟で川遊びをしていて、遠くの岸辺ではキャサリンがお茶をしながら相席している知人の男性にアンドレとの離婚をほのめかしているというシーン。アンドレが口説いている女性パトリシアはキャサリンの親友だという事もこの後分かる。
帰って来たパトリシアにキャサリンが忠告として言う。アンドレが彼女を口説いていただろう事は百も承知だ。
『彼は世界中の女を振り向かせたいの。陥落しないとすぐに飽きるし、陥落してもまた飽きてしまう。これからもずっとそうだわ。そういう人よ』
数日後、実家のあるエディンバラに帰っていたキャサリンがロンドンに戻って来るのでアンドレは車で迎えに行こうとするが、そこにパトリシアから電話がかかってくる。ロンドンに来たのでキャサリンに逢いたいらしいんだが、今から空港に迎えに行く所だと答えると、『ではまた電話するわ』と切り上げる。再び出かけようとすると今度はキャサリンからの電話。まだエディンバラに居て、弁護士と打ち合わせをしているらしい。
『忙しくなるわよ。こんどこそ離婚だから。決心は固いから覚悟していて』
どうやら浮気がバレてアンドレは謝罪の手紙を書いたらしいが、それが雑誌のコピーだった事もバレたらしい。
逆玉離婚でさぞかし意気消沈するかと思ったらアンドレにはさして影響はないみたい。
さっそく今度は近くのホテルにいるパトリシアに電話して、こう言うのだ。『キャサリンと三人で食事をしよう。1時間後に来て』
まったく。懲りない男、アンドレ・リポア。
キャサリンが帰ってくるのは明日。なので三人で食事をと言いながら、実は二人っきりになろうとしているわけだ。
1時間後にやって来たパトリシアにキャサリンは予定の飛行機に乗ってなかったと言い、後の便かもしれないから先に食べていようと食事を始める。少し前に頼んでいた電話サービスからかかってきた電話をキャサリンからと騙しながら、霧で飛行機が飛ばなくなったらしいと嘘をつく。女たらしの面目躍如の計略でありますな。
こうして二人っきりの夜を過ごしながら成り行きでアンドレは過去の女性遍歴を語りだすのだ。
惚れた女に女たらしの手練手管を事細かに話して彼に何のメリットがあるんだろうと思うんですが、映画としてはそれぞれのストーリーも面白いし、男と女の色模様の違いも面白い。
カンヌで評価された三作はドキュメンタリータッチらしいですが、この映画にもそういう雰囲気がありますね。特に街中でのシーンは(誰もジェラール・フィリップに気が付いていないから)どれだけのエキストラを使ったんだろうと思わせるモノでした。
ネタバレになりますがアンドレの過去の女たちも少し紹介しておきましょうか。未見の方は当然スルーして下さい。
▼(ネタバレ注意)
アンはアンドレが勤めていた会社の上司。チャラ男の仕事ぶりには厳しい態度で接していたが、ある日彼女の美しい脚を見たアンドレがプレゼント攻撃をかますと簡単に陥落してしまう。アンドレが彼女のアパートにもぐり込んでくるが、些細な事で険悪なムードになった後アンドレはアパートを出て行き次のターゲットを見つけ出す。
ノラは通勤バスの中でひっかけた女。お堅い家庭で育ったノラはガードも固く結婚話をちらつかせることで心身共に親密になることが出来たが、そこは飽き性のアンドレ、途端にアパートも引き払ってしまう。
アンと別れた後に会社も首になり、次の仕事も見つからずに路頭に迷うアンドレを救ったのがマルセルだった。マルセルはフランス人の街娼。まさにヒモになったわけだが、マルセルに転がり込んだ遺産を融通するから新しい事業を起こせばと言われるとまた黙って去ってしまうアンドレだった。
マルセルの財布から少し頂戴したお金を元にフランス語の個人授業の教室を開き、そこにやって来たのがキャサリンだった。
キャサリンとの馴れ初めはとっかかりだけで結婚に至る重要な場面は割愛されていました。なんか都合よく端折られてる感じでしたね。
ネタバレについでに、このドラマの結末も書いておきましょうか。
アンドレの告白を聞き、再度必死の求愛を受けて心揺れるもパトリシアはホテルに戻ろうとし、最後の手段としてアンドレは三階のベルコニーから飛び降りようとする。勿論絶望を装った狂言だが、うっかり足を滑らせて本当に落ちてしまう。
翌日、入院先にやって来たキャサリンは、離婚に動揺したせいとアンドレを不憫に思い、また勝手に彼の改心を信じるようになる。
ラストシーンは、ゴルフ場でキャサリンとパトリシアが交代でアンドレの車椅子を押している図。
この後夫婦は末永く暮らしましたとナレーションが入るが、アンドレは男の友人に誘われゴルフバッグを抱えて去って行くパトリシアを浮かない顔で見つめている。
やはり彼の下半身はこの後使い物にならなくなったんでしょうなぁ。
▲(解除)
お薦め度は★三つ。
クレマンの語り口が★四つ~五つの秀作クラスであることは充分分かるんですが、主人公たちの心理に良く分からない部分が多く、クレマンが何を描きたかったのも把握出来ていないので★三つです。
撮影は後に英国アカデミー賞を三度(全てモノクロで)受賞するオズワルド・モリス。
屋外シーンには詩情を感じさせるものが多く、僕は夕暮れに街灯に火をつけて廻る父親と幼い娘のシーンが印象に残りました。
1954年のカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を獲ったそうです。
ルネ・クレマンと言えば「太陽がいっぱい (1959)」であり「禁じられた遊び (1952)」であり「居酒屋 (1956)」なんですけどね、僕にとっては。
それ以前の、カンヌ国際映画祭で評価された「鉄路の闘い (1946)」、「海の牙 (1947)」、「鉄格子の彼方 (1949)」なんちゅうのもとっても観たいんだけど、未だに逢うことが出来ないのであります。
さて1954年の「しのび逢い」は「禁じられた遊び」と「居酒屋」の間に作られた映画で、タイトルからロマンチックな恋愛モノを想像させますが、実は女たらしのチャラ男が主人公の半コメディっぽいところもある作品なのであります。ま、その事は双葉さんの解説で知ってはいたんですけど、双葉さんの評価が☆四つの傑作だったので随分前に録画していたんです。今回お初にお目にかかりました。
*
 フランス人青年アンドレ・リポアは母国を嫌い外国で暮らすことを望んでいたけれど、先の大戦が終わった時にイギリスにいた為にそのまま帰国せずロンドンで仕事と住まいを探した。やりたい仕事というものもなく求人のあった商社に勤めたが地道な事をコツコツやるタイプでもなく、給料も前借が常習だったので給料袋には毎度小銭が少し入っているだけだった。そんなアンドレの日々の楽しみは退社後のガールハント。街に出た後には公衆電話ボックスでネクタイを替えて気分を上げるのだった。
フランス人青年アンドレ・リポアは母国を嫌い外国で暮らすことを望んでいたけれど、先の大戦が終わった時にイギリスにいた為にそのまま帰国せずロンドンで仕事と住まいを探した。やりたい仕事というものもなく求人のあった商社に勤めたが地道な事をコツコツやるタイプでもなく、給料も前借が常習だったので給料袋には毎度小銭が少し入っているだけだった。そんなアンドレの日々の楽しみは退社後のガールハント。街に出た後には公衆電話ボックスでネクタイを替えて気分を上げるのだった。そんな綱渡りのような生活が数年続いた後、アンドレは一人の資産家の娘キャサリンと結婚した。逆玉と言うべきだが、彼の女遊びはやむことはなく、結婚式から数か月後キャサリンはアンドレとの離婚を決心していた。
と、上記したドラマの設定は後々分かることで、映画のオープニングはアンドレが一人の女性と舟で川遊びをしていて、遠くの岸辺ではキャサリンがお茶をしながら相席している知人の男性にアンドレとの離婚をほのめかしているというシーン。アンドレが口説いている女性パトリシアはキャサリンの親友だという事もこの後分かる。
帰って来たパトリシアにキャサリンが忠告として言う。アンドレが彼女を口説いていただろう事は百も承知だ。
『彼は世界中の女を振り向かせたいの。陥落しないとすぐに飽きるし、陥落してもまた飽きてしまう。これからもずっとそうだわ。そういう人よ』
数日後、実家のあるエディンバラに帰っていたキャサリンがロンドンに戻って来るのでアンドレは車で迎えに行こうとするが、そこにパトリシアから電話がかかってくる。ロンドンに来たのでキャサリンに逢いたいらしいんだが、今から空港に迎えに行く所だと答えると、『ではまた電話するわ』と切り上げる。再び出かけようとすると今度はキャサリンからの電話。まだエディンバラに居て、弁護士と打ち合わせをしているらしい。
『忙しくなるわよ。こんどこそ離婚だから。決心は固いから覚悟していて』
どうやら浮気がバレてアンドレは謝罪の手紙を書いたらしいが、それが雑誌のコピーだった事もバレたらしい。
逆玉離婚でさぞかし意気消沈するかと思ったらアンドレにはさして影響はないみたい。
さっそく今度は近くのホテルにいるパトリシアに電話して、こう言うのだ。『キャサリンと三人で食事をしよう。1時間後に来て』
まったく。懲りない男、アンドレ・リポア。
キャサリンが帰ってくるのは明日。なので三人で食事をと言いながら、実は二人っきりになろうとしているわけだ。
1時間後にやって来たパトリシアにキャサリンは予定の飛行機に乗ってなかったと言い、後の便かもしれないから先に食べていようと食事を始める。少し前に頼んでいた電話サービスからかかってきた電話をキャサリンからと騙しながら、霧で飛行機が飛ばなくなったらしいと嘘をつく。女たらしの面目躍如の計略でありますな。
こうして二人っきりの夜を過ごしながら成り行きでアンドレは過去の女性遍歴を語りだすのだ。
惚れた女に女たらしの手練手管を事細かに話して彼に何のメリットがあるんだろうと思うんですが、映画としてはそれぞれのストーリーも面白いし、男と女の色模様の違いも面白い。
カンヌで評価された三作はドキュメンタリータッチらしいですが、この映画にもそういう雰囲気がありますね。特に街中でのシーンは(誰もジェラール・フィリップに気が付いていないから)どれだけのエキストラを使ったんだろうと思わせるモノでした。
ネタバレになりますがアンドレの過去の女たちも少し紹介しておきましょうか。未見の方は当然スルーして下さい。
▼(ネタバレ注意)
アンはアンドレが勤めていた会社の上司。チャラ男の仕事ぶりには厳しい態度で接していたが、ある日彼女の美しい脚を見たアンドレがプレゼント攻撃をかますと簡単に陥落してしまう。アンドレが彼女のアパートにもぐり込んでくるが、些細な事で険悪なムードになった後アンドレはアパートを出て行き次のターゲットを見つけ出す。
ノラは通勤バスの中でひっかけた女。お堅い家庭で育ったノラはガードも固く結婚話をちらつかせることで心身共に親密になることが出来たが、そこは飽き性のアンドレ、途端にアパートも引き払ってしまう。
アンと別れた後に会社も首になり、次の仕事も見つからずに路頭に迷うアンドレを救ったのがマルセルだった。マルセルはフランス人の街娼。まさにヒモになったわけだが、マルセルに転がり込んだ遺産を融通するから新しい事業を起こせばと言われるとまた黙って去ってしまうアンドレだった。
マルセルの財布から少し頂戴したお金を元にフランス語の個人授業の教室を開き、そこにやって来たのがキャサリンだった。
キャサリンとの馴れ初めはとっかかりだけで結婚に至る重要な場面は割愛されていました。なんか都合よく端折られてる感じでしたね。
ネタバレについでに、このドラマの結末も書いておきましょうか。
アンドレの告白を聞き、再度必死の求愛を受けて心揺れるもパトリシアはホテルに戻ろうとし、最後の手段としてアンドレは三階のベルコニーから飛び降りようとする。勿論絶望を装った狂言だが、うっかり足を滑らせて本当に落ちてしまう。
翌日、入院先にやって来たキャサリンは、離婚に動揺したせいとアンドレを不憫に思い、また勝手に彼の改心を信じるようになる。
ラストシーンは、ゴルフ場でキャサリンとパトリシアが交代でアンドレの車椅子を押している図。
この後夫婦は末永く暮らしましたとナレーションが入るが、アンドレは男の友人に誘われゴルフバッグを抱えて去って行くパトリシアを浮かない顔で見つめている。
やはり彼の下半身はこの後使い物にならなくなったんでしょうなぁ。
▲(解除)
お薦め度は★三つ。
クレマンの語り口が★四つ~五つの秀作クラスであることは充分分かるんですが、主人公たちの心理に良く分からない部分が多く、クレマンが何を描きたかったのも把握出来ていないので★三つです。
撮影は後に英国アカデミー賞を三度(全てモノクロで)受賞するオズワルド・モリス。
屋外シーンには詩情を感じさせるものが多く、僕は夕暮れに街灯に火をつけて廻る父親と幼い娘のシーンが印象に残りました。
1954年のカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を獲ったそうです。
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 

(1955/オットー・プレミンジャー監督・製作/フランク・シナトラ、エリノア・パーカー、キム・ノヴァク、ダーレン・マクギャヴィン、ロバート・ストラウス/115分)
前回記事「第十七捕虜収容所」のオットー・プレミンジャー繋がりで今回は彼の監督作品として名高い「黄金の腕」を観た。大分前に買った1コインDVDだ。
1945年にビリー・ワイルダーが作った「失われた週末」はアルコール中毒の怖さを描いたが、10年後のこの作品では薬物中毒の恐怖が描かれる。主演はフランク・シナトラ。ジャズシンガーの大御所というイメージが強いんだが、改めてフィルモグラフィーを見ると結構な出演映画があるんですなぁ。
<1950年に第1回全米図書賞を受賞したネルソン・オルグレンの小説『黄金の腕』>が原作だそうです。【原題:The Man with the Golden Arm】
 カード賭博の罪で半年間刑務所暮らしをしていたフランキーが地元に帰って来た。
カード賭博の罪で半年間刑務所暮らしをしていたフランキーが地元に帰って来た。
賭博場を開いていたのはシュワイフカという男だがフランキーは彼の身代わりになったのだ。その世界では“黄金の腕”を持つと言われるカード捌きの名人フランキーは、その界隈では単に『ディーラー』と呼ばれることが多かった。刑務所暮らしと書いたが殆どは薬物中毒の治療の為の病院暮し。半年かかったがなんとか中毒から抜け出してきたのだ。
“ヤク”が切れた今、二度と薬に手を出さない為に『ディーラー』は止める決心をし、裏街道にも足を踏み入れないと覚悟していた。病院の先生の勧めで覚えたドラムで次の人生を歩もうと思っていたのだ。ビッグバンドでドラマーとしてやっていくのが今の夢。既に芸名迄考えているくらい本気だった。
半年ぶりにアパートに帰ると妻のザシュが車椅子で待っていた。3年前、飲酒運転で事故を起こしたフランキーの車にザシュも乗っていて彼女は大怪我をしたのだ。以来車椅子が手放せない生活となった。お金はシュワイフカ経由で送金してきたし、近所には親切にしてくれる女友達もいたのでなんとか生活は出来ていたようだった。
フランキーは今後はドラムで生計をたてる事をザシュに伝えた。病院でお世話になった先生が音楽関係の仕事を紹介してくれる人への手紙を書いてくれていて、数日中に会うつもりだとも話した。しかし、ザシュは上手いドラマーなんて沢山いるし仕事になるかは分からないと否定的な言葉を並べた。今まで通りにカード師として暮らそうと言うのだ。
面会の為のスーツを弟分のスパローが用意してくれたが、それは万引きで手に入れたものだったのでフランキーも警察に連行されることとなった。シュワイフカが(実は万引きをチクったのも彼なのだが)用立てた保釈金の交換条件に一夜限りのディーラーを引き受けるフランキー。賭場には馴染みだった薬の売人ルイもいたが彼の誘いに乗ることはなかった。
ドラムの仕事が思うように進まない事に加えて、ザシュからは練習の音が五月蠅いと言われ、更には訪問治療にやってきた怪しげな医者にザシュは大怪我をした時の新聞のスクラップを見せるのでフランキーはやるせなくなった。彼女には自分が不自由をしている事がフランキーを繋ぎとめる魔法の杖と思われたのだろう。
鬱々たる気分に苛まれたフランキーはアパートを飛び出しバーに逃げ込む。そこにはルイが居た。ルイはフランキーの様子に気付き、さりげなく近づいていくのだった・・・。
薬物中毒の話だからフランキーが再びクスリに手を出すのは予想出来るわけだけど、やはり周囲の人間関係を含めた環境が与える影響が如何に大きいかが分かりますな。
そしてダーレン・マクギャヴィン扮する売人ルイの人たらしぶりが憎い位に巧み。
妻のザシュに扮するのはシナトラと「波も涙も暖かい (1959)」でも共演したエリノア・パーカー。ビックリするくらい美人なのに、ここでは自己中の醜い女を演じています。
映画の序盤で実はザシュの脚が治っていることが分かるので、その事が何時どのように周囲に知れるかというのも興味を引く要素になっています。
キム・ノヴァクは同じアパートに住むバーのホステス、モリー。ザシュより早く巡り逢っていれば良かったと思わせる世話女房タイプのイイ女。ドラムの練習にと部屋は提供してくれるし、終盤で再び薬中になって苦しむフランキーを親身になって介抱してくれる恩人でもあります。
「第十七捕虜収容所」でコミカルな役どころだったロバート・ストラウスが今作では悪役のシュワイフカでした。
1955年のアカデミー賞で、主演男優賞、劇・喜劇映画音楽賞(エルマー・バーンスタイン)、美術監督・装置賞(白黒)(Joseph C.Wright、Darrell Silvera)にノミネートされたそうです。
お薦め度は★四つ半。
当時としても衝撃的だったろうシナトラの禁断症状に苦しむ演技が今でも恐怖を感じるくらい真に迫っています。
知らない内に聴き覚えていたジャズのテーマ曲。クールなソウル・バスのクレジットデザイン。
観ながらポール・ニューマン主演の「ハスラー (1961)」を思い出しました。
前回記事「第十七捕虜収容所」のオットー・プレミンジャー繋がりで今回は彼の監督作品として名高い「黄金の腕」を観た。大分前に買った1コインDVDだ。
1945年にビリー・ワイルダーが作った「失われた週末」はアルコール中毒の怖さを描いたが、10年後のこの作品では薬物中毒の恐怖が描かれる。主演はフランク・シナトラ。ジャズシンガーの大御所というイメージが強いんだが、改めてフィルモグラフィーを見ると結構な出演映画があるんですなぁ。
<1950年に第1回全米図書賞を受賞したネルソン・オルグレンの小説『黄金の腕』>が原作だそうです。【原題:The Man with the Golden Arm】
*
 カード賭博の罪で半年間刑務所暮らしをしていたフランキーが地元に帰って来た。
カード賭博の罪で半年間刑務所暮らしをしていたフランキーが地元に帰って来た。賭博場を開いていたのはシュワイフカという男だがフランキーは彼の身代わりになったのだ。その世界では“黄金の腕”を持つと言われるカード捌きの名人フランキーは、その界隈では単に『ディーラー』と呼ばれることが多かった。刑務所暮らしと書いたが殆どは薬物中毒の治療の為の病院暮し。半年かかったがなんとか中毒から抜け出してきたのだ。
“ヤク”が切れた今、二度と薬に手を出さない為に『ディーラー』は止める決心をし、裏街道にも足を踏み入れないと覚悟していた。病院の先生の勧めで覚えたドラムで次の人生を歩もうと思っていたのだ。ビッグバンドでドラマーとしてやっていくのが今の夢。既に芸名迄考えているくらい本気だった。
半年ぶりにアパートに帰ると妻のザシュが車椅子で待っていた。3年前、飲酒運転で事故を起こしたフランキーの車にザシュも乗っていて彼女は大怪我をしたのだ。以来車椅子が手放せない生活となった。お金はシュワイフカ経由で送金してきたし、近所には親切にしてくれる女友達もいたのでなんとか生活は出来ていたようだった。
フランキーは今後はドラムで生計をたてる事をザシュに伝えた。病院でお世話になった先生が音楽関係の仕事を紹介してくれる人への手紙を書いてくれていて、数日中に会うつもりだとも話した。しかし、ザシュは上手いドラマーなんて沢山いるし仕事になるかは分からないと否定的な言葉を並べた。今まで通りにカード師として暮らそうと言うのだ。
面会の為のスーツを弟分のスパローが用意してくれたが、それは万引きで手に入れたものだったのでフランキーも警察に連行されることとなった。シュワイフカが(実は万引きをチクったのも彼なのだが)用立てた保釈金の交換条件に一夜限りのディーラーを引き受けるフランキー。賭場には馴染みだった薬の売人ルイもいたが彼の誘いに乗ることはなかった。
ドラムの仕事が思うように進まない事に加えて、ザシュからは練習の音が五月蠅いと言われ、更には訪問治療にやってきた怪しげな医者にザシュは大怪我をした時の新聞のスクラップを見せるのでフランキーはやるせなくなった。彼女には自分が不自由をしている事がフランキーを繋ぎとめる魔法の杖と思われたのだろう。
鬱々たる気分に苛まれたフランキーはアパートを飛び出しバーに逃げ込む。そこにはルイが居た。ルイはフランキーの様子に気付き、さりげなく近づいていくのだった・・・。
*
薬物中毒の話だからフランキーが再びクスリに手を出すのは予想出来るわけだけど、やはり周囲の人間関係を含めた環境が与える影響が如何に大きいかが分かりますな。
そしてダーレン・マクギャヴィン扮する売人ルイの人たらしぶりが憎い位に巧み。
妻のザシュに扮するのはシナトラと「波も涙も暖かい (1959)」でも共演したエリノア・パーカー。ビックリするくらい美人なのに、ここでは自己中の醜い女を演じています。
映画の序盤で実はザシュの脚が治っていることが分かるので、その事が何時どのように周囲に知れるかというのも興味を引く要素になっています。
キム・ノヴァクは同じアパートに住むバーのホステス、モリー。ザシュより早く巡り逢っていれば良かったと思わせる世話女房タイプのイイ女。ドラムの練習にと部屋は提供してくれるし、終盤で再び薬中になって苦しむフランキーを親身になって介抱してくれる恩人でもあります。
「第十七捕虜収容所」でコミカルな役どころだったロバート・ストラウスが今作では悪役のシュワイフカでした。
1955年のアカデミー賞で、主演男優賞、劇・喜劇映画音楽賞(エルマー・バーンスタイン)、美術監督・装置賞(白黒)(Joseph C.Wright、Darrell Silvera)にノミネートされたそうです。
お薦め度は★四つ半。
当時としても衝撃的だったろうシナトラの禁断症状に苦しむ演技が今でも恐怖を感じるくらい真に迫っています。
知らない内に聴き覚えていたジャズのテーマ曲。クールなソウル・バスのクレジットデザイン。
観ながらポール・ニューマン主演の「ハスラー (1961)」を思い出しました。
・お薦め度【★★★★★=大いに見るべし】 

(1958/小津安二郎監督・共同脚本/佐分利信、田中絹代、有馬稲子、山本富士子、浪花千栄子、久我美子、佐田啓二、高橋貞二、笠智衆、桑野みゆき、渡辺文雄/118分)
 2018年の正月にはテレ東で「娘の結婚」が、今年はTBSで「あしたの家族」と、或る一家の娘の結婚に纏わるスペシャルドラマが放送されたけど、どっちも良い作品だった。あれってやっぱ小津の名残りかねぇ。娘の結婚なんてものはやっぱり家族にしたら今でも一大事で、人間の繋がり方にも色々とバリエーションがあって、1時間では収まらないドラマが出来るんだね。
2018年の正月にはテレ東で「娘の結婚」が、今年はTBSで「あしたの家族」と、或る一家の娘の結婚に纏わるスペシャルドラマが放送されたけど、どっちも良い作品だった。あれってやっぱ小津の名残りかねぇ。娘の結婚なんてものはやっぱり家族にしたら今でも一大事で、人間の繋がり方にも色々とバリエーションがあって、1時間では収まらないドラマが出来るんだね。

 小津安二郎の「彼岸花」もやはり或る一家の娘の結婚に纏わる騒動がテーマだった。1958年=昭和33年の作品で小津初のカラー作品らしい。「彼岸花」は別名「曼珠沙華」。花言葉は花びらの色によって違うらしいんだが、クレジットの文字が赤と白だった事がヒントかも知らんな。
小津安二郎の「彼岸花」もやはり或る一家の娘の結婚に纏わる騒動がテーマだった。1958年=昭和33年の作品で小津初のカラー作品らしい。「彼岸花」は別名「曼珠沙華」。花言葉は花びらの色によって違うらしいんだが、クレジットの文字が赤と白だった事がヒントかも知らんな。
 この作品の一家は商社に重役として勤める佐分利信と田中絹代の夫婦と娘が二人。結婚問題が浮上するのが長女の有馬稲子で、次女には桑野みゆきが扮していた。
この作品の一家は商社に重役として勤める佐分利信と田中絹代の夫婦と娘が二人。結婚問題が浮上するのが長女の有馬稲子で、次女には桑野みゆきが扮していた。
ウィキにあらすじが書いてあったので少し修正を加えて引用する。
<大手企業の常務である平山渉(佐分利信)は、旧友の河合(中村伸郎)の娘の結婚式に、同じく学校同期仲間の三上(笠智衆)が現れないことを不審に思っていた。実は三上は自分の娘・文子(久我美子)が家を出て男と暮らしていることに悩んでおり、いたたまれずに欠席したのだった。後日、三上の頼みで平山は銀座のバーで働いているという文子の様子を見に行くことになる。
その一方で平山は長女・節子(有馬稲子)の良縁に思いをめぐらしていたが、突然会社に現れた谷口(佐田啓二)から節子と付き合っていること、結婚を認めてほしい旨を伝えられて愕然とする。さらに平山の馴染みの京都の旅館の女将・佐々木初(浪花千栄子)も娘・幸子(山本富士子)に良い縁談をと奔走していたが、幸子には一向にその気がなかった。
平山は三上の娘・文子や旅館の娘・幸子には理解を示す一方で、自分の娘・節子の結婚には反対する。平山の妻・清子(田中絹代)や次女・久子(桑野みゆき)も間に入って上手く取りなそうとするが、平山はますます頑なになる・・・>
 主人公は父親の平山で、娘もその恋人も大して活躍はしない。冒頭で旧友の結婚式で祝辞を言って良識ある大人を演じながら段々と化けの皮が剥がれていく面白さ。家族には頑なながら、京都の旅館の女将母娘にはやはり物分かりの良いオヤジっぷりを見せるも結局は翻弄されてしまう。化けの皮が剥がれる、というよりは家族愛と自負していた娘への想いが一人相撲だった事に愕然とする父親の悲哀をユーモラスに描いたと言った方が良いのかな。又は、家長として尊敬されているはずだったのに知らぬ間にないがしろにされていた悲哀と言いますか。
主人公は父親の平山で、娘もその恋人も大して活躍はしない。冒頭で旧友の結婚式で祝辞を言って良識ある大人を演じながら段々と化けの皮が剥がれていく面白さ。家族には頑なながら、京都の旅館の女将母娘にはやはり物分かりの良いオヤジっぷりを見せるも結局は翻弄されてしまう。化けの皮が剥がれる、というよりは家族愛と自負していた娘への想いが一人相撲だった事に愕然とする父親の悲哀をユーモラスに描いたと言った方が良いのかな。又は、家長として尊敬されているはずだったのに知らぬ間にないがしろにされていた悲哀と言いますか。
後半ではそんな夫の振る舞いに悩ませられながらも最後まで辛抱強く事態を見据えていく母親(亡き母がファンだった田中絹代が好演)の心情にもハラハラさせられる。終わってみれば夫婦が主人公だったと言っていいでしょうな。

 ただ、父親としては平山の気持ちが分からんでもない。見合い話を進めてはいたけれど別段無理強いする気はなかったんだし、付き合っている男がいたのならそう言えばよかったんだ。あれだな。やっぱり娘からの言葉が足りないのがカチンときたんだろうな。勿論、娘も男からのプロポーズを待っていたのなら親に話せる状況ではなかったかも知れないけど。
ただ、父親としては平山の気持ちが分からんでもない。見合い話を進めてはいたけれど別段無理強いする気はなかったんだし、付き合っている男がいたのならそう言えばよかったんだ。あれだな。やっぱり娘からの言葉が足りないのがカチンときたんだろうな。勿論、娘も男からのプロポーズを待っていたのなら親に話せる状況ではなかったかも知れないけど。
その関係でいえば、娘の彼氏も配慮が足りないよね。彼女に対してもそうだし、彼女の親に対してもだ。広島への転勤が急だったとしても、せめて彼女を通して話をするべきだったよな。
結局平山は最後まで娘婿と膝を交えて話をする事も無かった。エピローグで娘夫婦の住む広島まで会いに行くところで映画は終わり。ハッピーエンドだけど、やっぱり気にはなるってのはバランスが悪いのかも知れないな。
佐田啓二扮する谷口は節子が勤める会社の同僚だった。
 まぁ、それにしてもこの映画で僕が好きなのは浪花千栄子と山本富士子だな。二人共映画で観るのは初めてと言っていいくらい珍しいんだけど、何処か堅苦しい感じがする東京連中の会話の後に、スラスラと流れるように繰り出される京都弁の心地良さ。そして正面カメラにも動じることなく自然体の浪花千枝子と、何処から撮っても美しい娘役の山本富士子。終盤で見せる娘の母親への愛情も説得力があったなぁ。
まぁ、それにしてもこの映画で僕が好きなのは浪花千栄子と山本富士子だな。二人共映画で観るのは初めてと言っていいくらい珍しいんだけど、何処か堅苦しい感じがする東京連中の会話の後に、スラスラと流れるように繰り出される京都弁の心地良さ。そして正面カメラにも動じることなく自然体の浪花千枝子と、何処から撮っても美しい娘役の山本富士子。終盤で見せる娘の母親への愛情も説得力があったなぁ。
 三上の娘の勤めるバーに行くのに平山は若い部下(高橋貞二)を連れて行くんだが、誘われたサラリーマンの応対ぶりが如何にも昭和っぽくて笑わせる。バーのママには馴れ馴れしいのに、上司の前では先生に同伴された中学生みたいに大人しいんだ。昨今の若者にはどんな風に見えるのかなぁ。
三上の娘の勤めるバーに行くのに平山は若い部下(高橋貞二)を連れて行くんだが、誘われたサラリーマンの応対ぶりが如何にも昭和っぽくて笑わせる。バーのママには馴れ馴れしいのに、上司の前では先生に同伴された中学生みたいに大人しいんだ。昨今の若者にはどんな風に見えるのかなぁ。
三上の娘・文子(久我美子)が同棲している男はピアノを弾くバンドマン。演じたのが若くてスラっとしている渡辺文雄だった。
 序盤の結婚式の後、平山達同級生が料亭で酒を酌み交わす一幕があるが、その中でそれぞれの子供の男女の数を確かめ合うシーンがある。亭主が元気な夫婦には女の子が多く、女房が強い夫婦には男の子供が多い、なんて下世話な法則を確認し合っている親父ども。何時の時代にも酒の席にはこういう話は出るんですなぁ。
序盤の結婚式の後、平山達同級生が料亭で酒を酌み交わす一幕があるが、その中でそれぞれの子供の男女の数を確かめ合うシーンがある。亭主が元気な夫婦には女の子が多く、女房が強い夫婦には男の子供が多い、なんて下世話な法則を確認し合っている親父ども。何時の時代にも酒の席にはこういう話は出るんですなぁ。
 お薦め度は★三つ。一見の価値有り。
お薦め度は★三つ。一見の価値有り。
観る度に良くなっていくけれど、今時の映画ファンに大いにお勧めするには僕にも理解できない部分もあるしネ。
あと、娘と彼氏のエピソードがすんなりと受け入れられない所もマイナス点かな。確かに主人公は親夫婦だから娘の方は省略しても良いんだけど、そんな中でも描かれた彼氏のエピソードが不自然な感じがした。
 2018年の正月にはテレ東で「娘の結婚」が、今年はTBSで「あしたの家族」と、或る一家の娘の結婚に纏わるスペシャルドラマが放送されたけど、どっちも良い作品だった。あれってやっぱ小津の名残りかねぇ。娘の結婚なんてものはやっぱり家族にしたら今でも一大事で、人間の繋がり方にも色々とバリエーションがあって、1時間では収まらないドラマが出来るんだね。
2018年の正月にはテレ東で「娘の結婚」が、今年はTBSで「あしたの家族」と、或る一家の娘の結婚に纏わるスペシャルドラマが放送されたけど、どっちも良い作品だった。あれってやっぱ小津の名残りかねぇ。娘の結婚なんてものはやっぱり家族にしたら今でも一大事で、人間の繋がり方にも色々とバリエーションがあって、1時間では収まらないドラマが出来るんだね。
 小津安二郎の「彼岸花」もやはり或る一家の娘の結婚に纏わる騒動がテーマだった。1958年=昭和33年の作品で小津初のカラー作品らしい。「彼岸花」は別名「曼珠沙華」。花言葉は花びらの色によって違うらしいんだが、クレジットの文字が赤と白だった事がヒントかも知らんな。
小津安二郎の「彼岸花」もやはり或る一家の娘の結婚に纏わる騒動がテーマだった。1958年=昭和33年の作品で小津初のカラー作品らしい。「彼岸花」は別名「曼珠沙華」。花言葉は花びらの色によって違うらしいんだが、クレジットの文字が赤と白だった事がヒントかも知らんな。 この作品の一家は商社に重役として勤める佐分利信と田中絹代の夫婦と娘が二人。結婚問題が浮上するのが長女の有馬稲子で、次女には桑野みゆきが扮していた。
この作品の一家は商社に重役として勤める佐分利信と田中絹代の夫婦と娘が二人。結婚問題が浮上するのが長女の有馬稲子で、次女には桑野みゆきが扮していた。ウィキにあらすじが書いてあったので少し修正を加えて引用する。
<大手企業の常務である平山渉(佐分利信)は、旧友の河合(中村伸郎)の娘の結婚式に、同じく学校同期仲間の三上(笠智衆)が現れないことを不審に思っていた。実は三上は自分の娘・文子(久我美子)が家を出て男と暮らしていることに悩んでおり、いたたまれずに欠席したのだった。後日、三上の頼みで平山は銀座のバーで働いているという文子の様子を見に行くことになる。
その一方で平山は長女・節子(有馬稲子)の良縁に思いをめぐらしていたが、突然会社に現れた谷口(佐田啓二)から節子と付き合っていること、結婚を認めてほしい旨を伝えられて愕然とする。さらに平山の馴染みの京都の旅館の女将・佐々木初(浪花千栄子)も娘・幸子(山本富士子)に良い縁談をと奔走していたが、幸子には一向にその気がなかった。
平山は三上の娘・文子や旅館の娘・幸子には理解を示す一方で、自分の娘・節子の結婚には反対する。平山の妻・清子(田中絹代)や次女・久子(桑野みゆき)も間に入って上手く取りなそうとするが、平山はますます頑なになる・・・>
 主人公は父親の平山で、娘もその恋人も大して活躍はしない。冒頭で旧友の結婚式で祝辞を言って良識ある大人を演じながら段々と化けの皮が剥がれていく面白さ。家族には頑なながら、京都の旅館の女将母娘にはやはり物分かりの良いオヤジっぷりを見せるも結局は翻弄されてしまう。化けの皮が剥がれる、というよりは家族愛と自負していた娘への想いが一人相撲だった事に愕然とする父親の悲哀をユーモラスに描いたと言った方が良いのかな。又は、家長として尊敬されているはずだったのに知らぬ間にないがしろにされていた悲哀と言いますか。
主人公は父親の平山で、娘もその恋人も大して活躍はしない。冒頭で旧友の結婚式で祝辞を言って良識ある大人を演じながら段々と化けの皮が剥がれていく面白さ。家族には頑なながら、京都の旅館の女将母娘にはやはり物分かりの良いオヤジっぷりを見せるも結局は翻弄されてしまう。化けの皮が剥がれる、というよりは家族愛と自負していた娘への想いが一人相撲だった事に愕然とする父親の悲哀をユーモラスに描いたと言った方が良いのかな。又は、家長として尊敬されているはずだったのに知らぬ間にないがしろにされていた悲哀と言いますか。後半ではそんな夫の振る舞いに悩ませられながらも最後まで辛抱強く事態を見据えていく母親(亡き母がファンだった田中絹代が好演)の心情にもハラハラさせられる。終わってみれば夫婦が主人公だったと言っていいでしょうな。

 ただ、父親としては平山の気持ちが分からんでもない。見合い話を進めてはいたけれど別段無理強いする気はなかったんだし、付き合っている男がいたのならそう言えばよかったんだ。あれだな。やっぱり娘からの言葉が足りないのがカチンときたんだろうな。勿論、娘も男からのプロポーズを待っていたのなら親に話せる状況ではなかったかも知れないけど。
ただ、父親としては平山の気持ちが分からんでもない。見合い話を進めてはいたけれど別段無理強いする気はなかったんだし、付き合っている男がいたのならそう言えばよかったんだ。あれだな。やっぱり娘からの言葉が足りないのがカチンときたんだろうな。勿論、娘も男からのプロポーズを待っていたのなら親に話せる状況ではなかったかも知れないけど。その関係でいえば、娘の彼氏も配慮が足りないよね。彼女に対してもそうだし、彼女の親に対してもだ。広島への転勤が急だったとしても、せめて彼女を通して話をするべきだったよな。
結局平山は最後まで娘婿と膝を交えて話をする事も無かった。エピローグで娘夫婦の住む広島まで会いに行くところで映画は終わり。ハッピーエンドだけど、やっぱり気にはなるってのはバランスが悪いのかも知れないな。
佐田啓二扮する谷口は節子が勤める会社の同僚だった。
 まぁ、それにしてもこの映画で僕が好きなのは浪花千栄子と山本富士子だな。二人共映画で観るのは初めてと言っていいくらい珍しいんだけど、何処か堅苦しい感じがする東京連中の会話の後に、スラスラと流れるように繰り出される京都弁の心地良さ。そして正面カメラにも動じることなく自然体の浪花千枝子と、何処から撮っても美しい娘役の山本富士子。終盤で見せる娘の母親への愛情も説得力があったなぁ。
まぁ、それにしてもこの映画で僕が好きなのは浪花千栄子と山本富士子だな。二人共映画で観るのは初めてと言っていいくらい珍しいんだけど、何処か堅苦しい感じがする東京連中の会話の後に、スラスラと流れるように繰り出される京都弁の心地良さ。そして正面カメラにも動じることなく自然体の浪花千枝子と、何処から撮っても美しい娘役の山本富士子。終盤で見せる娘の母親への愛情も説得力があったなぁ。 三上の娘の勤めるバーに行くのに平山は若い部下(高橋貞二)を連れて行くんだが、誘われたサラリーマンの応対ぶりが如何にも昭和っぽくて笑わせる。バーのママには馴れ馴れしいのに、上司の前では先生に同伴された中学生みたいに大人しいんだ。昨今の若者にはどんな風に見えるのかなぁ。
三上の娘の勤めるバーに行くのに平山は若い部下(高橋貞二)を連れて行くんだが、誘われたサラリーマンの応対ぶりが如何にも昭和っぽくて笑わせる。バーのママには馴れ馴れしいのに、上司の前では先生に同伴された中学生みたいに大人しいんだ。昨今の若者にはどんな風に見えるのかなぁ。三上の娘・文子(久我美子)が同棲している男はピアノを弾くバンドマン。演じたのが若くてスラっとしている渡辺文雄だった。
 序盤の結婚式の後、平山達同級生が料亭で酒を酌み交わす一幕があるが、その中でそれぞれの子供の男女の数を確かめ合うシーンがある。亭主が元気な夫婦には女の子が多く、女房が強い夫婦には男の子供が多い、なんて下世話な法則を確認し合っている親父ども。何時の時代にも酒の席にはこういう話は出るんですなぁ。
序盤の結婚式の後、平山達同級生が料亭で酒を酌み交わす一幕があるが、その中でそれぞれの子供の男女の数を確かめ合うシーンがある。亭主が元気な夫婦には女の子が多く、女房が強い夫婦には男の子供が多い、なんて下世話な法則を確認し合っている親父ども。何時の時代にも酒の席にはこういう話は出るんですなぁ。 お薦め度は★三つ。一見の価値有り。
お薦め度は★三つ。一見の価値有り。観る度に良くなっていくけれど、今時の映画ファンに大いにお勧めするには僕にも理解できない部分もあるしネ。
あと、娘と彼氏のエピソードがすんなりと受け入れられない所もマイナス点かな。確かに主人公は親夫婦だから娘の方は省略しても良いんだけど、そんな中でも描かれた彼氏のエピソードが不自然な感じがした。
・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 

(1992/ジェームズ・アイヴォリー監督/エマ・トンプソン、アンソニー・ホプキンス、ヴァネッサ・レッドグレーヴ、ヘレナ・ボナム=カーター、ジェームズ・ウィルビー、サミュエル・ウェスト、ジェマ・レッドグレーヴ/143分)
 歳のせいか根気がなくなって長い文章を書けなくなったみたい。なので今回も(或いはこれからもずっと)ツイート風の備忘録になります。
歳のせいか根気がなくなって長い文章を書けなくなったみたい。なので今回も(或いはこれからもずっと)ツイート風の備忘録になります。
 しばらく自分好みのテイストの映画に触れてないのでJ・アイヴォリーの「ハワーズ・エンド」をツタヤで借りてきた。「日の名残り」が大好きだったからだけど、1回目の鑑賞後の印象は「とにかく長い」。観終わってチェックしたら2時間20分という大作でした。ま、それでもダレる事は無かったんだけどね。
しばらく自分好みのテイストの映画に触れてないのでJ・アイヴォリーの「ハワーズ・エンド」をツタヤで借りてきた。「日の名残り」が大好きだったからだけど、1回目の鑑賞後の印象は「とにかく長い」。観終わってチェックしたら2時間20分という大作でした。ま、それでもダレる事は無かったんだけどね。
 時代背景は違っても主演の二人が同じこともあって画のテイストは似てるけれど、語り口は「日の名残り」ほどのピリピリ感がないというか、かなり違ってる。考えればアレは原作がイシグロ・カズオだし、コレはE・M・フォスターだしね。14年前に観たきりだから明言は出来ないけど、語り口は同じE・M・フォスター原作の「眺めのいい部屋」に似てる気がする。同じ監督だし、脚本も同じだから当然かもしれないけど・・。
時代背景は違っても主演の二人が同じこともあって画のテイストは似てるけれど、語り口は「日の名残り」ほどのピリピリ感がないというか、かなり違ってる。考えればアレは原作がイシグロ・カズオだし、コレはE・M・フォスターだしね。14年前に観たきりだから明言は出来ないけど、語り口は同じE・M・フォスター原作の「眺めのいい部屋」に似てる気がする。同じ監督だし、脚本も同じだから当然かもしれないけど・・。

 20世紀初頭のイギリスが舞台の「ハワーズ・エンド」には二つの家族が出てくる。
20世紀初頭のイギリスが舞台の「ハワーズ・エンド」には二つの家族が出てくる。
 マーガレット(トンプソン)を長女とするシュレーゲル家は父親がドイツ人で母親はイギリス人。既に親夫婦は亡くなっていて、次女のヘレン(カーター)と高等学校に行っているティビーという少年がいる。更には何かと口を出してくる母方の叔母がいて、四人で仲良く暮らしている感じ。シュレーゲル家には大きな屋敷などは無いが、日々の暮らしに困らないだけの財産を受け継いでいるようだった。文学や芸術を愛し、食事やコーヒーを摂りながら諸々な議論を交わすのも好きな家族だ。
マーガレット(トンプソン)を長女とするシュレーゲル家は父親がドイツ人で母親はイギリス人。既に親夫婦は亡くなっていて、次女のヘレン(カーター)と高等学校に行っているティビーという少年がいる。更には何かと口を出してくる母方の叔母がいて、四人で仲良く暮らしている感じ。シュレーゲル家には大きな屋敷などは無いが、日々の暮らしに困らないだけの財産を受け継いでいるようだった。文学や芸術を愛し、食事やコーヒーを摂りながら諸々な議論を交わすのも好きな家族だ。
 ヘンリー(ホプキンス)を家長とするウィルコックス家は、一代で会社を興して富豪になった資産家で、妻のルース(レッドグレーヴ)と二人の息子と末の長女がいた。子供たちは既に大人で、映画の冒頭、ウィルコックス家の田舎の別荘「ハワーズ・エンド」にヘレンが泊まっている所から物語はスタートする。「ハワーズ・エンド」はルースの生家でもあった。
ヘンリー(ホプキンス)を家長とするウィルコックス家は、一代で会社を興して富豪になった資産家で、妻のルース(レッドグレーヴ)と二人の息子と末の長女がいた。子供たちは既に大人で、映画の冒頭、ウィルコックス家の田舎の別荘「ハワーズ・エンド」にヘレンが泊まっている所から物語はスタートする。「ハワーズ・エンド」はルースの生家でもあった。
 二つの家族は共にドイツを旅行した折に旅先で知り合い、ウィルコックス家の次男ポールに惹かれたヘレンが「ハワーズ・エンド」に招待されたというのが冒頭のシーンの経緯だ。そこで二人は燃え上がるが、それは一晩で萎むことになる。ヘレンが勢いでマーガレットに『ポールと婚約した』なんていう手紙を出したもんだから、大慌てで叔母さんが「ハワーズ・エンド」を訪ねるという一幕もあり、両家にとっても気まずさを残すことになってしまう。という所までがいわばプロローグだろうか。その数か月後、ロンドンのシュレーゲル家の住む家の前に偶然にウィルコックス家が引っ越してくるのである。
二つの家族は共にドイツを旅行した折に旅先で知り合い、ウィルコックス家の次男ポールに惹かれたヘレンが「ハワーズ・エンド」に招待されたというのが冒頭のシーンの経緯だ。そこで二人は燃え上がるが、それは一晩で萎むことになる。ヘレンが勢いでマーガレットに『ポールと婚約した』なんていう手紙を出したもんだから、大慌てで叔母さんが「ハワーズ・エンド」を訪ねるという一幕もあり、両家にとっても気まずさを残すことになってしまう。という所までがいわばプロローグだろうか。その数か月後、ロンドンのシュレーゲル家の住む家の前に偶然にウィルコックス家が引っ越してくるのである。
 知らぬ振りもできまいと考えたのか、マーガレットは向いのウィルコックス家を訪ね、ルースと親しくなっていく。ルースはマーガレットよりもかなり年上だったが彼女を妹の様に信頼した。マーガレットも実業家の妻にしては繊細な雰囲気を醸し出すルースに親しみを覚え、クリスマスプレゼントのリストアップや買い物に付き合ったりした。
知らぬ振りもできまいと考えたのか、マーガレットは向いのウィルコックス家を訪ね、ルースと親しくなっていく。ルースはマーガレットよりもかなり年上だったが彼女を妹の様に信頼した。マーガレットも実業家の妻にしては繊細な雰囲気を醸し出すルースに親しみを覚え、クリスマスプレゼントのリストアップや買い物に付き合ったりした。
 実はルースは病気を抱えておりもうすぐ手術をするんだとマーガレットに告白した。マーガレットもまた今の家が借家であり1年半後には明け渡さねばならないと話した。それを聞いたルースは是非とも「ハワーズ・エンド」を見せたいと言った。
実はルースは病気を抱えておりもうすぐ手術をするんだとマーガレットに告白した。マーガレットもまた今の家が借家であり1年半後には明け渡さねばならないと話した。それを聞いたルースは是非とも「ハワーズ・エンド」を見せたいと言った。
 E・M・フォスターの作品は文化や階級の違いからくる葛藤をテーマにすることが多いらしいが、「ハワーズ・エンド」には二つの割と裕福な家庭の他にもう一つ、仕事に就いていなければ生活に困ってしまう所謂一般人の家庭も出てくる。ロンドンに帰ったヘレンが行った音楽会で間違って傘を持ち帰った青年レナード・バストのそれである。
E・M・フォスターの作品は文化や階級の違いからくる葛藤をテーマにすることが多いらしいが、「ハワーズ・エンド」には二つの割と裕福な家庭の他にもう一つ、仕事に就いていなければ生活に困ってしまう所謂一般人の家庭も出てくる。ロンドンに帰ったヘレンが行った音楽会で間違って傘を持ち帰った青年レナード・バストのそれである。
 生命保険会社に勤めるレナードは年の離れた女性ジャッキーと二人暮らしだが、文学や天文学に興味を持つロマンチックで繊細な青年だった。一方、ジャッキーは物事を深く考えず、レナードの愛だけを生きる縁(よすが)にしているような女だった。
生命保険会社に勤めるレナードは年の離れた女性ジャッキーと二人暮らしだが、文学や天文学に興味を持つロマンチックで繊細な青年だった。一方、ジャッキーは物事を深く考えず、レナードの愛だけを生きる縁(よすが)にしているような女だった。
 隣に座っていたヘレンに自分の雨傘を持ち帰られたレナードは彼女の後を追い、シュレーゲル家に立ち寄ることになる。傘を取り戻しただけでなく、彼にすれば意外なおもてなしを受けそうになり早々に帰路に着くが、その時に渡されたマーガレットの名刺がその後の二つの家族に何かと面倒になるくらいの縁をもたらしてしまうのである。
隣に座っていたヘレンに自分の雨傘を持ち帰られたレナードは彼女の後を追い、シュレーゲル家に立ち寄ることになる。傘を取り戻しただけでなく、彼にすれば意外なおもてなしを受けそうになり早々に帰路に着くが、その時に渡されたマーガレットの名刺がその後の二つの家族に何かと面倒になるくらいの縁をもたらしてしまうのである。
 ルースは手術を受けるが経過は思わしくなく、ほどなくして亡くなってしまう。亡くなる直前ルースは看護婦に紙と鉛筆を頼み、「ハワーズ・エンド」をマーガレットに譲るとメモをしたためた。ルースの死後、病院からその手紙を受け取ったウィルコックス家では家族会議が開かれたが、ルースのメモは遺言書として不備でもあったし、彼女の意思は黙殺されることになった。
ルースは手術を受けるが経過は思わしくなく、ほどなくして亡くなってしまう。亡くなる直前ルースは看護婦に紙と鉛筆を頼み、「ハワーズ・エンド」をマーガレットに譲るとメモをしたためた。ルースの死後、病院からその手紙を受け取ったウィルコックス家では家族会議が開かれたが、ルースのメモは遺言書として不備でもあったし、彼女の意思は黙殺されることになった。
 マーガレットとヘレンは週に一度の討論会の後、偶然街でヘンリーと会う。その時にヘレンはヘンリーにレナードの事について相談をする。傘の件の後、浮気を疑ったジャッキーの勘違いを正すためにレナードが再度シュレーゲル家を訪れる機会があり、姉妹は彼に好印象を持っていた。知的で繊細な事務員をしている青年が、仕事だけでなく知的活動においても十分な成果が上げられるようにという親切な友人としての相談だったが、立ち話でもあり、ヘンリーはレナードが勤める保険会社の悪い評判を聞いていたので早めに退職することを進言した。後に姉妹の助言を信じたレナードは会社を辞めるが、ヘンリーが破産すると明言した保険会社は潰れる事は無く、反対に転職先の銀行から業績悪化の為の人員整理の対象にされてしまう。これは全てヘンリー・ウィルコックスのせいだとヘレンは思うようになる。
マーガレットとヘレンは週に一度の討論会の後、偶然街でヘンリーと会う。その時にヘレンはヘンリーにレナードの事について相談をする。傘の件の後、浮気を疑ったジャッキーの勘違いを正すためにレナードが再度シュレーゲル家を訪れる機会があり、姉妹は彼に好印象を持っていた。知的で繊細な事務員をしている青年が、仕事だけでなく知的活動においても十分な成果が上げられるようにという親切な友人としての相談だったが、立ち話でもあり、ヘンリーはレナードが勤める保険会社の悪い評判を聞いていたので早めに退職することを進言した。後に姉妹の助言を信じたレナードは会社を辞めるが、ヘンリーが破産すると明言した保険会社は潰れる事は無く、反対に転職先の銀行から業績悪化の為の人員整理の対象にされてしまう。これは全てヘンリー・ウィルコックスのせいだとヘレンは思うようになる。
 ヘレンはヘンリーを嫌っていたが、逆にマーガレットは新しい家を探すのに彼を頼り、ヘンリーも彼女の力になることに喜びを見出し始めた。新しい家が見つかった頃、ヘンリーはマーガレットに求婚し、マーガレットも快く受けた。ヘンリーの子供たちは若い後妻候補に「ハワーズ・エンド」を獲られてしまうと危機感を募らせ、マーガレットは妹のヘンリー嫌いに難儀する。更にはレナードを巡るヘレンの対応の過程でヘンリーとジャッキーの意外な関係も暴かれることになり、それはヘンリーとマーガレットの関係、そしてウィルコックス家の尊厳にもかかわる事件へと発展していく・・。
ヘレンはヘンリーを嫌っていたが、逆にマーガレットは新しい家を探すのに彼を頼り、ヘンリーも彼女の力になることに喜びを見出し始めた。新しい家が見つかった頃、ヘンリーはマーガレットに求婚し、マーガレットも快く受けた。ヘンリーの子供たちは若い後妻候補に「ハワーズ・エンド」を獲られてしまうと危機感を募らせ、マーガレットは妹のヘンリー嫌いに難儀する。更にはレナードを巡るヘレンの対応の過程でヘンリーとジャッキーの意外な関係も暴かれることになり、それはヘンリーとマーガレットの関係、そしてウィルコックス家の尊厳にもかかわる事件へと発展していく・・。
 まぁ、あらすじを書いていてもエピソードの順番がどうだったか分からなくなってしまう感じなんだけど、登場人物の心情も少しあやふやな感じもある。マーガレットとヘンリーの恋の進展もいつ始まったのかもわからないし、なにしろレナードの気持ちが分からない。あんなにジャッキーを疎ましく思っていた彼が、何故にずるずると同棲から結婚へと進んでしまったのか? どうやら小説を読めばもう少し分かるみたいだけど、映画は2回観たけど不可解だった。レナード・バストは映画ではただの厄介な青年でしかない。最後に彼は「ハワーズ・エンド」にやって来るんだけど、マーガレットに陳謝に来たはずなのに、最後の最後に一番ひどい結果をもたらしてしまうんだ。そしてヘレンもマーガレットにとっては身内だけにもっと厄介な存在かも知れない。映画のその後を考えると、彼女が一番疫病神だな。
まぁ、あらすじを書いていてもエピソードの順番がどうだったか分からなくなってしまう感じなんだけど、登場人物の心情も少しあやふやな感じもある。マーガレットとヘンリーの恋の進展もいつ始まったのかもわからないし、なにしろレナードの気持ちが分からない。あんなにジャッキーを疎ましく思っていた彼が、何故にずるずると同棲から結婚へと進んでしまったのか? どうやら小説を読めばもう少し分かるみたいだけど、映画は2回観たけど不可解だった。レナード・バストは映画ではただの厄介な青年でしかない。最後に彼は「ハワーズ・エンド」にやって来るんだけど、マーガレットに陳謝に来たはずなのに、最後の最後に一番ひどい結果をもたらしてしまうんだ。そしてヘレンもマーガレットにとっては身内だけにもっと厄介な存在かも知れない。映画のその後を考えると、彼女が一番疫病神だな。
 「ハワーズ・エンド」が結局は元の持ち主ルースの望んだようになって、この物語が人の世の不思議さを描き出したようになってるけど、色々と無理くりな設定、展開が感じられて感服することは無かったな。お薦め度は★三つ半。繊細な心理状態を見事に表現した主演の二人の演技に★半分おまけです。
「ハワーズ・エンド」が結局は元の持ち主ルースの望んだようになって、この物語が人の世の不思議さを描き出したようになってるけど、色々と無理くりな設定、展開が感じられて感服することは無かったな。お薦め度は★三つ半。繊細な心理状態を見事に表現した主演の二人の演技に★半分おまけです。
 1992年のアカデミー賞で作品賞他にノミネート。主演女優賞(トンプソン)、脚色賞(ルース・プラワー・ジャブヴァーラ)、そして美術賞を受賞した。
1992年のアカデミー賞で作品賞他にノミネート。主演女優賞(トンプソン)、脚色賞(ルース・プラワー・ジャブヴァーラ)、そして美術賞を受賞した。
 歳のせいか根気がなくなって長い文章を書けなくなったみたい。なので今回も(或いはこれからもずっと)ツイート風の備忘録になります。
歳のせいか根気がなくなって長い文章を書けなくなったみたい。なので今回も(或いはこれからもずっと)ツイート風の備忘録になります。 しばらく自分好みのテイストの映画に触れてないのでJ・アイヴォリーの「ハワーズ・エンド」をツタヤで借りてきた。「日の名残り」が大好きだったからだけど、1回目の鑑賞後の印象は「とにかく長い」。観終わってチェックしたら2時間20分という大作でした。ま、それでもダレる事は無かったんだけどね。
しばらく自分好みのテイストの映画に触れてないのでJ・アイヴォリーの「ハワーズ・エンド」をツタヤで借りてきた。「日の名残り」が大好きだったからだけど、1回目の鑑賞後の印象は「とにかく長い」。観終わってチェックしたら2時間20分という大作でした。ま、それでもダレる事は無かったんだけどね。 時代背景は違っても主演の二人が同じこともあって画のテイストは似てるけれど、語り口は「日の名残り」ほどのピリピリ感がないというか、かなり違ってる。考えればアレは原作がイシグロ・カズオだし、コレはE・M・フォスターだしね。14年前に観たきりだから明言は出来ないけど、語り口は同じE・M・フォスター原作の「眺めのいい部屋」に似てる気がする。同じ監督だし、脚本も同じだから当然かもしれないけど・・。
時代背景は違っても主演の二人が同じこともあって画のテイストは似てるけれど、語り口は「日の名残り」ほどのピリピリ感がないというか、かなり違ってる。考えればアレは原作がイシグロ・カズオだし、コレはE・M・フォスターだしね。14年前に観たきりだから明言は出来ないけど、語り口は同じE・M・フォスター原作の「眺めのいい部屋」に似てる気がする。同じ監督だし、脚本も同じだから当然かもしれないけど・・。*

 20世紀初頭のイギリスが舞台の「ハワーズ・エンド」には二つの家族が出てくる。
20世紀初頭のイギリスが舞台の「ハワーズ・エンド」には二つの家族が出てくる。 マーガレット(トンプソン)を長女とするシュレーゲル家は父親がドイツ人で母親はイギリス人。既に親夫婦は亡くなっていて、次女のヘレン(カーター)と高等学校に行っているティビーという少年がいる。更には何かと口を出してくる母方の叔母がいて、四人で仲良く暮らしている感じ。シュレーゲル家には大きな屋敷などは無いが、日々の暮らしに困らないだけの財産を受け継いでいるようだった。文学や芸術を愛し、食事やコーヒーを摂りながら諸々な議論を交わすのも好きな家族だ。
マーガレット(トンプソン)を長女とするシュレーゲル家は父親がドイツ人で母親はイギリス人。既に親夫婦は亡くなっていて、次女のヘレン(カーター)と高等学校に行っているティビーという少年がいる。更には何かと口を出してくる母方の叔母がいて、四人で仲良く暮らしている感じ。シュレーゲル家には大きな屋敷などは無いが、日々の暮らしに困らないだけの財産を受け継いでいるようだった。文学や芸術を愛し、食事やコーヒーを摂りながら諸々な議論を交わすのも好きな家族だ。 ヘンリー(ホプキンス)を家長とするウィルコックス家は、一代で会社を興して富豪になった資産家で、妻のルース(レッドグレーヴ)と二人の息子と末の長女がいた。子供たちは既に大人で、映画の冒頭、ウィルコックス家の田舎の別荘「ハワーズ・エンド」にヘレンが泊まっている所から物語はスタートする。「ハワーズ・エンド」はルースの生家でもあった。
ヘンリー(ホプキンス)を家長とするウィルコックス家は、一代で会社を興して富豪になった資産家で、妻のルース(レッドグレーヴ)と二人の息子と末の長女がいた。子供たちは既に大人で、映画の冒頭、ウィルコックス家の田舎の別荘「ハワーズ・エンド」にヘレンが泊まっている所から物語はスタートする。「ハワーズ・エンド」はルースの生家でもあった。 二つの家族は共にドイツを旅行した折に旅先で知り合い、ウィルコックス家の次男ポールに惹かれたヘレンが「ハワーズ・エンド」に招待されたというのが冒頭のシーンの経緯だ。そこで二人は燃え上がるが、それは一晩で萎むことになる。ヘレンが勢いでマーガレットに『ポールと婚約した』なんていう手紙を出したもんだから、大慌てで叔母さんが「ハワーズ・エンド」を訪ねるという一幕もあり、両家にとっても気まずさを残すことになってしまう。という所までがいわばプロローグだろうか。その数か月後、ロンドンのシュレーゲル家の住む家の前に偶然にウィルコックス家が引っ越してくるのである。
二つの家族は共にドイツを旅行した折に旅先で知り合い、ウィルコックス家の次男ポールに惹かれたヘレンが「ハワーズ・エンド」に招待されたというのが冒頭のシーンの経緯だ。そこで二人は燃え上がるが、それは一晩で萎むことになる。ヘレンが勢いでマーガレットに『ポールと婚約した』なんていう手紙を出したもんだから、大慌てで叔母さんが「ハワーズ・エンド」を訪ねるという一幕もあり、両家にとっても気まずさを残すことになってしまう。という所までがいわばプロローグだろうか。その数か月後、ロンドンのシュレーゲル家の住む家の前に偶然にウィルコックス家が引っ越してくるのである。 知らぬ振りもできまいと考えたのか、マーガレットは向いのウィルコックス家を訪ね、ルースと親しくなっていく。ルースはマーガレットよりもかなり年上だったが彼女を妹の様に信頼した。マーガレットも実業家の妻にしては繊細な雰囲気を醸し出すルースに親しみを覚え、クリスマスプレゼントのリストアップや買い物に付き合ったりした。
知らぬ振りもできまいと考えたのか、マーガレットは向いのウィルコックス家を訪ね、ルースと親しくなっていく。ルースはマーガレットよりもかなり年上だったが彼女を妹の様に信頼した。マーガレットも実業家の妻にしては繊細な雰囲気を醸し出すルースに親しみを覚え、クリスマスプレゼントのリストアップや買い物に付き合ったりした。 実はルースは病気を抱えておりもうすぐ手術をするんだとマーガレットに告白した。マーガレットもまた今の家が借家であり1年半後には明け渡さねばならないと話した。それを聞いたルースは是非とも「ハワーズ・エンド」を見せたいと言った。
実はルースは病気を抱えておりもうすぐ手術をするんだとマーガレットに告白した。マーガレットもまた今の家が借家であり1年半後には明け渡さねばならないと話した。それを聞いたルースは是非とも「ハワーズ・エンド」を見せたいと言った。 E・M・フォスターの作品は文化や階級の違いからくる葛藤をテーマにすることが多いらしいが、「ハワーズ・エンド」には二つの割と裕福な家庭の他にもう一つ、仕事に就いていなければ生活に困ってしまう所謂一般人の家庭も出てくる。ロンドンに帰ったヘレンが行った音楽会で間違って傘を持ち帰った青年レナード・バストのそれである。
E・M・フォスターの作品は文化や階級の違いからくる葛藤をテーマにすることが多いらしいが、「ハワーズ・エンド」には二つの割と裕福な家庭の他にもう一つ、仕事に就いていなければ生活に困ってしまう所謂一般人の家庭も出てくる。ロンドンに帰ったヘレンが行った音楽会で間違って傘を持ち帰った青年レナード・バストのそれである。 生命保険会社に勤めるレナードは年の離れた女性ジャッキーと二人暮らしだが、文学や天文学に興味を持つロマンチックで繊細な青年だった。一方、ジャッキーは物事を深く考えず、レナードの愛だけを生きる縁(よすが)にしているような女だった。
生命保険会社に勤めるレナードは年の離れた女性ジャッキーと二人暮らしだが、文学や天文学に興味を持つロマンチックで繊細な青年だった。一方、ジャッキーは物事を深く考えず、レナードの愛だけを生きる縁(よすが)にしているような女だった。 隣に座っていたヘレンに自分の雨傘を持ち帰られたレナードは彼女の後を追い、シュレーゲル家に立ち寄ることになる。傘を取り戻しただけでなく、彼にすれば意外なおもてなしを受けそうになり早々に帰路に着くが、その時に渡されたマーガレットの名刺がその後の二つの家族に何かと面倒になるくらいの縁をもたらしてしまうのである。
隣に座っていたヘレンに自分の雨傘を持ち帰られたレナードは彼女の後を追い、シュレーゲル家に立ち寄ることになる。傘を取り戻しただけでなく、彼にすれば意外なおもてなしを受けそうになり早々に帰路に着くが、その時に渡されたマーガレットの名刺がその後の二つの家族に何かと面倒になるくらいの縁をもたらしてしまうのである。 ルースは手術を受けるが経過は思わしくなく、ほどなくして亡くなってしまう。亡くなる直前ルースは看護婦に紙と鉛筆を頼み、「ハワーズ・エンド」をマーガレットに譲るとメモをしたためた。ルースの死後、病院からその手紙を受け取ったウィルコックス家では家族会議が開かれたが、ルースのメモは遺言書として不備でもあったし、彼女の意思は黙殺されることになった。
ルースは手術を受けるが経過は思わしくなく、ほどなくして亡くなってしまう。亡くなる直前ルースは看護婦に紙と鉛筆を頼み、「ハワーズ・エンド」をマーガレットに譲るとメモをしたためた。ルースの死後、病院からその手紙を受け取ったウィルコックス家では家族会議が開かれたが、ルースのメモは遺言書として不備でもあったし、彼女の意思は黙殺されることになった。 マーガレットとヘレンは週に一度の討論会の後、偶然街でヘンリーと会う。その時にヘレンはヘンリーにレナードの事について相談をする。傘の件の後、浮気を疑ったジャッキーの勘違いを正すためにレナードが再度シュレーゲル家を訪れる機会があり、姉妹は彼に好印象を持っていた。知的で繊細な事務員をしている青年が、仕事だけでなく知的活動においても十分な成果が上げられるようにという親切な友人としての相談だったが、立ち話でもあり、ヘンリーはレナードが勤める保険会社の悪い評判を聞いていたので早めに退職することを進言した。後に姉妹の助言を信じたレナードは会社を辞めるが、ヘンリーが破産すると明言した保険会社は潰れる事は無く、反対に転職先の銀行から業績悪化の為の人員整理の対象にされてしまう。これは全てヘンリー・ウィルコックスのせいだとヘレンは思うようになる。
マーガレットとヘレンは週に一度の討論会の後、偶然街でヘンリーと会う。その時にヘレンはヘンリーにレナードの事について相談をする。傘の件の後、浮気を疑ったジャッキーの勘違いを正すためにレナードが再度シュレーゲル家を訪れる機会があり、姉妹は彼に好印象を持っていた。知的で繊細な事務員をしている青年が、仕事だけでなく知的活動においても十分な成果が上げられるようにという親切な友人としての相談だったが、立ち話でもあり、ヘンリーはレナードが勤める保険会社の悪い評判を聞いていたので早めに退職することを進言した。後に姉妹の助言を信じたレナードは会社を辞めるが、ヘンリーが破産すると明言した保険会社は潰れる事は無く、反対に転職先の銀行から業績悪化の為の人員整理の対象にされてしまう。これは全てヘンリー・ウィルコックスのせいだとヘレンは思うようになる。 ヘレンはヘンリーを嫌っていたが、逆にマーガレットは新しい家を探すのに彼を頼り、ヘンリーも彼女の力になることに喜びを見出し始めた。新しい家が見つかった頃、ヘンリーはマーガレットに求婚し、マーガレットも快く受けた。ヘンリーの子供たちは若い後妻候補に「ハワーズ・エンド」を獲られてしまうと危機感を募らせ、マーガレットは妹のヘンリー嫌いに難儀する。更にはレナードを巡るヘレンの対応の過程でヘンリーとジャッキーの意外な関係も暴かれることになり、それはヘンリーとマーガレットの関係、そしてウィルコックス家の尊厳にもかかわる事件へと発展していく・・。
ヘレンはヘンリーを嫌っていたが、逆にマーガレットは新しい家を探すのに彼を頼り、ヘンリーも彼女の力になることに喜びを見出し始めた。新しい家が見つかった頃、ヘンリーはマーガレットに求婚し、マーガレットも快く受けた。ヘンリーの子供たちは若い後妻候補に「ハワーズ・エンド」を獲られてしまうと危機感を募らせ、マーガレットは妹のヘンリー嫌いに難儀する。更にはレナードを巡るヘレンの対応の過程でヘンリーとジャッキーの意外な関係も暴かれることになり、それはヘンリーとマーガレットの関係、そしてウィルコックス家の尊厳にもかかわる事件へと発展していく・・。*
 まぁ、あらすじを書いていてもエピソードの順番がどうだったか分からなくなってしまう感じなんだけど、登場人物の心情も少しあやふやな感じもある。マーガレットとヘンリーの恋の進展もいつ始まったのかもわからないし、なにしろレナードの気持ちが分からない。あんなにジャッキーを疎ましく思っていた彼が、何故にずるずると同棲から結婚へと進んでしまったのか? どうやら小説を読めばもう少し分かるみたいだけど、映画は2回観たけど不可解だった。レナード・バストは映画ではただの厄介な青年でしかない。最後に彼は「ハワーズ・エンド」にやって来るんだけど、マーガレットに陳謝に来たはずなのに、最後の最後に一番ひどい結果をもたらしてしまうんだ。そしてヘレンもマーガレットにとっては身内だけにもっと厄介な存在かも知れない。映画のその後を考えると、彼女が一番疫病神だな。
まぁ、あらすじを書いていてもエピソードの順番がどうだったか分からなくなってしまう感じなんだけど、登場人物の心情も少しあやふやな感じもある。マーガレットとヘンリーの恋の進展もいつ始まったのかもわからないし、なにしろレナードの気持ちが分からない。あんなにジャッキーを疎ましく思っていた彼が、何故にずるずると同棲から結婚へと進んでしまったのか? どうやら小説を読めばもう少し分かるみたいだけど、映画は2回観たけど不可解だった。レナード・バストは映画ではただの厄介な青年でしかない。最後に彼は「ハワーズ・エンド」にやって来るんだけど、マーガレットに陳謝に来たはずなのに、最後の最後に一番ひどい結果をもたらしてしまうんだ。そしてヘレンもマーガレットにとっては身内だけにもっと厄介な存在かも知れない。映画のその後を考えると、彼女が一番疫病神だな。 「ハワーズ・エンド」が結局は元の持ち主ルースの望んだようになって、この物語が人の世の不思議さを描き出したようになってるけど、色々と無理くりな設定、展開が感じられて感服することは無かったな。お薦め度は★三つ半。繊細な心理状態を見事に表現した主演の二人の演技に★半分おまけです。
「ハワーズ・エンド」が結局は元の持ち主ルースの望んだようになって、この物語が人の世の不思議さを描き出したようになってるけど、色々と無理くりな設定、展開が感じられて感服することは無かったな。お薦め度は★三つ半。繊細な心理状態を見事に表現した主演の二人の演技に★半分おまけです。 1992年のアカデミー賞で作品賞他にノミネート。主演女優賞(トンプソン)、脚色賞(ルース・プラワー・ジャブヴァーラ)、そして美術賞を受賞した。
1992年のアカデミー賞で作品賞他にノミネート。主演女優賞(トンプソン)、脚色賞(ルース・プラワー・ジャブヴァーラ)、そして美術賞を受賞した。・お薦め度【★★★★=シリアスドラマの好きな、友達にも薦めて】 

■ YouTube Selection (予告編)
■ Information&Addition
※gooさんからの告知です:<「トラックバック機能」について、ご利用者数の減少およびスパム利用が多いことから、送受信ともに2017年11月27日(月)にて機能の提供を終了させていただきます>[2017.11.12]
●2007年10月にブログ名を「SCREEN」から「テアトル十瑠」に変えました。
●2021年8月にブログ名を「テアトル十瑠」から「テアトル十瑠 neo」に暫定的に変えました。姉妹ブログ「つれづる十瑠」に綴っていた日々の雑感をこちらで継続することにしたからです。
●2025年2月にブログ名を「テアトル十瑠」から「::: テアトル十瑠 :::」に変えました。
●コメントは大歓迎。但し、記事に関係ないモノ、不適切と判断したモノは予告無しに削除させていただきます。
◆【著作権について】 当ブログにおける私の著作権の範囲はテキスト部分についてのみで、また他サイト等からの引用については原則< >で囲んでおります。 ★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)
★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)
*
●映画の紹介、感想、関連コラム、その他諸々綴っています。
●2007年10月にブログ名を「SCREEN」から「テアトル十瑠」に変えました。
●2021年8月にブログ名を「テアトル十瑠」から「テアトル十瑠 neo」に暫定的に変えました。姉妹ブログ「つれづる十瑠」に綴っていた日々の雑感をこちらで継続することにしたからです。
●2025年2月にブログ名を「テアトル十瑠」から「::: テアトル十瑠 :::」に変えました。
●コメントは大歓迎。但し、記事に関係ないモノ、不適切と判断したモノは予告無しに削除させていただきます。
*
◆【管理人について】
HNの十瑠(ジュール)は、あるサイトに登録したペンネーム「鈴木十瑠」の名前部分をとったもの。由来は少年時代に沢山の愛読書を提供してくれたフランスの作家「ジュール・ヴェルヌ」を捩ったものです。
◆【著作権について】 当ブログにおける私の著作権の範囲はテキスト部分についてのみで、また他サイト等からの引用については原則< >で囲んでおります。
*
 ★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)
★
バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)
























