(1953/ビリー・ワイルダー監督・製作・共同脚本/ウィリアム・ホールデン、ドン・テイラー、オットー・プレミンジャー、ロバート・ストラウス、ハーヴェイ・レンベック、ネヴィル・ブランド、ピーター・グレイヴス、シグ・ルーマン、リチャード・アードマン/119分)
お茶の間のテレビ(今でいう地上波)の吹き替えで洋画を観ていた頃、ワイルダーの名作と知りながらもなかなか放映されずに待ち続けた記憶がある映画だ。それでも何とか十代のうちに観たはずだが、とにかく昔の話なので今回が何十年ぶりかもわからないし、何回目なのかも覚えていない。多分2回目か3回目だろう。ドイツ軍の捕虜収容所が舞台の戦争の話と思って観ていたら、戦争云々よりもスパイが絡む謎解きサスペンスが面白かったという印象が残っている。さて、モノクロ・スタンダードサイズのスクリーンに繰り広げられるドラマは自粛中のモヤモヤを解消してくれるだろうか・・。
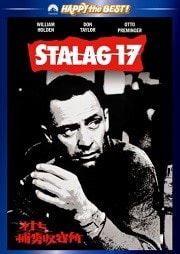 オープニングは鉄条網の柵の横をシェパードを連れて夜の警戒をしているドイツ兵の姿。そして捕虜用兵舎がずらりと並んでいる第十七捕虜収容所の遠景だ。最初にロングショットを入れておくというのが如何にもワイルダーらしいが、その後ナレーションで物語が始まるというのもワイルダーらしい。
オープニングは鉄条網の柵の横をシェパードを連れて夜の警戒をしているドイツ兵の姿。そして捕虜用兵舎がずらりと並んでいる第十七捕虜収容所の遠景だ。最初にロングショットを入れておくというのが如何にもワイルダーらしいが、その後ナレーションで物語が始まるというのもワイルダーらしい。
語るのはC・H・クックと名乗る男。後で分かるが、この男はW・ホールデン扮するセフトン軍曹の相棒でなにかと補助をしてくれる弟分のような存在のクッキーの事だった。その彼がかつてドイツの捕虜収容所にいた頃の思い出を語っているという設定になっている。【原題:STALAG 17】
『戦争映画と言えば航空隊か潜水艦、或いはゲリラ戦の話ばかりでうんざりする。捕虜を描いた映画が観たいんだが、実は俺は乗っていた戦闘機をドイツ軍に撃墜されて1943年から2年半ほど捕虜収容所にいたんだ。その頃連合国の捕虜は4万人ほどいて、俺がいたドナウ川の近くにあった第十七捕虜収容所には630人くらい居た。収容所には敵側のスパイも居て色々ともめ事もあったんだ。あれは44年のクリスマス前の事だったか、同じ第4兵舎のアメリカ兵二人が脱走しようとしていたんだが・・・』
いきなり脱走のシーンになるが、ストーブをどけた後の床に穴が開いているというのは後年の「大脱走 (1963)」と同じだった。高床式の床下に潜り込んで、消灯後の共同洗面所まで行き、そこの簀の子の様な板を捲ると竪穴があり更に収容所の敷地外まで届いている横穴を這って行くのだ。この穴を伝って脱走するというのも「大脱走」と同じだった。ところが、これでひと安心と二人が立ち上がった所で前には機関銃を構えたドイツ兵が。あえなくハチの巣になる二人。兵舎の中で息を殺していた捕虜たちの耳にも銃声が聞こえてくる。
『何故だ?』
まるで待ち伏せしていたかのようなあっけない結末に驚く彼らだった。
第4兵舎にはおよそ70人のアメリカ兵がいるが全員空軍の軍曹らしい。
選挙で選ばれたであろうリーダーのホフィ(アードマン)と警務係のプライス(グレイブス)、血の気の多いデューク(ブランド)の三人が脱走の計画者の様である。
脱走のあった夜、二人が兵舎を出て行った後、セフトンはこの計画が失敗すると賭けを持ちかける。掛けたのはタバコ。その場にいた彼以外の全員が縁起の悪いことを言うなと成功に札をあげるが結果は前述の通り。デュークとセフトンは一発触発の状態になった。
セフトンは言った。
『脱走してなんになる。成功したって、また太平洋戦線へ送られるだけだ。運が良ければ今度は日本軍の捕虜になるかも知れん。俺はごめんだね。そんなに英雄になりたいのか。俺はそんな事よりもここでなるべく気楽に過ごしたい。それだけだ』
セフトンは他の兵隊達とは一線を画していた。
一見悲観論者に見えるが、彼の荷物箱の中身は綺麗に整理されていた。ストーブが脱走のカムフラージュに使われたので撤去されることになり、最後の温かい食事だとセフトンは目玉焼きを一人作って食べた。デュークには仲間を殺したドイツ人と取引したのかとなじられたがこう反論した。
『俺がココにやって来た時すぐに毛布と靴下を盗まれた。頼れるのは自分だけだと知った。だから例えドイツ人相手でも必要ならば取引もする』
セフトンは金儲けの才にも長けていた。
土日にはネズミを馬に見立てた競馬場を作って賭場を開くし、密造酒を作って煙草と交換したりする。少し離れた兵舎にロシアの女性兵士の捕虜が来た時には望遠鏡を作って有料で覗かせたりした。そんな事でせしめた煙草をドイツ兵との闇取引に使うのだ。それがまたデューク達の神経を逆なでする事になった。
セフトンに対するスパイ疑惑は燻っていたが、クリスマス直前についに爆発する事件が発生する。
新たに捕虜として連行されてきたダンパー中尉と軍曹の二人が、少し前のドイツ軍の弾薬列車爆破事件の実行者であり、その事が又してもドイツ軍に知られてしまったからだ。二人が事件を起した事は第4兵舎以外の人間は知らないはず。捕虜収容所の所長自ら中尉を連行に来て、これから拷問が始まると分かった捕虜たちはついにセフトンをリンチにかけるのだった・・・。
ドナルド・ビーヴァン、エドモンド・トルチンスキー共作戯曲のブロードウェイの舞台劇が元ネタだそうで、確かにサスペンスだけでなく捕虜たちの人間模様も描かれていて戦争映画の範疇に入れても違和感は無さそうである。
コメディリリーフを担当するのが、漫才コンビのようなアニマル(ストラウス)とハリー(レンベック)の二人。
その二人と何かと絡む第4兵舎担当のドイツ兵シュルツ軍曹(ルーマン)もユーモラスに描かれていた。スパイとの連絡役だからにっくき奴だが人間味が少し滲むシーンもあった。
その他、機械に強い金髪のブロンディとか、戦争体験から心の病におかされているジョーイ、各棟にニュースや郵便物等の配信、配達をする捕虜の兵隊などなど。
ダンパー中尉には「花嫁の父」でリズ・テイラーのフィアンセになったドンテイラー。
そして、収容所のシェルバッハ所長に扮したのは映画監督としても名高いオットー・プレミンジャーだった。冷酷なドイツ人将校を完璧に演じていたが、彼自身はオーストリア系のユダヤ人だそうである。
お薦め度は★四つ半。
終盤にはスパイが誰なのかもハッキリしてセフトンの容疑は晴れるし、ラストで中尉も無事に脱走出来てスカッとする。
1953年のアカデミー賞では監督賞、主演男優賞(ホールデン)、助演男優賞(ストラウス)にノミネートされ、ホールデンが初受賞したそうだ。
TVシリーズもあったはずと思っていたが、深夜放送しかされていなかったその番組は「0012捕虜収容所」というタイトルで、むしろ「大脱走」の影響でつくられた番組らしい。深夜帯での放送だったので当時子供だった僕は観ていない。
▼(ネタバレ注意)
最後にナチスの親衛隊に引き渡されそうになったダンパー中尉と共に脱走するのはセフトンだ。スパイを一人で暴き、危険な任務も引き受けるセフトンに、今までスパイと疑っていた連中も心の中で喝采を上げていたに違いない。宿舎のベッドの上でクッキーが口笛で鳴らした『♪ジョニーが凱旋するとき』がカッコいい。
戦争云々よりもスパイが絡む謎解きサスペンスが面白かったと書いているけど、実はスパイが誰だったか完全に忘れていた。
まさかTV「スパイ大作戦」のリーダー、フェルプス君だったとはねぇ~。
▲(解除)
お茶の間のテレビ(今でいう地上波)の吹き替えで洋画を観ていた頃、ワイルダーの名作と知りながらもなかなか放映されずに待ち続けた記憶がある映画だ。それでも何とか十代のうちに観たはずだが、とにかく昔の話なので今回が何十年ぶりかもわからないし、何回目なのかも覚えていない。多分2回目か3回目だろう。ドイツ軍の捕虜収容所が舞台の戦争の話と思って観ていたら、戦争云々よりもスパイが絡む謎解きサスペンスが面白かったという印象が残っている。さて、モノクロ・スタンダードサイズのスクリーンに繰り広げられるドラマは自粛中のモヤモヤを解消してくれるだろうか・・。
*
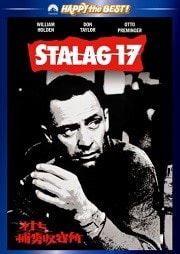 オープニングは鉄条網の柵の横をシェパードを連れて夜の警戒をしているドイツ兵の姿。そして捕虜用兵舎がずらりと並んでいる第十七捕虜収容所の遠景だ。最初にロングショットを入れておくというのが如何にもワイルダーらしいが、その後ナレーションで物語が始まるというのもワイルダーらしい。
オープニングは鉄条網の柵の横をシェパードを連れて夜の警戒をしているドイツ兵の姿。そして捕虜用兵舎がずらりと並んでいる第十七捕虜収容所の遠景だ。最初にロングショットを入れておくというのが如何にもワイルダーらしいが、その後ナレーションで物語が始まるというのもワイルダーらしい。語るのはC・H・クックと名乗る男。後で分かるが、この男はW・ホールデン扮するセフトン軍曹の相棒でなにかと補助をしてくれる弟分のような存在のクッキーの事だった。その彼がかつてドイツの捕虜収容所にいた頃の思い出を語っているという設定になっている。【原題:STALAG 17】
『戦争映画と言えば航空隊か潜水艦、或いはゲリラ戦の話ばかりでうんざりする。捕虜を描いた映画が観たいんだが、実は俺は乗っていた戦闘機をドイツ軍に撃墜されて1943年から2年半ほど捕虜収容所にいたんだ。その頃連合国の捕虜は4万人ほどいて、俺がいたドナウ川の近くにあった第十七捕虜収容所には630人くらい居た。収容所には敵側のスパイも居て色々ともめ事もあったんだ。あれは44年のクリスマス前の事だったか、同じ第4兵舎のアメリカ兵二人が脱走しようとしていたんだが・・・』
いきなり脱走のシーンになるが、ストーブをどけた後の床に穴が開いているというのは後年の「大脱走 (1963)」と同じだった。高床式の床下に潜り込んで、消灯後の共同洗面所まで行き、そこの簀の子の様な板を捲ると竪穴があり更に収容所の敷地外まで届いている横穴を這って行くのだ。この穴を伝って脱走するというのも「大脱走」と同じだった。ところが、これでひと安心と二人が立ち上がった所で前には機関銃を構えたドイツ兵が。あえなくハチの巣になる二人。兵舎の中で息を殺していた捕虜たちの耳にも銃声が聞こえてくる。
『何故だ?』
まるで待ち伏せしていたかのようなあっけない結末に驚く彼らだった。
第4兵舎にはおよそ70人のアメリカ兵がいるが全員空軍の軍曹らしい。
選挙で選ばれたであろうリーダーのホフィ(アードマン)と警務係のプライス(グレイブス)、血の気の多いデューク(ブランド)の三人が脱走の計画者の様である。
脱走のあった夜、二人が兵舎を出て行った後、セフトンはこの計画が失敗すると賭けを持ちかける。掛けたのはタバコ。その場にいた彼以外の全員が縁起の悪いことを言うなと成功に札をあげるが結果は前述の通り。デュークとセフトンは一発触発の状態になった。
セフトンは言った。
『脱走してなんになる。成功したって、また太平洋戦線へ送られるだけだ。運が良ければ今度は日本軍の捕虜になるかも知れん。俺はごめんだね。そんなに英雄になりたいのか。俺はそんな事よりもここでなるべく気楽に過ごしたい。それだけだ』
セフトンは他の兵隊達とは一線を画していた。
一見悲観論者に見えるが、彼の荷物箱の中身は綺麗に整理されていた。ストーブが脱走のカムフラージュに使われたので撤去されることになり、最後の温かい食事だとセフトンは目玉焼きを一人作って食べた。デュークには仲間を殺したドイツ人と取引したのかとなじられたがこう反論した。
『俺がココにやって来た時すぐに毛布と靴下を盗まれた。頼れるのは自分だけだと知った。だから例えドイツ人相手でも必要ならば取引もする』
セフトンは金儲けの才にも長けていた。
土日にはネズミを馬に見立てた競馬場を作って賭場を開くし、密造酒を作って煙草と交換したりする。少し離れた兵舎にロシアの女性兵士の捕虜が来た時には望遠鏡を作って有料で覗かせたりした。そんな事でせしめた煙草をドイツ兵との闇取引に使うのだ。それがまたデューク達の神経を逆なでする事になった。
セフトンに対するスパイ疑惑は燻っていたが、クリスマス直前についに爆発する事件が発生する。
新たに捕虜として連行されてきたダンパー中尉と軍曹の二人が、少し前のドイツ軍の弾薬列車爆破事件の実行者であり、その事が又してもドイツ軍に知られてしまったからだ。二人が事件を起した事は第4兵舎以外の人間は知らないはず。捕虜収容所の所長自ら中尉を連行に来て、これから拷問が始まると分かった捕虜たちはついにセフトンをリンチにかけるのだった・・・。
*
ドナルド・ビーヴァン、エドモンド・トルチンスキー共作戯曲のブロードウェイの舞台劇が元ネタだそうで、確かにサスペンスだけでなく捕虜たちの人間模様も描かれていて戦争映画の範疇に入れても違和感は無さそうである。
コメディリリーフを担当するのが、漫才コンビのようなアニマル(ストラウス)とハリー(レンベック)の二人。
その二人と何かと絡む第4兵舎担当のドイツ兵シュルツ軍曹(ルーマン)もユーモラスに描かれていた。スパイとの連絡役だからにっくき奴だが人間味が少し滲むシーンもあった。
その他、機械に強い金髪のブロンディとか、戦争体験から心の病におかされているジョーイ、各棟にニュースや郵便物等の配信、配達をする捕虜の兵隊などなど。
ダンパー中尉には「花嫁の父」でリズ・テイラーのフィアンセになったドンテイラー。
そして、収容所のシェルバッハ所長に扮したのは映画監督としても名高いオットー・プレミンジャーだった。冷酷なドイツ人将校を完璧に演じていたが、彼自身はオーストリア系のユダヤ人だそうである。
お薦め度は★四つ半。
終盤にはスパイが誰なのかもハッキリしてセフトンの容疑は晴れるし、ラストで中尉も無事に脱走出来てスカッとする。
1953年のアカデミー賞では監督賞、主演男優賞(ホールデン)、助演男優賞(ストラウス)にノミネートされ、ホールデンが初受賞したそうだ。
TVシリーズもあったはずと思っていたが、深夜放送しかされていなかったその番組は「0012捕虜収容所」というタイトルで、むしろ「大脱走」の影響でつくられた番組らしい。深夜帯での放送だったので当時子供だった僕は観ていない。
▼(ネタバレ注意)
最後にナチスの親衛隊に引き渡されそうになったダンパー中尉と共に脱走するのはセフトンだ。スパイを一人で暴き、危険な任務も引き受けるセフトンに、今までスパイと疑っていた連中も心の中で喝采を上げていたに違いない。宿舎のベッドの上でクッキーが口笛で鳴らした『♪ジョニーが凱旋するとき』がカッコいい。
戦争云々よりもスパイが絡む謎解きサスペンスが面白かったと書いているけど、実はスパイが誰だったか完全に忘れていた。
まさかTV「スパイ大作戦」のリーダー、フェルプス君だったとはねぇ~。
▲(解除)
・お薦め度【★★★★★=大いに見るべし】 




















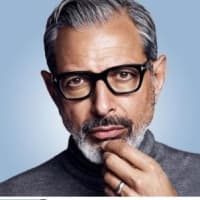



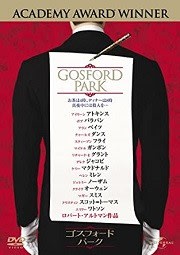









十瑠さんの感想と私の感想を比べてみたら、当時私が内容を理解してたのかすら怪しい気がしてきました(笑)
戦争ものなのにコミカルで見やすい作品でしたよね。
「緩急」と言いますけど、コミカルな部分は緩の部分ですよね。
ちょっと馬鹿馬鹿しいくらいなシーンもありますが、あくまでも娯楽映画ですからソコは緩~く見て、サスペンスの積み重ねを楽しみました。