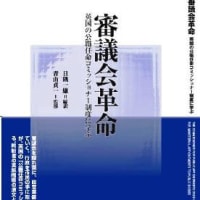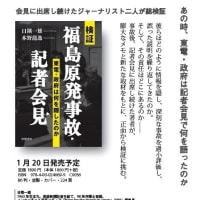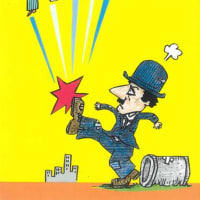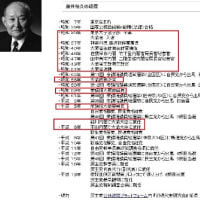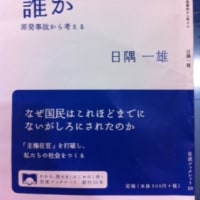皆さんは、いま、日本で、銀行などの金融機関が年間の取引を「疑わしい取引」だとして、金融庁に通報しているかご存じだろうか?そして、そのうちの何件が捜査機関に提供されているかを…。読売新聞は、日弁連が犯罪収益流通防止法案に反対していることを批判するが、ことはそう簡単ではないのだ…。
「疑わしい取引」としての届け出は年間9万8935件、捜査機関への提供は6万6812件である。これらは、捜査機関からの照会によるものは含まれていない。組織的犯罪防止法に規定のある「疑わしい取引」の届け出義務によるものだ。
この届け出義務は、FATF(資金洗浄に関する金融活動作業部会)という国際的政府間組織の勧告に基づくものだ(FATFのメンバーは33カ国・地域)。
日本で、この規定ができた1997年当初、疑わしい取引は麻薬関連に関するものを指していたため、年間数件ということもあった。しかし、2000年にはTAFTの審査があり、その結果、200件を超える犯罪に関するものについて届け出ることとなり、一気に増大し、1万件台(2002年)→4万件台(2003年)→9万件台(2004年)と急上昇している。
現在、政府が検討しているのは、この届け出義務を金融機関のみならず、弁護士や公認会計士、司法書士、不動産業者らにも拡大するというものだ。
読売が指摘するとおり、【日弁連は「弁護士から警察への依頼者密告制度だ。一般市民の弁護士への信頼を傷つける」として反対してきた】ため、【警察庁は、6月にまとめた法案概要のうち、弁護士の取り扱いを見直し、今回の案を示した】のは事実だ。
しかし、読売がいうように、
【弁護士法で規定される守秘義務の範囲は変わらない。刑事弁護や法律相談で得た情報は届け出義務から除外される。】
【弁護士以外の公認会計士などの情報は所管官庁経由でそのまま警察庁に上がるが、弁護士は日弁連に届け出る。日弁連が守秘義務に抵触しないかどうかなどを判断した上で警察庁に通知する。】
【弁護士以外の場合、立ち入り検査、義務違反に対する是正命令など、所管官庁や国家公安委員会の監督を受けるが、弁護士は国の監督を受けない。届け出ルールを含め日弁連の会則に委任する。】
からと言って、日弁連がこの法案を受け入れることは妥当なのだろうか?
新しい法律を設けるにあたっては、それを設ける必要性、いわゆる立法事実が必要になる。読売は、【国内では暴力団の勢力が衰えを見せない。海外の犯罪組織の動きも警戒しなければならない。テロや覚せい剤の密売など、北朝鮮の脅威もある。すでに主要国の多くが法整備を終えている。国際犯罪やテロ対策では各国の連携が重要だ。】と説明する。
しかし、【暴力団の勢力】が衰えないのは、警察にその気がないだけであり、本気で取り締まるつもりならば、幹部の動きをきちんと追うなどして、潰すことは可能なはずだ。国旗国歌の押しつけに反対する集会などにやたらと押し掛ける私服警官が行っている執拗な「捜査」を、暴力団対策に向ければ、あるいは、薬物犯罪などの金の流れを本気で追えば、比較的容易に暴力団を取り締まることはできるはずだ。
また、【海外の犯罪組織の動き】【テロや覚せい剤の密売など、北朝鮮の脅威】を日本の弁護士が報告しなければならないような状況だろうか?あるいは、日本の弁護士が報告できるような活動をしているのだろうか?
【主要国の多くが法整備を終えている】というが、実際に、弁護士が報告までしているところはわずかであり、「テロ」対策大国である米国は、提案すらしていない状況だ(ここ←参照)。各国弁護士会は、このシステムの異常さに一斉に反発しているのだ。読売の上記表現は「偽装」である。
そもそも、「守秘義務」は弁護士業務の大原則だ。
【依頼者は、秘密を守ってもらえると思うからこそ、安心して弁護士に本当のことを打ち明けることができるのですし、弁護士も、本当のことを打ち明けられるからこそ、依頼者のために十分な弁護活動をし、また、法律を守るようアドバイスすることができるのです。】(日弁連HP←クリック)
また、弁護士の職務の本質に反する。
時として【国を相手どって裁判をおこす弁護士は、当然のことながら、国家権力から独立した存在である必要があります。しかし、この法案により、警察への密告が義務づけられれば、弁護士の政府機関からの独立性は損なわれ、その職務の本質に反することになってしまいます】(上記HP)
そして、もう一つ、重大なことは、権力が常に「小さく生んで大きく育てようとする」ことだ。共謀罪で民主党案丸飲みを図った時もそうだった。とりあえず、民主党案で通過させて、改正すればいい。自民党幹部はそう本音を漏らした。
本法案も、当初は、弁護士業務への一定の配慮はあるだろう。しかし、数件だった金融機関による届け出も、FATFの何度かの審査で不十分との指摘を受け、法改正などが行われた結果、一気に十万件にまで増えた。弁護士の通報義務も拡大されるのは間違いない。
通報した人は、通報したことをクライアントに伝えてはいけないと定められている。あなたの知らないうちに顧問弁護士があなたのことを警察に売るかもしれない…。それもおそれがあるというだけで…。そして、警察はその情報をもとに、おそれがあるとして、あなたを逮捕するかもしれないのだ。そのとき、あなたは、なぜ、自分が逮捕されるような状況になったかを知ることは出来ない…。
読売新聞は、最後に【弁護士が指導的役割を発揮して不正資金に目を光らせれば、組織犯罪やテロの抑止効果は計り知れない】という。具体的にどう効果があるのか具体的な事例を上げて指摘してほしいもんだ!
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。
「疑わしい取引」としての届け出は年間9万8935件、捜査機関への提供は6万6812件である。これらは、捜査機関からの照会によるものは含まれていない。組織的犯罪防止法に規定のある「疑わしい取引」の届け出義務によるものだ。
この届け出義務は、FATF(資金洗浄に関する金融活動作業部会)という国際的政府間組織の勧告に基づくものだ(FATFのメンバーは33カ国・地域)。
日本で、この規定ができた1997年当初、疑わしい取引は麻薬関連に関するものを指していたため、年間数件ということもあった。しかし、2000年にはTAFTの審査があり、その結果、200件を超える犯罪に関するものについて届け出ることとなり、一気に増大し、1万件台(2002年)→4万件台(2003年)→9万件台(2004年)と急上昇している。
現在、政府が検討しているのは、この届け出義務を金融機関のみならず、弁護士や公認会計士、司法書士、不動産業者らにも拡大するというものだ。
読売が指摘するとおり、【日弁連は「弁護士から警察への依頼者密告制度だ。一般市民の弁護士への信頼を傷つける」として反対してきた】ため、【警察庁は、6月にまとめた法案概要のうち、弁護士の取り扱いを見直し、今回の案を示した】のは事実だ。
しかし、読売がいうように、
【弁護士法で規定される守秘義務の範囲は変わらない。刑事弁護や法律相談で得た情報は届け出義務から除外される。】
【弁護士以外の公認会計士などの情報は所管官庁経由でそのまま警察庁に上がるが、弁護士は日弁連に届け出る。日弁連が守秘義務に抵触しないかどうかなどを判断した上で警察庁に通知する。】
【弁護士以外の場合、立ち入り検査、義務違反に対する是正命令など、所管官庁や国家公安委員会の監督を受けるが、弁護士は国の監督を受けない。届け出ルールを含め日弁連の会則に委任する。】
からと言って、日弁連がこの法案を受け入れることは妥当なのだろうか?
新しい法律を設けるにあたっては、それを設ける必要性、いわゆる立法事実が必要になる。読売は、【国内では暴力団の勢力が衰えを見せない。海外の犯罪組織の動きも警戒しなければならない。テロや覚せい剤の密売など、北朝鮮の脅威もある。すでに主要国の多くが法整備を終えている。国際犯罪やテロ対策では各国の連携が重要だ。】と説明する。
しかし、【暴力団の勢力】が衰えないのは、警察にその気がないだけであり、本気で取り締まるつもりならば、幹部の動きをきちんと追うなどして、潰すことは可能なはずだ。国旗国歌の押しつけに反対する集会などにやたらと押し掛ける私服警官が行っている執拗な「捜査」を、暴力団対策に向ければ、あるいは、薬物犯罪などの金の流れを本気で追えば、比較的容易に暴力団を取り締まることはできるはずだ。
また、【海外の犯罪組織の動き】【テロや覚せい剤の密売など、北朝鮮の脅威】を日本の弁護士が報告しなければならないような状況だろうか?あるいは、日本の弁護士が報告できるような活動をしているのだろうか?
【主要国の多くが法整備を終えている】というが、実際に、弁護士が報告までしているところはわずかであり、「テロ」対策大国である米国は、提案すらしていない状況だ(ここ←参照)。各国弁護士会は、このシステムの異常さに一斉に反発しているのだ。読売の上記表現は「偽装」である。
そもそも、「守秘義務」は弁護士業務の大原則だ。
【依頼者は、秘密を守ってもらえると思うからこそ、安心して弁護士に本当のことを打ち明けることができるのですし、弁護士も、本当のことを打ち明けられるからこそ、依頼者のために十分な弁護活動をし、また、法律を守るようアドバイスすることができるのです。】(日弁連HP←クリック)
また、弁護士の職務の本質に反する。
時として【国を相手どって裁判をおこす弁護士は、当然のことながら、国家権力から独立した存在である必要があります。しかし、この法案により、警察への密告が義務づけられれば、弁護士の政府機関からの独立性は損なわれ、その職務の本質に反することになってしまいます】(上記HP)
そして、もう一つ、重大なことは、権力が常に「小さく生んで大きく育てようとする」ことだ。共謀罪で民主党案丸飲みを図った時もそうだった。とりあえず、民主党案で通過させて、改正すればいい。自民党幹部はそう本音を漏らした。
本法案も、当初は、弁護士業務への一定の配慮はあるだろう。しかし、数件だった金融機関による届け出も、FATFの何度かの審査で不十分との指摘を受け、法改正などが行われた結果、一気に十万件にまで増えた。弁護士の通報義務も拡大されるのは間違いない。
通報した人は、通報したことをクライアントに伝えてはいけないと定められている。あなたの知らないうちに顧問弁護士があなたのことを警察に売るかもしれない…。それもおそれがあるというだけで…。そして、警察はその情報をもとに、おそれがあるとして、あなたを逮捕するかもしれないのだ。そのとき、あなたは、なぜ、自分が逮捕されるような状況になったかを知ることは出来ない…。
読売新聞は、最後に【弁護士が指導的役割を発揮して不正資金に目を光らせれば、組織犯罪やテロの抑止効果は計り知れない】という。具体的にどう効果があるのか具体的な事例を上げて指摘してほしいもんだ!
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。