
4/26(月)、「ナント・なら応援団」(南都銀行退職者によるボランティアグループ)の活動を支援するため、大安寺(奈良市大安寺2-18-1)を訪れて、驚いた。ナラノヤエザクラ(奈良の八重桜)が咲き始めていたのである。お寺の方によると、縁あって、東大寺知足院の「ナラノヤエザクラ」を接ぎ木されたものだというから、これは本物である。まだ3分咲きだったが、これから順次開花していくことだろう。おそらく森林インストラクターのひろこさんも、ご存じないだろう。
※お寺の公式サイト
http://www.daianji.or.jp/
この桜をご存じない方のために、Wikipedia(ナラノヤエザクラ)を引用しながら、私がこの日に撮った写真を紹介する。《ナラノヤエザクラ(奈良の八重桜)もしくはナラヤエザクラ(奈良八重桜)(学名: Prunus verecunda 'Antiqua')はサクラの栽培品種の一つ。オクヤマザクラ(カスミザクラ)の変種で、4月下旬から5月上旬に開花する八重桜である。他の桜に比べて開花が遅く、八重桜の中では小ぶりな花をつけるのが特徴である》。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%A9%E3%83%8E%E3%83%A4%E3%82%A8%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%83%A9

《ナラノヤエザクラは『詞花集』の伊勢大輔の和歌により著名になった八重桜である。『詞花集』には「一条院御時、奈良の八重桜を人のたてまつりて侍けるを、そのおり御前に侍ければ、その花をたまひて、歌よめとおほせられければよめる」とあり、伊勢大輔は「いにしへの奈良のみやこの八重ざくらけふ九重ににほひぬるかな」と詠んでいる。一条院御時から数えてちょうど1000年目をむかえている。奈良の文化の一片を今に伝える桜である。奈良を代表する花として、奈良県花、奈良市章・市花に用いられる》。
《「奈良の八重桜」はれっきとした八重桜の一品種であり「奈良に植わっている八重桜」の総称ではない。ナラノヤエザクラは落葉高木であり、カスミザクラが重弁化した変種であると考えられている。ナラノヤエザクラの繁殖力は極めて弱く、殖やすのが非常に難しい。樹勢は弱く、寿命も短い。後述する「知足院奈良八重桜」も1923年に天然記念物に指定された樹は既に枯れてしまっている》。

《芽は赤紫色を帯びた褐色をしている。芽は最終的に、長さ 5 cmから 9 cm、幅 2.5 cmから 5 cm に成長した葉になる》《葉身の全体の形は長楕円状倒卵形で、葉身の先端は尾状鋭尖形をしている。葉身の基部は円形もしくは心臓形(ハート型)で、ほとんどが円形である。葉身の周辺にある鋸歯は重鋸歯(大きなギザギザにさらに小さなギザギザあること)で先端は鋭く尖っている(鋭尖形)。葉身の表側は暗い黄緑色をしており、光沢は無く、表側の全面に毛がまばらに存在する。葉身の裏側は白っぽい黄緑色をしており、葉脈の上に毛が生えている。葉柄には伏せていない毛(開出毛)が生えており、上端から少し下に濃い紅紫色の蜜腺が存在する》。
《花序は散房花序をしており 2 - 4 花からなる。鱗片葉は紅紫色、苞は緑色で基部は紅紫色をしている。花柄と小花柄には白色の開出毛が存在する。萼筒は長鐘形をしており、外側に毛がまばらに存在する。萼裂片は内側外側とも毛がないが縁に縁毛がある。花弁は「奈良市史 自然編」によると 22 枚から 79 枚、「新日本の桜」によると 30 枚から 36 枚とされる》。

《花弁は楕円形で先端は二つに深く裂けたいわゆる「桜の花びら」の形をしている。花弁の色は淡い紅色である。雄しべは「奈良市史 自然編」によると 10 本から 42 本、「新日本の桜」によると 32 本から 45 本とされる。雌しべは 1 本から 4 本である》。

《ナラノヤエザクラはカスミザクラが重弁化した品種であるため、八重桜にしては小ぶりで清楚な花を咲かせる。花は 4 月下旬から 5 月上旬に咲き、ゴールデンウィークの頃に満開となる。他の八重桜と違い、ナラノヤエザクラには果実がよく実る。ただし、果実は若いときに枝から落ちることが多く、残って成熟する果実は珍しい。ナラノヤエザクラの花には複数の雌しべがあるため、果実もしばしば複数個くっついた状態になっている。果実は黒く熟し、食べると苦味と酸味がある》。

《奈良の旧都に美しい八重桜があった事実は『詞花和歌集』『袋草子』『沙石集』『徒然草』などの文献に、また江戸時代の図譜として残されている。江戸時代初期、1678年に出版された『奈良名所八重桜』は奈良の八重桜について記述している。『奈良名所八重桜』は名所案内記に名をかりたフィクションであり、東大寺、興福寺はじめ作り話が多い》。

《ナラノヤエザクラは伊勢大輔の詠んだ和歌により名高い。いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に 匂ひぬるかな 『七大寺巡礼私記』には、奈良の都の八重桜が植わっていた場所と開花時期が記載されている。記載によると、奈良の八重桜は興福寺の東円堂にあり、他の全ての桜が散ってから咲く遅咲き桜であったとされる》。

《1922 年に東京大学の植物学者であった三好学が東大寺知足院の裏山に植わっていた特徴ある八重桜を岡本勇治の案内で視察(調査)した(三好の岡本への追悼文より)。小清水は1922年4月に三好が発見したとするが、三好の論文の掲載号はこの年の1月である。三好は論文で産地として「京都と奈良」をあげている。ナラノヤエザクラは岡本勇治が大正10年頃(この年に三好が来県しているので早い月か前年)に天然記念物指定申請をおこなっている。申請は知足院のほか師範学校、春日神社(現春日大社)の三樹である。大阪朝日新聞大和版にも関連の記事がある。この「知足院の奈良八重桜」は1923年に国の天然記念物に指定されている》。

《ナラノヤエザクラは奈良を代表する花として1968年には奈良県花に制定された。さらに1998年には奈良市花に制定されている》。
小さくて可憐なこの桜は「知る人ぞ知る」桜であったが、最近は奈良女子大や今西清兵衛商店、植嶋などの「奈良八重桜プロジェクト」で、次第にメジャーな存在になってきた。
http://www.nara-wu.ac.jp/liaison/product/narayae.html
東大寺、奈良公園、奈良新公会堂、奈良県庁東駐車場、奈良女子大、若草山麓、春日大社、奈良ホテルなどとともに、大安寺のナラノヤエザクラも、ぜひ楽しんでいただきたい。
※お寺の公式サイト
http://www.daianji.or.jp/
この桜をご存じない方のために、Wikipedia(ナラノヤエザクラ)を引用しながら、私がこの日に撮った写真を紹介する。《ナラノヤエザクラ(奈良の八重桜)もしくはナラヤエザクラ(奈良八重桜)(学名: Prunus verecunda 'Antiqua')はサクラの栽培品種の一つ。オクヤマザクラ(カスミザクラ)の変種で、4月下旬から5月上旬に開花する八重桜である。他の桜に比べて開花が遅く、八重桜の中では小ぶりな花をつけるのが特徴である》。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%A9%E3%83%8E%E3%83%A4%E3%82%A8%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%83%A9

《ナラノヤエザクラは『詞花集』の伊勢大輔の和歌により著名になった八重桜である。『詞花集』には「一条院御時、奈良の八重桜を人のたてまつりて侍けるを、そのおり御前に侍ければ、その花をたまひて、歌よめとおほせられければよめる」とあり、伊勢大輔は「いにしへの奈良のみやこの八重ざくらけふ九重ににほひぬるかな」と詠んでいる。一条院御時から数えてちょうど1000年目をむかえている。奈良の文化の一片を今に伝える桜である。奈良を代表する花として、奈良県花、奈良市章・市花に用いられる》。
《「奈良の八重桜」はれっきとした八重桜の一品種であり「奈良に植わっている八重桜」の総称ではない。ナラノヤエザクラは落葉高木であり、カスミザクラが重弁化した変種であると考えられている。ナラノヤエザクラの繁殖力は極めて弱く、殖やすのが非常に難しい。樹勢は弱く、寿命も短い。後述する「知足院奈良八重桜」も1923年に天然記念物に指定された樹は既に枯れてしまっている》。

《芽は赤紫色を帯びた褐色をしている。芽は最終的に、長さ 5 cmから 9 cm、幅 2.5 cmから 5 cm に成長した葉になる》《葉身の全体の形は長楕円状倒卵形で、葉身の先端は尾状鋭尖形をしている。葉身の基部は円形もしくは心臓形(ハート型)で、ほとんどが円形である。葉身の周辺にある鋸歯は重鋸歯(大きなギザギザにさらに小さなギザギザあること)で先端は鋭く尖っている(鋭尖形)。葉身の表側は暗い黄緑色をしており、光沢は無く、表側の全面に毛がまばらに存在する。葉身の裏側は白っぽい黄緑色をしており、葉脈の上に毛が生えている。葉柄には伏せていない毛(開出毛)が生えており、上端から少し下に濃い紅紫色の蜜腺が存在する》。
《花序は散房花序をしており 2 - 4 花からなる。鱗片葉は紅紫色、苞は緑色で基部は紅紫色をしている。花柄と小花柄には白色の開出毛が存在する。萼筒は長鐘形をしており、外側に毛がまばらに存在する。萼裂片は内側外側とも毛がないが縁に縁毛がある。花弁は「奈良市史 自然編」によると 22 枚から 79 枚、「新日本の桜」によると 30 枚から 36 枚とされる》。

《花弁は楕円形で先端は二つに深く裂けたいわゆる「桜の花びら」の形をしている。花弁の色は淡い紅色である。雄しべは「奈良市史 自然編」によると 10 本から 42 本、「新日本の桜」によると 32 本から 45 本とされる。雌しべは 1 本から 4 本である》。

《ナラノヤエザクラはカスミザクラが重弁化した品種であるため、八重桜にしては小ぶりで清楚な花を咲かせる。花は 4 月下旬から 5 月上旬に咲き、ゴールデンウィークの頃に満開となる。他の八重桜と違い、ナラノヤエザクラには果実がよく実る。ただし、果実は若いときに枝から落ちることが多く、残って成熟する果実は珍しい。ナラノヤエザクラの花には複数の雌しべがあるため、果実もしばしば複数個くっついた状態になっている。果実は黒く熟し、食べると苦味と酸味がある》。

《奈良の旧都に美しい八重桜があった事実は『詞花和歌集』『袋草子』『沙石集』『徒然草』などの文献に、また江戸時代の図譜として残されている。江戸時代初期、1678年に出版された『奈良名所八重桜』は奈良の八重桜について記述している。『奈良名所八重桜』は名所案内記に名をかりたフィクションであり、東大寺、興福寺はじめ作り話が多い》。

《ナラノヤエザクラは伊勢大輔の詠んだ和歌により名高い。いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に 匂ひぬるかな 『七大寺巡礼私記』には、奈良の都の八重桜が植わっていた場所と開花時期が記載されている。記載によると、奈良の八重桜は興福寺の東円堂にあり、他の全ての桜が散ってから咲く遅咲き桜であったとされる》。

《1922 年に東京大学の植物学者であった三好学が東大寺知足院の裏山に植わっていた特徴ある八重桜を岡本勇治の案内で視察(調査)した(三好の岡本への追悼文より)。小清水は1922年4月に三好が発見したとするが、三好の論文の掲載号はこの年の1月である。三好は論文で産地として「京都と奈良」をあげている。ナラノヤエザクラは岡本勇治が大正10年頃(この年に三好が来県しているので早い月か前年)に天然記念物指定申請をおこなっている。申請は知足院のほか師範学校、春日神社(現春日大社)の三樹である。大阪朝日新聞大和版にも関連の記事がある。この「知足院の奈良八重桜」は1923年に国の天然記念物に指定されている》。

《ナラノヤエザクラは奈良を代表する花として1968年には奈良県花に制定された。さらに1998年には奈良市花に制定されている》。
小さくて可憐なこの桜は「知る人ぞ知る」桜であったが、最近は奈良女子大や今西清兵衛商店、植嶋などの「奈良八重桜プロジェクト」で、次第にメジャーな存在になってきた。
http://www.nara-wu.ac.jp/liaison/product/narayae.html
東大寺、奈良公園、奈良新公会堂、奈良県庁東駐車場、奈良女子大、若草山麓、春日大社、奈良ホテルなどとともに、大安寺のナラノヤエザクラも、ぜひ楽しんでいただきたい。


















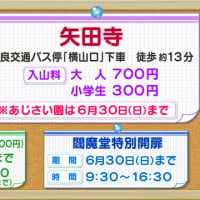







平城宮跡のちょっと古い写真(第2次大極殿が整備された頃?)を見ると、朝堂院と朝集殿院の境目にずらっと並木があります。それが全部奈良八重桜だったということはないんでしょうか。
但し、美味しいもののご紹介は、取材している方の健康を心配して仕舞います。今後も楽しみにして拝見させて頂きますがご健康にご留意を・・・・・
で、おっしゃるとおり大安寺のナラノヤエザクラは存じませんでした!
でも、案外人知れずあちこちにあるんですよ、ナラノヤエザクラ。やはり県花ですから、一時は増殖に力を入れられたんでしょうね。
以前大和高田市のある幼稚園に森林インストラクター関連でお邪魔したとき、敷地続きの系列短大のお庭に何本か植わっていて驚きました。幼稚園の方にお教えすると、「え、これ桜ですか?!咲いてるの見たことないんですけど」と・・・(^^;)その時すでに小さなつぼみを幾つか付けていたのですが、四月下旬でしたから気付かれなかったようです。
奈良公園でも、他の桜がほとんど終わり、人々の関心が新緑と藤に移る頃咲き始め、満開時には赤みを帯びた葉もかなり大きくなるため、目立たないんですよねえ。でもその、人知れず、といったところが奥ゆかしくていいですねえ。
また、ナラノヤエザクラは確かに八重桜の割には結実しやすく、実生苗を作ることも可能なようですが、実生苗の80%以上がカスミザクラに先祖帰りし、それ以外も交配した父系の桜の性質が出るなど、ナラノヤエザクラになることは5%にも満たないと聞いたことがあります。だから増殖は接ぎ木や挿し木、バイオで増やすしかなく大量には生産できないんですね。他府県で見ることはまずないですから。
だからこそ、大事にしていきたい桜ですね!
> 平城宮跡の第二次大極殿基壇のはるか南、朝堂院と朝集殿院の
> 境目付近に立っている3本の桜も奈良八重桜ではないでしょうか
先日、今西清兵衛商店さんの「奈良の八重桜」試飲会で、カラーのパンフレットをいただきました。そこには「平城宮跡地には伊勢大輔が詠んだ和歌が刻まれた石碑と奈良八重桜樹があります」と載っていました。その桜のことでしょうか。
> 美味しいもののご紹介は、取材している方の健康を心配して仕舞います。
楽しいブログをお作りですね。これから時々、拝見します。「奈良を食べ尽くす男」といわれたこともありますが、「グルメガイド」は、最近ではあっさり系を中心に取材することにしていますので、どうぞご心配なく。
> 案外人知れずあちこちにあるんですよ、ナラノヤエザクラ。
> やはり県花ですから、一時は増殖に力を入れられたんでしょうね。
そんなにあるのですね、存じませんでした。
> 増殖は接ぎ木や挿し木、バイオで増やすしかなく大量には
> 生産できないんですね。他府県で見ることはまずないですから。
なるほど、微妙なものなのですね。県内で、大切に育てたいものです。
> 先日、今西清兵衛商店さんの「奈良の八重桜」試飲会で、カラーのパンフレ
> ットをいただきました。そこには「平城宮跡地には伊勢大輔が詠んだ和歌が
> 刻まれた石碑と奈良八重桜樹があります」と載っていました。その桜のこと
> でしょうか。
私が言っている桜は朱雀門前の伊勢大輔の歌碑のそばではなく、第二次朝堂院と朝集殿院の境界線の西端、みやと通り寄りにあります。私のbbs(http://tenb.bbs.coocan.jp/?m=listthread&t_id=394&summary=on)に写真がありますが、その写真を見ただけではどこにあるのかわからないでしょう(^^;)。
資料館なんかに置いてある「世界文化遺産 特別史跡平城宮跡」という奈文研発行の資料の表紙写真には、3本の木が小さく写っています。
> 朱雀門前の伊勢大輔の歌碑のそばではなく、第二次朝堂院
> と朝集殿院の境界線の西端、みやと通り寄りにあります。
これは失礼。歌碑は朱雀門前でしたか。時間を見つけて訪ねたいと思います。