
今回も、NPO 法人「スマート観光推進機構」理事長の星乃勝さんからいただいた情報を紹介する。観光経済新聞(2023.8.15付)「VOICE」欄に掲載された「観光は物見遊山かーコロナを経て思うこと」で、執筆者はJR東日本企画常勤監査役・日本観光振興協会顧問 の久保田穣氏である。星乃さんは、
日本は「気候」「自然」「文化・歴史」「食」に恵まれた国だ。これらの資源を活かし、日本の観光はGDPの5%を占め、「訪日外国人旅行消費額」は自動車産業、化学産業に次ぐ第3位の輸出産業となった。しかし日本の観光は、国内旅行をターゲットとしてきたため、団体旅行などマス経済から脱却できていない。ドル高、ユーロ高を背景とする中、インバウンドが欲する観光の姿が多様化しているので、高付加価値、高単価を目指さなければならない。
とコメントされている。奈良県のGDPに占める観光業の割合は5%までは行かないだろうが(観光消費単価が低いため)、新しい宿泊施設が続々と誕生している今、高価格で高付加価値の観光サービスの提供が求められている。では、久保田氏の記事全文を紹介する。
価格見直しの最良のチャンス
観光資源は「気候」「自然」「文化(歴史)」「食」の4要素からなるといわれています。これらは、日本に、各地に固有(天賦)であったり、先人たちが守り育ててきたもので、観光産業側からは利用対象であるとともにビジネスの元手でもあり、産業全体でとらえれば「資本」(無形もありますが)と位置付けることもできます。
故宇沢弘文教授は「ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を安定的に維持する」社会的装置を「社会的共通資本」としましたが、観光資源はまさにそのようなものだと思います。
実際、4つの観光資源を元手にインバウンドを誘致し、効率的経営で地域を豊かにすることによって、日本の観光はGDPの約5%を占めるに至り、外国人が日本のサービスを購入するので経済的には輸出と同列で、「訪日外国人の観光消費」は「自動車産業」「化学産業」に次いで第3位の輸出産業となって日本経済の一翼を担ってきました。昨今の円安下では、さらにその重要性は高まっています。
コロナ禍を経て、借入金の増大によるバランスシートの悪化、人手不足による収益機会の逸失、エネルギーコストをはじめとする原価高騰などにより、引き続き厳しい経営を強いられている中、売価の適正化(値上げ)に取り組んでおられる企業も多いと思います。現下においては、売価の適正化(値上げ)は喫緊のテーマだと思います。
これまで、観光分野に限らず価格競争、薄利多売、非正規労働者によるコスト削減等によって経営を維持してきたわけですが、観光の政策目標である高付加価値化の方向に照準を合わせる意味でも、高価格化は必然でしょう。
特に、昨今の円安下では円ベースで50%値上げしてもドルベースでみればコロナ前と大差なく、逆に値上げしないならば円安による利益を海外に流出させる結果になるわけです。今こそが、価格見直し(値上げ)の最良のチャンスでしょう。
日本は世界に十分通用する観光資源を備えているので、中長期的なインバウンド需要は十分確保できると思います。そのうえで、観光産業の経営の安定(高付加価値なサービスと価格、良い雇用環境、適正な利益と納税、健全な財務状況で必要な再投資など)を図り、その経済効果を、観光の「資本」である観光資源(社会的共通資本)の維持・整備、投資による拡充・魅力アップに反映させていく、といった国内側の大きな経済循環を確実にしていくことこそが持続可能な観光振興ではないでしょうか。
日本は「気候」「自然」「文化・歴史」「食」に恵まれた国だ。これらの資源を活かし、日本の観光はGDPの5%を占め、「訪日外国人旅行消費額」は自動車産業、化学産業に次ぐ第3位の輸出産業となった。しかし日本の観光は、国内旅行をターゲットとしてきたため、団体旅行などマス経済から脱却できていない。ドル高、ユーロ高を背景とする中、インバウンドが欲する観光の姿が多様化しているので、高付加価値、高単価を目指さなければならない。
とコメントされている。奈良県のGDPに占める観光業の割合は5%までは行かないだろうが(観光消費単価が低いため)、新しい宿泊施設が続々と誕生している今、高価格で高付加価値の観光サービスの提供が求められている。では、久保田氏の記事全文を紹介する。
価格見直しの最良のチャンス
観光資源は「気候」「自然」「文化(歴史)」「食」の4要素からなるといわれています。これらは、日本に、各地に固有(天賦)であったり、先人たちが守り育ててきたもので、観光産業側からは利用対象であるとともにビジネスの元手でもあり、産業全体でとらえれば「資本」(無形もありますが)と位置付けることもできます。
故宇沢弘文教授は「ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を安定的に維持する」社会的装置を「社会的共通資本」としましたが、観光資源はまさにそのようなものだと思います。
実際、4つの観光資源を元手にインバウンドを誘致し、効率的経営で地域を豊かにすることによって、日本の観光はGDPの約5%を占めるに至り、外国人が日本のサービスを購入するので経済的には輸出と同列で、「訪日外国人の観光消費」は「自動車産業」「化学産業」に次いで第3位の輸出産業となって日本経済の一翼を担ってきました。昨今の円安下では、さらにその重要性は高まっています。
コロナ禍を経て、借入金の増大によるバランスシートの悪化、人手不足による収益機会の逸失、エネルギーコストをはじめとする原価高騰などにより、引き続き厳しい経営を強いられている中、売価の適正化(値上げ)に取り組んでおられる企業も多いと思います。現下においては、売価の適正化(値上げ)は喫緊のテーマだと思います。
これまで、観光分野に限らず価格競争、薄利多売、非正規労働者によるコスト削減等によって経営を維持してきたわけですが、観光の政策目標である高付加価値化の方向に照準を合わせる意味でも、高価格化は必然でしょう。
特に、昨今の円安下では円ベースで50%値上げしてもドルベースでみればコロナ前と大差なく、逆に値上げしないならば円安による利益を海外に流出させる結果になるわけです。今こそが、価格見直し(値上げ)の最良のチャンスでしょう。
日本は世界に十分通用する観光資源を備えているので、中長期的なインバウンド需要は十分確保できると思います。そのうえで、観光産業の経営の安定(高付加価値なサービスと価格、良い雇用環境、適正な利益と納税、健全な財務状況で必要な再投資など)を図り、その経済効果を、観光の「資本」である観光資源(社会的共通資本)の維持・整備、投資による拡充・魅力アップに反映させていく、といった国内側の大きな経済循環を確実にしていくことこそが持続可能な観光振興ではないでしょうか。










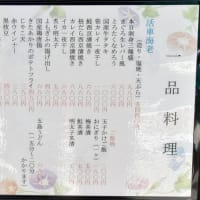
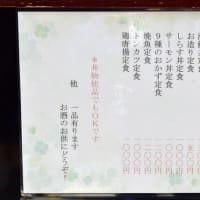














私の見立てですが、現在の物価上昇は、元々、ムリをしてディスカウントしていた価格が、バブル経済前の価格になりつつある様な感です。つまり、むちゃくちゃな価格になったのが、元に戻って来たと思っています。
ただ、元に戻ったとしても、社会保険料が上がり、消費税は10%、所得税率の上昇と、これは可処分所得が当時よりも下がっている事を意味しています。更に、平均給与も減少している訳で、これは高額消費をしようとする事自体に無理が生じている訳です。それだけ、日本の経済状況が、もはや救いようの無い所まで来てしまい、復帰不可能なのかも知れません。
そこで、外国人観光客に、もっと使って貰おうって、これまた、バブル期以前の日本人の海外旅行ですね。香港や台湾などで、大量にブランドグッズを買い込んで帰って来たのが、はるか昔に感じます。それを、日本に来て貰っている外国人観光客に、やって貰おうと云うのが、この文章の趣旨に感じました。
ただ、外国人観光客に、こうやって貰おうとすれば、奈良県では、ハードの側から見直さないと無理です。奈良公園自体は、柵もナニも無く、事実上の開放状態。平城宮跡も然りですね。東大寺や興福寺などの個別拝観をしないと、料金は発生しません。
荒井前知事が連れて来た自慢のホテルも、果たしてそうした方々に使って貰えるのかは、甚だ疑問です。そうした方々に対するサービス基準が、あの時給で行えるとは、どう考えても思えません。
この「値上げしないならば円安による利益を海外に流出させる結果になるわけです。今こそが、価格見直し(値上げ)の最良のチャンスでしょう。」と有りますが、現在の外国人観光客で採算の取れる施設や地域は、日本でも限定されたエリアで、更に、特定の施設に限定されています。大半の地域や施設は、外国人観光客など無縁な訳です。
その証拠に、奈良県でも、外国人観光客を見られる場所は、JR奈良駅から大仏殿までの都合5キロ程度。それ以外の場所となれば、全くと言って良い位居られません。例えば、私のゲストハウスの有るきたまちでも、外国人観光客を見かける事は有りません。私のゲストハウスに宿泊する外国人程度です。尤も、大仏殿にしても、講堂跡は、もうガラガラです。それだけ、日本の見学場所が偏っている訳です。この文章は、そうした地域格差を解消出来たと云う事が前提にならないと、作文以外のナニモノでも無いと考えます。
> 現在の物価上昇は、元々、ムリをしてディスカウントしていた
> 価格が、バブル経済前の価格になりつつある様な感です。つまり、
> むちゃくちゃな価格になったのが、元に戻って来たと思っています。
それは私も同感です。失われた30年のデフレ時代にムリしていた価格が、元に戻って来たのでしょう。しかし「官製不況」といわれるように、税率も社会保険料も上がりました。そこへこの円安、それで外国人観光客に期待がかかる、という構図です。
> 外国人観光客に、こうやって貰おうとすれば、奈良県では、ハードの側から見直さ
> ないと無理です。奈良公園自体は、柵もナニも無く、事実上の開放状態。平城
> 宮跡も然りですね。東大寺や興福寺などの個別拝観をしないと、料金は発生しません。
おっしゃるとおりで、奈良公園も平城宮跡もタダで入れますし、東大寺や興福寺も、有料のお堂に入らなければ、タダです。そこが、塀で囲われて入り口でおカネを取る京都と、大きく違います。
奈良は「気候」「自然」「文化(歴史)」「食」の全てにおいて、恵まれています。
「きたまち」は厳しいのかも知れませんが、「ならまち」では、たくさんの外国人観光客を見かけます。幸か不幸か、ラグジュアリーな宿泊施設も増えています。
インバウンド再燃の風潮のもと、社寺、宿泊施設、地域と行政がタッグを組んで、外国人観光客を引きつける「魅力の創造」に取り組まねばならないと思います。