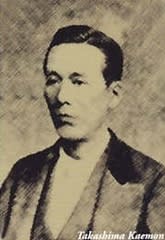 横浜関内にある横浜開港資料館で「創業の時代を生きた人びと-黒船来航から明治憲法まで-」が4月23日まで開かれている。横浜開港資料館と横浜市開港記念会館は近くにあるが違うものなので注意が必要。記念会館の方は建物の外観が売りだが、資料はない(と思う)。
横浜関内にある横浜開港資料館で「創業の時代を生きた人びと-黒船来航から明治憲法まで-」が4月23日まで開かれている。横浜開港資料館と横浜市開港記念会館は近くにあるが違うものなので注意が必要。記念会館の方は建物の外観が売りだが、資料はない(と思う)。
弊ブログでは、2005年4月22日付維新のホリエモンか平成のカエモンか、2006年2月1日再度、ホリエモンとカエモンに堀江貴文と比較する形で高島嘉右衛門のことを紹介してきたが、起業家としての彼の実績について、まとまった形で公式的に最評価されたということであろうか。「私の方が発掘は先だ!」と自己満足。新事実があるのではないかと期待しつつ、会場に向かう。
この展示会で紹介されるのは、嘉右衛門の他、成島柳北、ヴァンリード、H・S・パーマー、伊藤博文ということだが、実業として、横浜に大きな足跡を残したのは高島嘉右衛門が一番多大だろう。現在の横浜駅の周辺を埋め立てたのは、彼の実績である。高島町は地名にもなり、駅名にもなっている。またガス会社を作り、市内にガス灯を灯している。
まず、今回明らかになったのは、彼の江戸時代末期の足跡であるが、父親は材木商であったそうで、遠州屋嘉平と名乗り、材木商兼建築業だった。特に、江戸末期は地震や火災が多発し、大いに儲かっていたらしい。特に、新規売込みに長けていて、南部藩と肥前鍋島藩からは、火事の後の突貫工事で、厚い信頼を受けていたという。さらに、天保の大飢饉の時、鍋島藩のコメを南部藩に無事に届けるという大役をつとめている。その結果、南部の鉱山開発権を入手し、江戸の店は、番頭に任せて父子で東北へ向かう。
ところが、鉱山開発はあまりうまくいかず、江戸の番頭も無能だったこともあり本業が不振となる。番頭をクビにして、息子(嘉右衛門)の方が実権を握る。そして次は、肥前鍋島藩の方の商売として、江戸の商人数名と組んで、有田焼などを海外に輸出する「肥前屋」という店を横浜に構える。そして、正規貿易をしているうちに、内外の金銀交換格差に着目するようになるわけだ。
その後、誰でも捕まえることのできる魔法の法律「外為法違反」で彼は捕まるのだが、具体的な犯行方法には諸説ある。私が最初に聞いたのは、金の売買と銀の売買をそれぞれ先物で行い、決済日に利ざやをとる、という話だったが、小判そのものが金含有量が多く、流通価値を上回っているため、そのまま小判をつぶして、金そのものにしていたという説もある。今回の展示会では、小判を売買(輸出)したという手法が紹介されていた。犯行手口があやふやなのは、当局が類似犯の出現をおそれ、詳細を公開しなかったからかもしれない。
そして、なんらかの通貨に対する罪を犯したあと、懲役10年がいい渡され、佃島に軟禁されたのだが、5年10ヶ月で釈放されている。得意の高島流の占いで、看守の出世を予言したかららしい。
その後、鉄道事業はじめ数々の新事業を始めたのだが、今回の展示会で初耳だったのは教育産業だ。明治4年に、政府による学制発布の1年前、横浜町学校という全寮制の学校を創立している(通称、高島学校)。現在の桜木町駅の伊勢山寄り(市立本町小学校の場所)に建設している。関東一円から優秀なこどもたちが集まってきて、岡村天心もその一人だった。
そして、驚くことに、あの福澤諭吉先生をこの学校に引き抜こうとしていたそうだ。しかし不調に終わり、数年後に横浜市に学校を売却。学校経営から手を引く。もし、この時、福澤先生が「ペンは剣よりは強いが、小判よりは弱い」とか考え、高額移籍金に目がくらみ、慶応義塾をたたんでしまっていたら、小泉首相も早稲田大学に入学し、一芸入学のフィギュアスケートゴールドメダリストの先輩にならざるを得なかっただろう。
そして、民間人としては始めて明治天皇に謁見。その時には既に亡き父母の位牌を懐に忍ばせていたそうだ。そして40歳代半ばで突然実業界を去り、高島易断教祖になるのだが、後継者に恵まれず、その後の高島易断はずっと内部抗争を続けているらしい。
彼の人生を見ると、口がうまく、様々な事業にすぐにスポンサーやフィクサーを探してくる。伊藤博文や大隅重信も彼の口車に乗った口であるのだが、なぜか大隅を自分の学校にスカウトしようとはしなかったのは、彼の脳みそを見切ったからなのだろうか。あるいは、大隈の方が、「福沢に負けた!」と奮起して学校を創ったのだろうか?(この謎は追わないことにする)




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます