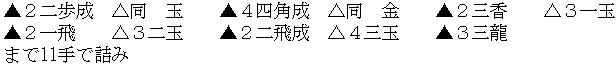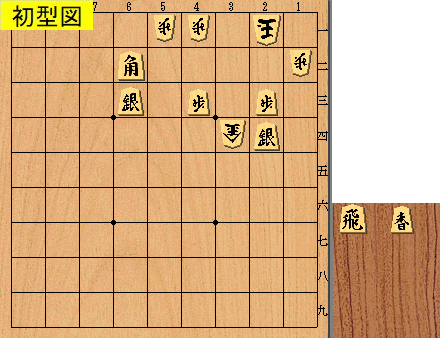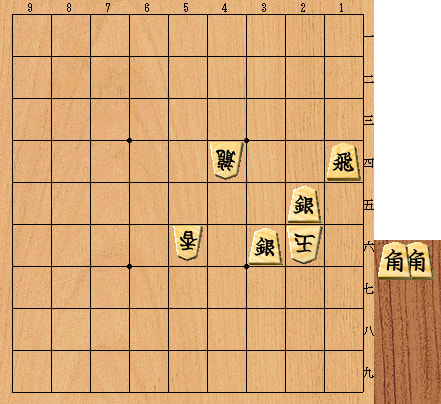原作は同名のエッセイ漫画シリーズ。夫がうつ病になり、会社を辞め、漫画家だった自分(細川貂々)の連載も打ち切りになり、唯一の解決策である「夫の病気をネタにする」という方法でうつ病と戦う夫婦の日常を漫画にし、これが大当たりになった。
映画の話ではないが、日本の小説には「私小説」という歴史的ジャンルがあって、その多くは男性作家が不倫を続け泥沼の中を逃げ回るというのが多いが、病気をネタにするとは大胆だ。北杜夫は、自分は躁鬱病(現在は双極障害と表現)だと公言していたが、そもそも彼は父と同じく精神科医だったかな。
さて、映画では夫が堺雅人、妻を宮﨑あおいと技巧派俳優が演じる。なんとなくピタリとはまっているキャスティングだ。そういえば2009年公開の南極調理人では南極に行ったものの気分が落ち込んでしまい、調理のできない調理人を演じていた、後年の「倍返し」の怪演は反動かな。
実は、私は大坂商工会議所が中心となって認定している『メンタルヘルス・マネジメント検定』で1種・2種・3種の3種類の試験で合格している。中心的な分野は、うつ病対策。3種はうつ病の原因を個人が理解して、なるべくうつ病になりにくい生活を送ること。2種はうつ病の特徴である自分で気が付かないということで重症にならないように、近い人が気づいて早めに治療に入ること。1種は、組織の長(社長とか校長とか院長とか)うつ病にならないような環境を作ること。
少なくても、この映画の事案では1種も2種も3種も全部だめである。
思うに、3種の範囲(うつ病の仕組みと予防対策)については、中学あるいは高校で、しっかり教えれば患者数は激減するはず。もっとも、教えるべきことは、それに限らず、選挙に行く意味、ギャンブルの危険、ドラッグの危険、ホストクラブの危険、各種詐欺の手口、お金の使い方、護身術、などなど多すぎるのかもしれない。