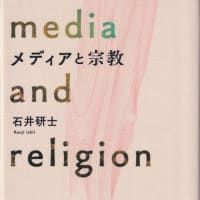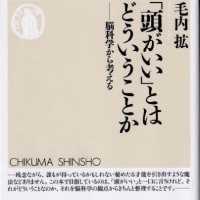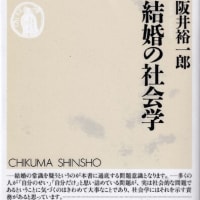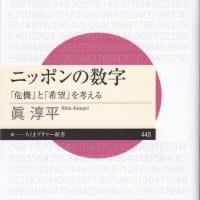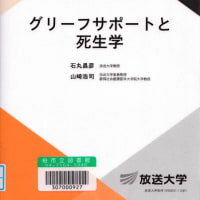九条武子の福祉の原点は、1920 (大正9)年12月、東京築地本願寺内に移り住んだ九條武子は、東京に居住していた兄、大谷尊由(本願寺派管長事務取扱・真宗文書伝道会総裁)のすすめもあって、真宗文書伝道会の活動の一環として、大正11(1922)年11月5日、深川地区に連なる「トンネル長屋」を訪問したことです。
武子が慰問直後に友人に宛てた書簡の一節に「頭が変になりましたのは、この間御聞き遊ばしましてーあの細民窟にまゐりました。とてもとても私の思ひもっかぬ敗残の人達でした。…どんなに尊とい半日で御座いましたか。」と書き、「二畳敷 九人のひとの居ならびて 足だにもやすくのぶるすべなし」と詠んでいます。
<考現学>という学問があります。社会のあらゆる分野にわたり,生活の変容をありのままに記録し研究することで、古物研究を専門とする考古学に対し,現代学で、日本で発達した学問で,大正末期に今和次郎らによって提唱されたものです。
その今和次郎の書に『考現学入門』(1987年)があり、「本所深川貧民窟付近風俗採集」という章があり、次のようにあります。
震災後、賀川豊彦さんのやっている本所基督教産業青年会が、精細な細民窟住居の実地踏査をした図をだしていますが、それによると、一エーカー(1.224坪)に1.560戸の家が建てられているのが普通の状態のようです(普通の小住宅は、一エーカーに12戸ないし、15戸が適当とされておりますが)。路地などをも加えて一戸についてわずかに七坪余の地積しかあてられていないわけです。そして二畳、三畳、六畳というような大きさの家ないし長屋が並んでいるのです。(以上)
同氏が昭和初期の東京の様子を描いた 「新版・大東京案内」 の中で、「細民街、貧民窟は都会に取っての、一つの大きな癌である」 と述べ、昭和4年当時の東京下町の細民団地11区のうち、第一位が深川の細民街で、5,676世帯、次が浅草の4,637世帯、本所の3,569世帯の順に表示しています。
深川の貧民窟が、どの様なものであったのか、https://ksei.exblog.jp/d2012-09-14/からの引用です。
昭和42年(1967)に東北大学で開かれた 「日本教育社会学会大会」 で、現在では不適切な用語だが、そのまま引用すると、江東区教育委員会の田宮 寛己氏が 「精神薄弱児(者)のスラム-東京深川高橋ドヤ街における実態について」 と題して、深川高橋の簡易宿泊街と江東区を取り上げ、都内の他地域と比べて、知的障害者が 「全国平均を超える出現率。 特殊学級の在級者の1/3を占める生活保護、教育扶助家庭。 欠損家庭あるいは実際上それに近いものの高率。 非行、怠休の高率。 家族性精薄の頻度の高さ。 発生原因別に見た単純型の多いこと」 などをあげ、「幼児期の不適切な教育環境による仮性精薄(環境因子による知的障害者)の多いこと。 社会の吹きだまりとしての気易さや食物の低廉さから精薄者が多く住みついたということが相互に因果関係を形成している」 と述べ、不衛生な貧困生活環境が児童の発育に及ぼす障害を指摘している(日本教育社会学会大会発表要旨)。
(以上)
武子をして「頭が変になりましたのは、この間御聞き遊ばしましてーあの細民窟にまゐりました。とてもとても私の思ひもっかぬ敗残の人達でした。…どんなに尊とい半日で御座いましたか。」といわせた現実は、相当なものであったようです。
武子が慰問直後に友人に宛てた書簡の一節に「頭が変になりましたのは、この間御聞き遊ばしましてーあの細民窟にまゐりました。とてもとても私の思ひもっかぬ敗残の人達でした。…どんなに尊とい半日で御座いましたか。」と書き、「二畳敷 九人のひとの居ならびて 足だにもやすくのぶるすべなし」と詠んでいます。
<考現学>という学問があります。社会のあらゆる分野にわたり,生活の変容をありのままに記録し研究することで、古物研究を専門とする考古学に対し,現代学で、日本で発達した学問で,大正末期に今和次郎らによって提唱されたものです。
その今和次郎の書に『考現学入門』(1987年)があり、「本所深川貧民窟付近風俗採集」という章があり、次のようにあります。
震災後、賀川豊彦さんのやっている本所基督教産業青年会が、精細な細民窟住居の実地踏査をした図をだしていますが、それによると、一エーカー(1.224坪)に1.560戸の家が建てられているのが普通の状態のようです(普通の小住宅は、一エーカーに12戸ないし、15戸が適当とされておりますが)。路地などをも加えて一戸についてわずかに七坪余の地積しかあてられていないわけです。そして二畳、三畳、六畳というような大きさの家ないし長屋が並んでいるのです。(以上)
同氏が昭和初期の東京の様子を描いた 「新版・大東京案内」 の中で、「細民街、貧民窟は都会に取っての、一つの大きな癌である」 と述べ、昭和4年当時の東京下町の細民団地11区のうち、第一位が深川の細民街で、5,676世帯、次が浅草の4,637世帯、本所の3,569世帯の順に表示しています。
深川の貧民窟が、どの様なものであったのか、https://ksei.exblog.jp/d2012-09-14/からの引用です。
昭和42年(1967)に東北大学で開かれた 「日本教育社会学会大会」 で、現在では不適切な用語だが、そのまま引用すると、江東区教育委員会の田宮 寛己氏が 「精神薄弱児(者)のスラム-東京深川高橋ドヤ街における実態について」 と題して、深川高橋の簡易宿泊街と江東区を取り上げ、都内の他地域と比べて、知的障害者が 「全国平均を超える出現率。 特殊学級の在級者の1/3を占める生活保護、教育扶助家庭。 欠損家庭あるいは実際上それに近いものの高率。 非行、怠休の高率。 家族性精薄の頻度の高さ。 発生原因別に見た単純型の多いこと」 などをあげ、「幼児期の不適切な教育環境による仮性精薄(環境因子による知的障害者)の多いこと。 社会の吹きだまりとしての気易さや食物の低廉さから精薄者が多く住みついたということが相互に因果関係を形成している」 と述べ、不衛生な貧困生活環境が児童の発育に及ぼす障害を指摘している(日本教育社会学会大会発表要旨)。
(以上)
武子をして「頭が変になりましたのは、この間御聞き遊ばしましてーあの細民窟にまゐりました。とてもとても私の思ひもっかぬ敗残の人達でした。…どんなに尊とい半日で御座いましたか。」といわせた現実は、相当なものであったようです。