春霞(はるがすみ)。
遠山霞(とおやまがすみ)。
2011年のGW(ゴールデン・ウィーク)は、
なぜか憂鬱。
4月30日、5月1日は強風吹き荒れ、
5月2~4日は黄砂を観測。
明日の石川県も黄砂が残る模様で、
7日から再び多量の黄砂と8日は雨。
でも、
2~7日は青空の見えない“晴れ日”が続く模様で、
お出かけ日和は周辺でも多くの人出が見られた。
春霞。
日本的な言い回しは調べてみると多くの和歌に詠まれているようで、
・春霞 たてるやいずこ みよしのの 吉野の山に 雪はふりつつ
・春霞 立つを見捨てて 行く雁は 花なき里に 住みやならへる
・春霞 かすみていにし かりがねは 今ぞなくなる 秋ぎりの上に
・春霞 たなびく山の 桜花 うつろはむとや 色かはりゆく
・春霞 たなびきにけり 久方の 月の桂も 花や咲くらむ
日本の古典にかかっては花粉や黄砂による視界不良の現象も、
春霞と言葉にすると意味が分からずとも優雅にさえも感じる不思議。
みどりの日。
染井吉野(ソメイヨシノ)が散る頃から徐々に緑が街中から山沿いへと目に付く季節。
濃い杉の緑とは対照的な落葉樹の淡い緑(発芽)との対比は目に優しく美しい。
木の芽時(きのめどき)と言われるこの季節は花粉飛び散る季節でもあることは、
多くの人達にとって憂鬱な季節に違いないことも事実だ。。
春霞=花粉?
空気の澄んだ寒い冬の朝には、
立ち昇る水蒸気も押さえられ、
遠くの山が眼前に迫ることは、
以前に文字にした。
逆に、
風の強い暖かい春の日差しは、
花粉が飛び散ることで、
遠山が霞んで見えることは、
説明の必要もないだろう。
*さらに気温上昇と水分の蒸発。
木の芽時は気がふれる。
とは昔から伝えられた言葉らしく、
その意味を、
“暖かくなることで人も浮かれる”
と解釈する人もいるが、
花粉症が知識として入る以前の昔に、
何故か分からぬ憂鬱を感じる人々が、
*この場合の憂鬱の正体はアレルギーだろう。
(アレルギーの)対処の仕方がないために、
人目におかしな行動(言動)をとったのではないか?
女性特有と見られた更年期障害(の個人差)も、
本人でなければ分からない(絶え難い)苦しみは、
アレルギー症状に於いても同じ事ではないか?
今の世では、
様々なアレルギー反応(心的を含む)に対して、
原因やそれなりの対処療法もあるものの、
知識のない時代(医学の未成熟な時代)には、
精神の悩みは病気として認められなかった。
個人個人の特性を持つ外的要因(体質・環境適応)からの憂鬱。
さらに、
経験からくる内的要因(過去の経験・教育環境)からの拒否反応。
知識のない時代には、
精神の悩みは病気として認められなかった。
2011年5月現在の私達が、
目の前の現実として気に留めておくべき事は、
地震や津波等の自然災害(身の危険)を経験した事で起きる、
PTSD(心的外傷後ストレス障害)反応の個々の兆候や、
放射性物質の恐怖や極度の中毒&アレルギー症状から起きる、
脳内の強い記憶が引き起こすPTSD症状が将来表面化する可能性。
~身体が覚えてしまった事を理性で取り除く事は困難を極める。
*補足事項として“危険体験と逃避反応”は進化のメカニズムに於いて必要だった。
私達は知識に満ちた時代を生きている。
私達は情報過多の時代を生きている。
しかし、
私自身が重視すべき事柄として、
私個人の脳の働きを知る事は、
必ず人の心の動きを知る事。
と肝に銘じ、、
些細な経験も検証する事を心がけている。
今夜は何故か憂鬱。
では、
何故憂鬱なのか?
その原因を探る事が、
自分を知り、
人を知る事につながる。
2011年5月4日。
私にとっては、
あちらに行ったり、
こちらに行ったりと、
楽しい一日だった。
でもフッと独りPCに向かい何故か憂鬱。
その答えは?と自分に問えば、
文字にしたいことが文字にできないもどかしさ。
紹介したいことが紹介できないジレンマ。
答えは自分で分かってる。
本当は文字にしたい事が別にある。
それでも…。
憂鬱やストレスの正体。
それは、
思考と行動の距離。
であり、
憂鬱の正体とは、
原因不明な漠然とした不安であり、
さらに、
ストレスの正体は、
距離を埋める努力への肯定と否定。
であろう。
時に人は、
憂鬱やストレスから逃れられない事もある。
その多くが、
理性(大脳など新しい脳)が要求する責任感や使命感と
本能(小脳など古い脳)が要求する逃避意識や怠惰志向
との葛藤
言葉を置き変えれば、
“留まらなければならない現実&その場から逃げ出したい欲求”
との葛藤こそが憂鬱やストレスの最大要因となり、
“逃げられない現実と逃げたい気持ち”
の心の動き(=脳内の対立)は多様な要因から生まれる。
さらに深く言葉を置けば、
憂鬱の最大要因としての漠然とした不安は、
“理性(or 知識)では答えの出せない本能的な逃避願望”
なのだろうし、
“漠然とした不安=無知や誤った知識の習得(収得)”
が理由である事例も多いように思う。
知識のない過去の時代には、
精神の悩みは病気として認められなかった。
ならば知識を持とう。
*しかし知識は漠然とした不安を確定的不安に置き換える可能性を持ち、
必ずしも人々にとって不安の解消になるとは限らない事実も明記する。
と文字にして、
読み手の方々の理解は得られるか?
でもそれ(現実×逃避)が、
“ストレスの正体”であり、
“憂鬱の正体”であると、
私は感じている。
がさらに、
それが総べての答えではない事も、
私は理解しているつもりだ。










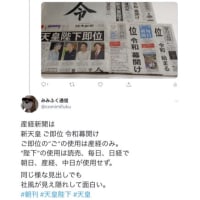

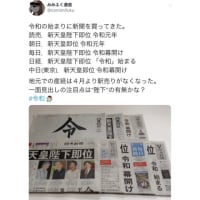

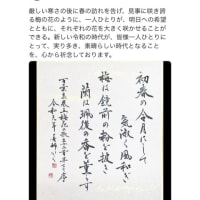
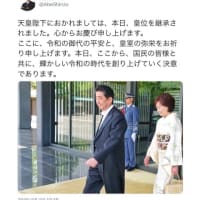



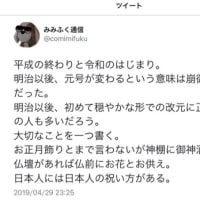





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます