
10月31日・11月1日、1泊2日で恒例の福島県南会津町(旧舘岩村)へ「紅葉狩り」と「新そば」を食しに行ってきました。
ちょうど一仕事終わったばかりだったので(「立松和平全小説」第4巻・解説の執筆)、のんびりした気持で前橋から栃木県の足尾―日光―今市―鬼怒川―五十里湖を経て、塩原温泉から続く会津西街道を目前に迫る錦繍の紅葉に染まる山々を眺めながらひた走り、目的の旧舘岩村へ。途中、前々から食べたいと思っていた「三依(みより)そば街道」に点在するそば店で昼食を摂る。「新そば」に期待していたのだが、「大盛りそば」に付けられていた漬け物はおいしかったのだが、そばはどう贔屓目に見ても、そば粉7割、つなぎ3割の機械打ち、店の看板には「10割そば・手打ち」と出ていたのに、正直言って騙された感じ。それでも久しくおいしいそばを食べていなかったので、僕は「まあまあかな」と思ったのだが、同行していた家人は、「つゆがまずい」と一言言い、不満足な様子だった。
腹が満たされ、行けども行けども錦繍の中を走る感じに、毎年のことながら感心しながら「道の駅・田島」に寄る。ここに必ず寄るのは、いつもおいしいリンゴが安く買えるからである。この季節、会津ではどこでもリンゴは買えるのだが、何故かこの「道の駅」のリンゴは当たり外れが無く、今年も試食してみたら満足できる味だったので、予定より少し多めに買い(2500円)、家人は「そんなに買って大丈夫なの」と心配していたが、僕としてはこれで当分はおいしいリンゴが食べられる、と充実した気持になる。
そこから一路旧舘岩村「湯ノ花温泉」の定宿にしている民宿「北の宿」へ。ここに最初に連れてきてくれたのは立松和平で、10年ほど前新潮社の編集者たちと「おいしいそばと面白い露天風呂があるから」ということで来たのである。そばは立松が言うように、これまで食したことのない食感と味で、一遍で虜になってしまった。露天風呂の方は、川のそばに湧出する本来は近所の住民の人たちが昔から利用している天然温泉で、男女混浴、湯量も豊富な「石湯温泉」であった。中年・初老の男が5人、ワイワイガヤガヤ、その時は大いに露天風呂を愉しんだのだが、最近はその温泉にはいることはあまりなく、もっと広い男湯と女湯が別れている「公共浴場」(もちろん、天然温泉掛け流し)をゆったりと利用することが多い。露天風呂(混浴)を利用したときには、それより10キロほど離れた「木賊温泉」を利用することが多い(この木賊温泉は、僕の中ではこれまで入った温泉の中で5本の指に入るものである)。
温泉の後は夕食、ビールを少しのでところで待望の「新そば」、期待に違わず今年も大変おいしかった。家人は「おいしい」と言いながら、それまでに出た山菜やイワナを中心とした料理(ことのほかおいしかったのは、裏の畑で取れたという里芋や大根が入ったキノコ汁であった。家人も僕もおかわりをしてしまった)をみんな平らげていたので余り量は食べず、その分僕は十二分にそばを堪能することができた(そばは足らなければ、おかわり自由で、満足いくまで食することができる)。
翌朝、「茅刈」のパフォーマンスを見て(この旧舘岩村には「会津曲がり家」と言われる茅葺きの家がまだ数多く残っており、風情のある風景を形作っている。ぼくらが泊まった民宿も、部屋は新築の民食仕立ての建物であるが、食事をする場所は「いろり」の掘ってある茅葺きの糧ものである)、次の目的地、只見田之倉ダムへ。途中で、朝早かったのだが日帰り温泉「むら湯」に入る。ロードマップで適当に見つけた温泉であったが、入って吃驚、広い窓から見えるのは錦繍に染まった山々で、湯は俗に言う「錆湯」で、鉄分が多く含まれているのであろう、赤茶けた湯がざあざあ流れている、もちろん「掛け流し」、ぶらりと入った日帰り温泉であったが、何だか儲けたような気がした。昨年も、檜枝岐のそばを食べたくて行ったところにあった「燧の湯」、これも素晴らしい思いをして、また来ようと思ったのだが、何よりも「むら湯」も「燧の湯」も人がそんなに多くないので、ゆったりすきなだけ温泉につかることができるのがいい。
そう言えば、前日も「湯ノ花温泉」に行く前に、会津高原駅前にある、前から気になっていた日帰り温泉に入ったのだが、これも絶景を目にしながらゆったり入ることができたので、満足を覚えたのを思い出した。
さて、田之倉ダム、前に一度何かの折に見たことがあるのだが、今年は文字通り「全山紅葉」状態の谷間に満々と水をたたえたダムが連なり、美しい景色を眺めながら、思わず「八ツ場ダム」のことを考えてしまった(と書いて、新聞を見たら、今日付の「東京新聞」が、八ツ場ダムの上流に「酸性」を中和するダムがあって、八ッ場ダムの本流である吾妻川は未だ「酸性」濃度が高く、果たして「治水・利水」に適しているのか、酸性の水はコンクリートのダムを溶かしてしまう、とも記事は書いており、前に僕が「死の川」と言っていたのが証明されたようで、大変よい記事だと思った)。
帰りは、新潟から関越自動車道を利用したのだが、紅葉狩りの季節であり土日で高速利用料1000円だというのに、交通量は少なく、全く渋滞せずに帰れた。余程景気が悪いのだろうか。
ちょうど一仕事終わったばかりだったので(「立松和平全小説」第4巻・解説の執筆)、のんびりした気持で前橋から栃木県の足尾―日光―今市―鬼怒川―五十里湖を経て、塩原温泉から続く会津西街道を目前に迫る錦繍の紅葉に染まる山々を眺めながらひた走り、目的の旧舘岩村へ。途中、前々から食べたいと思っていた「三依(みより)そば街道」に点在するそば店で昼食を摂る。「新そば」に期待していたのだが、「大盛りそば」に付けられていた漬け物はおいしかったのだが、そばはどう贔屓目に見ても、そば粉7割、つなぎ3割の機械打ち、店の看板には「10割そば・手打ち」と出ていたのに、正直言って騙された感じ。それでも久しくおいしいそばを食べていなかったので、僕は「まあまあかな」と思ったのだが、同行していた家人は、「つゆがまずい」と一言言い、不満足な様子だった。
腹が満たされ、行けども行けども錦繍の中を走る感じに、毎年のことながら感心しながら「道の駅・田島」に寄る。ここに必ず寄るのは、いつもおいしいリンゴが安く買えるからである。この季節、会津ではどこでもリンゴは買えるのだが、何故かこの「道の駅」のリンゴは当たり外れが無く、今年も試食してみたら満足できる味だったので、予定より少し多めに買い(2500円)、家人は「そんなに買って大丈夫なの」と心配していたが、僕としてはこれで当分はおいしいリンゴが食べられる、と充実した気持になる。
そこから一路旧舘岩村「湯ノ花温泉」の定宿にしている民宿「北の宿」へ。ここに最初に連れてきてくれたのは立松和平で、10年ほど前新潮社の編集者たちと「おいしいそばと面白い露天風呂があるから」ということで来たのである。そばは立松が言うように、これまで食したことのない食感と味で、一遍で虜になってしまった。露天風呂の方は、川のそばに湧出する本来は近所の住民の人たちが昔から利用している天然温泉で、男女混浴、湯量も豊富な「石湯温泉」であった。中年・初老の男が5人、ワイワイガヤガヤ、その時は大いに露天風呂を愉しんだのだが、最近はその温泉にはいることはあまりなく、もっと広い男湯と女湯が別れている「公共浴場」(もちろん、天然温泉掛け流し)をゆったりと利用することが多い。露天風呂(混浴)を利用したときには、それより10キロほど離れた「木賊温泉」を利用することが多い(この木賊温泉は、僕の中ではこれまで入った温泉の中で5本の指に入るものである)。
温泉の後は夕食、ビールを少しのでところで待望の「新そば」、期待に違わず今年も大変おいしかった。家人は「おいしい」と言いながら、それまでに出た山菜やイワナを中心とした料理(ことのほかおいしかったのは、裏の畑で取れたという里芋や大根が入ったキノコ汁であった。家人も僕もおかわりをしてしまった)をみんな平らげていたので余り量は食べず、その分僕は十二分にそばを堪能することができた(そばは足らなければ、おかわり自由で、満足いくまで食することができる)。
翌朝、「茅刈」のパフォーマンスを見て(この旧舘岩村には「会津曲がり家」と言われる茅葺きの家がまだ数多く残っており、風情のある風景を形作っている。ぼくらが泊まった民宿も、部屋は新築の民食仕立ての建物であるが、食事をする場所は「いろり」の掘ってある茅葺きの糧ものである)、次の目的地、只見田之倉ダムへ。途中で、朝早かったのだが日帰り温泉「むら湯」に入る。ロードマップで適当に見つけた温泉であったが、入って吃驚、広い窓から見えるのは錦繍に染まった山々で、湯は俗に言う「錆湯」で、鉄分が多く含まれているのであろう、赤茶けた湯がざあざあ流れている、もちろん「掛け流し」、ぶらりと入った日帰り温泉であったが、何だか儲けたような気がした。昨年も、檜枝岐のそばを食べたくて行ったところにあった「燧の湯」、これも素晴らしい思いをして、また来ようと思ったのだが、何よりも「むら湯」も「燧の湯」も人がそんなに多くないので、ゆったりすきなだけ温泉につかることができるのがいい。
そう言えば、前日も「湯ノ花温泉」に行く前に、会津高原駅前にある、前から気になっていた日帰り温泉に入ったのだが、これも絶景を目にしながらゆったり入ることができたので、満足を覚えたのを思い出した。
さて、田之倉ダム、前に一度何かの折に見たことがあるのだが、今年は文字通り「全山紅葉」状態の谷間に満々と水をたたえたダムが連なり、美しい景色を眺めながら、思わず「八ツ場ダム」のことを考えてしまった(と書いて、新聞を見たら、今日付の「東京新聞」が、八ツ場ダムの上流に「酸性」を中和するダムがあって、八ッ場ダムの本流である吾妻川は未だ「酸性」濃度が高く、果たして「治水・利水」に適しているのか、酸性の水はコンクリートのダムを溶かしてしまう、とも記事は書いており、前に僕が「死の川」と言っていたのが証明されたようで、大変よい記事だと思った)。
帰りは、新潟から関越自動車道を利用したのだが、紅葉狩りの季節であり土日で高速利用料1000円だというのに、交通量は少なく、全く渋滞せずに帰れた。余程景気が悪いのだろうか。












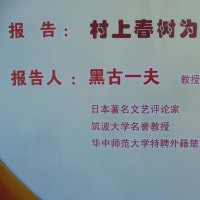

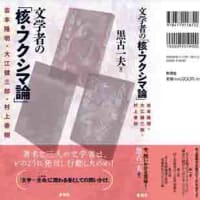




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます