このところ過ぎ去った時間の遠近感が失われてきて困っている。たとえば1週間前の出来事の記憶が随分遠くなってしまい、極端に言えば1か月前の出来事と区別がつかなくなっている(笑)。
9日(土)の試聴会は我がオーディオの歴史の中でも特筆すべき出来事だったが、それでさえも早くも忘却の彼方に去っていこうとしているが、中には忘れては困ることがあるので(自分のために)「落穂ひろい」をしておこう。
☆ ドライバー管の重要性

当日、一躍皆の脚光を浴びた「PX25」アンプだが、ドライバー管によっても大きく音が左右されたことを銘記しておかねばならない。
このアンプの音声信号の流れを記すと、「ドライバー管」 → 「ドライバー・トランス」 → 「出力管」 → 「出力トランス」となる。そしてドライバー管は2種類の球が挿し替えられるようになっている。
すなわち「〇〇〇」(カニンガムのナス管)と画像にある「3A/109B」(以下「STC」)だが、両方を挿し替えて聴き比べてみると前者が断然よかった。音場の奥行き感に随分差があって、これには一同ビックリ。
PX25と名ブランドのSTCは同じイギリス勢同士なので相性の良さからいっても、結果は火を見るまでもないと予想したところだったが、どうやら同じお国柄では括りきれないものがあるようだ。通常出力管として使う「〇〇〇」だが出力がメチャ低くて0.8ワット前後なので高能率のスピーカーしか使えないが、この球をドライバー管として使うGさんのセンスには一同恐れ入った。
それだけに「〇〇〇」にはクセのなさ、透明感、フラットな帯域どれをとっても非の打ちどころがなく、並みの真空管では測り知れない魅力があることを確認した。およそ90年前の球だが真空管の世界は古くなればなるほど音が良くなる。逆に言うと、大量生産化すればするほど、例外なく音質がぞんざいになっていく。
いずれにしても、出力管を生かすも殺すも「ドライバー管」次第ということを肝に銘じたことだった。
☆ エリカ・モリーニの芸術

当日、Kさんが持参された盤はいずれもヴァイオリン系のCDだった。曰く「ヴァイオリンと女性ボーカルの再生にかけては、AXIOM80の右に出るスピーカーはありませんからね。」。
いきなりだが、お医者さんの世界を引き合いに出させてもらうと、概ね総合医と専門医とに大別される。前者は内科系の総合医として一次医療のレベルで重宝されるし、それに比して後者は細かく分かれた専門分野に特化した医師として高度医療の分野で活躍する。
何が言いたいかといえば、オーディオの世界も似たようなものである。総合的に、たとえばジャズもクラシックも適当に聴けるシステムが総合医だとすると、クラシックならクラシック、中でもヴァイオリンの再生に特化した専門医のようなシステムがあってもちっともおかしくないと思うのである。
何でもかんでも70点で鳴らすシステムよりも、特定のジャンルにおいて90点を取ってくれるシステムの方が断然面白い。その反面、中には50点というジャンルもたしかに出てくるが、そういうジャンルはあえて聴かないようにすればいいのだから(笑)。
さて、画像にある「エリカ・モリーニ」さんは初めて耳にした女流ヴァイオリニストだった。モノラルだし、古色蒼然とした録音だったが、その演奏ぶりには一同たいへんな感銘を受けた。こんな凄いヴァイオリニストがいたのか!
翌日(10日)になって大いに気になるのでググってみたところ、どなたかのブログに次のような記載があった。
「モリーニはヴァイオリン好きのファンがとても多いヴァイオリニストである。ヌヴーやマルツィ、あるいはオークレールなどといったヴァイオリニストとともに今もCDが出ているので、忘れられた演奏家というのはあたらないかも知れないが、この1950年代までに頂点を迎えた演奏家たちは、ちょっとした盲点になっていることが多いので、しばらく集中してとりあげてみようと思う。
エリカ・モリーニは、1904年1月5日、当時のオーストリア・ハンガリー帝国の都市であったのトリエステ(現在はイタリア領)に生まれたヴァイオリニストだ。彼女は、ヴァイオリニストにして音楽学校を経営していた父(ヨアヒムの系列に属していたという)に手ほどきを受け、後にウィーンでオトカール・シュフチクとローザ=ホッホマン・ローゼンフェルトに学び、このウィーンで育った。だからモリーニはドイツ・オーストリア系のヴァイオリニストで、よく言われるようにウィーンの生んだヴァイオリニストである。~中略~
バッハの協奏曲やモーツァルトの協奏曲の録音などもあるし、前述のフィルクスニーと共演したフランクのヴァイオリン・ソナタなどは絶品である。これほどの人だから、やはり今も人気があるのだろう。過去の人として終わらせるには、実に惜しい人である。」
自分が知らなかっただけで、有名なヴァイオリニストだったというわけ。こういう収穫があるから人との交流は欠かせない。
☆ JBL3ウェイ・マルチシステムの功罪
お客さんたちにたいへん満足していただいた(と思っている)試聴会だったが、最後にJBL3ウェイマルチシステムを聴いていただいた。
ただし根っからのJBL嫌いのSさん曰く「聴かなくてももう分かってます。」と、拒否反応を示されたが、そこを「まあ、何とか」と口説いて無理矢理聴いてもらったが、やっぱり悪評さくさく(笑)。倍音の出方がまったく性に合っていないご様子だった。
前述した総合医と専門医の話に相通じるが「ワーグナーを聴くときだけは必要だと認めます。」とのことで、ようやく一件落着。
我が家の医療体制は一次医療も高度医療も広く充実している(笑)!
当日(9日)の夜、Sさんから次のようなメールが届いた。
「昼食まで御馳走になり、大変お世話になりました。〇〇〇+PP5/400アンプと最初期版AXIOM80で音楽再生装置として既に完成していると思います。私の好きなブリティッシュサウンド系の理想的な音が鳴っていました。今日は〇〇さんの努力の結果を聴かせて戴き良い経験になりました。私なら、あのシステムからは、もう何も足さない何も引かないでしょう。JBLシステムは………研究実験の為に弄って楽まれる分には宜しいかと思います。S 拝」
最新の画像[もっと見る]
-
 「早咲きタイプ」 と 「遅咲きタイプ」
3ヶ月前
「早咲きタイプ」 と 「遅咲きタイプ」
3ヶ月前
-
 「早咲きタイプ」 と 「遅咲きタイプ」
3ヶ月前
「早咲きタイプ」 と 「遅咲きタイプ」
3ヶ月前
-
 「早咲きタイプ」 と 「遅咲きタイプ」
3ヶ月前
「早咲きタイプ」 と 「遅咲きタイプ」
3ヶ月前
-
 「周波数レンジ」よりも「ハーモニー」を大切にしたい
3ヶ月前
「周波数レンジ」よりも「ハーモニー」を大切にしたい
3ヶ月前
-
 もしも村上春樹さんがオーディオ評論家だったら
3ヶ月前
もしも村上春樹さんがオーディオ評論家だったら
3ヶ月前
-
 もしも村上春樹さんがオーディオ評論家だったら
3ヶ月前
もしも村上春樹さんがオーディオ評論家だったら
3ヶ月前
-
 もしも村上春樹さんがオーディオ評論家だったら
3ヶ月前
もしも村上春樹さんがオーディオ評論家だったら
3ヶ月前
-
 CDのコピー及び貸与は違法ですか?
3ヶ月前
CDのコピー及び貸与は違法ですか?
3ヶ月前
-
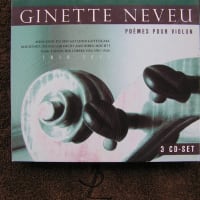 CDのコピー及び貸与は違法ですか?
3ヶ月前
CDのコピー及び貸与は違法ですか?
3ヶ月前
-
 日本でクラシック音楽の「すそ野」を広げる妙案がありますか?
3ヶ月前
日本でクラシック音楽の「すそ野」を広げる妙案がありますか?
3ヶ月前














