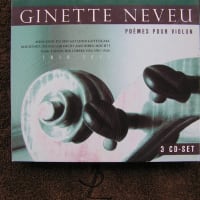前回からの続きです。
フィリップスのSPユニットが我が家の真空管アンプでうまく鳴ってくれて、お客さんのKさん(福岡)も一緒に喜んでくれたが、次にKさん持参のアンプに切り替えて聴いてみた。

この「VT25」(ウェスタン)シングルアンプは、以前、Kさん宅でラウザーの「PM6」をたっぷりと音量豊かに鳴らしていたので、たっての願いで持参してもらったもの。トランス類も大きくて持ち運びが大変だが、そこは仲間のよしみで無理をさせてもらった(笑)。
電源コード、RCAコードやSPコードなどの結線も無事済んで、音が鳴り始めたとたんにビックリ仰天!
これまで楚々とした可憐な鳴りっぷり、喩えて言えばヨーロッパの上流社会の貴婦人の佇まいを思わせる音だったものが、いきなりアメリカのとても元気のいいグラマラスな女性に変身したかのようだった。部屋中いっぱいに力強く豪快な音が鳴り響いた。
「スピーカーはアンプ次第でどのようにも変身するもんですね~。我が家にもこういうアンプが1台欲しいなあ。」と、まるで子供が気に入ったおもちゃを欲しがるような物言い(笑)。
Kさんは「フルレンジでこの音ですから立派なもんです。3ウェイシステムなんて目じゃないですよ~」と言いながら、追い討ちをかけるようにバッグの中から次から次に同種の球を取り出した。
RCAの210(VT25同等管:トリタン仕様)、レイセオンの4ピラー「210」、フランス製のVT25同等管。いずれも1920年代~1930年代の古典管である。
ちなみにKさんに言わせると古典管と近代管の境目は1940年というから恐れ入る。自分の基準は1970年なんだから、感覚がまるで違う(笑)。
次から次に球を挿しかえての「球転がし」それも、稀少管ばかりだから真空管マニアにとってはまるで天国のようなひと時だった。そして、ひときわ「いい音」だと思ったのがフランス製の球。
「フランス人はファッションと料理ばかりにうるさいと思ってましたが、音にもなかなか拘るもんですなあ。これほどの真空管を作る技術があるとは驚きました。」
「フランス人はやっぱりセンスがいいですね。刻印入りの2A3なんかは、一枚プレートを別にしてアメリカ製を軽く凌駕していますよ。味覚は聴覚と相通じるものがありまして、ほら、日頃から塩辛い味に馴れた人が正常な料理を口にすると物足りないと思うでしょう。聴覚も同じで、いつも低音をドスン、ドスンと鳴らして聴き慣れている人がAXIOM80みたいな音を聴くと物足りないと思うのと一緒ですよ。」
「成る程、それでわかりました。我が家にお見えになるお客さんは、これまでの経験上、音が気に入る人と気に入らない人がおよそ半々の確率なんですが、気に入らない人は日常聴き慣れている音と比べてあまりの違いに違和感の方が先に立ってしまうんですね。」
「半々の確率なら上等ですよ。世の中には舌が正常でなくてほんとうの味が分からない人が意外に多いみたいですよ。」
「そもそも門外漢に我が家の音を理解してもらおうなんて発想が間違いなんですね~」
どうやら「馬を水際まで連れて行くことは出来るが、水を飲ませることは出来ない」(英語のことわざ)と相通じるものがあるようでして~(笑)。
それやこれやで、試聴もいよいよ佳境に入って、次に「AXIOM301」(タンノイ・ウェストミンスターの箱入り)に移った。
これはフィリップスのユニットと比べて一筋縄ではいかなかった。
アンプをWE300Bシングル、PX25シングル、2A3(刻印入り)シングル、71Aシングルと、とっかえひっかえして「アンプ転がし」をやってみた。
さらに、これらに組み合わせるプリアンプが3台入り乱れるのだから、その乱戦模様は推して知るべし(笑)。
プリアンプは、「真空管プリ」、「トランス式アッテネーター」(カンノ)、そしてクレルの「PAM-5」(TR式)。
いつぞやのブログで触れた「PAM-5」は、この6月のオークションで望外の安値で手に入れたものの使い出してものの2週間もしないうちに、ガサゴソとノイズが発生して修理に出さざるを得ない破目に陥った。
梅雨の湿気ということもあるだろうし、別府温泉特有の大気中に撒き散らされる噴気のせいもあるかもしれない。別府はとかく電気機器の故障が多いのは周知の事実。
それはともかく、とうとうコンデンサーを20個も交換して目の玉が飛び出るような修繕代がかかってしまい、安値の積もりが結局高値になってしまってガックリ。ま、いっか、家内にはくれぐれも内緒~(笑)。

しかし、この「PAM-5」が今回は名誉挽回とばかりに大活躍だった。さすがはクレル!
「これまでいろんなお宅でAXIOM301を聴いてきましたが、ここの音がベストですよ。あまりいい評判を聞かないAXIOM301ですが、ここまで鳴ってくれれば立派なものです。これならもうツィーター(高音用)は必要ありませんよ。」
「もともとAXIOM301は発売当時、トレバックス(グッドマン)というツィーター付きでのセット販売でしたが、必要ありませんかね?」
「ええ、当時はトランジスターアンプの時代でしたからツィーターをつけざるを得なかったのでしょう。そもそもフルレンジの場合、真空管アンプで澄み切った中高音が出せればツィーターの必要性を感じないものです。ツィーターが欲しくなるときはアンプに原因がありますよ。」
結局、「AXIOM301」のベストの組み合わせはプリアンプが「PAM-5」、パワーアンプが「71Aシングル2号機」に落ち着いた。
今回の試聴会も「真空管オーディオ」の奥深さを実感した一日となった。
これまで50年近くにわたってオーディオをやってきたのにいまだに未知の世界が果てしなく広がっている気がしているが、はたして自分は進歩しているんだろうか?
「この道を 行く人なしに 秋の暮」(芭蕉)