これまでの長~いオーディオ人生の中でいろんな方と接触してきたが、大きく分けると2つのタイプがあるように思う。
一つはメーカーがつくった製品に絶大の信頼を置き、あちこち弄ることなくオリジナルのまま終生大切に使うタイプ。これを「オリジナル至上派」としよう。
もう一つはメーカーがつくった製品に初めから疑いの眼を向けるタイプ。どうせメーカーなんて儲けることを至上の目的にしているんだから、目に見えないところでコストダウンを図っており該当するとおぼしき箇所を弄ればもっと音が良くなるだろうと信じ込む輩でこれを「改造派」としよう。
もう言わずもがなだが、じぶんは明らかにずっと「改造派」を通してきた。しかし来し方を振り返ってみてはたしてこれで正しかったのかどうか、いまだに確信が持てないところがあるのも事実。
まあ、音響ひいてはオーディオなんてすべて科学的に解明されているわけではないので、断定的な物言いや思考は厳に慎むべきことであることもたしかだ。
ただ、一つ確実に言えることは、オリジナルを改造した製品をオークションに出した場合、確実に相場より値が下がることだけは請け合っておこう(笑)。
それではここで「最たる改造派」の失敗例を具体的に上げてみることにしよう。なにしろタンノイのフラッグシップモデル「ウェストミンスター」の中身を改造してユニットを入れ替えるほどの無茶をやる男だから「最たる改造派」といってもおかしくはないだろう。
☆ 「AXIOM80」のARUについて
「ARU」とは「Acoustic Resistance Unit」の略で、音響的にユニットに負荷をかけて低い音を平坦に伸ばす役目を持っている。
これだけではサッパリだろうからもっと立ち入ると、コーン型ユニットは前に出る音(正相)と同時に後ろにも音を出す(逆相)。この両者が混じり合うと音を打ち消し合うので仕方なくユニットを箱に納めているわけだが、この逆相の音(背圧)をうまく利用してユニットに負荷をかけるのがARUというわけ。

画像中央部分のお粗末で小さな桟で囲まれた部分がARUの実体である。普通のバスレフタイプみたいに簡単に背圧を逃がすことなく、いわゆるタメをつくってユニットに負荷をかけて低音域を伸ばそうという天才的な着想である。
実を言うと、我が家の場合これまでこの部分に細かなメッシュ(網の目)状の金網をずっと被せてきた。背圧をさらに逃がさないようにすると、もっと低音域が伸びるかもしれないという期待からである。今思うと、これぞまさしく「素人の生兵法」だった。
さすがにオーディオ仲間のSさん(福岡)からは見るに見かねて、「早く元通りにした方がいいと思いますよ」というアドバイスをいただいたものの、それほど違和感を感じることもなく「まあいいか」と、半信半疑ながらこれで通してきた。
しかし、このたびの中低音域に豊かな響きを持つ「71APP」アンプの出現がオーディオ環境を一変させた。大いに刺激を受けてようやく「金網を外してみるとどうなるかな」という思いに至った。
昨日(24日)の早朝、起き抜けにスピーカーボックスを裏返しにして左右両方のARUの部分に釘を打って取り付けていた金網を難なく取り払った。時間にして20分あまり。
工事終了後、さあ、どのくらい音が変わったのだろうかと興味津々で機器のスイッチをオン。
ウ~ン、参った!音の豊饒さとともに鮮度が向上しヴァイオリンの音色が一段と冴えわたってきた。中低音域の物足りなさはスピーカーではなくてアンプに責任を求めるべきだったのだ。
「グッドマンさん、信用しなくてどうも申し訳ありませんでした。」と深々と頭を垂れたことだった(笑)。
最新の画像[もっと見る]
-
 「早咲きタイプ」 と 「遅咲きタイプ」
4ヶ月前
「早咲きタイプ」 と 「遅咲きタイプ」
4ヶ月前
-
 「早咲きタイプ」 と 「遅咲きタイプ」
4ヶ月前
「早咲きタイプ」 と 「遅咲きタイプ」
4ヶ月前
-
 「早咲きタイプ」 と 「遅咲きタイプ」
4ヶ月前
「早咲きタイプ」 と 「遅咲きタイプ」
4ヶ月前
-
 「周波数レンジ」よりも「ハーモニー」を大切にしたい
4ヶ月前
「周波数レンジ」よりも「ハーモニー」を大切にしたい
4ヶ月前
-
 もしも村上春樹さんがオーディオ評論家だったら
4ヶ月前
もしも村上春樹さんがオーディオ評論家だったら
4ヶ月前
-
 もしも村上春樹さんがオーディオ評論家だったら
4ヶ月前
もしも村上春樹さんがオーディオ評論家だったら
4ヶ月前
-
 もしも村上春樹さんがオーディオ評論家だったら
4ヶ月前
もしも村上春樹さんがオーディオ評論家だったら
4ヶ月前
-
 CDのコピー及び貸与は違法ですか?
4ヶ月前
CDのコピー及び貸与は違法ですか?
4ヶ月前
-
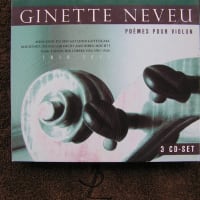 CDのコピー及び貸与は違法ですか?
4ヶ月前
CDのコピー及び貸与は違法ですか?
4ヶ月前
-
 日本でクラシック音楽の「すそ野」を広げる妙案がありますか?
4ヶ月前
日本でクラシック音楽の「すそ野」を広げる妙案がありますか?
4ヶ月前














