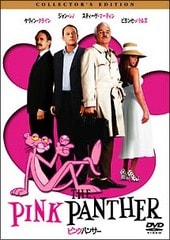嗅覚の天才児ジャンにとって匂いこそが神。彼の神はただ一人、匂いだった。追い求める匂いを得るために彼は身も心も投げ出し、禁断の匂いをついに手に入れたとき、ついに彼こそが神となった。
これはたった一人の神に魅入られ神のために全てを捧げ、神のために破滅する孤独な男の壮絶な物語。クライマックスシーンのどんでん返しには息を飲んだ。スピーディでスタイリッシュなティクヴァの映像センスが全開した作品。途中ちょっとだれて眠くなり、寝たきりおばさんになってしまったけれど、後半は一気に魅せます。
18世紀、パリの街はとても臭かったという。その臭気を消すために人々はやっきになり、香水が人気を集めた。調香師がヒット作を作れば飛ぶように売れるし、そうでなければ落ち目となる。
かつての栄華も何処へやら、いまやすっかり客足の遠のいたベテラン調香師の店に押しかけて弟子入りするのが我等がヒーロー、ジャン=バティスト・グルヌイユ(ベン・ウィショー)だ。彼は汚く臭いパリの市場で産み落とされ、鬼婆の養母のもとで13歳まで育てられた。彼の出生と育成にまつわるエピソードがまさに臭い立つほど汚く印象的だ。
映画の最後の技術的難問といわれている「匂い」がこの作品のテーマ。実際に映画館でチョコレートの香りを噴霧した
「チャーリーとチョコレート工場」が上映されたとはいえ、まだ香りつき映画というのは一般化するのは程遠い。第一、異臭を放つような映画ではこういうことは困るしね。本作の見所は「香り」をいかに映像で見せるか、ということに尽きる。
それにしても「臭い」をテーマに持ってきたというのがいかにも現代風だ。欧米ではどうか知らないが、日本では今や空前の消臭ブームが続いている。かつて日本人は今ほど臭いに敏感ではなかったと思う。せいぜい香を焚き染めるぐらいだったのに、もはや着香を通り越して消臭時代なのだ。売らんかなの広告に指摘されるまでは、人々は自分が臭いということを気にしていなかった。口臭体臭を今ほど気にする時代はないのでは? 食生活が欧米化して肉食が増えたから実際に日本人が臭くなったのかもしれないし、エスニック料理が好まれて口臭もきつくなったのだろうか? それよりも、やはり「お前は臭い、臭いニオイは消さなきゃダメ」という強迫観念のほうが強いではないだろうか。臭いについて社会学的に研究したらかなり面白い結果が出そうな気がするが、この話はともかくとして映画の話に戻る。
ティクヴァのカメラは舐めるように臭いを映し出す。赤毛の美少女の匂いに魅せられたジャン=バティストが思わず殺してしまった相手の匂いを嗅ぎまわる場面といい、薄汚い彼がかぐわしい香水を生み出す場面といい、常に不機嫌でにこりとも笑わない演技で観客の嫌悪と畏怖の念を招来するベン・ウィショー、お見事でした。しかし個人的な趣味からいうともっとイケメンだったらよかったのに…
フランスのお話なのにフランス語が聞けなかったというのはまあ、許すとしよう。とにかくクライマックスシーンは圧巻、これに尽きます。香りによって天使になった男。淫猥な天使の香りは聖職者をもたぶらかす。ラストもすごいよ、愛は貪りつくす。すさまじいです。
<2007.12.27追記>
ラストシーンはテオ・アンゲロプロス監督の「アレクサンダー大王」へのオマージュと思われる。
-----------------------------------------------
パフューム ある人殺しの物語
PERFUME: THE STORY OF A MURDERER
上映時間147分(ドイツ/フランス/スペイン、2006年)
映倫 PG-12
監督・脚本・音楽: トム・ティクヴァ、原作: パトリック・ジュースキン
出演: ベン・ウィショー、ダスティン・ホフマン、アラン・リックマン、レイチェル・ハード=ウッド、アンドレス・エレーラ