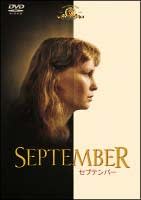物語は室内に限定され、舞台劇のような会話主体の作品。ウディ・アレンの作品の中では「インテリア」系列のシリアスドラマだけれど、「インテリア」ほどには緊張感や寂寞感がない。それは、アレンの視線が「インテリア」のときよりやさしくなっているからではなかろうか。そして、緊張感を解きほぐすのは音楽だ。古いジャズが流れるととてもいいムードが漂い、重い話の中に軽さをトッピングする。この音楽、すっかり気に入ってしまった。
家族の中に一人過去の傷の犠牲になっている娘レーンがいて、その娘もすでに中年という年齢なのに、恋人もいない。心を寄せている作家ピーターはレーンの親友ステファニーを愛しているのだが、そのことをレーンは知らない。そしてレーンに心を寄せて告白する年上の男もいるのに、レーンの気持ちはピーターへの片想いでいっぱいだ。お互いへの想いは見事にすれ違い、危うい感情のもつれが行き来する。ステファニーには夫も子どももいるのに、ピーターに言い寄られると心が揺れる。
レーンの心の傷は我が儘で奔放な母のせいなのだが、母は自分の波瀾万丈の人生をピーターに伝記小説として書かせようともくろんでいる。傍若無人で他者を顧みることのない母だけがこの作品のなかであっけらかんと輝いている。彼女は人生を楽しみ、これからも他者の優しさを踏み台にして生きていくのだろう。
レーンの心の傷が物語の最後にさしかかってやっと爆発するように彼女の口から語られたとき、わたしは思わず息を呑んだが、その物語がより深く紡がれることはない。結局のところ、いろいろ撒かれた種は物語の最後に回収されることなくそのまま流れるようにあるいは澱みながら人々の心に「想い」を残していく。ベルイマン監督の「秋のソナタ」と同じ構造、同じテーマを持つ作品だけれど、ベルイマンのように徹底して人の心理の奥底や醜さに分け入ることをしなかったために、本作はどこか中途半端な印象が残る。それだけにかえってレーンの心の傷が癒されていくのではないかという希望も感じる。
本作で光っていたのはダイアン・ウィーストの演技だ。彼女の個性的な小さなそして美しい目、苦悩を目の縁に宿す表情が印象に残る。(レンタルDVD)
------------------------
SEPTEMBER
アメリカ、1987年、上映時間 83分
監督・脚本: ウディ・アレン、製作: ロバート・グリーンハット、チャールズ・H・ジョフィ
出演: ミア・ファロー、デンホルム・エリオット、ダイアン・ウィースト、エレイン・ストリッチ、サム・ウォーターストン、ジャック・ウォーデン
家族の中に一人過去の傷の犠牲になっている娘レーンがいて、その娘もすでに中年という年齢なのに、恋人もいない。心を寄せている作家ピーターはレーンの親友ステファニーを愛しているのだが、そのことをレーンは知らない。そしてレーンに心を寄せて告白する年上の男もいるのに、レーンの気持ちはピーターへの片想いでいっぱいだ。お互いへの想いは見事にすれ違い、危うい感情のもつれが行き来する。ステファニーには夫も子どももいるのに、ピーターに言い寄られると心が揺れる。
レーンの心の傷は我が儘で奔放な母のせいなのだが、母は自分の波瀾万丈の人生をピーターに伝記小説として書かせようともくろんでいる。傍若無人で他者を顧みることのない母だけがこの作品のなかであっけらかんと輝いている。彼女は人生を楽しみ、これからも他者の優しさを踏み台にして生きていくのだろう。
レーンの心の傷が物語の最後にさしかかってやっと爆発するように彼女の口から語られたとき、わたしは思わず息を呑んだが、その物語がより深く紡がれることはない。結局のところ、いろいろ撒かれた種は物語の最後に回収されることなくそのまま流れるようにあるいは澱みながら人々の心に「想い」を残していく。ベルイマン監督の「秋のソナタ」と同じ構造、同じテーマを持つ作品だけれど、ベルイマンのように徹底して人の心理の奥底や醜さに分け入ることをしなかったために、本作はどこか中途半端な印象が残る。それだけにかえってレーンの心の傷が癒されていくのではないかという希望も感じる。
本作で光っていたのはダイアン・ウィーストの演技だ。彼女の個性的な小さなそして美しい目、苦悩を目の縁に宿す表情が印象に残る。(レンタルDVD)
------------------------
SEPTEMBER
アメリカ、1987年、上映時間 83分
監督・脚本: ウディ・アレン、製作: ロバート・グリーンハット、チャールズ・H・ジョフィ
出演: ミア・ファロー、デンホルム・エリオット、ダイアン・ウィースト、エレイン・ストリッチ、サム・ウォーターストン、ジャック・ウォーデン