このところ恒例になった東響プレミアムコンサートに行った。このコンサートの楽しみが二つある。一つは本番前に、ロビーコンサートと称して東響のメンバーがプレコンサートを行うことだ。自己紹介を皮切りに、おしゃべりを交え、自分の楽器に合わせて、数曲の小品を演奏するのだが、立ち見主体で、椅子は20人分ほどしか用意されない。あくまで演奏前のサービスだが、ここにも心豊かにする音楽を聴きに心の狭い自己中のバーさんがいたのだ。演奏者の真ん前に、席取りをするため2席分傘を置いて、演奏直前に自分の身内を捜して連れてきたのだ。しかもいい年をした2人は衆人の冷たい視線を何喰わぬ顔をして着席したのだ。孫が体の不自由なおばあさんのためにするならまだしも、周りにはそれこそ年寄りも多かった中で、このババーとしか言いようのない心狭き感性のない人が、コンサートに来るとは思えなかった。 せっかくの地元所沢出身のハーピストの演奏は素晴らしかっただけに、よい音楽に水を差した、ババーのあさましき行為は許しがたかった。これと似たことは、ワンコイン(500円コンサート)でもよく見かける光景なのだが、これまた決まってババーのグループなのだ。
二つ目は地元県立芸術高校の生徒が学内オーディションの合格者が参加することだ。ここ何年かは私が聞いた限りでは女子生徒の女優勢なのだが、今回も、ホルン2名、トロンボーン1名の3名が参加した。
最初の曲目である「はげ山の一夜」に3名の女子学生が参加し、ド派手な金管を見事にオケに溶け合って演奏した。指揮者のアンドレ・フェーフェル、全く知らない人で、名前も知ったのも、演奏も聞いたのも、この日が初めてだった。テンポの良い演奏で、お尻フリフリの指揮姿は、同じルーマニア出身の大指揮者チェリビダッケを真似たのか同かは知らないが、小気味よいテンポでの演奏は良いが、この曲の持つドロドロした混迷の中へ引きこまれそうな恐怖感は感じられず、祭りの時の「お化け屋敷」的な雑踏感だけが残った演奏だった。
(私の手持ち)
 ロリス・チェックナヴォリアン:アルメニア・フィルファーモニー:今日の演奏を一回り大きく(強弱の幅が)した演奏。
ロリス・チェックナヴォリアン:アルメニア・フィルファーモニー:今日の演奏を一回り大きく(強弱の幅が)した演奏。
 ロリン・マゼール:ベルリンフィル:この曲のスタンダードな演奏
ロリン・マゼール:ベルリンフィル:この曲のスタンダードな演奏
 イーゴリ―・マルケヴィッチ:ゲバントハウスOrch :1974年録音:フランツ・コンビチュニーの率いたドイツの伝統を、インターナショナル化した。強弱の激しい演奏だが野卑ではなくマルケヴィッチの力量を示した演奏。
イーゴリ―・マルケヴィッチ:ゲバントハウスOrch :1974年録音:フランツ・コンビチュニーの率いたドイツの伝統を、インターナショナル化した。強弱の激しい演奏だが野卑ではなくマルケヴィッチの力量を示した演奏。
 私の推薦盤:1994年10月14日サントリーホールでの実況録画・録音DVD:クラウデイオ・アバド*ベルリンフィル:圧倒的な力量をいかんなく発揮した。スケールの大きな演奏でそれでいながら音楽は美しく流れる名演奏。画像も比較的きれいに見られる。
私の推薦盤:1994年10月14日サントリーホールでの実況録画・録音DVD:クラウデイオ・アバド*ベルリンフィル:圧倒的な力量をいかんなく発揮した。スケールの大きな演奏でそれでいながら音楽は美しく流れる名演奏。画像も比較的きれいに見られる。
チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲:今日のメインの曲目だ・神尾自身がチコフスキーコンクールの優勝者だけに、看板プログラムではあるが、正直私自身はさほどこの曲は好きではない。でもいざ演奏が始まるや、神尾の音色には引き込まれた。やはり何度聞いても、力強さと美しさを兼ね備えた神尾の音色に引き込まれた。音色の美しさと力強さの両者がバランスよく備えている人はそう多くはいない。神尾の音を聴くことは両者のすばらしさを聴く喜びでもある。今日の曲目がブラームスであったなら、もっと楽しめたのだが。それでも今日のコンサートはこの曲で元は十分に取れた。素晴らしかった。
アンコールにパガニーニの24のカプリチョの最終曲が聴けた。これまた力強い素晴らしい演奏だった
チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲の手持ちはこのブログの 2017年12月12日を参考にしてください。
最後は、久しぶりに、ショスタコーヴィチの交響曲5番が聴けた。正直、最近きく外来のオケと比較しても、日本のオーケストラの音は、負けてはいないと思う。むしろ、ムカシの名前ででています的な、かつての「名オーケストラ」よりは優れていると実感として感じる。オケにも若い人が多く、みな楽器もよいものを持っているのだろう。ミューズで聴いた外来オケにがっかりさせられたこともしばしばあった。今日の演奏に関しては、オケの問題よりは指揮者の問題だと思うが、ショスタコの5番としては響きは軽く、音色は明るすぎたと思う。やはりこの曲の持つ歴史は、「歴史に翻弄され虐げられた民へのレクイエム」だと思う。その歴史を無視した演奏はシンセサイザーの機械的打ち込みで足りる。
私の手持ち
AはUSAからの輸入VHSのビデオテープを現在はDVDに焼き直したものを所持。BはCBSソニー時代のCD。どちらも音源は1979年7月2日OR7月3日の東京文化会館での実況録画録音だが、Aはどちらかの日付けをTBS・TVが録画録音したものだが、Bは演奏時間が微妙に違い、2日間の録音を編集したのかAとは違う日の録音か不明。正直録音はあまりよくないが、Aの映像はそれなりで、あまり演出はなく自然体でとらえている。
② エフゲニー・ムラヴィンスキー+レニングラードフィル 1973年録画・録音 観客のいないフィルハーモニー大ホールでのゲネプロを録画録音。映像も録音も古さを感じる
エフゲニー・ムラヴィンスキー+レニングラードフィル 1973年録画・録音 観客のいないフィルハーモニー大ホールでのゲネプロを録画録音。映像も録音も古さを感じる
③ エフゲニー・ムラヴィンスキー+レニングラードフィル 1982.11.18 録音 場所不明 基本的に②の演奏と大差なし。録音面では改善されているがさほど進化は感じない。
エフゲニー・ムラヴィンスキー+レニングラードフィル 1982.11.18 録音 場所不明 基本的に②の演奏と大差なし。録音面では改善されているがさほど進化は感じない。
④ ルドルフ・バルシャイ +WDR交響楽団 1995/7-1996/7録音 ケルン 作曲者の長きにわたる友人の「ショスタコ―ビッチの証言」(=現在で真偽半々の作曲者の名をかたった伝記ものとされている=)以後に録音された全集盤の一部)
ルドルフ・バルシャイ +WDR交響楽団 1995/7-1996/7録音 ケルン 作曲者の長きにわたる友人の「ショスタコ―ビッチの証言」(=現在で真偽半々の作曲者の名をかたった伝記ものとされている=)以後に録音された全集盤の一部)
⑤ オレグ・カエターニ+ミラノ・ベルディー交響楽団 2001-2年録音 デジタル録音と私の好きな指揮者であるイーゴリ・マルケヴィッチの息子ということで購入したが、24bit/96kHzの録音メリットもあまり感じられない、オケの音も荒いし演奏も雑だ。
オレグ・カエターニ+ミラノ・ベルディー交響楽団 2001-2年録音 デジタル録音と私の好きな指揮者であるイーゴリ・マルケヴィッチの息子ということで購入したが、24bit/96kHzの録音メリットもあまり感じられない、オケの音も荒いし演奏も雑だ。
⑥ ベルナルト・ハイティンク+アムステルダム・コンセルトヘボウ 1981/03録音 私の推薦盤 演奏・録音ともに変な思い入れもなく淡々とした曲運びだが、それだけに終わった後に曲のすばらしさが押し寄せてくような名演だと思う。
ベルナルト・ハイティンク+アムステルダム・コンセルトヘボウ 1981/03録音 私の推薦盤 演奏・録音ともに変な思い入れもなく淡々とした曲運びだが、それだけに終わった後に曲のすばらしさが押し寄せてくような名演だと思う。
アンコールは、高校生も加わり、チャイコフスキーの「くるみ割り人形」からのトレパックだった。
カミサンからは夕食はなしと告げられていたことから、航空公園駅の駅ビル内の京樽で持ち帰りの「茶きん寿司」と朝食用のパンを仕入れて帰宅。それにしても所沢ミューズの改装工事で、あと2か月の数公演を残して、来年からの、ミューズでの音楽生活がなくなることでその代替をどうするか探さねばならなくなった。
菩提樹田んぼの会のBlogを更新しました
おっくっぽのブログ
http://bodaiigitannbo.cocolog-nifty.com/blog/



















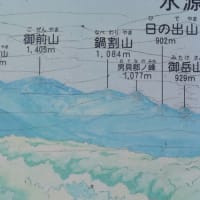





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます