私の音楽コレクションの数量では、シャルル・ミュンシュ、イーゴリ・マルケヴィッチの二人の指揮者が群を抜く。これは一種の刷り込み現象のようなもので、クラシック音楽を聴き始めた中学・高校のころに家にあった数少ない二人のLPレコードをよくきいていたからだ。しかし70超えになって振り返れば、様々な指揮者の音楽に接してきたがこの二人ほど真逆の個性的な唯一無二の指揮者だったのだと思わずにいられない。
そんな二人のモスクワでのLive録音のCDがソ連崩壊後にメジャーレーベルと怪しげなマイナーレーベルから出現した。
先ずはミュンシュがボストン交響楽団を引き連れての演奏会、1956年9月モスクワ音楽院大ホール。

この年の2月にはフルシチョフのスターリン批判が起こり、それが東欧圏内広がり、ポーランド、ハンガリーでの動乱が起こるなか、ミュンシュとボストンSymの演奏は自由を謳歌する西側のある種プロパガンダの役割を果たすべく、当時のソ連に演奏旅行をおこなった。変幻自在なリズムに合わせて、明るく、透明度の高い響きは当時のモスクワ市民?(おそらく当時の聴衆者は共産党の幹部連中の家族が中心と思われるが)には驚きだっただろうと思われる。残念ながら当時のソ連の技術ではミュンシュの音楽を捉えることができず音割れしているのが残念であるが、1956年の歴史を語っている。この日の演奏は、R.シュトラウス、デュカス、ラヴェルと音色の多彩さを示すとともに「暗黒のスターリン時代」に対して「アメリカンドリーム」の豊かさの象徴を示したのかもしれない。
そしてミュンシュは10年後に単独で1965年にスベトラーノフが常任指揮者を務めたソ連国立交響楽団に招かれ、オールフランスもののプログラムのコンサートを行った。このCDはその時の会場録音ではなく私の推測だがゲネプロの録音と実況との切り張りに思うのだが?あまりにもミュンシュの実演時の感情の爆発が感じられないのだ。

ジャケットの説明ではスベトラーノフが1956年の先の演奏を聴き感動し、自身が新設されたオケのシェフになり、どうしてもドビュッシーの音がだせないオケに、ミュンシュに教えを乞うために招いたとのことだそうだ。
言われてみれば、ミュンシュの演奏にしてみれば、素晴らしい演奏ではあるが、至極真っ当な演奏で、爆発的な感動はないものソ連国立交響楽団の粗っぽさが弱めに抑えられているのはミュンシュののなせる業なのだろう。
ソ連時代のメロディアレーベルのLPを知っている身には私のスキャナーでは上手くスキャンできなかったが、このCDのジャケットは当時のメロディアレーベルのクラシック音楽とは思えないほど素敵なデザインだと思った。
演奏曲の中では、ミュンシュといえどもドビュッシーの海はオケの透明感が弱いが、反面、オネゲルの交響曲No2は弦楽器の鈍重さが効果を発揮しているとおもった。
「ミュンシュ大好き」人間には予期せぬ演奏に巡り会えた感じでひさしぶりにCDに感動した。














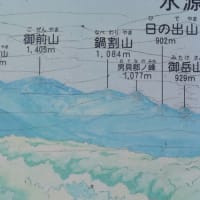





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます