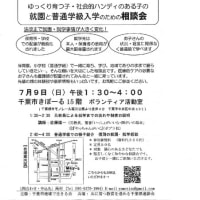《通級を語るために確認しておきたい大切なこと》
(最初のメモ・02)
《通級をすすめる前の確認事項
[1] 通級に行くことが、真に「状況の支援」のためであり、誰でも歯が痛いときには歯医者に行くように、ただそれだけの、「状況の支援」だと、「抜き出して個別指導」することの意味と限界を、担任として理解しているか。
[2]それを、子ども自身が理解しているか
[3]それを、周りの子どもが理解しているか
[4]それを、子どもの親が理解しているか
[5] 「状況の支援」とは、ある一定の期間のことだという、了解ができているか
[6]たとえば、歯科の矯正の説明のように、その効用と期間と改善の見込みを、きちんと説明した上での了解を得ているか。
[7]たとえば、外国から来たばかりの子どもへの「日本語の個別指導」のように、個別の配慮が必要な意味と、期間と、「みんなと一緒に過ごす時間」の中での、「日本語をめぐる状況の支援」が、どれくらい考えられているか。
[8] 大人の理屈や事情がどうであれ、みんなと違う扱いをされる、「分けられる子どもの恥ずかしさ」を理解しているか。
[9] 「恥ずかしさの体験」が、子どもの一生背負う生きづらさの原因になることがあると、理解しているか。
みんなと「別」に扱うということ、それが子どもの命を救う「入院」であれ、家族や友だちと分けられた子どもは、「何か自分が悪いことをしたから、だいすきな人たちと分けられてしまった」のだと感じることがあると、「子どもの気持ち」(心理)にきちんと配慮ができているか。
[10] 骨折や火傷で入院したのであれば、ある期間が過ぎれば退院して、家族の元へ、友だちのなかへ還ることができる。
でも、たとえば、両親が事故で亡くなったときには、子どもはそれまでの生活の場から「施設」へいくこともある。
その場合、子どもの中で「個別」は一生つづく。
「通級」であれ、「個別指導」であれ、大切な居場所から子どもを抜き出すということは、子どものこころに「副作用」のおそれがあると、理解しているか。
[11] それは、「自己肯定感」を長期にわたって、損ねる場合がある。
その後の人生で、学びの場面だけでなく、人間関係や、仕事の面においても、あらゆる場面で、たとえ不足がないときにも自分に足りないものがあると間違わせる「おそれ」を与えることがある。
その「初期設定」を行う危険があると、理解しているか。
[12] そもそも、大人は、「子どもの《恥ずかしさ》を分かってあげる感覚が足りない」という自覚があるか。
・・・で、いろいろ考えているうちに、このブログの左上の言葉に戻る。
いっぱいサイコロを振って、いっぱい進んだように思ったのに、結局は「振り出しにもどる」ってやつだ(゜o゜)
《子どもの屈辱をわかってやる感覚が、
私たちにはまだ備わっていません。
子どもを尊重しその傷ついた心を知るというのは、
知的な行為ではありません。
もしそれがそんなものだったら、
もうずっと前に世間一般に広まっていたことでしょう。》
(アリスミラー)