著者 田辺聖子(1928~) 発行者と年 新潮社/1987年
図書館より借用 初出 1985年9月~1987年11月「小説新潮」
78歳の歌子さんは、夫に先立たれ、3人の息子たちとも別居して、
気侭な独り暮らし。大店を切り廻した才覚で、株でもうけ、
書道を教え、訪問販売を撃退し、趣味や社交を楽しんでいる。
「姥シリーズ」は4冊で歌子さん77歳~80歳、著者50代~60代。
1.姥ざかり 2.姥 . . . 本文を読む
著者 田辺聖子(1928~)副題 私の終戦まで 新潮文庫/1981年初出 ポプラ社/1977年 購入1991年@無暦堂/三鷹市(200÷3)円日の丸の鉢巻をして、防空頭巾をつけた少女の絵。健気さと可笑味の漂う横顔に、聖子さんの面影がある表紙だ。13歳から17歳の時期、女学校の友と作った雑誌や、ノートに書いた小説類をもとに振り返っている。戦争に明け暮れた少女時代である。防災訓練や、工 . . . 本文を読む
著者 米谷ふみ子 (コメタニ フミコ)
副題 ある国際結婚の話 <Tales of Inter Marriage>
発行者と年 文芸春秋社 1989年(1988年「新潮」初出)
【物語】留学中の20歳の息子とその同棲相手と、両親であるユダヤ系米国人と日系の妻とが、パリで会食する。「ボチチェルリーのビーナスの顔から哀愁を除いたような、朗らかな顔をしている」息子の彼女に、意外にも嫉妬よりは友情を感 . . . 本文を読む
こましゃく・きみ〔1925-2007.〕大阪市生まれ
元法政大教授。静岡県伊豆市姫の湯の「友だち村」で死去。
去る5月22日に、82歳で亡くなった駒尺喜美さん。30年以上にわたり、私にとって親しい友、尊敬する先達、頼もしい同志だった。(手紙を出すことも、面会することもなく、単なる一読者として、こちらで勝手に思い込んでいた丈だが。)日本文学と女性学の研究者。実践的女性解放活動家・小西綾さんと、5 . . . 本文を読む
著者 きだみのる(1895-1975) 発行所・年 読売新聞社 1971年
「きだみのる自選集・第2巻」(図書館より4・11~)
現象氏のブログで映画「気違い」(3月12日記)を読んで食指が動き、図書館から借りて読んだ。
放浪の作家、きだみのるの人物像は、私の中で長い間、はっきりしないままだった。顔写真を見たのもつい最近。ベレーの似合う丸顔だとばかり思っていたが、実は長方形だった。 . . . 本文を読む
壇もとい檀一雄(1912-1976)の、私にとって幻の作品。「花筐」の意味は花を入れる目のつんだ竹かごで、謡曲の題にもある。※作家の花登筺(はなとこばこ)の「筺」の字に似ているが、こちらは王ではなく玉で1画多い。けさ松江の即席しるこを喫してから包み紙を見ると「花小筐(はなこばこ)」とあったので思い出した次第。1973年に旺文社文庫で出ているがそれ以前、どこかで一度だけ読んだ事がある。その時受けた衝 . . . 本文を読む
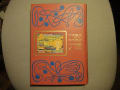 著者 デ・ラ・メア 訳者 野上彰 出版社と年 創元社 1956年
収録 世界少年少女文学全集 34巻 イギリス篇
デ・ラ・メアは1887ー1956の英国の詩人・小説家。
現実と空想がまざりあったふしぎな世界を書くのが好きだった。
詩も幻想的なのが多いし、小説も同様だ。
野上彰は1909-1967、第七高等学校卒(後略)鬼才・多才といわれた
前衛詩人、らしい。(偶然にも私の伯父が同じ年齢、同じ高 . . . 本文を読む
著者 デ・ラ・メア 訳者 野上彰 出版社と年 創元社 1956年
収録 世界少年少女文学全集 34巻 イギリス篇
デ・ラ・メアは1887ー1956の英国の詩人・小説家。
現実と空想がまざりあったふしぎな世界を書くのが好きだった。
詩も幻想的なのが多いし、小説も同様だ。
野上彰は1909-1967、第七高等学校卒(後略)鬼才・多才といわれた
前衛詩人、らしい。(偶然にも私の伯父が同じ年齢、同じ高 . . . 本文を読む
著者 谷崎潤一郎(1886-1965) 中公文庫 97年版(図書館)
初出 1956年1月 中央公論
初老の男性の性の悩みがテーマの小説。
雑誌連載当時は、売春禁止法案を審議中の衆院法務委員会で取り上げられ、
「文芸の名の下に老人たちがああいういたずらをすること」
「新道徳が確立しない時期に、ああいうものがハンランすること」が思春期の
青少年に悪影響を与えるのではと、「太陽の季節」ともども懸念 . . . 本文を読む
著者 勝目梓 発行所 講談社 発行年 2006年 (図書館)
作者(1932~)は、雑誌や本の広告でよく名前を見ているが、読んだ事はない。
「バイオレンスとセックス」の大家では、無理もないか。
私がつとめて避ける方面だ。私だけでなく、大抵の女子はそうだろう。
先日、新聞の書評の文面で、ふと興味を持ったので、早速借りに行った。
幸い、近くの図書館にあった。そして、一読、面白いのである。とくに、 . . . 本文を読む
著者 松本清張(1909-1992) 発行所・年 中央公論社・1967年
1965年9月婦人公論に連載開始(図書館)
初めて読んだのは30年近く前、小説の舞台となるシリアで、しかも登場人物のモデルだった獣医のO氏にそのことを教えられてだった。「私は”猫背の獣医”になっているのですよ」と、氏は面映ゆげに語った。1冊しかないその本は娯楽の少ない現地では引張りだこだったので、ゆっくり味わえなかった。3 . . . 本文を読む
1988年講談社 耕治人(コウ・ハルト)1906-1988(図書館)
同じ名前の映画を見たおかげで、この人の名前を初めて知りました。
命終3部作といわれる「天井から降る哀しい音」「どんなご縁で」
「そうかもしれない」と、より若いころの「料理」を借りてきました。
作者は熊本県の出身、7歳で母、15歳で父と2人の兄を、数年後に
妹も亡くし、天涯孤独の身です。町の床屋ではうつるからと、
入店をことわ . . . 本文を読む
著者:小田嶋隆 発行所:メディアワークス 2000年(図より11-24~12-5)「学歴にはこだわらない」のが今の日本の風潮に表向きはなっているが、実際はどうなのか。著者は、学歴とは、江戸時代の身分制に変わるもので、違いは世襲制でなく一代限りであること、獲得可能であることだという。明治以来の日本が世界でも例外的な飛躍を遂げた背景には、「学歴身分制」(と著者は名づける)があったというのだ。しかし、学 . . . 本文を読む
1999年マガジンハウス刊 北村薫編の傑作アンソロジー全4冊の第4巻図書館より11月17日~24日借りる 収録されているのが 林房雄「四つの文字」 西村玲子「かくれんぼう」城昌幸「絶壁」 ハリイ・ミューヘイム「埃だらけの抽斗」福田善之「真田風雲録」(お目当てはこれだった) なかで異色は西村玲子「かくれんぼう」3頁の短さなのに(自筆の)挿絵入り。「読売新聞家庭版」が出典と言うのがミソだ。活字中毒の . . . 本文を読む
林芙美子 「めし・女家族」 1955 新潮社
「大きくなったら、林芙美子のような小説家になれば」とよく言われた。今思えば、彼女が46歳の若さで亡くなったのが、その、1951年だ。 . . . 本文を読む
「地上ー地に潜むもの」島田清次郎(1899-1930)初出 1919年1990年 季節社(図書館より)映画化された「地上」(1957)はメロドラマとされている。島田清次郎は物語の作者としても大したものだが、他の部分を知らなければ、彼のみならず、私たちの損失である。彼の「地上」と、同じ年に出た吉屋信子の「屋根裏の二処女」と比べて見る時、表現の端々に似通ったものはあるが、あまりの違いに驚くほか無い。こ . . . 本文を読む