
<能の教本「風姿花伝」>
世阿弥(ぜあみ)の「風姿花伝(ふうしかでん)」は、「能」を勉強
しようとするものにとっては必須の教本であるが、一通り読んで理解
した積りでも、研究者から直接話を聞くことによってそれまでの解釈
が間違っていたことに気づいたり、あるいは新たな感銘を受けたりす
ることが多い。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私は独学で「能・歌舞伎」を勉強しているが、当然分からないことが
多いため、能楽は法政大学で、歌舞伎は早稲田大学と学習院大学のエ
クステンションカレッジで、テーマを選んで学んでいる。
例えば、法政大学の平成17年春季能楽講座は、「道成寺徹底研究」
である。講師は、能楽研究の権威、表 章名誉教授、国立能楽堂講師
松本 雍、喜多流能楽師(シテ方)友枝雄人、法政大学能楽研究所教
授(文学博士)山中玲子教授他である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
矢張り、専門家の話を聞くことによって一人合点の解釈に気づくこと
が多い。また、あらためて、感銘を受けることも多い。世阿弥につい
ては、世阿弥研究の専門家である、山中玲子教授の講話を聞いている
が、多分、「第三問答条々」の中で、咲く花は、当然、やがて散り行
くものなのに、昔の名望にしがみついているばかりで・・・の次に
世阿弥は、「老いは老いなりの花を持て」とも言っているのですよ、
という解説があり、私は勝手に、時分の花、年(とし)相応、年寄り
は年寄りらしく、年寄りの冷や水・・・と考えてしまいました。
余談はこのくらいにしましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<美しい世阿弥の文章>
室町時代の文章は、平安時代までの言葉と違い貴族の言葉から武家の
言葉に変化してきているので、古語に対する知識がなくても比較的意味
が通ずることが多いと思われる。もっとも現代流の解釈は往々にして当時
の意味と正反対に使われていることもあるので注意が必要である。それを
注意すれば声を出して読むことをお勧めする。
++++++++++++
世阿弥の文章は非常に論旨明快であり、語調も歯切れよく名文である。
世阿弥の能理論に出てくる最大のキーワードは「花」である。「能」の極意
は「花」である、と説きながら、「花」とは何か、と論ずる。
++++++++++++
さらに、言葉が美しい。「時分の花」、「まことの花」、「秘する花」、「因果の
花」を説く。さらに、世阿弥が書き著わした伝書の題名にも、「風姿花伝」、
「花習内抜書」、「花鏡」、「至花道」、「拾玉得花」、「却来華」などがある。
***************************************************
<「花」の極意>
極め付きは、「されば、この道を極め終りて見れば、花とて別にはなきもの
なり。奥義を極めて、よろづにめづらしき理(ことわり)を我れと知るならでは、
花はあるべからず。」と断言していることである。
「されば、能の道をしっかり研究し尽くして考えて見るに、花というものが
別個に存在しているわけではないのである。
能の極意を極め、あらゆる場合について、どうすれば珍しさを生み出せ
るか、その道理を自分自身が悟ることこそが花を知ることであり、それ
以外に花は見つからない。」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<風姿花伝第七別紙口伝>抜粋ほか
世阿弥が「花」について述べている名文のうち、「風姿花伝」(第一~第六)、
および「風姿花伝第七別紙口伝」他の中から幾つかの文章を抜き出して、
声を出して読んでみよう。世阿弥の言葉は、案外すらすら読める。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<万木千草四季折々に咲く花>
花と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じこころなり。
いづれの花か散らで残るべき。散るゆゑによりて、咲く頃あれば
めづらしきなり。能も、住する所なきを、まづ花と知るべし。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(注)「花」は、世阿弥の能芸術理論の中心となる概念である。「花」と
は、能に宿る生命であり、面白さと珍しさとひとつである、という。
「花、面白い、珍しい、の三つは同じ「こころ」である。いづれの花も
必ず散るものだ。花は散り、また咲くがゆえに、珍しいのだ。
能も、一所に常住しないことを、まづ花と知るべきである。一所に
留まらず他の姿に移り行くことが、珍しい、ということなのだ。」
(第七別紙口伝)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<時分の花、まことの花>
時分の花をまことの花と知る心が、真実の花に猶遠ざかる心なり。
ただ、人ごとに、この時分の花に迷いて、やがて花の失するをも
知らず。初心と申すはこの比のことなり。
(24、5の頃、生涯の芸風が定まりはじめる。この時分、観客も喝采し
自分も得意になりだすのだ)
(この時の花こそ、初心のたまものと認識すべきなのに、あたかも芸を
極めたかのように思い上がり・・・)
「この一時の花をまことの花と取り違えてしまう心こそ、真実の花を
更に遠ざけてしまう心のあり様なのだ。人によっては、この一時の
花を最後に花が消えうせてしまう理を知らぬ者もいる。初心とは、
このようなものである。」
(第一年来稽古條々)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<秘する花>
秘する花を知ること。
「秘すれば花なり。秘せずば花なるべからず。」となり。
この分け目を知ることが肝要の花なり。
(そもそも、諸芸一切、その家で秘事とされるものは、秘することによって
大きな効用がある所以である。)
「秘すべき花は何か。その花を知り、その花を秘すことが大事である。
秘すからこそ、花なのである。秘すことをしないものは、花ではない。
その違いを知ることが、重要な花なのである。」
(・・・つまりは、人の心に思いも寄らない感動を呼び起こす手立て
こそが花なのである。)
(第七別紙口伝)
********************************************************
( おわり/次回につづく)



















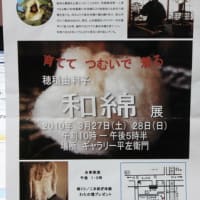
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます