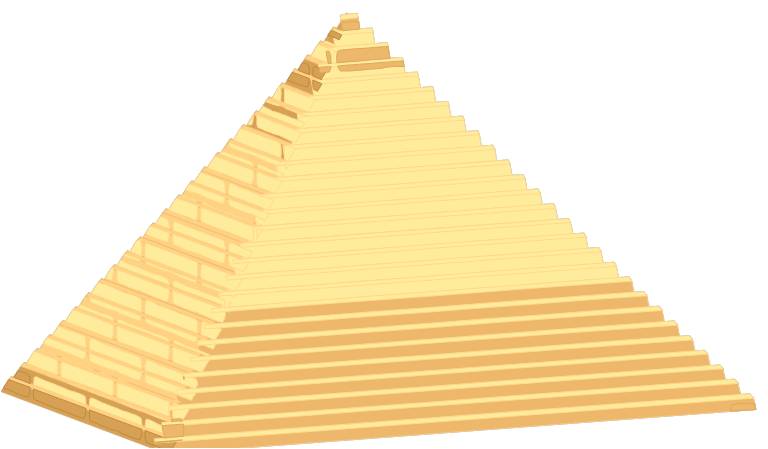琵琶湖ホテルで開催された京都弁護士会の刑事弁護合宿、
昨年に引き続き、今年も講師を務めさせていただきました。
昨年は、めざせ!リーガルハイ!!と題して、みんなで「キャリーぱみゅぱみゅ」と言えるようになろう!と、ボイトレや滑舌、プレゼンの基本という、エンターテイメント満載の話をしたのですが、
今年は、一転!!
「量刑評議について学ぶ!!裁判官を知り、裁判官を突破する!」
という、きわめてまじめな研修講師です。

とはいえ、やはり、せっかく参加してくれたみなさんに楽しんでもらわないといけないということで、
去年に引き続き、こんな格好でやりました。

白衣 に特に深い意味はありません。
着てみたかったのです。
さて、裁判で量刑がどのように決まっていくのか?
裁判員裁判が始まって今年で6年目。
いろいろと試行錯誤、紆余曲折があって、裁判の実務は落ち着きor硬直化を見せてきているようです。
最近の量刑で重視されているのは、どうやら、「安定性と公平性」
そのために、
行為、結果、動機などの主要な犯情をもとに、その事件の 社会的類型 を考え、これまでの裁判の結果をまとめた量刑分布表を使って、量刑の大枠を決める。
その次に、その社会的類型の事件の中で、量刑の分岐点・ポイントとなる犯情が何かを考え、その事件がどの程度の重さになるのかをさらに絞り込んでいく。
そして、最後に、反省や更生可能や、同種犯罪の防止という一般情状事実で微調整して、最終的な量刑を決める
という方法が裁判所が量刑を決める方法になっています。
こういう方法でやると、まず、一般市民である裁判員が自由な感覚で量刑を決めることはまずできなくなります。
これまでの量刑傾向の範囲内の判決しか出せなくなります。
このことが、裁判員の市民感覚をないがしろにしていると批判されることがあります。
しかし、感情的、感覚的に量刑を決めることを許してしまったために、求刑を超えるほどの極端な厳罰化傾向が出てしまった反省からすれば、被告人の公平な裁判を受ける権利を守るために、こういう客観性のある量刑判断の枠組みを明確にして、一定の縛りをかけることにも重要な意味があると思います。
ただ、この枠組みを絶対のものとしてしまうと、例えば何人も殺害した事件で死刑を回避しようとしたり、発達障害や過酷な生い立ち、少年である、前科がないといった事情を判決に反映させようとする弁護活動は、裁判所にまったく相手にしてもらえないことになってしまいます。
そこをいかに突破するのか?!というのが、今回の研修のテーマ。
一橋大学の葛野教授や香川県弁護士会の安西敦弁護士にも講演していただきました。
被告人の主観的事情、特に、これまでは微調整要素としかされなかった、更生可能性や過酷な生育歴といった一般情状に関わる主観的事情をいかにして、量刑に大きく反映させることができるか!ということが、いまの情状弁護の重大テーマです。
大阪アスペルガー事件の控訴審などいくつかの裁判例では成功事例もあるようですが、ほとんどの裁判では、主観的事情を判決に反映させようとした弁護活動は裁判所に一蹴されてしまっています。
私も一蹴された判決がいくつかあります。 
裁判官を知り、被告人を知り、そして、弁護活動を組み立てる。
弁護人の力量が問われています。














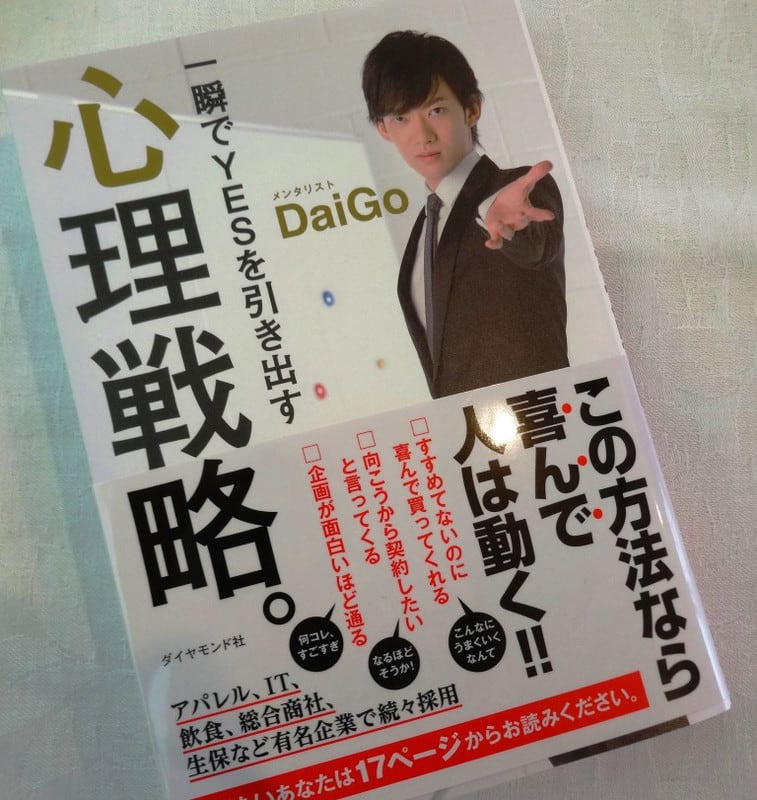

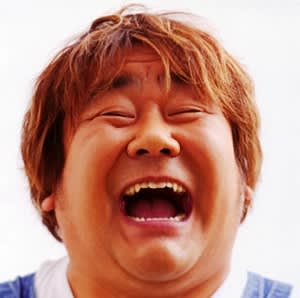
 」「レポーター失格
」「レポーター失格